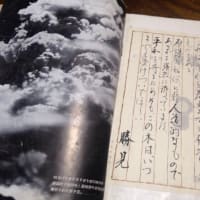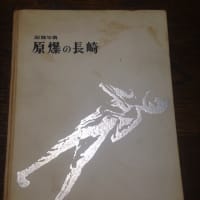29日
朝。昨夜から呪文のように同じテキストを唱え続けていた。
東武百貨店へ向かう。
搬入口。
次々とトラックが着き、商品をおろしてゆく。ダンボール箱、ハンガーに掛かった大量のスーツ。
働く人たちの邪魔にならない隅の方にいてテキストを唱え続けた。
屋上16階 快晴。
日の出ている間は暑いくらいだった。
屋上で初めて声を出す。一度下見には来たが、ここで稽古できるのは今日の本番までの時間のみ。
午前中は音響の仕込みなどあって通してやれるのはゲネが最初で最後だった。地下に控室を用意してもらっていたが、できるだけ場にいて感覚のチュー二ングをしようと思った。邪魔にならないようにうろうろしながらテキストを唱え続けた。
私は今回覚えて喋るということをほぼ全編に渡ってしていない。
最後の方に暗記して喋るところが少しあり、朝からずっと唱えているのはその部分のテキストだった。
その他はずっとヘッドホンから流れてくる自分の声のテキスト朗読を聞いて、聞こえた言葉を声に出して言う、ということをやっていた。45分の上演時間中ほぼ半分の時間はその状態であった。それはまるでスピーカーとか、電波を受信して喋るラジオのように、キャッチした音を外に出しているという感じで、聞こえてくるものを声として出す。
私のなかに記憶されているもの、ストックではなく、聞き取ったものを声に変換する中継地のように、やってくるものをひたすら声として出すということをしていた。そして目だけはそれとは関係なくずっと動かし続けている。
最初はできるだけ聞こえてくるものをそのままただ声に出す。言葉にニュアンスを込めたりせず声に出す。
徐々に声を大きくしてゆくよう演出から言われていた。声を出すときにはどうしても喉を、舌を、声帯を震わせる。声を大きくするとその振動は大きくなる。淡々と読むときよりも「肉」体が声に巻き込まれる感がある。そもそもアナウンサーのようにうまく喋ることは出来ないのだが、屋上でマイクを通さないで言葉を客席の最後尾にまで届かせるには、かなり声を張らなければならず、読み方は声を届けるために必死になる。6階にいても案外地上の駅や車の音、何かの宣伝の声は聞こえるもので、それに風の音、百貨店のアナウンスなど、声を出す場に既にさまざまな音があるから尚更だった。
この場でやってみるまで、屋上でどれ程声が届くものか、演出にも私にもわからなかった。
屋内の稽古場とは当然音の反響が違う。後ろの席でもどうにか声は聞こえるようだったが、客席を並べていざやってみて、後ろの方の席では全然見えない、といって、ずっと座った状態で読んでいたものを、椅子の上に立ってやることになった。それでその前後の動きが変更される。場との関係のなかで方法が選択されていく。
16時
開場時間になると、昼間のあたたかさは蒸発して、じっとしていると寒いと感じるようになった。
お客さんがやってくるのを陰から覗きつつ、朝から繰り返し続けているテキストを唱え続けた。
テキストが覚えられない。
ずっと聞こえてくる音声を受け流して喋っていると、体に言葉が留まりにくくなるのだろうか。
俳優は与えられた台詞を覚えてそれを体に落とし込む、ということをする。その台詞が自分の言葉となるように引き寄せる。発話されるとき、台詞対する俳優の解釈が含まれ、書かれた台詞は受肉する。
しかしいわゆる台詞ではない中平卓馬のテキストは、俳優に解釈されて読まれる言葉ではないだろう。
演じるための、一般的な意味においての「台詞を体に落とし込む」ことはこの場合、的が外れているし、聞こえてくる言葉を読み続けていると、記憶する能動性が麻痺して、聞こえて来なくても聞こえて来るのを待ってしまう、という困ったことになっていた。この状態は俳優として見たらおそろしく役立たず、ほとんど機能していない。そのときにやってきたものを受けることしか出来ない、自分がまったく頼りないデクノボーに思えた。
野外では、見えるもの、聞こえるもの、風の感触、気温、におい、知覚する要素が多く、それも時間ごとに変化する。最後に覚えて読むところは、観客席に背を向けて街の風景を見ながら読むのだが、夜景を前にして読んだことはなかった。昼と夜のがらりと姿を変えた街を目の前にして、昼とは違う温度、空気のなかで読むことも不安だった。外から入ってくるものを体は受けとってしまう。正解に言うと、単に街を借景にすることは不可能で、中平卓馬の言葉を借りて言うなら、「世界は単なる客体ではなく、私は堅牢なものでもない。相互に侵犯しあう白熱する地場、それが世界である」 そのように体は晒され、準備したものは脆く、ぶらされる。ニュアンスや演技の技術、「逃れ去る情緒、陰影」を奪われた体、であるように感じられた。
16時30分 開演
はじめ客席に背を向けている。そこからしばらくして客席を振り返ったとき、そのなかに中平卓馬氏の姿を見つけてしまった。あ、と思った。赤いキャップですぐにわかった。
『なぜ植物図鑑か』をはじめて読んだとき、この人は、なんて体でものを見、考えている人なのだろうと思った。
自らの仕事を「肉眼レフ」と言い、カメラを構えシャッターを切る。
「私」の視線と、ものの視線とが交錯するところで瞬間的に焦点を結ぶ「身体をもってこの世界に生きてあるということ」
見ることも、聞くことも、話すことも、この体なしには不可能である。いくらそこから離れようとしても知覚には自己の体がつきまとう。体そのものを使って何かを為す人、こと俳優、ダンサーには常に「私」というものがついてまわる。それはどのような役をしていようと何をしていようとそうだ。
私は幽体離脱するように自己の体を見ることは出来ない。イメージのなかでしか対象化することの出来ない自己の体を扱わなければならない。それは難儀なことだ。知覚には私見が伴う。介在せざるを得ない「私」というもの。この在ってしまうもの。そこからしか世界をみることは出来ないということ。そこにありつつ私見によって世界を歪めることなく、あるがままを受けとること。「身体を世界に貸し与える」という言葉がよぎる。
それは能動的受動体とでもいうような体である。体を使って何か為す時はいつもそのようにあるべき、と思う。
変幻自在な感情表現、演劇的技巧、そういう方法でもって私はこの体で何かを表現するのではなく、「身体を世界に貸し与える」こと。
もっとよく見るために聞くために、晒され透過していく体。
決して透明になったりしない血肉と共にありつつ。
上演中に日は沈み、16階屋上から見える池袋の街には徐々に灯りがともり、薄明るかった風景は様相を変えて、終演する頃には完全に夜の姿になっていた。ビルの上に点滅する赤いランプの呼吸のリズム。道路に連なる車のライトは血流のように流れていた。
『中平卓馬/見続ける涯に火が…』