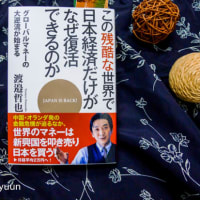「ミシュランガイド」が出れば、和の哲人として鳴らした道場六三郎の「銀座ろくさん亭」はまず落選だろう。
なぜなら、メニューが一つしかないからだ。
しかも、一ヶ月同じ料理で12600円。
昔このメニューを見て批判した評論家がいた。
毎日同じ料理しか作らないのなら、材料が無駄にならず経済的だが、お客のニーズに合わない。
しかも、前菜で7種類あっても1種類は一口サイズ。
色々と批判されたので、「懐食みちば」では同じ12600円でも
「懐食みちば」では、かねてよりお客様からご要望のあった一品料理や、
プリフィックス(チョイスのできるコース料理)をご用意いたしております。
とあるが、強肴と食事の部分だけだ。
後は全て同じ。
実は、「銀座ろくさん亭」も同じ部分が幾つかから選択できる。
それにしても、何やら「食べさせてやる」という店ではあるね。
【明解要解】ミシュランガイド「東京版」創刊へ 「日本料理」どう評価?
レストランとホテルの格付けで世界的に知られる「ミシュランガイド」の東京版が今年11月に創刊されることになり、早くも話題を集めている。同ガイドのアジア進出は初めて。果たしてミシュランは、日本の食文化をどのように評価するのだろうか。(文化部 黒沢綾子)
「伝統を尊重し、食材の質が高く、料理法が高度に発達している。つまり美食文化が息づいている。アジア進出にあたって東京を玄関口としたのは、至極当然なこと」
107年の歴史を誇るミシュランガイドの6代目総責任者、ジャンリュック・ナレ氏は、アジア各都市の視察を経て、こう結論づけた。ナレ氏はホテル業界などでキャリアを積んだ、初の外部採用の総責任者ということもあり、積極的な国際戦略を打ち出している。
東京進出の背景には、米国での成功がある。2年前に初めて大西洋を渡り、「ニューヨーク版」を刊行。格付け結果については「ニューヨークの食文化を見下すフランス人の傲慢(ごうまん)だ」などと物議を醸したが、逆にそれが知名度を上げ、初年から12万5000部を売り上げた。昨年には「サンフランシスコ版」も出し、「星が付いたことで、店によっては客が3~5割増えたところも」とナレ氏は胸を張る。
◆◇◆
東京のレストラン格付け本といえば、米国発祥の「ザガットサーベイ」東京版が8年“先輩”にあたるが、「調査員が格付けするミシュランに対し、われわれは一般のレストラン利用者のアンケートに依拠している。でも、格付け本自体の注目度が高まる相乗効果に期待したい」(発行元のCHINTAI)と歓迎する。
『おいしい店とのつきあい方』(角川書店)の著者、サカキシンイチロウ氏は「ミシュランにおいては、味や雰囲気、サービスは言うに及ばず、キッチンの設備の充実度とか、最終的には経営的にうまくいっているかどうかまで判断の材料になる。『客の目線』だけでなく、総合的判断なので興味深い」と期待を寄せる。また「世界的水準で見て、日本の和食店はどのように優れており、劣っているのかを知ることも有意義だ」とも指摘する。
◆◇◆
ナレ氏によるとミシュランでは、すでに昨年5月から、覆面調査員5人が、東京の1200店以上を対象に調査を開始。うち2人が日本人、3人は欧州系だが「日本文化にどっぷりつかっており、東京の多様な食文化を理解するよう努力している」という。
レストラン・ホテル業界は、今のところ「実際にフタを開けてみないと…」と静観の構えだが、サカキ氏によれば、業界における最大の関心事は「ミシュランは日本の食文化にどれほど配慮するのか」だという。「例えば従来のミシュラン見解なら、料理を出す場所と、汚れた食器が戻る場所が同じレストランには星を与えないでしょう。すると寿司屋はどうなるのか、とか」
ナレ氏は「調査には謙虚な気持ちであたりたい。われわれの役割はあくまで料理の才能を見つけだし、世界中の人々に東京の食文化のありのままを知ってもらうことだ」と話している。
◇
【用語解説】ミシュランガイド
フランスのタイヤメーカー、ミシュランが1900年、ドライバーに車の修理場所や宿泊・食事施設などを示したガイドを無料配布したのが始まり。20年に有料化し、31年に調査員による「星」の格付けが登場した。現在、欧州を中心に21カ国で計18種類のガイドが発行されている。
◇
一線記者がニュースの背景にせまり、わかりやすく解説します。読者の質問、疑問にもお答えします。ファクス03・3242・7745か、Eメールでspecial@sankei.co.jpへ。