タイトルに続きまして。。
最近の車に多いタイミングチェーン式のエンジンだと、「チェーンが伸びる」そうです。
さらに、燃費や環境性能対応のために可変バルブタイミングを採用していることがほとんどだと思います。
こちらも、エンジンオイルの状態を影響を受けやすいものだそうで。。
これから先の話題には関係なくなってしまうのですが、コモンレール式のディーゼルエンジン車だと、オイル希釈&増量問題もありますよね。
最近増えている0w-20のようなオイルは性能低下が比較的速いタイプと高負荷に耐えるタイプがあるので、使用状況に合わせて選ばないと、交換サイクルが思わぬ速さになってしまうことがあります。
オイルが多くなると抵抗が増えたり、重量がかさむという事で、オイルの使用量もひところより少なくなっていますから、循環速度も速いので、必然的に痛みも…という事になると思います。
そんなこともあり、ひと頃よりも最近の車はよりエンジンオイルのコンディション管理がシビアになっているという事を良く聞きます。
整備工場のセールストーク込みで、1万kmも同じオイルを使うのはもってのほかという事で。。
今回はトヨタの直列4気筒の超定番である、1NZ型エンジンを話題にしますが、オイル管理が悪くてタイミングチェーンの伸びが問題になるのは、日産のCR系も多いような気がします。
で、本題はエンジンオイルの交換をさぼった車がどうなるかというちょっとした例を見せてもらいました。
交換不要と言われるタイミングチェーンが8万km前にのびて、エンジン内部のどこかと接触しているような音がしていることに気が付いたのです。
こう書くと、タイミングチェーンの耐久性が低い車のような気がしますが、音の出ていた個体は2年間、4万km以上オイル無交換という恐ろしい状態のプロボックスワゴンです。
普通のクルマの倍ぐらい走っているにもかかわらず、前回の車検整備時からオイル交換がされた形跡がないという有様。
車検に合わせて、エンジンの不調の原因を出して欲しいという事で始めたら、衝撃的なオイル交換の履歴というが判明し、カムホルダーの摩耗等色々現認を探った結果、7.7万kmでタイミングチェーンとVVT-iコントローラ、オイルストレーナー交換、オイルパンのヘドロ状の旧オイル落し、ヘッドカバーを外してヘッド内の清掃という重整備をすることになりました。(これでも、使用状況不明の中古エンジンに載せ替えるよりも安く上がるらしい。)
件の個体は規定量の9割程度のオイルが抜けるようになるまで、3回のオイル交換を要したようです。
取り敢えず抜いてみたら、500ccもオイルが抜けなかったそうです。(これは下抜き、上抜きを併用しての量です。)
1NZは、車載状態でのタイミングチェーンの交換を考慮したカムカバー、フロントカバーの設計になっていて、車体もそれを考慮した設計になっていました。
タイミングチェーンは50万km近く持つ耐久性があるということで、車載状態での交換を考慮していない場合も多いですから。。
補足
修理されていたプロボックスワゴンは、4WDのATモデルと1NZ-FEとしては最もエンジンルーム内が詰まった状態になるモデルですが、車載状態どころかリフトアップしなくても作業が可能なんですね。
腰にやさしい作業環境が造りが、リフトではなくウマ掛けでしたから。。
プロボックスに限らず、初代ヴィッツのプラットフォームを使用している車は同等の整備性を持っているとのことです。
最近の車に多いタイミングチェーン式のエンジンだと、「チェーンが伸びる」そうです。
さらに、燃費や環境性能対応のために可変バルブタイミングを採用していることがほとんどだと思います。
こちらも、エンジンオイルの状態を影響を受けやすいものだそうで。。
これから先の話題には関係なくなってしまうのですが、コモンレール式のディーゼルエンジン車だと、オイル希釈&増量問題もありますよね。
最近増えている0w-20のようなオイルは性能低下が比較的速いタイプと高負荷に耐えるタイプがあるので、使用状況に合わせて選ばないと、交換サイクルが思わぬ速さになってしまうことがあります。
オイルが多くなると抵抗が増えたり、重量がかさむという事で、オイルの使用量もひところより少なくなっていますから、循環速度も速いので、必然的に痛みも…という事になると思います。
そんなこともあり、ひと頃よりも最近の車はよりエンジンオイルのコンディション管理がシビアになっているという事を良く聞きます。
整備工場のセールストーク込みで、1万kmも同じオイルを使うのはもってのほかという事で。。
今回はトヨタの直列4気筒の超定番である、1NZ型エンジンを話題にしますが、オイル管理が悪くてタイミングチェーンの伸びが問題になるのは、日産のCR系も多いような気がします。
で、本題はエンジンオイルの交換をさぼった車がどうなるかというちょっとした例を見せてもらいました。
交換不要と言われるタイミングチェーンが8万km前にのびて、エンジン内部のどこかと接触しているような音がしていることに気が付いたのです。
こう書くと、タイミングチェーンの耐久性が低い車のような気がしますが、音の出ていた個体は2年間、4万km以上オイル無交換という恐ろしい状態のプロボックスワゴンです。
普通のクルマの倍ぐらい走っているにもかかわらず、前回の車検整備時からオイル交換がされた形跡がないという有様。
車検に合わせて、エンジンの不調の原因を出して欲しいという事で始めたら、衝撃的なオイル交換の履歴というが判明し、カムホルダーの摩耗等色々現認を探った結果、7.7万kmでタイミングチェーンとVVT-iコントローラ、オイルストレーナー交換、オイルパンのヘドロ状の旧オイル落し、ヘッドカバーを外してヘッド内の清掃という重整備をすることになりました。(これでも、使用状況不明の中古エンジンに載せ替えるよりも安く上がるらしい。)
件の個体は規定量の9割程度のオイルが抜けるようになるまで、3回のオイル交換を要したようです。
取り敢えず抜いてみたら、500ccもオイルが抜けなかったそうです。(これは下抜き、上抜きを併用しての量です。)
1NZは、車載状態でのタイミングチェーンの交換を考慮したカムカバー、フロントカバーの設計になっていて、車体もそれを考慮した設計になっていました。
タイミングチェーンは50万km近く持つ耐久性があるということで、車載状態での交換を考慮していない場合も多いですから。。
補足
修理されていたプロボックスワゴンは、4WDのATモデルと1NZ-FEとしては最もエンジンルーム内が詰まった状態になるモデルですが、車載状態どころかリフトアップしなくても作業が可能なんですね。
腰にやさしい作業環境が造りが、リフトではなくウマ掛けでしたから。。
プロボックスに限らず、初代ヴィッツのプラットフォームを使用している車は同等の整備性を持っているとのことです。
















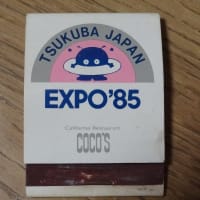



私も職場でサクシードバンに乗るのですが、貧弱そうに見えて意外と疲れない前席、1万kmでも30万kmでも同じようなキシミ音の出る内装も含めて、よくできているような気がします。
ちょっとだけ全長の長いサクシードのほうが荷役性も高いです。
アルファードのV6のスパークプラグ&イグニッションコイルの交換作業は、友人I氏(トヨペットのDメカ)がやりたくないけど、比較的機会の多い作業だそうです。しかも、作業しにくい側のほうが熱がこもって、コイル割れが起きやすいという、不条理仕様なんだそうです。