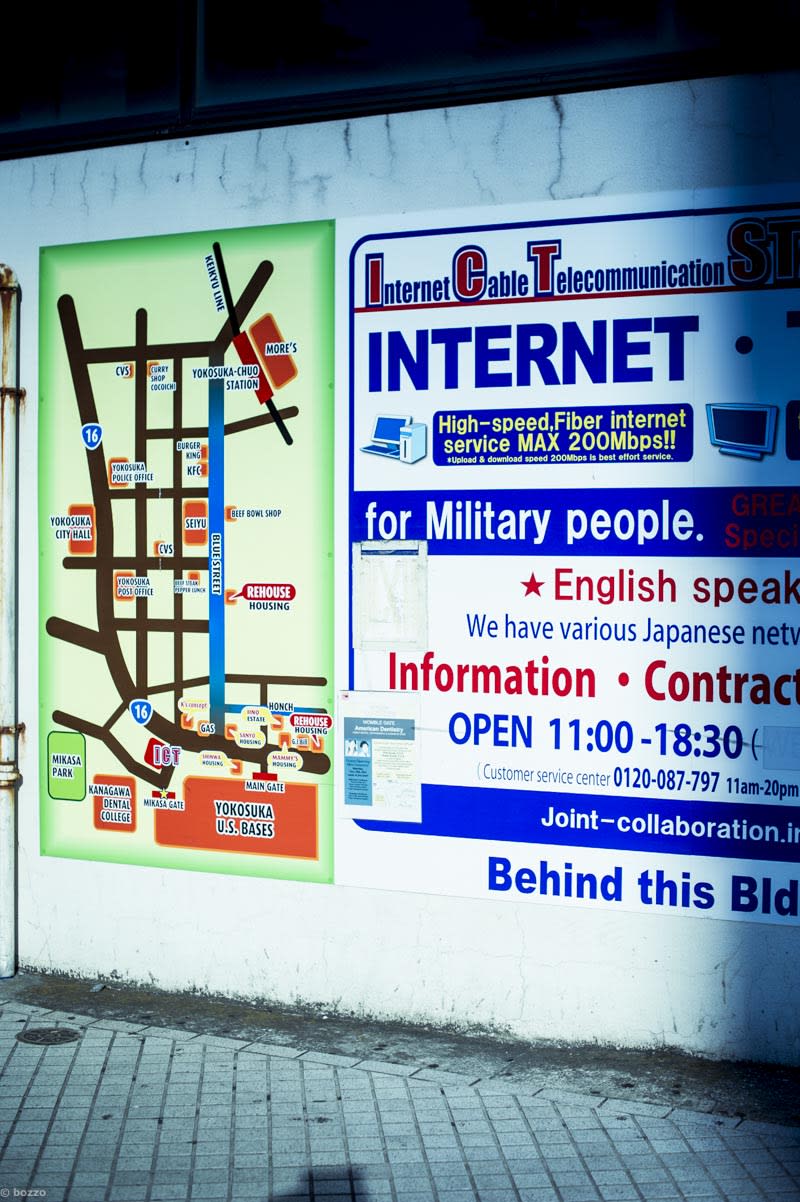緑にくっきりと浮かぶ日の丸。
この求心的な光景を、どう捉える?
なぜか日の丸には、強烈な求心力を感じてしまう。
的に通じる意匠だからか?
それだけではあるまい。
日本帝国という亡霊が常に彷徨っているからではないか?
日本が敗戦を無きモノにしようとすればするほど、
犬死にした何百万もの兵卒たちが、忿怒の思いで立ち上がるからではないか?
彼らは俘虜は帰ったら殺すという陸海軍刑法の明文があると思っていた。
これは彼らが受けた玉粋主義の教育と、軍隊内の経験に基づいた空想であるが、
人はやはりこういう予想の下に生き得るものではない。
だから彼らは何らかの特別な赦免が行われるはずだと信じていた。
上海事変の俘虜が満州に集団労働に送られたという噂が一般に信ぜられ、
彼らもまた同じ運命を辿るものと考えていた。そしてそこで二三年の贖罪を済ませた後、
自分たちもまた社会に容れられるであろうと期待していた。
(中略)
すべてこうした日本人が戦争という現実に示した反応は、
今日単に「バカだった」と考えられている。
しかし自分の過去の真実を否定することほど、今日の自分を愚かにするものはない。
(「俘虜記」大岡昇平著 )
日本の戦後は、まだ終わっていない。
この求心的な光景を、どう捉える?
なぜか日の丸には、強烈な求心力を感じてしまう。
的に通じる意匠だからか?
それだけではあるまい。
日本帝国という亡霊が常に彷徨っているからではないか?
日本が敗戦を無きモノにしようとすればするほど、
犬死にした何百万もの兵卒たちが、忿怒の思いで立ち上がるからではないか?
彼らは俘虜は帰ったら殺すという陸海軍刑法の明文があると思っていた。
これは彼らが受けた玉粋主義の教育と、軍隊内の経験に基づいた空想であるが、
人はやはりこういう予想の下に生き得るものではない。
だから彼らは何らかの特別な赦免が行われるはずだと信じていた。
上海事変の俘虜が満州に集団労働に送られたという噂が一般に信ぜられ、
彼らもまた同じ運命を辿るものと考えていた。そしてそこで二三年の贖罪を済ませた後、
自分たちもまた社会に容れられるであろうと期待していた。
(中略)
すべてこうした日本人が戦争という現実に示した反応は、
今日単に「バカだった」と考えられている。
しかし自分の過去の真実を否定することほど、今日の自分を愚かにするものはない。
(「俘虜記」大岡昇平著 )
日本の戦後は、まだ終わっていない。
駿監督が「風立ちぬ」に今、込めた思いとはなんだったのか。
以下の言葉がガンガン響く。
<宮崎駿の言葉>
◆人間の世界から外れたところには、何かがいるという自然観を日本人は持っていたんです。
だから、自然に対して謙虚で、慎ましい態度をとっていました。ところが自然に対して優位に立つと、その畏れを捨てて振舞ってきた。
◆ ぼくは地球の地殻変動や自然災害というのは、人間の営みとまったく無関係じゃないとどこかで思っているんですね。
人間社会の行き詰まりなんかとちゃんとつながっているんじゃないかって気がしてしかたがない。
◆ 地震はこれまで何回もあったことがまた起こったんです。
たくさんの悲劇がありましたが、震災を受けた人たちは、乗り越えていけると思います。
ですが 原発の問題はね、これはエネルギーを過剰消費していく文明のありように、はっきり警告が発せられたんだと思うんです。
◆ 大量消費文明が終焉する第一歩なのかどうか、僕にはよく分からないが、今の世の中は緊張感に満ちていると思う。
かつて堀越二郎と堀辰雄もこの先どうなるのか分からないということについて、どうもこれはまずいと意識しながら生きたに違いない。
堀越二郎と堀辰雄が生きた時代と現代に、同時代性を感じた。
◆ 突如歴史の歯車が動き始めたのです。生きていくのに困難な時代の幕が上がりました。
この国だけではありません。破局は世界規模になっています。おそらく大量消費文明のはっきりした終わりの第一段階に入ったのだと思います。
◆ 福島の原発が爆発した後、風が轟々と吹いたんです。
絵コンテに悩みながら、上の部屋で寝っころがっていると、その後ろの木が本当に轟々と鳴りながら震えていました。
爽やかな風だけじゃない、轟々と吹く、放射能を含んだ風もこの世界の一部なのだと思いました。風は世界だと。
◆ 自分たちは正気を失わずに生活をしていかなければなりません。
「風が吹き始めた時代」の風とはさわやかな風ではありません。
おそろしく轟々と吹きぬける風です。死をはらみ、毒を含む風です。人生を根こそぎにしようという風です。
◆ 人間のやることには必ず愚かなことが付きまとうから。
権力はすぐに腐敗するし、歴史はいつも残酷な結果を押しつける。
要するに、この世界は不条理だということ。
悪いことをしても天罰が下るわけではなく、良いことをしてもお褒めに預かるわけではない。
じゃあ何が違ってくるかというと、「顔が違ってくる」。
◆ 先頭を切って一生懸命やんなきゃ話になんない。死ぬ気でやるしかないんです。
どんな方法でもとにかくあげるしかない。自分の人生のためにやるしかないんです。
◆ 今の世の中全体のことで、政治がどうとか、社会状況がどうとか、
マスコミがどうのこうのということじゃなくても、自分ができる範囲で何ができるかって考えればいいんだと思います。
それで、随分いろんなことが変わってくるんじゃないでしょうか。
◆ 自分の今いる場所で、可能な限り誠実に、力いっぱい生きるしかない。
世界のあらゆることに関心をもち、政治情勢によって自分の行動を決めるなんてことはできないですから。
職業人は職業に専心することによって、小さな窓から世界を眺めて、初めて世界を感じ取ることができるんじゃないでしょうか。
◆ ぼくは生まれてこないほうが、良かったんじゃないかなって思ってる子に、「生まれてきてよかったんだよ」って言ってあげるんだよ。
以下の言葉がガンガン響く。
<宮崎駿の言葉>
◆人間の世界から外れたところには、何かがいるという自然観を日本人は持っていたんです。
だから、自然に対して謙虚で、慎ましい態度をとっていました。ところが自然に対して優位に立つと、その畏れを捨てて振舞ってきた。
◆ ぼくは地球の地殻変動や自然災害というのは、人間の営みとまったく無関係じゃないとどこかで思っているんですね。
人間社会の行き詰まりなんかとちゃんとつながっているんじゃないかって気がしてしかたがない。
◆ 地震はこれまで何回もあったことがまた起こったんです。
たくさんの悲劇がありましたが、震災を受けた人たちは、乗り越えていけると思います。
ですが 原発の問題はね、これはエネルギーを過剰消費していく文明のありように、はっきり警告が発せられたんだと思うんです。
◆ 大量消費文明が終焉する第一歩なのかどうか、僕にはよく分からないが、今の世の中は緊張感に満ちていると思う。
かつて堀越二郎と堀辰雄もこの先どうなるのか分からないということについて、どうもこれはまずいと意識しながら生きたに違いない。
堀越二郎と堀辰雄が生きた時代と現代に、同時代性を感じた。
◆ 突如歴史の歯車が動き始めたのです。生きていくのに困難な時代の幕が上がりました。
この国だけではありません。破局は世界規模になっています。おそらく大量消費文明のはっきりした終わりの第一段階に入ったのだと思います。
◆ 福島の原発が爆発した後、風が轟々と吹いたんです。
絵コンテに悩みながら、上の部屋で寝っころがっていると、その後ろの木が本当に轟々と鳴りながら震えていました。
爽やかな風だけじゃない、轟々と吹く、放射能を含んだ風もこの世界の一部なのだと思いました。風は世界だと。
◆ 自分たちは正気を失わずに生活をしていかなければなりません。
「風が吹き始めた時代」の風とはさわやかな風ではありません。
おそろしく轟々と吹きぬける風です。死をはらみ、毒を含む風です。人生を根こそぎにしようという風です。
◆ 人間のやることには必ず愚かなことが付きまとうから。
権力はすぐに腐敗するし、歴史はいつも残酷な結果を押しつける。
要するに、この世界は不条理だということ。
悪いことをしても天罰が下るわけではなく、良いことをしてもお褒めに預かるわけではない。
じゃあ何が違ってくるかというと、「顔が違ってくる」。
◆ 先頭を切って一生懸命やんなきゃ話になんない。死ぬ気でやるしかないんです。
どんな方法でもとにかくあげるしかない。自分の人生のためにやるしかないんです。
◆ 今の世の中全体のことで、政治がどうとか、社会状況がどうとか、
マスコミがどうのこうのということじゃなくても、自分ができる範囲で何ができるかって考えればいいんだと思います。
それで、随分いろんなことが変わってくるんじゃないでしょうか。
◆ 自分の今いる場所で、可能な限り誠実に、力いっぱい生きるしかない。
世界のあらゆることに関心をもち、政治情勢によって自分の行動を決めるなんてことはできないですから。
職業人は職業に専心することによって、小さな窓から世界を眺めて、初めて世界を感じ取ることができるんじゃないでしょうか。
◆ ぼくは生まれてこないほうが、良かったんじゃないかなって思ってる子に、「生まれてきてよかったんだよ」って言ってあげるんだよ。
中上健次を、同じに育った田畑稔氏との関係から語った名著。
被差別…関西に根深い「解体」の歴史と共に
健次がこだわった「路地」とはなにか…を、
健次のいとこである「田畑稔」氏の生き様を通して、見つめる。
差別を「無きモノ」にしようと戦後動き出した「解体」。
健次が育った新宮市春日地区も、総予算20億もの費用を投じて解体された。
1977年のことだ。
春日地区は、臥龍山という龍が横たわったような里山に抱かれて存在した。
しかし、その工事で里山は見事に更地になった。
20億円かけてひと山削った…それがを解体するということだった。
そして、山そのものを「無きモノ」にすべく幹線道路をかつての尾根伝いに引き、
その沿道に新宮市役所を新たに建てた。
被差別の淀みが、クルマの往来で時間とともに抹消されていった。
…見事なまでの隠蔽対策である。
健次のいとこにあたる「田畑稔」氏は、「解体」を逆手にとって、たくましく生きた。
繁盛している焼き肉屋の近所で焼き肉屋を開業し、ホルモン焼きで大繁盛。
3千万で900坪の山を一つ買い、400に区分けして墓地として売った。
「解体」の事業につけこんで、砂利手配の事業を興した。
赤木川の上流域をひたすら採掘し、護岸堤防そのものを無くすほどの環境破壊をした。
同和対策の貸付枠を巧妙に用いて市から3億もの金を借り、自前のソーセージ工場でもって、
食肉処理場で余った牛・豚のクズ肉を活用しようとした。…だが、これは大失敗だった。
、墓地販売、解体事業、産廃事業、屎尿処理業。
生と死の境界を巧みに見極め、あざとく商売に転化した。
それもこれも被差別という立場で生きたゆえ。
辺境で生きる知恵…とでも言おうか。
著者は沖縄を引き合いに出し、熊野の土地と相似形であると書く。
「田畑に学ぶべきは、くじけない心であろう。生命力と言い換えてもいい。バイアスがかかるほど、反発のバネが働く。
熊野と沖縄は相似形に映る。田畑の起伏に富む軌跡は、アララガマ精神そのものではないか。
アララガマとは、宮古島の方言で「なにくそ」の意だ。熊野は、廃藩置県により本来ひとつであるべき牟婁四郡が
和歌山県と三重県に分断された。廃仏毀釈で多くの寺院・修験道の堂宇が破却され、大逆事件では郷土の誉れ高い人々が
国家によって惨殺された。中央政府によって、理不尽な扱いをされてきた点では同類だ。
熊野も沖縄も、明治維新以来、良い目にあったことに乏しい土地である」
「まことに差別の問題は、ややこしい。ひとより優越した存在でありたい。この意識が根源的な〈生存の本能〉に根ざしているからだろうか。
古来、死者をホフル(葬る)のも、カミや霊をハフル(祝る)のも、畜獣をホフル(屠る)のも同義である。
これらは異界と現世をつなぐ行為であり、その接点に立つ者は畏怖の対象だった。畏怖は差別ときわめて近似の感情である」
「宮古島の人々は、沖縄本島の人々に搾取されつづけた。琉球王朝による人頭税が、その一例だ。民俗学者・谷川健一はこう指摘する。
〈首里城が沖縄のシンボルなんて、とんでもないことでしょう。宮古・八重山諸島の人々にとって、首里城こそ、代々の祖先をソテツ地獄
(ソテツの実で飢えを凌ぐ飢餓生活)に追い込んできた圧政の象徴そのもの〉という。
二千円札に描かれている守礼の門は、苦々しく唾棄すべき対象なのだ」
平準化・均質化する社会の中で、差別も【無きモノ】へ葬り去られようとしている。
過去を過去とし、忘れ去ることは簡単だ。しかし、そのことによって人間の本質も隠蔽しようとしていないか?
【ひとより優越した存在でありたい】…この〈生存の本能〉と呼ばれるところから、人間の歴史は逃れることができない。
形骸化した「天皇制」もまさしくこの本能から派生した制度であり、「貴が在るところ、賤あり」の現実なのだ。
その本質を見つめずして「天皇制」を語ることは、敗戦を見つめずして「改憲」を語るに等しい。
この問題は、表裏一体である。
被差別…関西に根深い「解体」の歴史と共に
健次がこだわった「路地」とはなにか…を、
健次のいとこである「田畑稔」氏の生き様を通して、見つめる。
差別を「無きモノ」にしようと戦後動き出した「解体」。
健次が育った新宮市春日地区も、総予算20億もの費用を投じて解体された。
1977年のことだ。
春日地区は、臥龍山という龍が横たわったような里山に抱かれて存在した。
しかし、その工事で里山は見事に更地になった。
20億円かけてひと山削った…それがを解体するということだった。
そして、山そのものを「無きモノ」にすべく幹線道路をかつての尾根伝いに引き、
その沿道に新宮市役所を新たに建てた。
被差別の淀みが、クルマの往来で時間とともに抹消されていった。
…見事なまでの隠蔽対策である。
健次のいとこにあたる「田畑稔」氏は、「解体」を逆手にとって、たくましく生きた。
繁盛している焼き肉屋の近所で焼き肉屋を開業し、ホルモン焼きで大繁盛。
3千万で900坪の山を一つ買い、400に区分けして墓地として売った。
「解体」の事業につけこんで、砂利手配の事業を興した。
赤木川の上流域をひたすら採掘し、護岸堤防そのものを無くすほどの環境破壊をした。
同和対策の貸付枠を巧妙に用いて市から3億もの金を借り、自前のソーセージ工場でもって、
食肉処理場で余った牛・豚のクズ肉を活用しようとした。…だが、これは大失敗だった。
、墓地販売、解体事業、産廃事業、屎尿処理業。
生と死の境界を巧みに見極め、あざとく商売に転化した。
それもこれも被差別という立場で生きたゆえ。
辺境で生きる知恵…とでも言おうか。
著者は沖縄を引き合いに出し、熊野の土地と相似形であると書く。
「田畑に学ぶべきは、くじけない心であろう。生命力と言い換えてもいい。バイアスがかかるほど、反発のバネが働く。
熊野と沖縄は相似形に映る。田畑の起伏に富む軌跡は、アララガマ精神そのものではないか。
アララガマとは、宮古島の方言で「なにくそ」の意だ。熊野は、廃藩置県により本来ひとつであるべき牟婁四郡が
和歌山県と三重県に分断された。廃仏毀釈で多くの寺院・修験道の堂宇が破却され、大逆事件では郷土の誉れ高い人々が
国家によって惨殺された。中央政府によって、理不尽な扱いをされてきた点では同類だ。
熊野も沖縄も、明治維新以来、良い目にあったことに乏しい土地である」
「まことに差別の問題は、ややこしい。ひとより優越した存在でありたい。この意識が根源的な〈生存の本能〉に根ざしているからだろうか。
古来、死者をホフル(葬る)のも、カミや霊をハフル(祝る)のも、畜獣をホフル(屠る)のも同義である。
これらは異界と現世をつなぐ行為であり、その接点に立つ者は畏怖の対象だった。畏怖は差別ときわめて近似の感情である」
「宮古島の人々は、沖縄本島の人々に搾取されつづけた。琉球王朝による人頭税が、その一例だ。民俗学者・谷川健一はこう指摘する。
〈首里城が沖縄のシンボルなんて、とんでもないことでしょう。宮古・八重山諸島の人々にとって、首里城こそ、代々の祖先をソテツ地獄
(ソテツの実で飢えを凌ぐ飢餓生活)に追い込んできた圧政の象徴そのもの〉という。
二千円札に描かれている守礼の門は、苦々しく唾棄すべき対象なのだ」
平準化・均質化する社会の中で、差別も【無きモノ】へ葬り去られようとしている。
過去を過去とし、忘れ去ることは簡単だ。しかし、そのことによって人間の本質も隠蔽しようとしていないか?
【ひとより優越した存在でありたい】…この〈生存の本能〉と呼ばれるところから、人間の歴史は逃れることができない。
形骸化した「天皇制」もまさしくこの本能から派生した制度であり、「貴が在るところ、賤あり」の現実なのだ。
その本質を見つめずして「天皇制」を語ることは、敗戦を見つめずして「改憲」を語るに等しい。
この問題は、表裏一体である。
猿田彦神社の後にある「御神田」。
東京千代田区の神田もこの「しんでん=神の田んぼ」から来ている。
米の種類は「イセヒカリ」と呼ばれるオリジナルなもの。
「こしひかり」から突然変異で生まれた伊勢独自の品種。
ここで獲れた米はすべて神に供えられる。
だから、新米を食す機会はない…と宮司さん。
とにかく、この場所に来たときが、一番清々しい気分になった。
なんといっても、空気が流れていた。淀み一切無し。
農耕民族の神は、このように一粒の米を700粒に増やす豊饒の力でもって、
この国の民に富をもたらせてくれたのだと、あらためて有り難く思った。
東京千代田区の神田もこの「しんでん=神の田んぼ」から来ている。
米の種類は「イセヒカリ」と呼ばれるオリジナルなもの。
「こしひかり」から突然変異で生まれた伊勢独自の品種。
ここで獲れた米はすべて神に供えられる。
だから、新米を食す機会はない…と宮司さん。
とにかく、この場所に来たときが、一番清々しい気分になった。
なんといっても、空気が流れていた。淀み一切無し。
農耕民族の神は、このように一粒の米を700粒に増やす豊饒の力でもって、
この国の民に富をもたらせてくれたのだと、あらためて有り難く思った。
二見興玉神社は、この夫婦岩を鳥居に見立て、沖合700mほどの海中にある
猿田彦神社の興玉神石をご神体とする元々は自然信仰=太陽信仰の神社。
この興玉というのも「沖会いにある御霊(魂)」を当てた字である。
異説もあるが、要は伊勢に古代あった太陽神の祖型だと思われる。
「興玉」は後付けだろう。猿田彦と習合させたのも何かの企てかもしれない。
純粋に太陽を祀る場所だと思う。
猿田彦神社の興玉神石をご神体とする元々は自然信仰=太陽信仰の神社。
この興玉というのも「沖会いにある御霊(魂)」を当てた字である。
異説もあるが、要は伊勢に古代あった太陽神の祖型だと思われる。
「興玉」は後付けだろう。猿田彦と習合させたのも何かの企てかもしれない。
純粋に太陽を祀る場所だと思う。
恥部をさらしたダンサー、天宇受売命を祀る。
そのことから芸能の神として崇められているらしい。
佐瑠女とは猿田彦の女、猿女を婉曲した表現。
神道の命名は面白いほどに、
このような当て字による表現の婉曲がみられる。
そのことから芸能の神として崇められているらしい。
佐瑠女とは猿田彦の女、猿女を婉曲した表現。
神道の命名は面白いほどに、
このような当て字による表現の婉曲がみられる。