くるまも鉄道も無かった江戸時代。
いつも気になるのは、物流はどうなっていたのだろう、ということです。
そこで、数回に分けて江戸時代における遠隔地間のものの流れを書いてみようと思います。
第1回は、飛脚。

江戸時代、今の郵便や電話の役目をしていたのが飛脚です。
江戸時代になって五街道や宿場が整備されると同時に、
飛脚による通信制度も発展していきました。
ひとことで飛脚といっても、継飛脚(つぎびきゃく)と呼ばれる公儀の飛脚、
各藩が江戸藩邸を結んで走らせた大名飛脚、
そして一般大衆が利用出来るように作られた町飛脚などの種類がありました。
それでは彼等はどのように、そのくらいの時間で届けていたのでしょうか。
基本的には江戸~大坂まで片道30日かかるのがフツウだったそうで、
これを「並便り」と称しました。
早く届けたい場合などには、現在の宅配便にもみられるように
速達便が存在し、所要10日の「十日限」(とうかぎり)、
6日の「六日限」あるいは「早便り」などがありました。
でも実際は宿場での停留や物流の物理的増加により
2~3日の延着は当たり前で確実性に欠くため、
江戸~大坂を6日間できっちり走りきる定期便(!)、
「定飛脚(じょうびきゃく)」が登場し、
これらは「定六」または「正六」と呼ばれました。
さらに早い飛脚には「四日限仕立飛脚」を選ぶことが出来ましたが、
料金は相当高かったとのこと。今も昔も、速達に追加料金を出すのは同じなんですね。
でも一番速かったのは前述の公儀の飛脚、継飛脚。
彼等は二人一組で宿駅ごとにリレーして走り、
一番速い場合では江戸~京都間は片道70時間ほどで結んだそうです。
その後明治時代に入っても飛脚は手紙・小荷物の輸送を続けていましたが、
明治4年(1871)に郵便制度が発足したことで手紙や書状の輸送が出来なくなり、
飛脚業者は結束して陸運会社を設立していったとのことでした。
>>素朴な疑問...なぜ馬を使わなかったのでしょうね。
馬なら、もっと早く届けられたと思うのですが...。
鎌倉時代には鎌倉飛脚・六波羅飛脚(ろくばらひきゃく)などがあり、
これらの飛脚は馬を用いていたそうですが...。
>>ちなみに全区間通しで一人で走る飛脚もいたそうな...って
片道500キロ以上!間寛平も真っ青です@o@










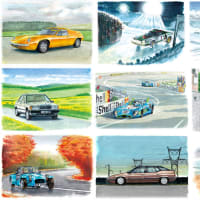
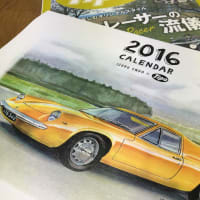
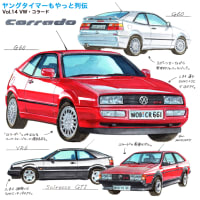




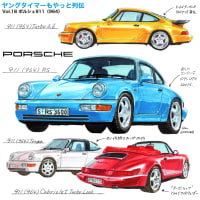








私のブログも、こういうネタを加えると、深みが増していいですね。
今後も参考にさせて頂きます。
>参考に
いえいえ、支離滅裂な僕そのものなんですよ、浅く広くの人間なもので...(汗
江戸時代ってオモシロイです。
何も無かった時代と思われがちですけど、
いまよりも豊かな時代だったと思える部分も多かったりします^^
学生時代、「歴史って全然たのしくない
な~」と思って全然勉強しませんでしたが、
きっとこういう話ならもう少し楽しかった
気がします。 それとも今聞くからいいの
かな!?(笑)
宅急便やさんのロゴが飛脚なのは、正統
後継者ってことですね~!!
歴史の授業って「年表の歴史」を眺めて覚えるだけなんですよね。
なぜ出来事が起こったのかを、その時点での横時間軸で見ていくとツナガリが出来て面白いです。
ちなみに、飛脚のマークの宅配便は、実際にはそんなに古い会社ではないです。
イメージとして飛脚図案を採用したらしいですよ^^
そんなに古くなかったです^;
「年表」ありましたねー。でも江戸とか近代
の部分は扱いが小さかった気がします。
武士とか古すぎてわからんよ~と嘆いてました(笑)
>年表
たった数頁で俯瞰的に眺めるしかないので年表って覚えられないんですよねえ(泣