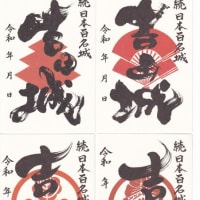お城検索は→こちら
天正8年(1580)袋田と呼ばれていたこの地に初めて城を築いたのは、柴田勝家の一族、勝安である。勝康は九頭竜川の河岸段丘である七里壁や、北側に広がる沼地などを利用して城を築き、勝山支配の拠点とした。勝安の築いた城は、元和元年(1615)の徳川幕府による一国一城令により壊されたようである。以後その跡地には代々の代官の館が建てられる程度であった。勝山において城郭と城下町が整備されてくるのは、元禄4年(1691)に小笠原貞信が入封してからである。貞信は2万2777石をもって美濃国高須から勝山に入封した。当時勝山には城跡しかなかったので、貞信は幕府に対し築城の許可を願い出たが、実際に許可が出たのは宝永6年(1709)7月、二代信辰の代になってからである。信辰はまず、本丸の普請に取り掛かった。古い堀を掘り返したり、土居を築いたりして一応その形を整えた。しかし財政が続かなかったようで、その後の工事は中断した。工事が再開されたのは、およそ60年後の明和7年(1770)五代信房の時である。信房は二の丸を築き、藩主の御殿をそこに移転した。七代長貴は幕府の若年寄りという要職に就いたが、藩の財政は出費がかさみ厳しかった。そのうえ、文政5年(1822)には本丸から出火し、門・高平・土蔵を残して全焼した。この時は町や村々からの見舞金や手伝いによって、瓦や檜皮葺の御殿が再建された。また長貴の代には、二の丸北部の未完成部分が仕上げられ、築城からおよそ120年が経過してようやく当初の計画に近い形の城郭が出来上がった。しかし、蔀曲輪と東馬出は造られず、天守閣も築かれることは無かった。
八代長守の時に明治維新を迎えたが、城郭の建物等は売りに出され、天守台と本丸の堀の一部を残し埋め立てられた。ここには永く小山状の天守台があり、市民から「お天守」と呼ばれ親しまれてきたが、昭和42年(1967)の市民会館建設に際し削平された。現在その跡地には、長守と長育の筆による「勝山城址之碑」が残るのみである。(福井・勝山日本遺産活用推進協議会)、、、現地説明板より
今回は越前大野を訪ねたついでに、勝山・松岡(永平寺町)の越前国、福井藩ゆかりの地を歩いてみることにした。
【勝山城は】
前記の通り、平城ゆえ明治維新後の急速な開発により跡形が無くなるほどに、その姿を替えている。
宝永6年の勝山城再建絵図に現在の地図を重ね合わせたもの、、、現地案内板より(一部加筆)

本丸は、現在の市民会館と市役所が建つ辺り

かつて小山状の天守台跡があった場所は削平され、市民会館となっている

その一角に「勝山城址之碑」が建立されている

「勝山城址之碑」
勝山藩主小笠原長守(七代)と八代長育(最後の藩主)の筆による表書きと裏書

二の丸跡
藩庁や御殿があったと思われる場所は、現在児童公園や教育会館前の中央公園となっています

「東御門橋石碑」
市役所から県道17号線に至る交差点辺りが、城郭東側外堀に架かる東御門橋であった。
図面ではこの辺りに「東馬出」が造られる計画だったが未完で終わっている。

東側外堀と思われる水路
県道17号線と平行に流れている水路は、かつて城郭東面の外堀だった思われる。

この水路を辿って教育会館の裏手まで細い路地を進んでみた。そこは教育会館(二の丸)より一段低い土地で、干上がった外堀の底地である事が伺われる。

当時の外堀は水路に姿を変え、二の丸から未完の蔀曲輪方向へと流れている。

【勝山城】
《》
名称(別名);袋田城
所在地;〒911-0804 福井県勝山市元町1丁目1-1
城地種類;梯郭式平城
築城年代;天正8年(1580年)
築城者;柴田勝安
主な城主;柴田氏、松平氏、小笠原氏ほか
文化財区分;なし
近年の主な復元等;
天守の現状、形態;
※出典、、、
地図;
明治維新後に城内の建築物などが売却に付された。そのうち藩校である「成器堂」の門や土蔵・講堂などが移築、現存していると知り訪ねてみた。
【神明神社社務所】
市指定文化財旧成器堂講堂
天保12年(1841)9月に勝山城追手筋(現在の勝山商工会議所辺り)に建てられた藩校の講堂で、明治44年(1911)この地に移築されたものである。瓦には勝山藩主小笠原家の家紋である「三階菱」があり、外観はほとんど当時のままである。
成器堂は、もともとは読書道と言われ、藩医秦魯斎の熱意と進言を取り入れた家老林毛川の努力によって建てられたものである。(勝山市教育委員会)、、、神明神社案内看板より



神明神社本殿

【神明神社】
住所;福井県勝山市元町1丁目19-24
地図;
【今井家】
市指定文化財旧成器堂の門と土蔵
この門と土蔵は、江戸時代末期に勝山藩の藩校として建てられた成器堂の遺構である。成器堂は主に藩士の子弟教育のため、天保12年(1841)に勝山城三の丸の西側(現在の元町1丁目)に建てられた読書堂に由来する。2年後には成器堂と改称され、弘化4年(1847)にすべての建物が完成した。以後、この成器堂からは多くの優秀な人材が輩出された。
明治に入ると成器堂の建物と建学精神は成器小学校に受け継がれた。古くなった藩校の建物は、新校舎建設に際し解体されたが、今井家が門と土蔵を買い取りこの地に移した。
現存する成器堂の建物の遺構は、この他に講堂(勝山神明神社社務所)と演武寮(荒土町布市の道場)がある。全国的に藩校の遺構は少なく、成器堂のように多くの建物が残っている例は珍しい。勝山市教育委員会、、、今井家説明看板より


場所;福井県勝山市郡町2丁目
地図;個人の住宅に面していますので特段の配慮が必要です

勝山で「勝山城」と言えばこちら↓が有名(笑)
勝山で生まれた大阪相互タクシーの創業者多田清文氏が勝山市活性化のために建てた勝山城と越前大仏は当時大きな話題となりました。

【勝山城博物館】
KATUYAMA CASTLE MUSEUM
公益財団法人多田清文教育記念財団

webページは→こちら
住所;福井県勝山市平泉寺町平泉寺町85-26-1
開館時間;9:30~16:30
休館日;水曜日
入館料;大人700円 小中高生260円 (勝山市在住者2割引、要証明)
石垣から一番の上の鯱までの高さは57.8mあり、天守の形に建てられた建築物としては最も高いものです。

石垣は花崗岩(御影石)で6,500個(7,500トン)を積み上げてあります。石垣の高さは15メートルあります。

表面に9頭の巨大な龍の彫刻が施されています。通常城郭の石垣にはこういった彫刻はありませんが、当館が博物館であると認識いただくためと、勝山市を流れる九頭竜川及び恐竜化石にちなんで施したものです。、、、以上HP建物の概要より引用

なお実業家多田清文氏は「勝山城」の他にも、地元勝山に「越前大仏」という巨大な施設を昭和62年5月28日に落慶させていらっしゃいます。
webページは→こちら

天正8年(1580)袋田と呼ばれていたこの地に初めて城を築いたのは、柴田勝家の一族、勝安である。勝康は九頭竜川の河岸段丘である七里壁や、北側に広がる沼地などを利用して城を築き、勝山支配の拠点とした。勝安の築いた城は、元和元年(1615)の徳川幕府による一国一城令により壊されたようである。以後その跡地には代々の代官の館が建てられる程度であった。勝山において城郭と城下町が整備されてくるのは、元禄4年(1691)に小笠原貞信が入封してからである。貞信は2万2777石をもって美濃国高須から勝山に入封した。当時勝山には城跡しかなかったので、貞信は幕府に対し築城の許可を願い出たが、実際に許可が出たのは宝永6年(1709)7月、二代信辰の代になってからである。信辰はまず、本丸の普請に取り掛かった。古い堀を掘り返したり、土居を築いたりして一応その形を整えた。しかし財政が続かなかったようで、その後の工事は中断した。工事が再開されたのは、およそ60年後の明和7年(1770)五代信房の時である。信房は二の丸を築き、藩主の御殿をそこに移転した。七代長貴は幕府の若年寄りという要職に就いたが、藩の財政は出費がかさみ厳しかった。そのうえ、文政5年(1822)には本丸から出火し、門・高平・土蔵を残して全焼した。この時は町や村々からの見舞金や手伝いによって、瓦や檜皮葺の御殿が再建された。また長貴の代には、二の丸北部の未完成部分が仕上げられ、築城からおよそ120年が経過してようやく当初の計画に近い形の城郭が出来上がった。しかし、蔀曲輪と東馬出は造られず、天守閣も築かれることは無かった。
八代長守の時に明治維新を迎えたが、城郭の建物等は売りに出され、天守台と本丸の堀の一部を残し埋め立てられた。ここには永く小山状の天守台があり、市民から「お天守」と呼ばれ親しまれてきたが、昭和42年(1967)の市民会館建設に際し削平された。現在その跡地には、長守と長育の筆による「勝山城址之碑」が残るのみである。(福井・勝山日本遺産活用推進協議会)、、、現地説明板より
今回は越前大野を訪ねたついでに、勝山・松岡(永平寺町)の越前国、福井藩ゆかりの地を歩いてみることにした。
【勝山城は】
前記の通り、平城ゆえ明治維新後の急速な開発により跡形が無くなるほどに、その姿を替えている。
宝永6年の勝山城再建絵図に現在の地図を重ね合わせたもの、、、現地案内板より(一部加筆)

本丸は、現在の市民会館と市役所が建つ辺り

かつて小山状の天守台跡があった場所は削平され、市民会館となっている

その一角に「勝山城址之碑」が建立されている

「勝山城址之碑」
勝山藩主小笠原長守(七代)と八代長育(最後の藩主)の筆による表書きと裏書

二の丸跡
藩庁や御殿があったと思われる場所は、現在児童公園や教育会館前の中央公園となっています

「東御門橋石碑」
市役所から県道17号線に至る交差点辺りが、城郭東側外堀に架かる東御門橋であった。
図面ではこの辺りに「東馬出」が造られる計画だったが未完で終わっている。

東側外堀と思われる水路
県道17号線と平行に流れている水路は、かつて城郭東面の外堀だった思われる。

この水路を辿って教育会館の裏手まで細い路地を進んでみた。そこは教育会館(二の丸)より一段低い土地で、干上がった外堀の底地である事が伺われる。

当時の外堀は水路に姿を変え、二の丸から未完の蔀曲輪方向へと流れている。

【勝山城】
《》
名称(別名);袋田城
所在地;〒911-0804 福井県勝山市元町1丁目1-1
城地種類;梯郭式平城
築城年代;天正8年(1580年)
築城者;柴田勝安
主な城主;柴田氏、松平氏、小笠原氏ほか
文化財区分;なし
近年の主な復元等;
天守の現状、形態;
※出典、、、
地図;
明治維新後に城内の建築物などが売却に付された。そのうち藩校である「成器堂」の門や土蔵・講堂などが移築、現存していると知り訪ねてみた。
【神明神社社務所】
市指定文化財旧成器堂講堂
天保12年(1841)9月に勝山城追手筋(現在の勝山商工会議所辺り)に建てられた藩校の講堂で、明治44年(1911)この地に移築されたものである。瓦には勝山藩主小笠原家の家紋である「三階菱」があり、外観はほとんど当時のままである。
成器堂は、もともとは読書道と言われ、藩医秦魯斎の熱意と進言を取り入れた家老林毛川の努力によって建てられたものである。(勝山市教育委員会)、、、神明神社案内看板より



神明神社本殿

【神明神社】
住所;福井県勝山市元町1丁目19-24
地図;
【今井家】
市指定文化財旧成器堂の門と土蔵
この門と土蔵は、江戸時代末期に勝山藩の藩校として建てられた成器堂の遺構である。成器堂は主に藩士の子弟教育のため、天保12年(1841)に勝山城三の丸の西側(現在の元町1丁目)に建てられた読書堂に由来する。2年後には成器堂と改称され、弘化4年(1847)にすべての建物が完成した。以後、この成器堂からは多くの優秀な人材が輩出された。
明治に入ると成器堂の建物と建学精神は成器小学校に受け継がれた。古くなった藩校の建物は、新校舎建設に際し解体されたが、今井家が門と土蔵を買い取りこの地に移した。
現存する成器堂の建物の遺構は、この他に講堂(勝山神明神社社務所)と演武寮(荒土町布市の道場)がある。全国的に藩校の遺構は少なく、成器堂のように多くの建物が残っている例は珍しい。勝山市教育委員会、、、今井家説明看板より


場所;福井県勝山市郡町2丁目
地図;個人の住宅に面していますので特段の配慮が必要です

勝山で「勝山城」と言えばこちら↓が有名(笑)
勝山で生まれた大阪相互タクシーの創業者多田清文氏が勝山市活性化のために建てた勝山城と越前大仏は当時大きな話題となりました。

【勝山城博物館】
KATUYAMA CASTLE MUSEUM
公益財団法人多田清文教育記念財団

webページは→こちら
住所;福井県勝山市平泉寺町平泉寺町85-26-1
開館時間;9:30~16:30
休館日;水曜日
入館料;大人700円 小中高生260円 (勝山市在住者2割引、要証明)
石垣から一番の上の鯱までの高さは57.8mあり、天守の形に建てられた建築物としては最も高いものです。

石垣は花崗岩(御影石)で6,500個(7,500トン)を積み上げてあります。石垣の高さは15メートルあります。

表面に9頭の巨大な龍の彫刻が施されています。通常城郭の石垣にはこういった彫刻はありませんが、当館が博物館であると認識いただくためと、勝山市を流れる九頭竜川及び恐竜化石にちなんで施したものです。、、、以上HP建物の概要より引用

なお実業家多田清文氏は「勝山城」の他にも、地元勝山に「越前大仏」という巨大な施設を昭和62年5月28日に落慶させていらっしゃいます。
webページは→こちら