4月は仕事の始まる月、名鉄の出札口には臨時の定期券受付カウンターが設けられ、帰り電車を降りた若者たちが列をつくる。今日はもう4日だから、長さは大分減っているが、それでも列は続いている。帰りはまだしも朝の出勤電車は結構な込み具合なのだろう。
こちらも一つ仕事を始めた。といってもNHKラジオの語学講座を4月からロシア語に変えたということ。大学時代に初級クラスでしばらく聴講したことがあったが、キリル文字からして、我が頭脳はもうすっかり初期化が出来ている。難しいロシア語文法に最後までついていけるかちょっと不安だ。それでもポッドキャストという文明の利器が出来たのはありがたい。一日15分間なら、認知症脳も記憶のかけらを残してくれるだろう。
ロシア語はメジャーな言語だが、世界中には自分の聞いたこともないマイナー言語がいっぱいあるのだろう。今日の中日夕刊「世界の街海外リポート」には「言葉の違いに複雑さ」というタイトルの短文が載っている。寄稿はタイ特派員だろうか。
人種差別問題で大量の難民を出し世界中の注目を浴びたミャンマー西部のラカイン州。特派員氏は少数民族ラカインの子どもたちを取材しようとバングラデシュにも近いチュイテー村を訪れた。多数派ビルマ族の助手を通訳兼で連れていったらしい。ラカインとヤンゴンでは同じミャンマー語でも発音やアクセントが違うらしく助手の通訳も大苦戦。ラカイン方言は地理的に近いバングラのベンガル語やインドのヒンズー語の影響もあるという。当然だろう。
問題のロヒンギャ難民もミャンマー語ではなく独自の言葉を使うようで、バングラのベンガル語では通じない。特派員氏も難民の取材をするのにロヒンギャ語のわかる通訳を探すのが一苦労だったと書いている。さらに、ミャンマーには100を超える少数民族が暮らすといい、互いが深刻な対立の中にあって和平は道半ば。問題はロヒンギャだけではないのだ。
オウン・サン・スーチー(ラカインではアウンとは発音しないらしい)はビルマ族だからロヒンギャ難民の虐待には無関心だと世界が非難したのだが、言葉の問題ひとつをとっても、ミャンマー語ではまったく通じない、人種の違う同国人がたくさん暮らしているという「内政問題」を考えれば、ことはそう単純ではないというのが判ってくる。
標準日本語を日本人も在留の外国人も共通言語として意思疎通のできるありがたさ。さしずめロシア語で感謝するなら「オーチン スパシーバ」である。
最新の画像[もっと見る]











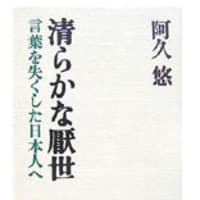






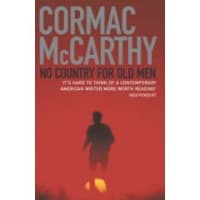
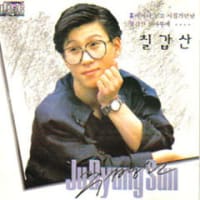
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます