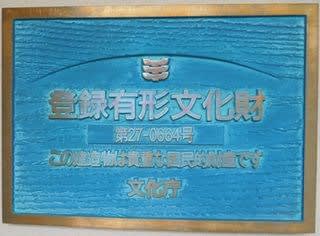昨日は、第5回関西花の寺で久安寺(池田市)・観音寺(福知山市)・永澤寺(三田市)へ。
家を出る時には雨、難波出発7時45分、梅田経由して高速道を北上。
最初の訪問地久安寺へ。
小雨の中ご住職のお出迎え、立派な楼門の先にはアジサイの参道、受付前には秀吉お手植えのカヤの大木。
本堂の奥の舎利殿涅槃堂で法話をお聞きしましたが、本堂も舎利殿涅槃堂も素晴らしい建物で、堂内ではご住職の声が反響するのにも併せて感嘆の声が上がりました。


久安寺
高野山真言宗。神亀2年(725年)行基の開創。
本尊千手観音立像。楼門は重文。
弘法大師も再興に尽力、久安1年(1145年)近衛帝の祈願所として、楼門・金堂・塔等伽藍49院の坊舎を再興し久安寺と称す。


豊臣秀吉、三光神を祀り月見茶会を親しんだ。
その後衰退を繰り返す中で法灯を護持。昭和興隆事業により諸堂を造営し庭園の整備、旧伽藍跡に霊園および仏塔を造営。
関西花の寺第12番霊場。


境内の池には、モリアオガエルが産卵していて池にせり出した枝には大きな泡の塊を見ることができました。
思いがけず立派な寺院に出会い、満開のアジサイと沙羅(夏椿)の花を楽しみました。


そこから福知山まで約1時間、昼食後観音寺へ。
雨は上がり青空も覗き日焼け対策が必要かと思えるほどの上天気の中、門前の山肌には一面のアジサイを見ながら山門へ。
アジサイの花に囲まれた山門をくぐり、参道脇のアジサイの花の道を進み本堂へ。


観音寺
高野山真言宗。
本尊十一面千手千眼観世音は、33年毎に開帳される秘仏。
養老4年(720年)インドの帰化僧法道仙人が十一面千手千眼観世音菩薩を刻んで草堂に安置されたのが開基。
応和元年(961年)空也上人が七堂伽藍を建立。
鎌倉時代、北条時頼、貞時の庇護を受け繁栄、しかし明智光秀の焼き討ちで全て灰燼に帰した。
江戸時代には本堂を再建され、現在はアジサイ100種1万株が全山を覆い丹波のアジサイ寺として知られる。
関西花の寺第1番霊場。


境内のアジサイの山を上って見晴らし台へ行ってみましたが取り立てて言うほどの景色でもありませんでした。
が、そこに書かれていた「何もない事=無事」の言葉が印象的でした。人生何もないのが一番、と添えてありました。
ご住職の話しの中に銀杯草が咲いているとのことでしたので見に行ってみました。
真っ白で径2~3センチ位の花が地面間近で咲いていました。
益々陽射しが強まる中、永沢寺へ。
3カ所ある入口の真ん中は勅使門。


永沢寺(ようたくじ)
曹洞宗。応安年間(1370年頃)後円融天皇の五州の太守細川頼之卿が七堂伽藍を建立したのが開創。
本尊釈迦三尊。
摂津と丹波両国にまたがっていた所から、通称摂丹境と呼ばれる。
この辺りの地名は、漢音での発音通り「えいたくじ」と呼ばれる。
関西花の寺第11番霊場。


この寺のこの時期の花はショウブで、土、日曜日には近郷からの見物者が押し寄せ歩くのもままならないとのことです。
ご住職の法話の際、本寺は標高560mの高地にある為植物の開花が少し遅いとのこと。
1万坪の敷地に約650種・300万本のほとんどが咲いている状態のショウブ園を散策。
ショウブ園は回遊式になっていて、満開のショウブの中を板敷の通路伝いに巡りますので、花は触れる距離で見ることができ途中の東屋や水車も趣を増していて、大変気持ちの良い時間が過ごせました。



大阪に向け5時30分出発、梅田に着くのは7時を回るかと思っていましたら梅田着6時40分、難波には7時着。
まったく渋滞に遭わず極めて順調に帰ってきました。
今回は満開のアジサイとショウブ、それに沙羅と銀杯草の白い花にも出会うことができ、また雨も上がるという幸運にも恵まれた素晴らしい旅で、相棒共々心が満たされた一日となりました。
家を出る時には雨、難波出発7時45分、梅田経由して高速道を北上。
最初の訪問地久安寺へ。
小雨の中ご住職のお出迎え、立派な楼門の先にはアジサイの参道、受付前には秀吉お手植えのカヤの大木。
本堂の奥の舎利殿涅槃堂で法話をお聞きしましたが、本堂も舎利殿涅槃堂も素晴らしい建物で、堂内ではご住職の声が反響するのにも併せて感嘆の声が上がりました。


久安寺
高野山真言宗。神亀2年(725年)行基の開創。
本尊千手観音立像。楼門は重文。
弘法大師も再興に尽力、久安1年(1145年)近衛帝の祈願所として、楼門・金堂・塔等伽藍49院の坊舎を再興し久安寺と称す。


豊臣秀吉、三光神を祀り月見茶会を親しんだ。
その後衰退を繰り返す中で法灯を護持。昭和興隆事業により諸堂を造営し庭園の整備、旧伽藍跡に霊園および仏塔を造営。
関西花の寺第12番霊場。


境内の池には、モリアオガエルが産卵していて池にせり出した枝には大きな泡の塊を見ることができました。
思いがけず立派な寺院に出会い、満開のアジサイと沙羅(夏椿)の花を楽しみました。


そこから福知山まで約1時間、昼食後観音寺へ。
雨は上がり青空も覗き日焼け対策が必要かと思えるほどの上天気の中、門前の山肌には一面のアジサイを見ながら山門へ。
アジサイの花に囲まれた山門をくぐり、参道脇のアジサイの花の道を進み本堂へ。


観音寺
高野山真言宗。
本尊十一面千手千眼観世音は、33年毎に開帳される秘仏。
養老4年(720年)インドの帰化僧法道仙人が十一面千手千眼観世音菩薩を刻んで草堂に安置されたのが開基。
応和元年(961年)空也上人が七堂伽藍を建立。
鎌倉時代、北条時頼、貞時の庇護を受け繁栄、しかし明智光秀の焼き討ちで全て灰燼に帰した。
江戸時代には本堂を再建され、現在はアジサイ100種1万株が全山を覆い丹波のアジサイ寺として知られる。
関西花の寺第1番霊場。


境内のアジサイの山を上って見晴らし台へ行ってみましたが取り立てて言うほどの景色でもありませんでした。
が、そこに書かれていた「何もない事=無事」の言葉が印象的でした。人生何もないのが一番、と添えてありました。
ご住職の話しの中に銀杯草が咲いているとのことでしたので見に行ってみました。
真っ白で径2~3センチ位の花が地面間近で咲いていました。
益々陽射しが強まる中、永沢寺へ。
3カ所ある入口の真ん中は勅使門。


永沢寺(ようたくじ)
曹洞宗。応安年間(1370年頃)後円融天皇の五州の太守細川頼之卿が七堂伽藍を建立したのが開創。
本尊釈迦三尊。
摂津と丹波両国にまたがっていた所から、通称摂丹境と呼ばれる。
この辺りの地名は、漢音での発音通り「えいたくじ」と呼ばれる。
関西花の寺第11番霊場。


この寺のこの時期の花はショウブで、土、日曜日には近郷からの見物者が押し寄せ歩くのもままならないとのことです。
ご住職の法話の際、本寺は標高560mの高地にある為植物の開花が少し遅いとのこと。
1万坪の敷地に約650種・300万本のほとんどが咲いている状態のショウブ園を散策。
ショウブ園は回遊式になっていて、満開のショウブの中を板敷の通路伝いに巡りますので、花は触れる距離で見ることができ途中の東屋や水車も趣を増していて、大変気持ちの良い時間が過ごせました。



大阪に向け5時30分出発、梅田に着くのは7時を回るかと思っていましたら梅田着6時40分、難波には7時着。
まったく渋滞に遭わず極めて順調に帰ってきました。
今回は満開のアジサイとショウブ、それに沙羅と銀杯草の白い花にも出会うことができ、また雨も上がるという幸運にも恵まれた素晴らしい旅で、相棒共々心が満たされた一日となりました。