長谷部浩さんの「野田秀樹の演劇」を読みました。長谷部浩さんは歌舞伎関係の本や劇評などもいろいろ書いていらっしゃるので、歌舞伎ファンの方も長谷部さんの名前はご存じの方が多いと思います。私も三津五郎さんの「歌舞伎の楽しみ」「踊りの楽しみ」、勘三郎さんと三津五郎さんのことを書いた「天才と名人」、菊ちゃんのことを書いた「菊之助の礼儀」を読んでいます。
長谷部さんはご自身のWebsiteをお持ちで、野田さんのことを書いた本もあるなとチラ見しながら、そこまで「読みたい!」とは思ってなかったのですが、アウトレットブックとして半額で売ってたのでついポチッとしてしまいました。2014年出版となってますが、元々は2005年に出版された「野田秀樹論」の増補版だそうです。
内容紹介です。
↑上を見て、野田秀樹ってもう40年も経つんですね、ってちょっと遠い目をしてしまいました。最初に見たのが大学を卒業してすぐくらいだったので、そのくらいになるんでしょうか。夢の遊眠社の関西初公演で、芦屋のルナホールで「野獣降臨(のけものきたりて)」を見ました。クロージングはみんなで「長崎は今日も雨だった」を合唱するのがお約束で、何となくまだ学生劇団のしっぽみたいなのがありました。それがあれよあれよという間に人気劇団となり、舞台装置や衣装もどんどん洗練されていき、「すっげー」と思いながら大阪公演はほぼ見てたような気がします。
1992年に「劇団夢の遊眠社」を解散した後、ロンドン留学を経て、「NODA・MAP」となります。この本はNODA・MAP以降の活動を取り上げていらっしゃいます。引き続き、NODA・MAPも見てるんですが、大阪で拠点とされていた近鉄劇場や近鉄アート館が閉館してしまい、大阪での上演がなくなってからはしばらく私の野田さん観劇も途絶えます。もちろん、野田さんが「何かする」と必ず話題になるのですが、さすがに東京遠征するほどファンってわけでもなく、「あぁ、やったはるなぁ」って思いながらニュースを見ておりました。
なので、本の中で取り上げられているお芝居も、見たのもあるし、見てないのもあるし、って感じです。それぞれのお芝居について俳優さんの名前やストーリーだけなく、演出の意図なんかも詳しく書いていらっしゃって、「見たかったなぁ」と思うのもいくつもありました。やっぱりお江戸ですよね。
NODA・MAPだけでなく勘三郎さん(当時勘九郎さん)との歌舞伎も取り上げられています。「野田版 研辰の討たれ」と「野田版 鼠小僧」です。どうしても歌舞伎の箇所は熱心に読んでしまいます。「研辰」は勘三郎さんの襲名披露で、「鼠小僧」はシネマ歌舞伎で見ています。「研辰」の初演の初日は歌舞伎座でカーテンコールがあったそうで、野田さんも舞台に上がられたそうです。こういうのに出会えるといいですよね。
「野田版」を見た後、「野田版ぢゃない研辰」も見ましたが、そんなに大幅にストーリーを変えてなくて「野田さん、そんなにめちゃくちゃしてないのね」と思った記憶があります。来月、シネマ歌舞伎が「野田版 研辰の討たれ」なので、見に行ってみようかと思います。
「パンドラの鐘」以降、野田さんのお芝居には社会的・政治的メッセージが発信されるようになってるそうです。確かに「THE BEE」や一昨年の「Q」は私には難しかったような気がします。そういうのから目を背けちゃいけないんでしょうけれど、できればお芝居はお気楽に見たいと思ってるほうなので…。ただ、メッセージの伝え方が野田さんらしいというか、掛詞・同音異義語・比喩など日本語の面白さを駆使してて、「凄いなぁ」とひたすら感心しまくっています。今年はまた新作があるようなのでそれはぜひ行きたいと思っています。その前に、来月は「パンドラの鐘」がくるので、この本を読んだこともあり、ついポチッとしてしまいました。野田さんの演出ではないのですが。予習して臨みたいと思います。
長谷部さんはご自身のWebsiteをお持ちで、野田さんのことを書いた本もあるなとチラ見しながら、そこまで「読みたい!」とは思ってなかったのですが、アウトレットブックとして半額で売ってたのでついポチッとしてしまいました。2014年出版となってますが、元々は2005年に出版された「野田秀樹論」の増補版だそうです。
内容紹介です。
約40年、演劇界を席巻し続けてきた野田秀樹。近年、多摩美大教授、東京芸術劇場芸術監督就任、話題作も次々に発表し益々進化する彼を、野田作品研究の第一人者が論じる、「野田秀樹論」決定版!
↑上を見て、野田秀樹ってもう40年も経つんですね、ってちょっと遠い目をしてしまいました。最初に見たのが大学を卒業してすぐくらいだったので、そのくらいになるんでしょうか。夢の遊眠社の関西初公演で、芦屋のルナホールで「野獣降臨(のけものきたりて)」を見ました。クロージングはみんなで「長崎は今日も雨だった」を合唱するのがお約束で、何となくまだ学生劇団のしっぽみたいなのがありました。それがあれよあれよという間に人気劇団となり、舞台装置や衣装もどんどん洗練されていき、「すっげー」と思いながら大阪公演はほぼ見てたような気がします。
1992年に「劇団夢の遊眠社」を解散した後、ロンドン留学を経て、「NODA・MAP」となります。この本はNODA・MAP以降の活動を取り上げていらっしゃいます。引き続き、NODA・MAPも見てるんですが、大阪で拠点とされていた近鉄劇場や近鉄アート館が閉館してしまい、大阪での上演がなくなってからはしばらく私の野田さん観劇も途絶えます。もちろん、野田さんが「何かする」と必ず話題になるのですが、さすがに東京遠征するほどファンってわけでもなく、「あぁ、やったはるなぁ」って思いながらニュースを見ておりました。
なので、本の中で取り上げられているお芝居も、見たのもあるし、見てないのもあるし、って感じです。それぞれのお芝居について俳優さんの名前やストーリーだけなく、演出の意図なんかも詳しく書いていらっしゃって、「見たかったなぁ」と思うのもいくつもありました。やっぱりお江戸ですよね。
NODA・MAPだけでなく勘三郎さん(当時勘九郎さん)との歌舞伎も取り上げられています。「野田版 研辰の討たれ」と「野田版 鼠小僧」です。どうしても歌舞伎の箇所は熱心に読んでしまいます。「研辰」は勘三郎さんの襲名披露で、「鼠小僧」はシネマ歌舞伎で見ています。「研辰」の初演の初日は歌舞伎座でカーテンコールがあったそうで、野田さんも舞台に上がられたそうです。こういうのに出会えるといいですよね。
「野田版」を見た後、「野田版ぢゃない研辰」も見ましたが、そんなに大幅にストーリーを変えてなくて「野田さん、そんなにめちゃくちゃしてないのね」と思った記憶があります。来月、シネマ歌舞伎が「野田版 研辰の討たれ」なので、見に行ってみようかと思います。
「パンドラの鐘」以降、野田さんのお芝居には社会的・政治的メッセージが発信されるようになってるそうです。確かに「THE BEE」や一昨年の「Q」は私には難しかったような気がします。そういうのから目を背けちゃいけないんでしょうけれど、できればお芝居はお気楽に見たいと思ってるほうなので…。ただ、メッセージの伝え方が野田さんらしいというか、掛詞・同音異義語・比喩など日本語の面白さを駆使してて、「凄いなぁ」とひたすら感心しまくっています。今年はまた新作があるようなのでそれはぜひ行きたいと思っています。その前に、来月は「パンドラの鐘」がくるので、この本を読んだこともあり、ついポチッとしてしまいました。野田さんの演出ではないのですが。予習して臨みたいと思います。















 よね、と思いながら読んでおりました。お古いことをご存じの方であれば、もっと「あ、これって、あの役者さんよね」っていう楽しみ方もできるのではないかと思いました。
よね、と思いながら読んでおりました。お古いことをご存じの方であれば、もっと「あ、これって、あの役者さんよね」っていう楽しみ方もできるのではないかと思いました。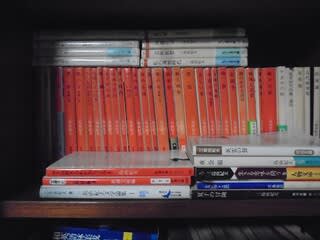


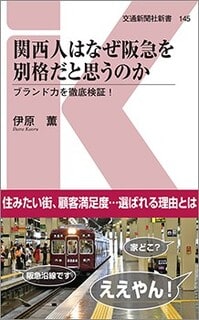


 です。
です。





