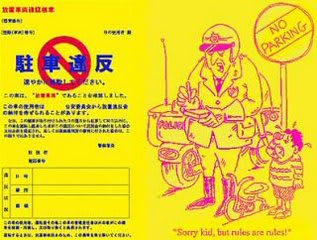ここでは、丼ものについて、関東・関西の比較をしてみたい。
先ず丼ものについて、味付けは変わるが、関東・関西とも同じように日常生活には欠かせない食べ物として定着している。
丼ものの代表格は、東西共「親子丼」といえるが、親子丼発祥の地と言われる、東京人形町の老舗店が今も健在。
親子丼の鶏肉には、秋田比内鶏、名古屋コーチン、奥久慈軍鶏(茨城県久慈郡のしゃも)、兵庫県丹波の地鶏などの旨味と卵の風味を活かした、ローカルだが、絶品の親子丼の数々をイメージするにつけ、思わずよだれが流れ出てしまうほど。
変わった丼どころでは、関西ではポピュラーな「他人丼」は、関東では珍しいと云う。「他人丼」という名前は「親子丼」が鳥肉・鳥卵を使うのに対したもので、鶏肉に変えて、牛肉もしくは豚肉を、玉ねぎなどで煮て卵でとじ、丼飯の上に乗せた丼物の一種で、「開化丼」とも称される。
「きつね丼」とは「カツどん」・「親子丼」と同系統の卵とじ丼の一種。

写真は、典型的な、京風のきつね丼。
「きつね」の名の通り油揚げを入れる、京都発祥と思われる丼もので、タップリとつゆを含んだ揚げと卵のやわらかい風味がマッチして、旨味な一品。
京都独自の丼ものとして、「衣笠丼」があるが、これは刻んだ揚げを玉子でとじたもの。


写真は上から、東京の典型的な天丼及び特に濃いだし汁が特徴の天丼。
天婦羅といえば、「天丼」は東京が主導で、男性が好むタイプ。
大阪と東京メイド天丼の典型的違いは、大阪天丼は薄い出汁でご飯は“びしょびしょ”、 一方東京天丼は少な目の濃い出汁で、ご飯はサラッとゴマ油を半分使うことによって天ぷらが香ばしく、エビも旨みが増し、濃い出汁がエビとナイスマッチングして旨い。
ご飯も出汁が少ないから、米本来の美味しさも楽しめるということで、天丼はどうも東京が勝の丼もの!
他に「うな丼」・「アナゴ丼」なども江戸湾で“とれとれ”の鮮魚を食材とした、江戸前の代表的グルメで、これらも東京の丼ものと云える。
丼で変わったところでは、大阪の「チーズかつ丼」・「おろしかつ丼」・「トマトかつ丼」・「カレーかつ丼」等々、「カツどん」の裾野は広く、その存在感はさすがで、大阪が勝の丼もの!


写真は、大阪日本橋の“こけしとんかつ”店頭の光景、及び安くて旨いカツ丼。
当店ならではの素早く・行届いたサービスは業界の模範として、知名度が高い。
ところで、「牛丼」が売り出されたのは、明治30年代で「牛めし」でデヴュー、場所は、当時東京日本橋に所在した魚河岸に「吉野屋」という、味で評判の牛丼屋があったという。

写真は、吉野家復活の米国産牛の丼。
現在の牛肉チェーン店・吉野家の元祖こそ、牛丼を誕生させたが、実はそれ以前に「牛鍋」が、江戸末期には、すでに大坂で大流行していたと云う。
牛肉大ファンであった“福沢諭吉”は、幕末の大坂でたびたび牛鍋屋ののれんをくぐっていたと云う。
さすが「自由と進取」の町民の街・大坂ならではのハプニングで、当時はまだ禁輸対象の牛肉が、既に大坂の巷で、食されていたことになる。
町民の食・伝統ある牛丼が、今や大手全国チェーン店展開に乗って、全国津々浦々にまで浸透しているとは!!!!!
「すきやねん!」
先ず丼ものについて、味付けは変わるが、関東・関西とも同じように日常生活には欠かせない食べ物として定着している。
丼ものの代表格は、東西共「親子丼」といえるが、親子丼発祥の地と言われる、東京人形町の老舗店が今も健在。
親子丼の鶏肉には、秋田比内鶏、名古屋コーチン、奥久慈軍鶏(茨城県久慈郡のしゃも)、兵庫県丹波の地鶏などの旨味と卵の風味を活かした、ローカルだが、絶品の親子丼の数々をイメージするにつけ、思わずよだれが流れ出てしまうほど。

変わった丼どころでは、関西ではポピュラーな「他人丼」は、関東では珍しいと云う。「他人丼」という名前は「親子丼」が鳥肉・鳥卵を使うのに対したもので、鶏肉に変えて、牛肉もしくは豚肉を、玉ねぎなどで煮て卵でとじ、丼飯の上に乗せた丼物の一種で、「開化丼」とも称される。
「きつね丼」とは「カツどん」・「親子丼」と同系統の卵とじ丼の一種。

写真は、典型的な、京風のきつね丼。
「きつね」の名の通り油揚げを入れる、京都発祥と思われる丼もので、タップリとつゆを含んだ揚げと卵のやわらかい風味がマッチして、旨味な一品。
京都独自の丼ものとして、「衣笠丼」があるが、これは刻んだ揚げを玉子でとじたもの。


写真は上から、東京の典型的な天丼及び特に濃いだし汁が特徴の天丼。
天婦羅といえば、「天丼」は東京が主導で、男性が好むタイプ。
大阪と東京メイド天丼の典型的違いは、大阪天丼は薄い出汁でご飯は“びしょびしょ”、 一方東京天丼は少な目の濃い出汁で、ご飯はサラッとゴマ油を半分使うことによって天ぷらが香ばしく、エビも旨みが増し、濃い出汁がエビとナイスマッチングして旨い。

ご飯も出汁が少ないから、米本来の美味しさも楽しめるということで、天丼はどうも東京が勝の丼もの!
他に「うな丼」・「アナゴ丼」なども江戸湾で“とれとれ”の鮮魚を食材とした、江戸前の代表的グルメで、これらも東京の丼ものと云える。
丼で変わったところでは、大阪の「チーズかつ丼」・「おろしかつ丼」・「トマトかつ丼」・「カレーかつ丼」等々、「カツどん」の裾野は広く、その存在感はさすがで、大阪が勝の丼もの!



写真は、大阪日本橋の“こけしとんかつ”店頭の光景、及び安くて旨いカツ丼。
当店ならではの素早く・行届いたサービスは業界の模範として、知名度が高い。
ところで、「牛丼」が売り出されたのは、明治30年代で「牛めし」でデヴュー、場所は、当時東京日本橋に所在した魚河岸に「吉野屋」という、味で評判の牛丼屋があったという。

写真は、吉野家復活の米国産牛の丼。

現在の牛肉チェーン店・吉野家の元祖こそ、牛丼を誕生させたが、実はそれ以前に「牛鍋」が、江戸末期には、すでに大坂で大流行していたと云う。
牛肉大ファンであった“福沢諭吉”は、幕末の大坂でたびたび牛鍋屋ののれんをくぐっていたと云う。
さすが「自由と進取」の町民の街・大坂ならではのハプニングで、当時はまだ禁輸対象の牛肉が、既に大坂の巷で、食されていたことになる。
町民の食・伝統ある牛丼が、今や大手全国チェーン店展開に乗って、全国津々浦々にまで浸透しているとは!!!!!
「すきやねん!」