最近出版され、下記に紹介している書籍によれば、「関西人は基本的に善悪で物事を考えるのではなく、損得で物事を考える。」とのこと。
この考え方に立てば、大阪で駐車違反がやたら多いことが説明できるし、納得してしまう。
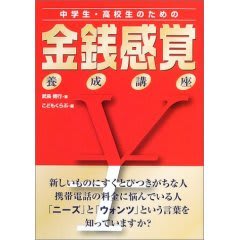
写真は、“金銭感覚”を題材にした、中学生・高校生のための書籍。
金銭感覚について、大阪人に対して「東京人は善悪で物事を考える。」見たいにとれるが、そうではなく、東京人の価値観は、「粋か、野暮か」或いは今風に「カッコ良いか、悪いか」でもよい。
東京浅草に代表される下町っ子、いわゆる“江戸っ子”の価値観は、「粋であること」・「カッコ良いこと」が大事であったと考えられる。
「野暮」とは、「規則だから守る」のではなく、「野暮でカッコ悪いから、しけた事はしない。」という意味。しつこく損得に拘るのは野暮なこと。
「野暮」は、大阪では「無粋」と云う言葉が当たるみたい。
又大阪人は遠慮と云う言葉を知らない。街頭で「ティッシュ」を配っていれば、「兄ちゃん、もっとちょうだい」とねだるが、東京人はノリが悪く、必要ないティッシュはもらわない。
大阪人はケチではなく、ノリが良い。
例えば、大阪人のブランドに対する認識は、「品格」よりも「価格」に重点を置き、「ルイヴィトンやシャネル」は「メーカーもん」として括り、「メーカーもん」の次は「安もん」しかない。
ブランドものは高級品ではなく、値段が高い品物で「メーカーもん」と見て、高級品でも安かったら「安もん」になる。
大阪人は、安く買ったら「メーカーもん」でなくても、絶対自慢する。
安ければ安いほど自慢したがるのは、大阪人の特性で、東京人は安く買えば恥ずかしくて、自慢できないカッコやり。

写真は、大阪人のがめつさをテーマにしたイラスト。
例えば大阪女性が衣服を褒められた時に、衣服そのものより「それを如何に安く買ったか」と云うことに焦点が移り、「すごい」・「見えない」と褒められた時に、満足感をくすぐられることになる。
大阪の場合、値段を聞くのは失礼とか、聞きにくいということもないらしい。
全国に店舗がある百貨店のデータによると、売上げ全体に占めるバーゲンの割合は、大阪が3割vs.東京が2割と云うが、分かるような気がする。
要は、大阪人はがめつく、なかなか堅実で、現実主義を生活信条としていると云える。
「ええやん!」
この考え方に立てば、大阪で駐車違反がやたら多いことが説明できるし、納得してしまう。
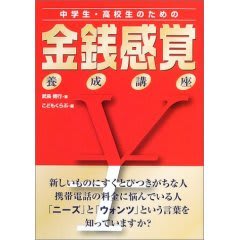
写真は、“金銭感覚”を題材にした、中学生・高校生のための書籍。
金銭感覚について、大阪人に対して「東京人は善悪で物事を考える。」見たいにとれるが、そうではなく、東京人の価値観は、「粋か、野暮か」或いは今風に「カッコ良いか、悪いか」でもよい。
東京浅草に代表される下町っ子、いわゆる“江戸っ子”の価値観は、「粋であること」・「カッコ良いこと」が大事であったと考えられる。
「野暮」とは、「規則だから守る」のではなく、「野暮でカッコ悪いから、しけた事はしない。」という意味。しつこく損得に拘るのは野暮なこと。
「野暮」は、大阪では「無粋」と云う言葉が当たるみたい。
又大阪人は遠慮と云う言葉を知らない。街頭で「ティッシュ」を配っていれば、「兄ちゃん、もっとちょうだい」とねだるが、東京人はノリが悪く、必要ないティッシュはもらわない。
大阪人はケチではなく、ノリが良い。

例えば、大阪人のブランドに対する認識は、「品格」よりも「価格」に重点を置き、「ルイヴィトンやシャネル」は「メーカーもん」として括り、「メーカーもん」の次は「安もん」しかない。
ブランドものは高級品ではなく、値段が高い品物で「メーカーもん」と見て、高級品でも安かったら「安もん」になる。
大阪人は、安く買ったら「メーカーもん」でなくても、絶対自慢する。
安ければ安いほど自慢したがるのは、大阪人の特性で、東京人は安く買えば恥ずかしくて、自慢できないカッコやり。


写真は、大阪人のがめつさをテーマにしたイラスト。
例えば大阪女性が衣服を褒められた時に、衣服そのものより「それを如何に安く買ったか」と云うことに焦点が移り、「すごい」・「見えない」と褒められた時に、満足感をくすぐられることになる。
大阪の場合、値段を聞くのは失礼とか、聞きにくいということもないらしい。

全国に店舗がある百貨店のデータによると、売上げ全体に占めるバーゲンの割合は、大阪が3割vs.東京が2割と云うが、分かるような気がする。
要は、大阪人はがめつく、なかなか堅実で、現実主義を生活信条としていると云える。
「ええやん!」



















































































