◆前号でピサロの第二回南米大陸探検の年代を1926年と記しましたが、1526年の誤りです。訂正します。
北米大陸や南米大陸に人類が到達したのはいつ頃だろうか。これまでの説では、ユーラシア大陸と北米大陸の間に横たわるベーリング海峡が凍結し陸地化したルートを渡って、約1万3000年前頃に北米大陸に到達したとされる。また、南米大陸には約1万2000年前頃には到達し、南米大陸の南端には約1万1000年前頃には到達したとされている。最新の説では、その到達した年代がさらに早いとされ始めてもいる。モンゴルを通過してベーリング海峡に人類は向かったのだろう。
モンゴル・ゴビ砂漠の恐竜発掘調査には4回参加したことがあった。ツグルキンシレーや炎の崖と呼ばれる有名な恐竜化石発掘地からほど近いアラグ・テグという恐竜化石の発掘地で人類の石器を大量に見つけた場所(石器工房)があった。なかには玉(ぎょく)でつくられていた矢じり石器もあった。1万年以上をはるかに超える時代の石器を日本に持ち帰り、京都に住んでいた梅原猛氏などにもこの石器を見せたこともあった。ここで最も多く見つかった石器は細石刃と呼ばれる石器だった。これは日本では北海道などても見つかっている。
北米大陸のロッキー山脈周辺の恐竜発掘調査には5回参加したことがあった。ある時、サウスダコタ州の発掘現場で日本人の生駒隊員が、ものすごく美しい、しかもかなり大きな白っぽい石器を見つけた。おそらく1万年頃前の石器で、木の先にこれをくくり付けて石槍として使われたものだ。この石器は約1万3000年頃前の時代の石器文化「北米クローヴィス」の時代のものかと思う。
その後、北米・中南米・南米の各大陸ではアメリカ大陸先住民たちの文明や王国や帝国がつくられていった。中でも有名なものとして「マヤ文明と王国」「インカ文明と帝国」「アステカ文明と王国」が知られている。
大航海時代の幕開けをつげた1492年のコロンブスによる新大陸の発見。コロンブスは船団を組織して4回の新大陸への渡航を行っている。(1492年・1493年・1498年・1502年) コロンブスはイタリア人だが、スペイン国のイザベル女王の賛同と資金を得て航海に乗り出したのだった。この当時、南北アメリカ大陸には2000万人あまりのさまざまな民族の先住民たちがいたとされている。これら先住民たちとコロンブスたちは戦闘におよぶこともあった。
スペイン王国のこのような動きに危機感をもったポルトガル王国は、1497年~1498年にかけて、ヴァスコ・ダ・ガマを総督とする船団を組んで、アフリカ大陸最南端の喜望峰周りでの航海を行わせた。そして船団はインドに到達している。また、1519年~1522年にかけて、スペイン国王の支援をうけたマゼランの船団は、スペインから大西洋を西に進み、南米大陸最南端のマゼラン海峡を発見、太平洋をヨーロッパ人として初めて横断しフィリピンに到達。インド、喜望峰を経由して世界一周を成し遂げている。このような大航海時代、1543年にポルトガルの船が日本の種子島に上陸をした。
南北アメリカ大陸の三大文明とも呼ばれる「マヤ・アステカ・インカ」。マヤとアステカは中南米のメキシコを中心に栄えた王国の文明。マヤは熱帯雨林に、アステカは高地に栄えた。距離的にも近いこともあり、ピラミッドの遺跡などはかなり似通ってもいる。
さて、南米大陸のアンデス山脈一帯にあった「インカ帝国」の滅亡に10年間ほど先立つ1521年にアステカ王国は滅亡させられた。スペイン人のコルテスは400人あまりの兵士を率いてこの王国に来た。アステカ王国(帝国)の首都・テノチティトラは湖の中に築かれた壮大な都だった。皇帝(国王)たちはコルテスたちを迎え入れ歓待したが、「銃・病原菌・鉄」によって滅亡させられてしまった。(※アステカ王国(帝国)は、1420年代から1521年までの約100年間成立していた。コルテスが征服したのだが、コルテスのこの時の年齢は34歳。)
◆「マヤ・アステカ・インカ」の3つの帝国や文明の中で、最も黄金が多かったのはインカだった。現在でもそうだが、インカ帝国のあったアンデス山脈一帯は金銀銅などの鉱物資源の宝庫の地でもあった。また、日本も南米ペルーなどと並び銀の世界的な産地となっていった。
アステカ王国滅亡の要因はやはり天然痘だった。爆発的にアステカ王国で流行し、国王や側近らも天然痘で死亡。路上におびただしい数の遺体が放置されたという。その結果、国力が弱体化し、結局、滅亡においこまれた。中南米の人口は10分の1ほどになったとも言われる。ここに進出したスペイン人たちは天然痘の免疫を持つ者も多く、また、感染しても発症しないケースもあったという。アステカの人々の間では「スペインの神の方が、アステカの神より優れている」という見方が広がり、スペイン人のキリスト教に改宗する人が増えた。天然痘は国家を滅亡させ、キリスト教を広めたこととなる。
マヤ文明は、紀元前(BC)1000年頃から紀元後(AC)1600年頃までの約2600年間、現在のメキシコのユカタン半島を中心に栄えた文明。この文明圏にはいくつかの王国が分立していた。最盛期の8世紀ころには、1都市につき6万人~10万人もの人々が、この一帯でいくつもの王国を形成していたとされる。4万あまりのマヤ文字を持ち、優れた天文学や暦を用いていた。
「世界の四代文明」と呼ばれる大河流域で形成された文明と違って、ジャングルやサバンナ、ステップ地帯など、さまざまな自然環境の中で発展することができたという文明の特徴も備えていた。1600年間もの間、マヤ文明がその歴史を絶やすことがなかった最大の要因は、それぞれの王国が文明の多様性を維持し続けていたからではないかと考えられている。
巨大な統一王朝(帝国)による統治ではなく、多くの王国による多様な文化を有していたマヤ文明。アステカやインカ帝国の滅亡からおよそ180年後の1697年に、マヤ文明圏の最後の王国がスペインの侵略を受けて併合された。ジャングルなどのユカタン半島の自然地理がスペイン人の進出と天然痘の広がりを遅らせたのかと思われる。マヤの末裔となる人々は今では800万人ほどがいるとされている。
◆コロンブスによる新大陸発見がされた1492年当時、南北アメリカ大陸には2000万人の先住民がいたが、その後の200年間で、人口が100万人ほどに激減した。(1700年頃) その原因の多くが、天然痘やインフルエンザ、チフス、麻疹(はしか)など、ヨーロッパから持ち込まれた感染症によるものだった。
◆ヨーロッパではその後、スペイン無敵艦隊を破り、そして産業革命も起きたイギリスが世界に勢力を拡大する。また、オランダも新興国として世界に進出する。そしてイギリスはインドを植民地化した。インドの地方病だったコレラは、1817年に感染爆発を起こし、世界中に広がった。コレラ対策の切り札は清潔な水を確保するための上水道の整備で、それを目的に、国家による大規模な水道事業が行われることとなった。
◆20世紀の1910年代に流行したインフルエンザ(スペイン風邪)は、米国が第一次世界大戦への参戦で兵士や物資を送り込む過程で感染が欧州に拡大。兵士たちの戦意の喪失を恐れた大戦への参加国は情報を秘匿した。この大戦に中立国で参戦していなかったスペインではこの感染の情報がオープンとなっていたため、スペインから情報が全世界に発信された。このため「スペイン風邪」と呼ばれるようになってしまった。感染は世界で数千万人の人々の命を奪った。その数は第一次世界大戦の戦いで亡くなった人よりもはるかに多かった。
日本には1918年に上陸し、その終息までに丸2年間を費やした100年前のパンデミック・スペイン風邪。当時の日本の総人口約5600万人に対し、45万人が死亡するという大惨事となった。
飛鳥時代や奈良時代、そして平安時代初期のころまで行われた中国への遣隋使や遣唐使事業。中国に渡るための航海ルートは主に3つがあった。まあ、台風などの遭難も多く、「命がけの長期海外出張」だった。大陸との交流が本格化したこの時代から、大陸伝来の「疫病」が日本にも広がることとなった。特に奈良時代はつくづく疫病に苦しめられた時代でもあった。まさか「令和の時代」が、世界中で猛威をふるう感染病からスタートするとは、1年ほど前の改元時には誰が思っただろうか。
思えば「令和」という元号は「万葉集」が出典だ‥‥。令和の最初は、元号の出典となった『万葉集』の時代―つまり奈良時代と同じく感染症に悩むこととなってしまった。安倍首相の辞任にともなう自民党総裁選挙で次期首相となる可能性が大きい菅義偉官房長官は、昨年に新元号「令和」を国民に向け発表し、「令和おじさん」の異名をもつ。奈良時代は当時の世界の超大国「隋や唐」などから人や文化や物が日本に流入した日本にとってのグローバル化の時代だった。人や物の流入、それと同時に感染症も流入し、引き起こる疫病。そもそも、奈良時代に大仏殿と大仏がつくられたのも、遷都が繰り返されたのも、「疫病の大流行」が要因だったのだ。
遣隋使や遣唐使だけでなく、戦乱のために中国本土や朝鮮半島から日本にやってきた人がかなり多かった時代でもある。それらの人々によって技術や文化が持ち込まれると同時に彼等は疫病を持ち帰ったり、入り込んだりもしたのだろう。疫病(おそらく天然痘だったのではないかと言われている)は九州から広まった。
どのくらい流行したかと言えば、当時の政治権力の最高権力にいた藤原四兄弟が全員死亡してしまってもいる。藤原四兄弟が権力を掌握するために自害に追い込んだ長屋王の呪いではとの噂が巷に溢れもした。ちなみにこの疫病は、当時 政治を担っていた公卿たちも襲い、その3分の1が亡くなったとも言われる。今で言えば、総理大臣や各省庁大臣の1/3がなくなるようなものである。
長屋王の呪いや疫病を怖れた聖武天皇は、「仏教」を広めることと「遷都」に情熱を注ぎこむこととなる。奈良の大仏殿や大仏を建てたのも聖武天皇だし、平城京から恭仁京、紫香楽宮、難波宮と次々に都を移しまくったのも聖武天皇だ。結局また平城京に都を戻すのだが。「なぜこんなに遷都をしまくったのか?」と後世の人々からも思われているが‥‥。とにかく「長屋王の呪いがあり疫病が大流行している平城京」から逃れたいという衝動だった可能性がある。また、大仏や各地の国分寺などを建立させたのも 仏の力で「疫病」を終息させたいという願いが最も大きな動機だったと考えられている。

























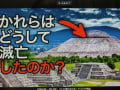




























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます