福井県(越前)の敦賀の町から福井県の府中(武生市[現・越前市])や北ノ庄(福井市)を往来する街道が北陸道だ。その最大の難所とされた「木の芽峠(標高630m)」は、新潟と富山の間にある「親知らず子知らず」とともに北陸道の二大難所と云われた。敦賀市の新保地区から木の芽峠までの2.4kmの山道(峠道)は、現在「木の芽古道」とよばれる山道が残っている。
歴史をさかのぼれば、平安時代には紫式部が父の府中任地に従い峠を越え、平安時代末期の源平の争いの時代には、ここを木曽義仲軍が京の都を目指して越えた。鎌倉時代には道元や親鸞が通った。そして、南北朝時代には新田義貞軍、戦国末期の時代には多くの戦国武将たちが 戦地に向かうためにここを行き来した。
ここ木の芽峠には「木の芽城塞群址」(木の芽城・西光城・鉢伏城など)がある。1575年に織田信長の軍勢5万が越前一向一揆勢力を根絶やしにするために侵攻。一向一揆勢力は、ここ木の芽城塞群などに拠って信長軍を迎え撃って侵攻を阻もうとしたが、数日間の戦いで守備網が崩壊し、その後 捕えられた約3万人もの人が殺された。
この峠には、江戸時代になってから番所が置かれた。代々、この番所役人の職にあった前川一族(家)の末裔が現在でも峠の家に住んでいる。「ポツンと一軒家」だが、この家の犬が数匹 放し飼いにされている。近づくと、放し飼いにされている犬たちが吠えながら走り寄って来る。怖いことこのうえない。
木の芽峠を下っていくと、「板取宿址」がある。そしてさらに5〜6kmほど行くと「今庄宿」に着く。この今庄は、江戸時代末期・明治の時代はじめころまでは、北陸道の大宿場町だった。明治11年(1879年)には、明治天皇もここ木の芽峠を越えて今庄宿にて宿泊している。
大名が宿泊するかっての本陣の建物をはじめとして、当時多くの旅籠屋や茶屋があり、現在でも営業している酒造会社もあった。江戸時代の1689年、松尾芭蕉もここで宿泊している。今庄宿の背後にある愛宕山には、木曽義仲が築城させた燧ケ城(ひうちがじょう)址がある。「義仲の 寝覚めの山か 月かなし」(木曽義仲も この景色を見ていたかと思うと 眺める月も 物悲しい)と詠んだ。また、幕末の1864年、尊王攘夷をかかげて蜂起した水戸天狗党の一行1000人あまりが 12月の雪の降り始めたころに この今庄宿を通過し、木の芽峠を越えて敦賀に到着し投降となり、そのほどとんどが、敦賀の地で命を落とすこととなった。
「すべての道は今庄に集まる」とあるように、多くの峠越えの道は今庄に集まった。その峠の一つが古代の奈良時代につくられた「中山峠越え」。明治時代の1887年に敦賀―武生(府中)間の鉄道が開通したが、その鉄道ルートはこの中山峠越えだった。今庄駅は当時、鉄道の重要駅として隆盛を誇った。そして、時代を経て「北陸トンネル」が開通されるとともに 廃線となった。
今庄は今、南越前町今庄となっている。北陸本線の中でも豪雪地帯として知られている。木の芽峠には今、スキー場や温泉が作られている。温泉からは雪を冠った霊峰・白山を望むことができる。
◆1570年(永禄13年)から1583年(天正11年)までの15年間あまりは、近江と越前の国境にある刀根坂峠や栃ノ木峠、越前の木の芽峠の一帯は、戦いに明け暮れた15年間となった。(1570年の信長の第一次越前侵攻、1573年の第二次侵攻と朝倉氏滅亡、1575年の第三次侵攻と一向一揆勢力の滅亡、そして1583年の賤ケ岳の戦いによる羽柴秀吉軍の侵攻)

























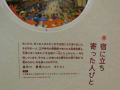







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます