(以下、NETIBNEWSから転載)
===============================
発達障害急増の要因は? 赤ちゃんに優しくない「お産」
社会2013年3月25日 17:58
前回(関連記事参照)、福岡市立こども病院の医師ら5名が1988年から2006年にかけて実施した「福岡市の発達障害児の実態調査」において、病院によって発達障害の発生頻度に差があること、および、同調査の報告の結語に、「幼児期以降の発達予後の情報を産科と共有しさらに詳細な検討が必要であると考えられた」という内容が含まれていたことを報じた。今のところ福岡市は、「市独自で産科と協力した実績はない」(市保健福祉局長、13年3月21日)というが、発達障害児急増の原因究明において、産科を交えた詳細な検討は本当に必要がないのだろうか。出産の現場(産科)における考えられうる違いについて述べる。
<許容範囲が拡大した生理的体重減少>
日本で主流となっている「完全母乳哺育」に、早くから警鐘を鳴らし続けてきた久保田産婦人科麻酔科医院の院長・久保田史郎氏は、発達障害の予防策として「栄養補給」と「体温管理」の徹底を訴えている。一方、日本では、厚生労働省によって「完全母乳哺育」が推奨されている。両者の明確な違いの1つには、生理的体重減少の許容範囲(表1参照)があげられる。生理的体重減少とは、新生児が尿・胎便、水分の蒸発など体外に出す量が多いために起こる一時的な体重減少のこと。
厚労省は1993年から、母乳哺育を薦めるWHO/ユニセフの10カ条を後援。その第6条には「医学的な必要がないのに母乳以外のもの、水分、糖水、人工乳を与えないこと」とある。さらに、同省は2007年に完全母乳哺育、カンガルーケア、母子同室を推奨するために「授乳と離乳の支援ガイド」を策定。そこは、新生児の出産時における体重の15%以内までを生理的体重減少の許容範囲としている。これを厳格に守るとすれば、たとえば3,000gで生まれた新生児は、450g以上やせない限り母乳以外の栄養補給はされない。
一方、出産後の新生児を保温した上で糖水による栄養補給を行なっている久保田産婦人科麻酔科医院では、生理的体重減少の幅がせまい(表1参照)。久保田医師は、「昔は、赤ちゃんを冷やさないようにと『産湯』を沸かして部屋を暖かくし、出産直後に十分な乳が出ない母親の代わりに『乳母』がいた。言うなれば、現代の保育器は『産湯』、糖水や人工乳が『乳母』の代わり」と語る。また、「小児科学の教科書には正常な生理的体重減少の範囲は5~7%以内とされていた。アメリカ小児医科学会も出生体重の7%以上減少した場合は適切な介入が必要としている」という。
久保田医師以外にも「-15%」という基準に疑問を抱かざるを得ない発表がなされている。日本小児科学会雑誌114巻12号に掲載されている富山県立中央病院小児科の田村賢太郎氏らの論文には、「体重減少10%以上の母乳栄養児の4割弱に高ナトリウム血症性脱水を認めた」とあり、「特に脱水が疑われる場合には積極的な介入が必要と考えられる」と結んだ。また、同論文では、トルコにおける6年間の調査で入院を要する高ナトリウム血症性脱水を発症した母乳栄養児116人のうち半数以上で1歳以降になんらかの発達障害を認められたことを紹介している。
久保田医師は、特に生後3日間は体重減少10%以上を「飢餓状態」とし、栄養不足などが引き起こす重症黄疸、低血糖症、高ナトリウム血症性脱水が脳機能の損傷へとつながり、発達障害になると訴え続けている。
表2は、福岡市の調査結果に久保田医師が注釈をつけた。厚労省が完全母乳哺育を本格的に推奨し始めた1993年と、「授乳と離乳の支援ガイド」を策定した2007年以降、発達障害児数の推移に変化が見られる。これが一体何を意味するのか。出産の現場においても発達障害児急増の要因を探す必要があるのではないだろうか。
(つづく)
【山下 康太】
===============================
発達障害急増の要因は? 赤ちゃんに優しくない「お産」
社会2013年3月25日 17:58
前回(関連記事参照)、福岡市立こども病院の医師ら5名が1988年から2006年にかけて実施した「福岡市の発達障害児の実態調査」において、病院によって発達障害の発生頻度に差があること、および、同調査の報告の結語に、「幼児期以降の発達予後の情報を産科と共有しさらに詳細な検討が必要であると考えられた」という内容が含まれていたことを報じた。今のところ福岡市は、「市独自で産科と協力した実績はない」(市保健福祉局長、13年3月21日)というが、発達障害児急増の原因究明において、産科を交えた詳細な検討は本当に必要がないのだろうか。出産の現場(産科)における考えられうる違いについて述べる。
<許容範囲が拡大した生理的体重減少>
日本で主流となっている「完全母乳哺育」に、早くから警鐘を鳴らし続けてきた久保田産婦人科麻酔科医院の院長・久保田史郎氏は、発達障害の予防策として「栄養補給」と「体温管理」の徹底を訴えている。一方、日本では、厚生労働省によって「完全母乳哺育」が推奨されている。両者の明確な違いの1つには、生理的体重減少の許容範囲(表1参照)があげられる。生理的体重減少とは、新生児が尿・胎便、水分の蒸発など体外に出す量が多いために起こる一時的な体重減少のこと。
厚労省は1993年から、母乳哺育を薦めるWHO/ユニセフの10カ条を後援。その第6条には「医学的な必要がないのに母乳以外のもの、水分、糖水、人工乳を与えないこと」とある。さらに、同省は2007年に完全母乳哺育、カンガルーケア、母子同室を推奨するために「授乳と離乳の支援ガイド」を策定。そこは、新生児の出産時における体重の15%以内までを生理的体重減少の許容範囲としている。これを厳格に守るとすれば、たとえば3,000gで生まれた新生児は、450g以上やせない限り母乳以外の栄養補給はされない。
一方、出産後の新生児を保温した上で糖水による栄養補給を行なっている久保田産婦人科麻酔科医院では、生理的体重減少の幅がせまい(表1参照)。久保田医師は、「昔は、赤ちゃんを冷やさないようにと『産湯』を沸かして部屋を暖かくし、出産直後に十分な乳が出ない母親の代わりに『乳母』がいた。言うなれば、現代の保育器は『産湯』、糖水や人工乳が『乳母』の代わり」と語る。また、「小児科学の教科書には正常な生理的体重減少の範囲は5~7%以内とされていた。アメリカ小児医科学会も出生体重の7%以上減少した場合は適切な介入が必要としている」という。
久保田医師以外にも「-15%」という基準に疑問を抱かざるを得ない発表がなされている。日本小児科学会雑誌114巻12号に掲載されている富山県立中央病院小児科の田村賢太郎氏らの論文には、「体重減少10%以上の母乳栄養児の4割弱に高ナトリウム血症性脱水を認めた」とあり、「特に脱水が疑われる場合には積極的な介入が必要と考えられる」と結んだ。また、同論文では、トルコにおける6年間の調査で入院を要する高ナトリウム血症性脱水を発症した母乳栄養児116人のうち半数以上で1歳以降になんらかの発達障害を認められたことを紹介している。
久保田医師は、特に生後3日間は体重減少10%以上を「飢餓状態」とし、栄養不足などが引き起こす重症黄疸、低血糖症、高ナトリウム血症性脱水が脳機能の損傷へとつながり、発達障害になると訴え続けている。
表2は、福岡市の調査結果に久保田医師が注釈をつけた。厚労省が完全母乳哺育を本格的に推奨し始めた1993年と、「授乳と離乳の支援ガイド」を策定した2007年以降、発達障害児数の推移に変化が見られる。これが一体何を意味するのか。出産の現場においても発達障害児急増の要因を探す必要があるのではないだろうか。
(つづく)
【山下 康太】















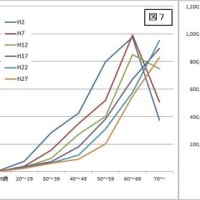
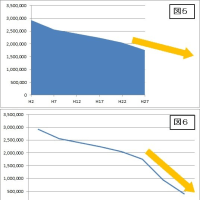
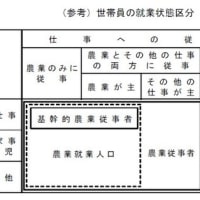
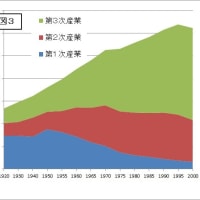
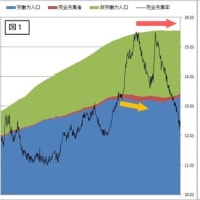
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます