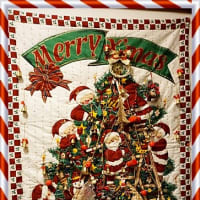東北の旅1 銀山温泉へ
東北の旅2 銀山温泉能登屋・散策
東北の旅3 銀山温泉散策・ライトアップ
東北旅行4 銀山温泉能登屋夕食~
東北の旅5 会津若松へ
東北旅行6 会津若松 鶴ヶ城
東北の旅7 白虎隊
東北旅行8 さざえ堂と武家屋敷
東北の旅9 東山温泉庄助の湯瀧の湯
東北旅行10 瀧の湯・夕ご飯~郡山へ
東北の旅11 日光の町
東北の旅12 日光山輪王寺・東照宮五重の塔
東北旅行13 東照宮三猿の教え
東北の旅14 日光東照宮・陽明門・唐門
東北旅行15 日光東照宮・眠り猫・鳴龍・二荒山神社
東北の旅16 日光温泉日光千姫物語
東北の旅17 ナチュラルパークツアー華厳の滝・中禅寺湖
東北旅行18 日光・中禅寺・龍頭の滝
東北旅行19 明治の館~京都
東北の旅7 白虎隊の続きです。
3月5日(土)
国指定重要文化財 さざえ堂
飯盛山では、白虎隊十九士の墓や宇賀神堂をお参りした後、
国指定重要文化財 「さざえ堂」 を参拝。
正式名称は「円通三匝堂(えんつうさんそうどう)」
1796年に建てられ、六稜三層の形がさざえに似ていることから
さざえ堂と親しまれています。

参拝後、運転手さんに、中に入ることもできますよと言われ
では。。と、主人と中に入ってみる事に。


上がりも下りも階段ではなく、らせん状のスロープを
ぐるぐる周っていきます。
上がりと下りの道が別々という珍しい構造の建物になっていて
参拝者たちは、すれ違うことなくお参りできるのです。
210年も前の古い木造建物で大丈夫かな。。と思ったけど、
中は結構しっかりしていて、
しかも2重のらせん状構造なんて。。どうなってんの?
。。って感じです。


昔は、スロープに沿って西国三十三観音像が安置され、
参拝者はこのお堂をお参りすることで、
夢の西国三十三観音参りが、あっという間にできたそうです。
明治になって、西国三十三観音像は取り外され、
西国三十三観音参りはできなくなりましたが、
建築史上の特異性が認められ、平成7年に国重要文化財に
指定されたそうですよ。
成瀬桜桃子句碑
近くにこんな句碑が。。
成瀬桜桃子(おうとうし)の
「天高し ピサの斜塔と さざえ堂」
さざえ堂が若干傾いている様に見えることから、
ピザの斜塔と重ねたのかもしれませんが、
なぜ、ここにピザの斜塔が出てくるの?と不思議。。


でも、そういえば、ローマ市からのボンペイの遺跡を使った
塔の寄贈があったり。。
会津とイタリアは何か特別な関係があるのかしらね。。
武家屋敷へ
さて、飯盛山を後にして、次は武家屋敷を見に行きます。


旧滝沢本陣
まずは、旧滝川本陣。
旧滝川本陣は、江戸へと続く旧白河街道沿い滝沢峠の入り口にあり、
江戸おもてへの参勤交代や領内巡視、旅支度の休憩所として
使われていたそうです。

白地に黒字の会津藩の旗印。
シンプルですが、ちょっと愛嬌があって可愛いです。
1643年、保科正之が会津初代藩主となった時、
家紋は会津葵、旗印は「会」の旧字体「會」の漢字一字としたそう。
でも、よく見ると、「會」は真ん中の縦棒が突き出た字の形に
なっていますね。


新政府軍は、滝沢峠を越え城下に侵入したので、
戦場となった滝沢本陣には今も砲弾や刀傷が残されています。
ほら、あそこにも。。と運転手さんが教えてくれた場所にも
砲弾の跡や刀傷があって、
本当に、ここが戦場だったんだ。。

今のこんなにのどかな景色からは、ちょっと想像できません。。
会津武家屋敷
さて、次にやって来たのは会津武家屋敷です。

会津藩家老 西郷頼母(たのも)邸を中心に、
中畑陣屋(県重要文化財)などが並ぶ歴史文化総合観光施設です。

西郷頼母(たのも)家老屋敷
西郷家は会津藩松平家譜代の家臣で、代々家老職を務め1700石取りの家柄。
敷地面積2400坪、建築面積280坪のお屋敷には、
部屋が38もあり、畳の総数は328枚なのだそうです。

表門を通り、表玄関へ。

奥方の人形が出迎えてくれます。人形はマネキンではなく蝋人形。
挨拶する奥方の手の先が少し上に上がっているのは、
手の内を見せる、つまり二心のない本心を
お見せしていますという意味なのだそう。。
武士の時代には、こんな所にも気を使っていたんですね~。
各部屋には生活調度品がおかれていて、
その当時の生活の様子が忍ばれます。
こちらは台所。お釜がいっぱい並んでいますね。

八重の桜
会津といえば、NHKの大河ドラマ八重の桜が
思い出されますが、

会津でのロケは、ほとんどなかったんですよ。。
と、運転手さん。
この武家屋敷では、こちらのシーンが撮られたそうで
DVDで、その場面だけを映しているのが面白かったです。

そりゃ、ここがロケに使われたとあらば、
武家屋敷の誇りですもんね。 

御成りの間の厠
こちらは御成りの間(おなりのま)の厠(かわや)
御成の間とは、お殿様が来られた時に使われる部屋の事。
つまり、会津藩主の松平容保(まつだいらかたもり)が
使われたお手洗いという訳です。
敵の間者が忍び込むのを防ぐため厠に天井はなく
三畳の畳敷きの部屋になっています。
天井はないし、広すぎるしで。。
なんだか落ち着かないでしょうね。。

床下には木製のレールの上に、砂を敷いた箱車があります。
医師が、お殿様の健康具合を便でチェックしてから
砂と一緒に捨てたそうです。
でも。。お殿様って大変。
プライバシーなんて、ほんと、ないんですね。
自刃(じじん)の間
若松城下の武士は妻子を含め新政府軍が侵攻してきた時は、
鶴ヶ城に籠城するよう言われていたそうです。
しかし、1868(慶応4)年8月23日、
政府官軍と会津藩の戦いが激しくなる中、
西郷家の婦女子21名は鶴ヶ城に籠城することなく
集団自刃の道を選びました。
「婦女子は足手まといになるから」
「新政府軍に捕まり恥辱をうけることを避けるため」
というのが一般的な理由ですが、
「新政府軍の会津に対する非道さに対する抗議」とか、
あるいは、ずっと京都守護職就任に反対し、
新政府と和平交渉することを訴えた西郷頼母を長きに謹慎させ
籠城の折には籠城戦闘員から外した主君松平容保への
物言わぬ抗議であったという説もあるそうです。
そうか。。歴史って知れば知るほど、深いものなんですね。。
老屋敷の中には、逆さ屏風(死の儀式のときは屏風を逆さにする)
の前での西郷婦女子の自刃の様子が
蝋人形で復元されています。
下は4つや2つの女の子にまで手をかけるなんて、
その気持ちを考えると、恐ろしくて、怖くて。。
実は、その時はとても写真を撮ることはできませんでした。
でも、ネットで写真を見つけたのでやっぱり載せておきます。

死にきれなかった長女、細布子(16歳)を
土佐藩士中島信行が(薩摩藩川島信行とも言われていますが)
「我ハ味方ナリ」と言って介錯する場面は有名で
八重の桜でも描かれていましたよね。
でも。。本当にショッキングな蝋人形でした。
中畑陣屋
家老屋敷の後は、武家屋敷の周りの片長屋を見て、

次は福島県西白河郡矢吹町中畑より移築した中畑陣屋です。
陣屋とは、徳川幕府直轄領の役所のことをいいます。

現在は、福島県の重要文化財に指定されているそうですよ。
色々と教えて下さった運転手さん。
でも、もうそろそろ武家屋敷探索も終わりです。
石風呂
最後に、ほんものの石風呂を見せてもらいました。
昔の日本人は小さかったとはいえ、なんと小さな
お風呂。。 

昔の一般家庭に据えられていたお風呂で、
浴槽内を通っている煙突の熱で湯をわかしたそうです。
沸かし口は杉の皮などで密閉し、熱くないように
工夫していたようですが。。

この小さいお風呂で、まだ沸かすための煙突と
杉の皮の保護部分があったら。。
まっすぐ立って、そのままそっと浸かるしかないな。。
って感じですよね。
運転手さんも、
ま、湯に浸かってくつろぐというより
肩から掛けた湯が流れないようするという感じでしょうね。。。
なるほど。。
昔の石風呂からしたら、現代のお風呂って。。
夢のまた夢のようなお風呂なんですね。
さて、次は、少しお買い物をして、その後は東山温泉です。
東北の旅9 東山温泉庄助の湯瀧の湯へ続きます。
いつもご訪問ありがとうございます。
応援クリックを押して頂けたら嬉しいです。
 こちらです。
こちらです。