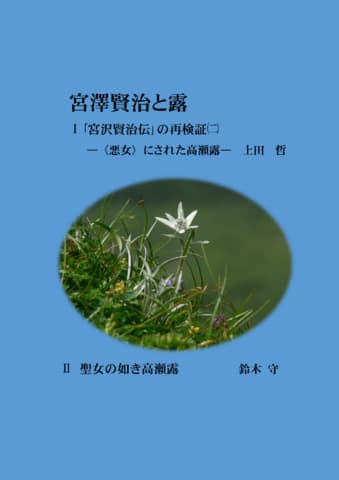
思考実験<賢治三回目の「家出」>
荒木 ところで、前に吉田が言っていた「ある伏線」はこれらとどう繋がるのだ?
吉田 ご免、そのためにはもう少し準備運動が必要なんだ。まずは、当時のことを時間的な流れで以下に確認したい。
・大正15年秋~昭和2年夏:下根子桜の賢治の許に露出入り(菊池映一氏の証言より)。
・昭和2年秋 :伊藤ちゑ兄と共に来花、賢治と会う(10月29日付藤原嘉藤治宛書簡より)。
・昭和3年6月 :賢治伊豆大島行。
・同時期帰花後 :賢治、「おれは結婚するとすれば、あの女性だな」と嘉藤治に語った。
・昭和3年8月~ :賢治実家に戻り、病臥。
・昭和6年7月7日:ちゑとの結婚話がまた持ち上がっていることを賢治自身が森に語った。
・同 年9月19日 :40㌔あまりのトランクを持って上京。
・同 年9月20日 :着京。以降滞京。発熱。
・同 年9月28日 :東京から花巻に戻り、病臥。
・同 年10月4日 :「夜、高瀬露子氏来宅の際、母来り怒る。露子氏宮沢氏との結婚話」
・同 年10月6日 :「高瀬つゆ子氏来り、宮沢氏より貰ひし書籍といふを頼みゆく」
・同 年10月24日 :〔聖女のさましてちかづけるもの〕
・ 推定同時期 :〔最も親しき友らにさへこれを秘して〕
・同 年11月3日 :〔雨ニモマケズ〕
そして、この中のポイントは
・昭和6年7月7日に賢治が森に対して語ったというところの、また持ち上がった伊藤ちゑとの結婚話
だと思っているんだ。そしてこの「また持ち上がった伊藤ちゑとの結婚話」が「伏線」となって〔聖女のさましてちかづけるもの〕が詠まれたのではなかろうかと僕は考えている。
荒木 もう少し具体的に説明してくれ。
吉田 これはあくまでも僕の推測であり、これから述べることは一つの思考実験だがそれでもいいか。
荒木 中身によりけりだがな。さあ、どうぞ。
吉田 僕も以前から、「聖女のさましてちかづけるもの」とは果たして露なのか? どうもそうとばかりは言い切れないと考えていた。
二人もそう訝っていると思っているが、昭和2年の夏以降になると賢治は露を拒絶するようになったと言われているのに、その頃から約4年もの時を経てしまった昭和6年の10月に、例の「このようななまなましい憤怒の文字はどこにもない」ような詩を露に当て付けて詠むか。
荒木 そりゃあ確かに常識的にはあり得ねえべ…。あっ、わがった、そういうことか。「聖女のさましてちかづけるもの」とは露のことではなくてちゑのことであり、ちゑとの結婚にまんざらでもないということが推察される「昭和六年七月七日の日記」に出てくるような賢治の想いが「伏線」となって、賢治をして〔聖女のさましてちかづけるもの〕を詠ましめた、ってわけな。
吉田 そう、実は「聖女のさましてちかづけるもの」とは巷間言われている露ではなくて、伊藤ちゑのことなのだ。
承知のように、昭和6年頃になると賢治自身が『「私も随分かわつたでしょう、変節したでしょう』というくらいだから、かつての賢治とはすっかり様変わりしてしまった。独身主義ももうやめた。ちなみに、
「私は結婚するかもしれません――」と盛岡にきて私に語つたのは昭和六年七月で、東北碎石工場の技師となり、その製造を直接指導し、出來た炭酸石灰を販賣して歩いていた。さいごの健康な時代であつた。
<『宮澤賢治と三人の女性』(森荘已池著、人文書房)104pより>
と森が証言している。
このように独身主義からはおさらばした賢治は、前々からちゑとならば結婚してもよいと思っていたがゆえに、再燃したちゑとの結婚話を持ち出して「私は結婚するかもしれません――」と昭和6年7月に森に喋った。そして、そのことをちゑと具体的に話し合おうと思ったこともあって同年9月に上京した。
荒木 おっと、それはまさかの展開だな。そんな話今まであったけがな?
鈴木 そっか、昭和6年の上京は東北砕石工場の製品売込みのためだったとばかり私は思っていたが、それだけではなくて、ちゑと会ってその結婚話を進めるためでもあったということな。だけど、その時の上京の際に賢治が伊豆大島まで行ったという証言や記述はどこにもないはずだが。
吉田 いやぁ、違うんだなそれが。その頃ちゑは東京に戻っていたようだし、僕はこの時の上京はまたぞろ賢治が「家出」をするためでもあったと推測している。
荒木 昭和6年の上京の一つの目的はちゑと会って結婚の話を具体的に進めるためだったはとりあえず了としても、もう一つは「家出」のためだったというのか。おいおい、思考実験とはいえそれはあまりにも荒唐無稽だべ。
吉田 まあまあ、これはあくまでも実験だ。まずは前者、ちゑとの結婚について。
澤村修治氏がこう述べている。
これでは学校の経営もままならない。そうした不如意のあげく、同年八月一三日、七雄は遂に逝去する。…(筆者略)…兄の逝去とともにチヱは東京に戻る。休職していた二葉保育園に保母として復帰。
<『宮澤賢治と幻の恋人』(澤村修治著、河出書房新社)182pより>
そしてここでいう「同年八月一三日」とは昭和6年8月13日のことだということが、同書から判る。
荒木 そっか、昭和6年9月の賢治の上京時には既に七雄は亡くなっており、ちゑは東京に戻って住んでいたのか。
鈴木 となれば伊豆大島の場合とは違って、上京した賢治ならば会おうと思えば比較的容易に伊藤ちゑに会えたことになるな。上京の前々月、再燃したちゑとの結婚話を持ち出して「私は結婚するかもしれません――」と森に喋っていた賢治のことだ、そのことをちゑと具体的に話し合おうと思ったこともあって同年9月に上京したということは確かにあり得る。
吉田 では次、後者について。
堀尾の『年譜 宮澤賢治伝』には、賢治が熱を出して寝ているという八幡館から電話連絡が入った菊池武雄が駆けつけて、
「花巻のおうちへ知らせよう」
といった。すると賢治はつよく、
「いやそれは絶対困ります。絶対帰りません。しらせないでください」
という。…(筆者略)…
それに賢治は、
「なあに風邪です、すぐよくなります」
と、いかにも病気のことは専門だといわぬばかりに自分でうけあい、
「よくなったら、ここから墨染の衣をきて托鉢でもしてまわりますよ」
と妙なことをいう。
<『年譜 宮澤賢治伝』(堀尾青史著、中公文庫)424p~より>
とある。
そこで、どうも賢治は花巻に帰りたくないらしいと判断した菊池は、武蔵野に小さい貸家を見つけ出して賢治にそのことを知らせた、というような貸屋探しのことが具体的にそこに続けて述べられている。
鈴木 つまり賢治はこの時花巻に戻るつもりは毛頭なく、このまま東京に居て托鉢などもして回りたい。ついては住む家を探している、というようなことなどを言ったものだから菊池は貸家を見つけてやったという次第か。なんだか、大正10年の「家出」の時と似たにおいがしてきた。
荒木 そうか、賢治は実質的に「家出」を目論んで上京したと吉田は言いたいわけだ。
鈴木 しかし賢治はこの上京の折り直ぐに、9月21日に「遺書」を書いていたわけで、着京即重態に陥り死を覚悟したと思うのだが。
吉田 確かに通説ではそうなっているがそれは「遺書」ではないという見方も可能だろう。ちなみにその中身は
この一生の間どこのどんな子供も受けないやうな厚いご恩をいたゞきながら、いつも我慢でお心に背きたうたうこんなことになりました。今生で万分一もついにお返しできませんでしたご恩はきっと次の生又その次の生でご報じいたしたいとそれのみを念願いたします。
どうかご信仰といふのではなくてもお題目で私をお呼びだしください。そのお題目で絶えずおわび申しあげお答へいたします。
九月廿一日
賢治
父上様
母上様
<『校本全集第十三巻』(筑摩書房)379pより>
というものだ。
荒木 あっ、そうそう奇しくも賢治の命日ってやつな。
吉田 だからなおさら「遺書」と思いたくもなるが、日にちの一致はそれとは無関係なこと。それよりは、この文面からは、花巻から離れての「家出」、決して花巻の実家に戻ることはないという自分自身に向けた決意表明だったととれなくもない。
鈴木 確かに、着京したと思われるのが9月20日、ところがその翌日に突如賢治は重篤となったので死を覚悟してこの「遺書」を書いた、ということは言われてみれば確かに奇妙だし不自然なことだ。
荒木 そういえば前に名前が挙がった菊池武雄とは、この上京の折りに賢治が「和とぢ」の本をプレゼントしたという人のことだよな。そうすると、賢治は何時どこでそれを菊池に渡したのだろうか。即重篤になったというのならばその機会がなかっただろうに。
吉田 そのことについては菊池自身が『宮澤賢治研究』所収の「賢治さんを想ひ出す」の中でこう語っている。
その後去年の春突然駿河臺のある旅館から電話で「宮澤さんといふ方が上京していま風邪を引いて休んで居られる」と知らせてくれたので行つて見たら、いつものニコニコした顔で床に就いて居られたが私は容易でないことを直感しました。その時「お土産に持つて來たのだけれども形見になるかも知れぬ」といつて私にレコード(死と永生)二枚と○本などをくれました。私は何とかして健康回復のために力になり度いと願つたけれど、一つは賢治さんの性質も解つてゐるからそれも尊重したいし、私も微力と生まれつきの不親切者故、なにもして上げられませんでした。
<『宮澤賢治研究』(草野心平編、十字屋書店)325p~より>
荒木 あれっ、ここには「和とぢ」の本などではなくて、プレゼントしたのは「○本」とあるけど? あっそうか、この「○本」は「和とぢ」の本つまり「春本」を憚った表現か。
鈴木 でも変だな。さっき吉田が教えてくれた堀尾の記述内容だと菊池は結構賢治の世話を焼いているのに、こちらの菊池の証言によれば菊池は何もしてやれなかったいうことだから矛盾がある。
吉田 矛盾ということで言えば、このことに関しては、深沢紅子の証言とも矛盾している。深沢は随筆「一ぱいの水-賢治との出会い」の中で次のように述べている。
昭和6年当時吉祥寺に住んでいた私の家に賢治がやって来て、
「宮沢ですが、お隣の菊池さんが留守ですから、これを預かってください」
<『追憶の詩人たち』(深沢紅子著、教育出版センター)124p~より>
と言われたと。
荒木 えっ! 深沢紅子は菊池武雄と隣同士だったのか。
吉田 そうだよ。たしか、「菊池さんとは私達夫婦も非常に親しい仲なので隣り同士に住んでいた」ということもそこで綴っていたはずだ。
鈴木 じぇじぇじぇ、菊池と深沢夫婦はそんなに懇意だったのか。確かに、言われてみれば三人とも同じ画家だからな。こうなったのではっきり言ってしまうけど、実は前に私が紹介した「私ヘ××コ詩人とお見合いしたのよ((註十三))」だが、このようにちゑが漏らしたその相手こそ深沢紅子だったのだ。
吉田 そうだったのか、な~るほどな。
鈴木 もちろん菊池は見合いの世話をしたくらいだからちゑとは何らかの繋がりはあっのだろうとは思っていたが、今までなぜ紅子にちゑがこんなことを、しかもざっくばらんに言ったのかその背景がいまひとつわからずにいた。それが、深沢と菊池は隣同士で住む程に親しくて
深沢紅子⇔菊池武雄⇔伊藤ちゑ
という繋がりができていたのか。これで腑に落ちた。
吉田 しかも、伊藤ちゑは1921年盛岡高等女学校卒(『宮澤賢治の幻の恋人』165p より)、一方の深沢(四戸)紅子も同じく盛岡高等女学校1919年卒 (『追憶の詩人たち』巻末より )だからちゑは2年後輩の同窓生、高等女学校の就学期間は5年間なのでちゑと深沢は3年間同時期に盛岡高女に通っていたと考えられる。だから、
菊池武雄⇔画家⇔深沢紅子⇔同窓生⇔伊藤ちゑ
という繋がりもあった。
鈴木 なるほど、そうなると菊池がちゑのお見合いをお膳立てしたということもなんとなく頷ける。
吉田 そこで先程の荒木の質問の「どこで」に対する答にもなると思うのだが、深沢はこんなことも証言している。
賢治はその時、『これを預かってください』と言って包みを二つ差し出して、一杯の水を飲んで帰っていった。
夕方吉祥寺に戻った菊池がその二つの包みを開けるのを見ていたならば、小さい方の包みは「和とぢ」の本であり、もう一つの方はレコードだった。菊池は、「何で俺にこんなものくれたべなあ」とお国なまりの独り言を言った。
<『追憶の詩人たち』124p~より>
鈴木 確かに菊池と深沢の証言の間には矛盾があるが、両者を比較すればこの件に関してはどうやら深沢の証言の方が信憑性が高いな。さっきの矛盾、今度の矛盾共に菊池絡みだからな。ここは信頼度が高いのは深沢の方とならざるを得ないだろうから、答は「吉祥寺で」となるのか。もしかすると、菊池は何かを庇っているのかもしれないな。
荒木 つまり、「賢治はどこでそれを渡したか」の答は駿河台の八幡館でではなくて吉祥寺でだろう、ということか。
吉田 そしてほら、この時の鈴木東藏宛書簡〔395〕にこんなことが書いてある。
実は申すも恥しき次第乍ら当地着廿日夜烈しく発熱致し今日今日と思ひて三十九度を最高に三十七度四分を最低とし八度台の熱も三日にて屡々昏迷致し候へ共心配を掛け度くなき為家へも報ぜず貴方へも申し上げず居り只只体温器を相手にこの数日を送りし次第に有之
<『校本全集第十三巻』(筑摩書房)380p~より>
荒木 となれば、「廿日夜烈しく発熱致し」ということだから賢治は9月20日の夜からひどい熱発、その後は床に就いていたようだから、その前に吉祥寺を訪れていたことになり、それはやはり9月20日しかあり得ないな。
鈴木 それに、9月20日付鈴木東藏宛書簡〔392〕方も見てみると「午后当地に着」とあるから20日の午後に着京しているようなので、その足で吉祥寺へ行ったかもしれないな。
吉田 実はこの件に関して、賢治はあの『雨ニモマケズ手帳』の二頁目にも次のように、
昭和六年九月廿日/再び/東京にて發熱。
と書き込んでいるから、賢治はやはり9月20日に突如「熱発」したとするしかない、と以前の僕は考えていた。
荒木 実はそうとも言えないというのか?
吉田 うん。というのも、この頃の賢治の体温はどうだったかというと、『兄妹像手帳』に賢治自身が次表のようにとメモしている(『校本全集第十二巻 (上)』134p)。
┌─────────┐
│ │
│ │
│ │
│ │
└─────────┘
しかも加藤謙次郎は、19日に仙台の古本屋内で浮世絵の話をしていた賢治に偶々出会い、
自宅に案内して夕食を共にし、夜遅くまで話し込んだ。…(筆者略)…化粧煉瓦を造つて売る計画を説明し、その試作品を携えて名古屋方面迄売込宣伝に行つて来ると張り切りつて居り、胸が悪い様子は全然感ぜられなかつた。
<『宮沢賢治とその周辺』(川原仁左エ門編著)315p~より>
と証言している。
荒木 そうなんだ。その上、21日までの体温はいずれも37℃台じゃないか。賢治は「九月廿一日」付の「遺書」を書いたというのが通説のようだが、これぽっちの「高熱」がたった二、三日続いただけであのような「遺書」を書くというのか? 書くわけねえべ。あれはもはや「遺書」などではないということだな。
ということは、先程の俺の質問の残り「いつ」に対する答は、
少なくとも9月22日以降の高熱から判断すれば22日以降に吉祥寺に行ったことはまずなかろうことと、着京が9月20日であることは間違いなさそうだから、吉祥寺行きは20日か21日であろう。
ということか。
吉田 いずれ、賢治の体温が高かったとはいえこの両日ならばまだ37℃台、無理すれば吉祥寺に行けないこともないから、このいずれかの日に賢治は少なくとも吉祥寺の菊池武雄の家に行き、また当時近くに住んでいたとも思われる伊藤ちゑの許へも訪ねて行った。まあ、これらはあくまでも思考実験上でのことだけど。
鈴木 あっそっか!
荒木 なんだよ、突然でかい声を出して。
鈴木 実は、ちゑの直ぐ上の姉ハナが当時吉祥寺に住んでいた(平成26年11月7日、伊藤ちゑの生家当主より)というんだな。だから、吉田の今の発言は現実的にもあり得た。
吉田 おっ、棚からぼた餅だな。よくよく考えてみれば、高熱にも関わらず菊池武雄へ「春本」等を届けるために賢治がわざわざ吉祥寺に行ったということは妙な話だと思っていたが、当時ちゑは吉祥寺の姉の家に住んでいた等ということもあり得るから、これでますますこの思考実験も現実味を帯びてきたぞ。
そのついでに調子に乗って言えば、場合によっては、この東藏宛書簡〔395〕中の「廿日夜烈しく発熱致し…熱納まるを待ちてどこかのあばらやにてもはいり」は賢治の方便であった可能性もあるということも視野に入れる必要があるかもしれん。
荒木 どういうことだ?
吉田 他でもない、そうすれば少なくとも取り敢えず家に戻らなくてもよいことになるから実質的な「家出」ができるだろう。裏を返せば、この東藏宛書簡は、実質的に賢治は三回目の「家出」をする覚悟であったということの一つの傍証となりそうな気もする。
鈴木 それはちょっと論理の飛躍で、無理筋だと思うがな。う~む、段々何が何だかわからなくなってきたぞ。
荒木 え~と、昭和3年の上京は「逃避行」と言えなくもない。一方今回の昭和6年の上京は「東北採石工場技師」になってから約7ヶ月後の仕事に行き詰まりを見せ始めた頃の上京だし、少なくとも直ぐに花巻に戻ることは考えていなかったそれだ。そういや羅須地人協会の活動の場合も約7ヶ月で頓挫した。
鈴木 しかも昭和3年の場合は田植え前後の、昭和6年の場合は稲刈り前後の共に農繁期の古里を離れての上京だ。だから、賢治の場合には、少しやってみて少し問題にぶつかったならば直ぐに放り出し、そこから逃避してしまうという性向がどうやらありそうで、確かに同じ構図がこの2つにはあるな。
荒木 ところでその「家出」だが、最初のは何となくわかるが…。
吉田 もちろん最初の一回目は、
その時頭の上の棚から御書が二冊共ばつたり背中に落ちました。さあもう今だ。今夜だ。時計を見たら四時半です。汽車は五時十二分です。すぐに臺所へ行つて手を洗ひ御本尊を箱に納め奉り御書と一緒に包み洋傘を一本持つて急いで店から出ました。
<『宮澤賢治素描』(関登久也著、共榮出版)47pより>
という大正10年1月の衝動的で突発的な「家出」。
二回目が、これもまた突如花巻農学校の職を辞して下根子桜で暮らしを始めたことも、確たる見通しもないままのそれだったのだから僕に言わせれば実質的には「家出」で、これ。
そして三回目が、この昭和6年9月の上京だ。ただしほとんどの人はそうは思わんだろうけどな。
荒木 いや、三回目も吉田に段々刷り込まれてきたせいか、それもありかなと思うようになってしまった。世の中、二度あることは三度あるとも言うしな。
吉田 あっそうそう。僕と似たことを小倉豊文がこう言っていたはずだ。
最後の上京にしても、その前後二回の家を出ての独立的生活にしても、賢治にとって実に思い出深いものであったろう。賢治はその都度命がけの「出家」を決行したのである。
<『「雨ニモマケズ手帳」新考』(小倉豊文著、東京創元社)47pより>
と。ただし、こちらは文字が逆で「出家」だけど。
鈴木 そうか、小倉も三回と見ていたのか。それも「命がけの」。なるほどな。いずれ、この三回の「家出」にしてもあるいは「出家」にしても、まさしく不羈奔放な賢治の面目躍如というところかな。
荒木 皮肉か?
鈴木 とんでもない、このような賢治だからこそあれだけの作品を書けたということだよ。あの『春と修羅』のようなものをスケッチ出来る人が今後現れることなど二度とないだろう。
荒木 確かにこうやって振り返ってみると、この時の上京は賢治<三回目の「家出」>というのは十分にあり得ることだ。
思考実験<賢治ちゑに結婚を申し込む>
吉田 さて思考実験の続きだが、昭和6年9月 賢治が東京に「家出」をしようと思ったのは、もちろんちゑと結婚しようと思ったからだ。
鈴木 確かにそう言われてみれば、『宮澤賢治』(佐藤隆房)や『宮澤賢治と三人の女性』によれば、
伊藤さんと結婚するかも知れません
と賢治がほのめかし、ちゑのことを
ずつと前に話があつてから、どこにも行かないで待つてゐるといはれると、心を打たれますよ。
と認識し、しかも、
禁欲は、けつきよく何にもなりませんでしたよ、その大きな反動がきて病氣になつたのです
と悔いていたようだから、この頃になると賢治は独身主義を棄て、賢治はちゑならば
自分のところにくるなら、心中のかくごで
来てくれると思っていた節もあり、この頃の賢治はいよいよちゑと結婚しようと決意した、という可能性はないとは言えない。
荒木 しかも森の「『三原三部』の人」によれば、
けれどもこの結婚は、世の中の結婚とは一寸ちがつて、一旦からだをこわした私ですから、日常生活をいたわり合う、ほんとうに深い精神的なものが主となるでせう。
<『宮澤賢治と三人の女性』(森荘已池著、人文書房)115p~より>
というようなところまでも賢治は考えていたようだからな。
吉田 一方、昭和3年の「逃避行」とも見られる上京の場合と同じように、東北採石工場の仕事も約7ヶ月が過ぎた頃からその仕事も行き詰まってきたのでそこから逃れたくなったこともあって、賢治はちゑとの結婚を決意、東京に出て「東北砕石工場」の代理店を開いて化粧煉瓦を売ったりしながら生計を立て、「日常生活をいたわり合」いながらちゑと一緒に暮らそうと計画した。そしていよいよ昭和6年9月19日、化粧煉瓦を詰めたトランクを持って花巻を後にした。
荒木 どうだべがな?
吉田 まあまあ、単なる思考実験だ。続けよう。
もちろん、上京した賢治はいの一番にちゑの許を訪ねてその決意をちゑに伝え、結婚しようと切り出した。ところが、「ずつと前に私との話があつてから、どこにもいかないで居るというのです」と認識していたのは賢治の方だけ。先に明らかにしたように、一方のちゑはもはや賢治と結婚するつもりは全くなかったからきっぱりと断った。
荒木 しかも兄七雄が急逝したばかりだからなおさらに、きっぱりとその申し出を断ったということもありかな。
吉田 それもあると思うし、我が身を擲ってきたスラム保育を続けたいという強い意志と信念もあったんじゃないのかな。
ただし、賢治の方は予想だにしなかったちゑの拒絶にすっかり打ちのめされてしまった。しかし賢治とすれば「家出」の覚悟だったから、今更直ぐさまおめおめと実家に戻るというわけにもいかず、貸屋探しを菊池武雄に依頼。
荒木 そうか。「家出」の覚悟だったからこそ当初は、上京して直ぐに熱発しても頑なに実家に戻ることを拒み、なおかつ東京で住む家まで探していたということか。
鈴木 それにしてもなあ、ちゑとならば結婚してもいいと覚悟を決めて折角「家出」までして来た賢治とすれば、それが完全に裏切られたと受け取っただろうな。
荒木 そこで賢治の心の中にちゑに対する憎しみがめらめらと燃え始めた。
吉田 そのこともあって緊張の糸が切れてしまった賢治は、その反動で、もともと体調不十分だったこともあって途端に熱発、床に伏した。
荒木 これで何もかも終わり、賢治は夢も希望も失ってしまってもはや生きる望みもなくなり、あの「遺書」を書いた。
吉田 なるほど、こうなってみると荒木のその見方もありかもな。たったあの程度の熱発で着京直後に「遺書」を書くのかということと、ちゑからの結婚拒絶で受けたショックで死にたくなって「遺書」を書いたということとを比べてみれば、後者の方が確かに説得力があるな。
荒木 なっ。
吉田 さて、連日の高熱で床に伏しながら賢治は今後のことに思いを巡らした。もはやちゑとの結婚計画も頓挫した、「家出」をする意味もなくなってしまった。当然東京にいる必要もなくなってしまった。切羽詰まってしまった。
鈴木 そこで、9月27日に賢治は父政次郎へ
もう私も終わりと思いますので最後にお父さんの御聲をきゝたくなつたから……
<『宮澤賢治の手帳 研究』(小倉豊文著、創元社)22pより>
と電話した。その時にどれほどの病状だったかはわからないにしても、精神的にはとことんまで追い詰められていたということだけはたしかであっただろう。
吉田 いやどうだか。賢治は泣きを入れただけのことかもしれないぞ。
とまれ、その電話を受けて父は即刻帰花するようにと厳命。賢治は後ろ髪引かれる思い、あるいは逆に「渡りに舟」だったかもしれないが、いずれにせよ帰花。実家にて病臥した。
鈴木 ちなみにこの時、花巻に戻った賢治は父政次郎に何と言ったか。小倉豊文は『「雨ニモマケズ手帳」新考』に、
賢治はこの時はじめて父に向って「我儘ばかりして済みませんでした。お許し下さい」という意味の言葉を発したという。
<『「雨ニモマケズ手帳」新考』(小倉豊文著、東京創元社)24pより>
と記している。
荒木 そっか、この謝罪の文言「我儘ばかりして済みませんでした。お許し下さい」がそのとおり事実であったとすれば、この時の賢治は「家出」という決意をして上京したという吉田の「私見」が、俄然説得力を持ってきたな。
思考実験<「聖女のさましてちかづけるもの」はちゑ>
さらに思考実験を続ける。
◇『二葉保育園』の保母としてのプライド
吉田 さて、花巻に戻った賢治は実家で病に伏せながら先にも引用したように、『雨ニモマケズ手帳』の実質的な一頁に「昭和六年九月廿日/再び/東京にて發熱。」というように、<三回目の「家出」>のことをまず書いた。そしてこの手帳を書き進めていくうちに、賢治とならば結婚してもいいとちゑの方も思っているものとばかりに思い込んでいた賢治だったが、実際に結婚を申し込んだところちゑからはけんもほろろに断られてしまったから、ちゑに一方的に裏切られてしまったという屈辱感が日に日に募ってきて病臥中の賢治を苛み、次第に溜まってくるフラストレーションがついに爆発、10月24日「なまなましい憤怒の文字」を連ねた〔聖女のさましてちかづけるもの〕を『雨ニモマケズ手帳』に書いてしまった。
荒木 つまり、再び持ち上がったちゑとの「結婚話」が伏線となってこの詩を詠ましめたというわけだ。したがって、
賢治が「聖女のさましてちかづけるもの」と詠んだ女性は巷間言われている露ではもちろんなくて、誰あろうちゑのことだった。
と、そう吉田は言いたいのだ。
吉田 そういうこと。
鈴木 実は賢治は、当時ちゑが勤めていた『二葉保育園』のことや、ちゑがそこでどのようなことをしていたのかということをある程度知っていたと思うんだな。
荒木 何だ藪から棒に。
鈴木 実は、『光りほのかなれど―二葉保育園と徳永恕』(上笙一郎・山崎朋子著、教養文庫)によれば、同園の創設者の野口幽香と森島美根は、当時東京の三大貧民窟随一と言われていた鮫河橋に同園を開いて、寄附金を募ってそれらを元にして慈善教育事業、社会事業としての貧民子女の保育等に取り組んでいたというんだな。
そして、野口も森島も敬虔なクリスチャンであり、ちゑが勤めていた頃の同園の実質的責任者は徳永恕はクリスチャンらしくないクリスチャンだったという。ちなみに、現在でも同園は「キリストの愛の精神に基づいて、健康な心とからだ、そしてゆたかな人間性を培って、一人ひとりがしっかりとした社会に自立していけることを目標としています」という理念を掲げている。
つまり当時のちゑは、スラム街の貧しい家の子どもたちのために保育実践等をしていた、いわば<セツルメントハウス>と言える『二葉保育園』に勤めていたんだ。
荒木 つい俺は今まで、『二葉保育園』とは普通の保育園だとばかり思っていたがそうではなかったんだ。同園はセツルメント活動をしてたのか。あっ、そうか腑に落ちたぞ。そういえば、
そのころちゑさんは、あるセッツルメントに働いていました。母子ホームです。
<『宮澤賢治と三人の女性』(森荘已池著、人文書房)118pより>
と森が述べていたがこのことを意味してたんだ。
吉田 だからか、森は同書で
そしてこの少女は…(筆者略)…兄の死んだあとは、東京の母子寮にその生活の全部、全身全霊をささげて働いた。
<『宮澤賢治と三人の女性』171pより>
とも述べている。
鈴木 そうそう、二葉保育園には母子寮があって、
恕のつくったこの二葉保育園の母の家は、近代日本における〈母子寮〉という社会福祉施設の嚆矢であった!
ということも前掲書では述べてあったから、おそらくちゑはその頃はこの「母子寮」にも勤めていたのだろう。
荒木 ということであれば、賢治はちゑがそのような所で働いていることはある程度知っていただろうから、ちゑが「聖女のさまして」見えたということは十分にあり得る。したがって、もしそのような女性から仮に裏切られてしまったと賢治が思い詰めたとすれば、まさに
ちゑ=聖女のさましてちかづけるもの
と言い募ってしまいたくなるのも理屈としては成り立つな。
鈴木 なお断っておきたいのだが、だからといってちゑが問題のある人だと私は言いたいわけでは毛頭ない。
それどころか、ちゑは「翔んでる女性」である一方で、『二葉保育園』ではスラム保育のセツルメント活動に取り組んでいただけではなくて、兄の看護のために伊豆大島に居た頃はこっそりと隣の老婆を助けたり、そこを去ってからもその老婆に毎月「5円」を送金し続けたりするような女性であったということだから、なかなかな人だ。
荒木 そっか、昭和3年6月の「伊豆大島行」の際に、ちゑが賢治と結婚しないと心に誓ったのは、この当時のちゑの生き方からすれば、「高等遊民」のような生き方をしていた賢治に惹かれることはなかったからか。確かに雲泥の差があるもんな、その生き方の姿勢に。
吉田 そうか、ちゑはそういうとても素晴らしい人だったんだ。一方では、ちゑは賢治をいわば「振った」という形に結果的にはなってしまったわけだから、後々いくら森が『あなたは、宮澤さんの晩年の心の中の結婚相手だつた』(『宮澤賢治と三人の女性』)116p)とちゑに迫っても、ちゑは賢治と結びつけられることをひたすら拒絶したのだと解釈できるわけだ。
鈴木 そうか、その拒絶はちゑの矜恃ゆえにだったと吉田は言いたいわけだな。確かにそう考えてみれば、ちゑの一連の言動はすんなりと納得できる。
荒木 なるほど、ちゑの『二葉保育園』の保母としてのプライドが賢治と結びつけられることをかたくなに拒絶させたというわけか。
◇関徳弥の『短歌日記』の位置づけ
吉田 さて、そろそろここに登場させたいのが例の関徳弥の『短歌日記』中の10月4日と6日の記述だ。この日記はほぼ間違いなく「昭和6年」のものであるということが僕らによって確かめられたから、そうなるとこの前後の時間的な流れは、
・昭和6年9月28日:東京で発病し、花巻に戻って病臥。
・ 同 年10月4日:「夜、高瀬露子氏来宅の際、母来り怒る。露子氏宮沢氏との結婚話」
・ 同 年10月6日:「高瀬つゆ子氏来り、宮沢氏より貰ひし書籍といふを頼みゆく」
・ 同 年10月24日:〔聖女のさましてちかづけるもの〕
・ 推定同時期 :〔最も親しき友らにさへこれを秘して〕
・ 同 年10月24?日:〔われに衆怨ことごとくなきとき〕
・ 同 年11月3日:〔雨ニモマケズ〕
となる。
荒木 ところで何んだ、この〔われに衆怨ことごとくなきとき〕とは? 今まで登場したことがなかったはずだが…。
吉田 すまんすまん、後で説明するからちょっと待ってくれ。とりあえず続けさせてくれ。
すると考えられるのが、賢治が帰花したのと相前後して小笠原牧夫と結婚する決意を固めた露が、昭和6年10月4日に花巻高等女学校時代からの友人であるナヲの許を訪ねてその旨を報告したということだ。
そこへたまたまナヲの母ヤスがやって来た。賢治はヤスの甥だ。その賢治に最近結婚話のトラブルがあったということをヤスは聞き知ってはいたのだがその詳細までは承知していなかったので、そのトラブル相手ちゑのことを露であると誤解してヤスは怒り、そんなことだったら、賢治があなた(露)にやったものを一切返せと迫った。そのやりとりを見ていた徳弥は、義母の性格を知っているがゆえに「女といふものははかなきもの也」と日記に記した。
鈴木 そうか、こういう流れであれば徳弥があの日記に「母来り怒る。露子氏宮沢氏との結婚話」と書いたことも頷ける。
吉田 一方、そう言われた露は、賢治からかつて貰っていた本を持参して翌々日また関の家にやって来て、この本を賢治に返して欲しいと、賢治の従妹でもあり露の友人でもあるナヲにお願いして帰って行った。
以上、鈴木の好きな思考実験を僕も真似てみた。
荒木 いいんじゃねぇ、なかなか説得力がある思考実験だった。こうなると逆に、矢っ張り徳弥の『短歌日記』は「昭和6年」に書かれたものであるということの真実味がますます増してきた。
鈴木 しかも、徳弥の『短歌日記』の記述内容がなかなかうまく当て嵌まっている。
荒木 なるほどな。帰花した賢治は病に伏せながら、折角<三回目の「家出」>をしてまでちゑと結婚しようと思って上京したというのに、ちゑに一方的に裏切られてしまったと受けとめた賢治は恨みと怨念が募っていった。そこへ、もしかすると露が小笠原牧夫と来年春結婚するという噂も耳に入ったりしてさらにダメージを受けた賢治は、すっかり打ちひしがれてしまった。
ますます募ってくる苛立ちに耐え切れず賢治は、帰花して約一ヶ月後、ちゑに対する恨みと憎しみを込めてとうとう〔聖女のさましてちかづけるもの〕を詠んでしまった、という可能性が少なからずあるということか。
だから、「聖女のさましてちかづくもの」は露ではなくて実はちゑである。確かに、露ではなくてちゑとした方がすんなりと解釈できるな。もしかするとこのことは思考実験にとどまらず、実際に十分あり得たことかもな。
◇「聖女のさましてちかづけるもの」は限りなくちゑ
吉田 ではここで思考実験は止めにして、ここからはオーソドックスな考察に戻ろう。
鈴木 了解。とはいえ、この実験によって 「聖女のさましてちかづけるもの」は露とは限らず、露以外の女性も考えられるということだけはもはや明らかになったと言える。
荒木 今までの思考実験で、その可能性が少なくとも否定できないことがはっきりしたのだからな。
吉田 とはいっても、その候補者はさしあたり露とちゑしかいないというのも現実だ。そしてそれぞれ、
・露 :「レプラ」と詐病までして賢治の方から拒絶したといわれている露に対して約4年後
・ちゑ:結婚するかもしれませんと賢治が言っていたちゑに対して約2ヶ月半後
となる。
さあ、ではどちらの女性に対して、例の「このようななまなましい憤怒の文字」を連ねた〔聖女のさましてちかづけるもの〕という詩を当て擦って詠むのかというと、その可能性は
ちゑ ≪ 露
となることは明らかだろう。
荒木 「約4年後」と「約2ヶ月半後」とを比べればそれは明らか。いくらなんでも「約4年後」までも相変わらず執念深く思い続けていることはなかなかいないし、普通でぎねえべ。
吉田 まあ、「聖女のさましてちかづけるもの」が露であるという可能性は否定しないが、そうでない可能性が、それもかなりの程度あるということが言える。したがって、
「聖女のさましてちかづけるもの」は限りなくちゑである。
ということは言える。
荒木 当然この可能性の方が極めて大なのだから、詩〔聖女のさましてちかづけるもの〕を用いて<仮説:高瀬露は聖女だった>の検証作業などやれない。検証以前である、となる。
鈴木 実は、「昭和6年」の場合に問題となるのはこの〔聖女のさましてちかづけるもの〕と、例の徳弥の『短歌日記』だったが、この日記のことも織り込んで既にここまで考察してきたから「昭和6年」に関しては以上で検証作業は終了。
荒木 ということは、「昭和6年」の場合も<仮説:高瀬露は聖女だった>は検証に耐えたわけだ。さあ、それじゃいよいよ残るは「昭和7年」だけだから早くそこに移るベ。
吉田 ちょ、ちょっと待て。ほらさっきの〔われに衆怨ことごとくなきとき〕のことがあったじゃないか。
荒木 やべぇ、そおそおそおだった。俺が質問したといのに情けない。
吉田 では。それは「雨ニモマケズ手帳」の32p~33pに書かれていて、小倉豊文によればここには、
◎われに
衆怨ことごとく
なきとき
これを怨敵
悉退散といふ
◎
衆怨
ことごとく
なし
<『「雨ニモマケズ手帳」新考』(小倉豊文著、東京創元社)116pより>
と書かれていて、小倉はどちらの頁も〔聖女のさましてちかづけるもの〕の書かれた日と同じ10月24日のものらしいと推測している。
そして、小倉は賢治がこの〔われに衆怨ことごとくなきとき〕をここに書き付けた理由を次のように解説している。
恐らく、賢治は「聖女のさましてちかづけるもの」「乞ひて弟子の礼とれる」ものが、「いまわが像に釘う」ち、「われに土をば送る」ように、恩を怨でかえすようなことありとも、「わがとり来しは、たゞひとすじのみちなれや」と、いささかも意に介しなかったのであるが、こう書き終わった所で、平常読誦する観音経の「念彼観音力衆怨悉退散」の言葉がしみじみ思い出されたことなのであろう。そして、自ら深く反省検討して「われに衆怨ことごとくなきとき、これを怨敵悉退散といふ」、われに「衆怨ことごとくなし」とかきつけたものなのであろう。
<『「雨ニモマケズ手帳」新考』(小倉豊文著、東京創元社)119p~より>
鈴木 そうかそういうステップをちゃんと踏んでいたのか。実は私は今まで、10月24日に詠まれた〔聖女のさましてちかづけるもの〕と、そのたった10日後に書かれたという〔雨ニモマケズ〕の間にある両極端とも思えるほどの賢治の心の振幅の大きさがどうしても理解できなかった。
ところが賢治は、〔聖女のさましてちかづけるもの〕を詠んだ後にそのことを実はしっかりと「自ら深く反省検討」し、そして〔雨ニモマケズ〕を詠んだということか。これでやっと腑に落ちた。
荒木 実は、賢治は感情の起伏が激しかったと俺も人づてに聞いていた。まあ、そこが天才の天才たる所以の最たるものの一つなのかもしれないのだが。少なくともこれら二つの間に〔われに衆怨ことごとくなきとき〕が書いてあったということならば、それならば「雨ニモマケズ」もありだな。
よし、これでまた《愛すべき賢治》にまた一歩近づけたような気がしてきた。
◇詩は単独では伝記研究の資料たり得ない
吉田 ところで、いつもの荒木なら
<仮説:高瀬露は聖女だった>を棄却する必要はないということになる。いやあ嬉しいな。
と言って抃舞していたはずなのに、今回の「昭和6年」の場合はなしか。
荒木 いやあ、おかしいと思うんだよ俺は。この前までは賢治周辺の人たちの証言や客観的な資料等に基づいて検証を行った来たのに、今回は詩によるものだったろ。
確かに、この詩はさておき、賢治の詩は素晴らしいものが多いということは俺でもわかる。しかしな、詩は所詮詩でしかないべ。創作の一つだ。だから端的に言えば、〔聖女のさまして近づけるもの〕に書いてある内容全てが事実であるとは言えないだろうに。
鈴木 いわゆる詩は還元できないというやつだな。だからこそ、もし詩を伝記の資料として使うのであればその裏を取ったり検証をしたりした上で使わねばならないのは当然だ。
吉田 ところが、この詩に関してはそのような為すべきことを為していないだけでなく、露はクリスチャンだ、クリスチャンは聖女だ、だからこの詩〔聖女のさましてちかづけるもの〕は露のことを詠んでいるんだというあまりにも杜撰すぎる論法が採られてしまっているとなれば、結果的には露のことをこの詩は<悪女>にしてしまったという責任の一端を免れられない。
鈴木 まあもちろん、この詩そのものにその責任があるわけではなく、そう理解した人の責任だけどね。
荒木 一方、実はそれは露ではなくてちゑである可能性が極めて大であるということを俺たちは導けたのだから、この詩を元にして<悪女>扱いされた節もある露にすれば踏んだり蹴ったりだ。濡れ衣もいいどこだべ。
吉田 確かにそうだが、かの小倉豊文でさえもこの〔聖女のさまして近づけるもの〕を引き合いに出して、「この詩を読むと、すぐに私はある一人の女性のことが想い出される」(『「雨ニモマケズ手帳」新考』(小倉豊文著、東京創元社)111p)と言って、これは露のことを詠んだのだと実質的に断定している。
あるいはまた、佐藤勝治でさえも例の「このようななまなましい憤怒の文字はどこにもない」と言いつつも、この詩は露のことを詠っているのだとつゆほども疑っていない。それは境忠一でさえもそう言えなくもないし、他の多くの人もおしなべてそのように認識し、これだけ賢治が憤怒を込めて詠っているくらいだから、露は相当な<悪女>だと単純に決めつけてしまうだろう。
荒木 しかしだよ、単に手帳に書かれた一篇の詩によってだぞ、その一枚の紙切れによって一人の人間の尊厳や人格が安易に全否定されるということは許されていいのが!
吉田 荒木が怒るのももっともだ。それもこれも、然るべき人たちがその裏付けも取らず、検証もせずに漫然と<悪女伝説>の再生産を繰り返してきたからだ。いかな賢治の詩といえども単独であっては「伝記研究」の資料たり得ないことは当たり前のことなのにさ。
鈴木 何かというと、それらしいことや不都合なことがあるといつもそれは露だと決めつけられてきた傾向がある。例えば、露であることが全く判然としていないのに「判然としている」と決めつけられた「昭和4年の書簡下書群」、そして今回の〔聖女のさまして近づけるもの〕の「聖女」、さらにはこの次の年に出てくる「悪口を言いふらした女性」、皆そうだ。
吉田 これらのことに鑑みれば、そこには明らかに何者かによるそれこそ「悪念」や「奸詐」があったということがもはや否定できなかろう。
荒木 おいおい憶測でそんな物騒なこと言ってもいいのか。ちょっとまずいよそれは。
吉田 実はある作家が、
もし硬い、高い壁と、そこに投げつけられて壊れる卵があるなら、たとえ壁がどんなに正しく、卵がどんなに間違っていても、私は卵の側に立つ。
<『朝日新聞、平成21年2月25日、斎藤美奈子・文芸時評』より>
と言ったということだが、僕は今このことを思い出している。
誰しも皆、自分が高い壁の側に立つとは言わないとは思うが、高い壁となって立っている人がいるのも紛れもない事実。そしてちょうどこの「卵」とは露、あるいはこの<仮説:高瀬露は聖女だった>のことかもしれない。
しかも、ここまで調べた来た限りにおいては「卵がどんなに間違っていても」どころか露の行為はほぼ間違っていないと言えるし、一方の壁については「壁がどんなに正しく」てもどころかかなり間違っていることがわかったのだから、少なくとも僕は「卵の側に立つ」。
荒木 何だよ突然に、それも一人だけかっこつけて。しかもそれって村上春樹のスピーチのパクリだべ。
鈴木 じゃじゃじゃ、すっかり吉田にしてやられたな。
荒木 なあに、さっき言い過ぎたからその照れ隠しだべ。
吉田 ばれたか。
鈴木 それでは、「昭和6年」に関わる検証結果をここで確認すれば、「そもそも詩を単独で伝記研究の資料として使うことには無理がある」ということを肝に銘じつつ、
詩〔聖女のさまして近づけるもの〕の内容によって、〈仮説:高瀬露は聖女だった〉を棄却する必要はない。
だ。これで「昭和6年」に関しての考察は一切終了。
荒木 ということは、<仮説:高瀬露は聖女だった>は相変わらず検証に耐え続けているということか。さしずめ検証に耐え続けている「卵」というところだな。それじゃ脆くて弱い「卵」よ、今はまだそうかも知れんがこの次の「昭和7年」も検証に耐え得れば、晴れて雛になって歩み始めることができて、そのうち空も飛べるかもしれんぞ、あと少し頑張れと願いつつ最後の年の検証作業に移ろうか。
 続きへ。
続きへ。
前へ 。
。
 〝「聖女の如き高瀬露」の目次〟 へ。
〝「聖女の如き高瀬露」の目次〟 へ。
 〝渉猟「本当の賢治」(鈴木守の賢治関連主な著作)〟へ。
〝渉猟「本当の賢治」(鈴木守の賢治関連主な著作)〟へ。
 ”みちのくの山野草”のトップに戻る。
”みちのくの山野草”のトップに戻る。 。
。
ある著名な賢治研究者が私(鈴木守)の研究に関して、私の性格がおかしい(偏屈という意味?)から、その研究結果を受け容れがたいと言っているという。まあ、人間的に至らない点が多々あるはずの私だからおかしいかも知れないが、研究内容やその結果と私の性格とは関係がないはずである。
おかしいと仰るのであれば、そもそも、私の研究は基本的には「仮説検証型」研究ですから、たったこれだけで十分です。私の検証結果に対してこのような反例があると、たった一つの反例を突きつけていただけば、私は素直に引き下がります。間違っていましたと。
一方で、私は自分の研究結果には多少自信がないわけでもない。それは、石井洋二郎氏が鳴らす、
そして実際、従前の定説や通説に鑑みれば、荒唐無稽だと言われそうな私の研究結果について、入沢康夫氏や大内秀明氏そして森義真氏からの支持もあるので、なおさらにである。
【新刊案内】
そのようなことも訴えたいと願って著したのが『このままでいいのですか 『校本宮澤賢治全集』の杜撰』(鈴木 守著、録繙堂出版、1,000円(税込み))

であり、その目次は下掲のとおりである。

現在、岩手県内の書店で販売されております。
なお、岩手県外にお住まいの方も含め、本書の購入をご希望の場合は葉書か電話にて、入手したい旨のお申し込みを下記宛にしていただければ、まず本書を郵送いたします。到着後、その代金として1,000円分(送料無料)の切手を送って下さい。
〒025-0068 岩手県花巻市下幅21-11 鈴木守 ☎ 0198-24-9813
荒木 ところで、前に吉田が言っていた「ある伏線」はこれらとどう繋がるのだ?
吉田 ご免、そのためにはもう少し準備運動が必要なんだ。まずは、当時のことを時間的な流れで以下に確認したい。
・大正15年秋~昭和2年夏:下根子桜の賢治の許に露出入り(菊池映一氏の証言より)。
・昭和2年秋 :伊藤ちゑ兄と共に来花、賢治と会う(10月29日付藤原嘉藤治宛書簡より)。
・昭和3年6月 :賢治伊豆大島行。
・同時期帰花後 :賢治、「おれは結婚するとすれば、あの女性だな」と嘉藤治に語った。
・昭和3年8月~ :賢治実家に戻り、病臥。
・昭和6年7月7日:ちゑとの結婚話がまた持ち上がっていることを賢治自身が森に語った。
・同 年9月19日 :40㌔あまりのトランクを持って上京。
・同 年9月20日 :着京。以降滞京。発熱。
・同 年9月28日 :東京から花巻に戻り、病臥。
・同 年10月4日 :「夜、高瀬露子氏来宅の際、母来り怒る。露子氏宮沢氏との結婚話」
・同 年10月6日 :「高瀬つゆ子氏来り、宮沢氏より貰ひし書籍といふを頼みゆく」
・同 年10月24日 :〔聖女のさましてちかづけるもの〕
・ 推定同時期 :〔最も親しき友らにさへこれを秘して〕
・同 年11月3日 :〔雨ニモマケズ〕
そして、この中のポイントは
・昭和6年7月7日に賢治が森に対して語ったというところの、また持ち上がった伊藤ちゑとの結婚話
だと思っているんだ。そしてこの「また持ち上がった伊藤ちゑとの結婚話」が「伏線」となって〔聖女のさましてちかづけるもの〕が詠まれたのではなかろうかと僕は考えている。
荒木 もう少し具体的に説明してくれ。
吉田 これはあくまでも僕の推測であり、これから述べることは一つの思考実験だがそれでもいいか。
荒木 中身によりけりだがな。さあ、どうぞ。
吉田 僕も以前から、「聖女のさましてちかづけるもの」とは果たして露なのか? どうもそうとばかりは言い切れないと考えていた。
二人もそう訝っていると思っているが、昭和2年の夏以降になると賢治は露を拒絶するようになったと言われているのに、その頃から約4年もの時を経てしまった昭和6年の10月に、例の「このようななまなましい憤怒の文字はどこにもない」ような詩を露に当て付けて詠むか。
荒木 そりゃあ確かに常識的にはあり得ねえべ…。あっ、わがった、そういうことか。「聖女のさましてちかづけるもの」とは露のことではなくてちゑのことであり、ちゑとの結婚にまんざらでもないということが推察される「昭和六年七月七日の日記」に出てくるような賢治の想いが「伏線」となって、賢治をして〔聖女のさましてちかづけるもの〕を詠ましめた、ってわけな。
吉田 そう、実は「聖女のさましてちかづけるもの」とは巷間言われている露ではなくて、伊藤ちゑのことなのだ。
承知のように、昭和6年頃になると賢治自身が『「私も随分かわつたでしょう、変節したでしょう』というくらいだから、かつての賢治とはすっかり様変わりしてしまった。独身主義ももうやめた。ちなみに、
「私は結婚するかもしれません――」と盛岡にきて私に語つたのは昭和六年七月で、東北碎石工場の技師となり、その製造を直接指導し、出來た炭酸石灰を販賣して歩いていた。さいごの健康な時代であつた。
<『宮澤賢治と三人の女性』(森荘已池著、人文書房)104pより>
と森が証言している。
このように独身主義からはおさらばした賢治は、前々からちゑとならば結婚してもよいと思っていたがゆえに、再燃したちゑとの結婚話を持ち出して「私は結婚するかもしれません――」と昭和6年7月に森に喋った。そして、そのことをちゑと具体的に話し合おうと思ったこともあって同年9月に上京した。
荒木 おっと、それはまさかの展開だな。そんな話今まであったけがな?
鈴木 そっか、昭和6年の上京は東北砕石工場の製品売込みのためだったとばかり私は思っていたが、それだけではなくて、ちゑと会ってその結婚話を進めるためでもあったということな。だけど、その時の上京の際に賢治が伊豆大島まで行ったという証言や記述はどこにもないはずだが。
吉田 いやぁ、違うんだなそれが。その頃ちゑは東京に戻っていたようだし、僕はこの時の上京はまたぞろ賢治が「家出」をするためでもあったと推測している。
荒木 昭和6年の上京の一つの目的はちゑと会って結婚の話を具体的に進めるためだったはとりあえず了としても、もう一つは「家出」のためだったというのか。おいおい、思考実験とはいえそれはあまりにも荒唐無稽だべ。
吉田 まあまあ、これはあくまでも実験だ。まずは前者、ちゑとの結婚について。
澤村修治氏がこう述べている。
これでは学校の経営もままならない。そうした不如意のあげく、同年八月一三日、七雄は遂に逝去する。…(筆者略)…兄の逝去とともにチヱは東京に戻る。休職していた二葉保育園に保母として復帰。
<『宮澤賢治と幻の恋人』(澤村修治著、河出書房新社)182pより>
そしてここでいう「同年八月一三日」とは昭和6年8月13日のことだということが、同書から判る。
荒木 そっか、昭和6年9月の賢治の上京時には既に七雄は亡くなっており、ちゑは東京に戻って住んでいたのか。
鈴木 となれば伊豆大島の場合とは違って、上京した賢治ならば会おうと思えば比較的容易に伊藤ちゑに会えたことになるな。上京の前々月、再燃したちゑとの結婚話を持ち出して「私は結婚するかもしれません――」と森に喋っていた賢治のことだ、そのことをちゑと具体的に話し合おうと思ったこともあって同年9月に上京したということは確かにあり得る。
吉田 では次、後者について。
堀尾の『年譜 宮澤賢治伝』には、賢治が熱を出して寝ているという八幡館から電話連絡が入った菊池武雄が駆けつけて、
「花巻のおうちへ知らせよう」
といった。すると賢治はつよく、
「いやそれは絶対困ります。絶対帰りません。しらせないでください」
という。…(筆者略)…
それに賢治は、
「なあに風邪です、すぐよくなります」
と、いかにも病気のことは専門だといわぬばかりに自分でうけあい、
「よくなったら、ここから墨染の衣をきて托鉢でもしてまわりますよ」
と妙なことをいう。
<『年譜 宮澤賢治伝』(堀尾青史著、中公文庫)424p~より>
とある。
そこで、どうも賢治は花巻に帰りたくないらしいと判断した菊池は、武蔵野に小さい貸家を見つけ出して賢治にそのことを知らせた、というような貸屋探しのことが具体的にそこに続けて述べられている。
鈴木 つまり賢治はこの時花巻に戻るつもりは毛頭なく、このまま東京に居て托鉢などもして回りたい。ついては住む家を探している、というようなことなどを言ったものだから菊池は貸家を見つけてやったという次第か。なんだか、大正10年の「家出」の時と似たにおいがしてきた。
荒木 そうか、賢治は実質的に「家出」を目論んで上京したと吉田は言いたいわけだ。
鈴木 しかし賢治はこの上京の折り直ぐに、9月21日に「遺書」を書いていたわけで、着京即重態に陥り死を覚悟したと思うのだが。
吉田 確かに通説ではそうなっているがそれは「遺書」ではないという見方も可能だろう。ちなみにその中身は
この一生の間どこのどんな子供も受けないやうな厚いご恩をいたゞきながら、いつも我慢でお心に背きたうたうこんなことになりました。今生で万分一もついにお返しできませんでしたご恩はきっと次の生又その次の生でご報じいたしたいとそれのみを念願いたします。
どうかご信仰といふのではなくてもお題目で私をお呼びだしください。そのお題目で絶えずおわび申しあげお答へいたします。
九月廿一日
賢治
父上様
母上様
<『校本全集第十三巻』(筑摩書房)379pより>
というものだ。
荒木 あっ、そうそう奇しくも賢治の命日ってやつな。
吉田 だからなおさら「遺書」と思いたくもなるが、日にちの一致はそれとは無関係なこと。それよりは、この文面からは、花巻から離れての「家出」、決して花巻の実家に戻ることはないという自分自身に向けた決意表明だったととれなくもない。
鈴木 確かに、着京したと思われるのが9月20日、ところがその翌日に突如賢治は重篤となったので死を覚悟してこの「遺書」を書いた、ということは言われてみれば確かに奇妙だし不自然なことだ。
荒木 そういえば前に名前が挙がった菊池武雄とは、この上京の折りに賢治が「和とぢ」の本をプレゼントしたという人のことだよな。そうすると、賢治は何時どこでそれを菊池に渡したのだろうか。即重篤になったというのならばその機会がなかっただろうに。
吉田 そのことについては菊池自身が『宮澤賢治研究』所収の「賢治さんを想ひ出す」の中でこう語っている。
その後去年の春突然駿河臺のある旅館から電話で「宮澤さんといふ方が上京していま風邪を引いて休んで居られる」と知らせてくれたので行つて見たら、いつものニコニコした顔で床に就いて居られたが私は容易でないことを直感しました。その時「お土産に持つて來たのだけれども形見になるかも知れぬ」といつて私にレコード(死と永生)二枚と○本などをくれました。私は何とかして健康回復のために力になり度いと願つたけれど、一つは賢治さんの性質も解つてゐるからそれも尊重したいし、私も微力と生まれつきの不親切者故、なにもして上げられませんでした。
<『宮澤賢治研究』(草野心平編、十字屋書店)325p~より>
荒木 あれっ、ここには「和とぢ」の本などではなくて、プレゼントしたのは「○本」とあるけど? あっそうか、この「○本」は「和とぢ」の本つまり「春本」を憚った表現か。
鈴木 でも変だな。さっき吉田が教えてくれた堀尾の記述内容だと菊池は結構賢治の世話を焼いているのに、こちらの菊池の証言によれば菊池は何もしてやれなかったいうことだから矛盾がある。
吉田 矛盾ということで言えば、このことに関しては、深沢紅子の証言とも矛盾している。深沢は随筆「一ぱいの水-賢治との出会い」の中で次のように述べている。
昭和6年当時吉祥寺に住んでいた私の家に賢治がやって来て、
「宮沢ですが、お隣の菊池さんが留守ですから、これを預かってください」
<『追憶の詩人たち』(深沢紅子著、教育出版センター)124p~より>
と言われたと。
荒木 えっ! 深沢紅子は菊池武雄と隣同士だったのか。
吉田 そうだよ。たしか、「菊池さんとは私達夫婦も非常に親しい仲なので隣り同士に住んでいた」ということもそこで綴っていたはずだ。
鈴木 じぇじぇじぇ、菊池と深沢夫婦はそんなに懇意だったのか。確かに、言われてみれば三人とも同じ画家だからな。こうなったのではっきり言ってしまうけど、実は前に私が紹介した「私ヘ××コ詩人とお見合いしたのよ((註十三))」だが、このようにちゑが漏らしたその相手こそ深沢紅子だったのだ。
吉田 そうだったのか、な~るほどな。
鈴木 もちろん菊池は見合いの世話をしたくらいだからちゑとは何らかの繋がりはあっのだろうとは思っていたが、今までなぜ紅子にちゑがこんなことを、しかもざっくばらんに言ったのかその背景がいまひとつわからずにいた。それが、深沢と菊池は隣同士で住む程に親しくて
深沢紅子⇔菊池武雄⇔伊藤ちゑ
という繋がりができていたのか。これで腑に落ちた。
吉田 しかも、伊藤ちゑは1921年盛岡高等女学校卒(『宮澤賢治の幻の恋人』165p より)、一方の深沢(四戸)紅子も同じく盛岡高等女学校1919年卒 (『追憶の詩人たち』巻末より )だからちゑは2年後輩の同窓生、高等女学校の就学期間は5年間なのでちゑと深沢は3年間同時期に盛岡高女に通っていたと考えられる。だから、
菊池武雄⇔画家⇔深沢紅子⇔同窓生⇔伊藤ちゑ
という繋がりもあった。
鈴木 なるほど、そうなると菊池がちゑのお見合いをお膳立てしたということもなんとなく頷ける。
吉田 そこで先程の荒木の質問の「どこで」に対する答にもなると思うのだが、深沢はこんなことも証言している。
賢治はその時、『これを預かってください』と言って包みを二つ差し出して、一杯の水を飲んで帰っていった。
夕方吉祥寺に戻った菊池がその二つの包みを開けるのを見ていたならば、小さい方の包みは「和とぢ」の本であり、もう一つの方はレコードだった。菊池は、「何で俺にこんなものくれたべなあ」とお国なまりの独り言を言った。
<『追憶の詩人たち』124p~より>
鈴木 確かに菊池と深沢の証言の間には矛盾があるが、両者を比較すればこの件に関してはどうやら深沢の証言の方が信憑性が高いな。さっきの矛盾、今度の矛盾共に菊池絡みだからな。ここは信頼度が高いのは深沢の方とならざるを得ないだろうから、答は「吉祥寺で」となるのか。もしかすると、菊池は何かを庇っているのかもしれないな。
荒木 つまり、「賢治はどこでそれを渡したか」の答は駿河台の八幡館でではなくて吉祥寺でだろう、ということか。
吉田 そしてほら、この時の鈴木東藏宛書簡〔395〕にこんなことが書いてある。
実は申すも恥しき次第乍ら当地着廿日夜烈しく発熱致し今日今日と思ひて三十九度を最高に三十七度四分を最低とし八度台の熱も三日にて屡々昏迷致し候へ共心配を掛け度くなき為家へも報ぜず貴方へも申し上げず居り只只体温器を相手にこの数日を送りし次第に有之
<『校本全集第十三巻』(筑摩書房)380p~より>
荒木 となれば、「廿日夜烈しく発熱致し」ということだから賢治は9月20日の夜からひどい熱発、その後は床に就いていたようだから、その前に吉祥寺を訪れていたことになり、それはやはり9月20日しかあり得ないな。
鈴木 それに、9月20日付鈴木東藏宛書簡〔392〕方も見てみると「午后当地に着」とあるから20日の午後に着京しているようなので、その足で吉祥寺へ行ったかもしれないな。
吉田 実はこの件に関して、賢治はあの『雨ニモマケズ手帳』の二頁目にも次のように、
昭和六年九月廿日/再び/東京にて發熱。
と書き込んでいるから、賢治はやはり9月20日に突如「熱発」したとするしかない、と以前の僕は考えていた。
荒木 実はそうとも言えないというのか?
吉田 うん。というのも、この頃の賢治の体温はどうだったかというと、『兄妹像手帳』に賢治自身が次表のようにとメモしている(『校本全集第十二巻 (上)』134p)。
┌─────────┐
│ │
│ │
│ │
│ │
└─────────┘
しかも加藤謙次郎は、19日に仙台の古本屋内で浮世絵の話をしていた賢治に偶々出会い、
自宅に案内して夕食を共にし、夜遅くまで話し込んだ。…(筆者略)…化粧煉瓦を造つて売る計画を説明し、その試作品を携えて名古屋方面迄売込宣伝に行つて来ると張り切りつて居り、胸が悪い様子は全然感ぜられなかつた。
<『宮沢賢治とその周辺』(川原仁左エ門編著)315p~より>
と証言している。
荒木 そうなんだ。その上、21日までの体温はいずれも37℃台じゃないか。賢治は「九月廿一日」付の「遺書」を書いたというのが通説のようだが、これぽっちの「高熱」がたった二、三日続いただけであのような「遺書」を書くというのか? 書くわけねえべ。あれはもはや「遺書」などではないということだな。
ということは、先程の俺の質問の残り「いつ」に対する答は、
少なくとも9月22日以降の高熱から判断すれば22日以降に吉祥寺に行ったことはまずなかろうことと、着京が9月20日であることは間違いなさそうだから、吉祥寺行きは20日か21日であろう。
ということか。
吉田 いずれ、賢治の体温が高かったとはいえこの両日ならばまだ37℃台、無理すれば吉祥寺に行けないこともないから、このいずれかの日に賢治は少なくとも吉祥寺の菊池武雄の家に行き、また当時近くに住んでいたとも思われる伊藤ちゑの許へも訪ねて行った。まあ、これらはあくまでも思考実験上でのことだけど。
鈴木 あっそっか!
荒木 なんだよ、突然でかい声を出して。
鈴木 実は、ちゑの直ぐ上の姉ハナが当時吉祥寺に住んでいた(平成26年11月7日、伊藤ちゑの生家当主より)というんだな。だから、吉田の今の発言は現実的にもあり得た。
吉田 おっ、棚からぼた餅だな。よくよく考えてみれば、高熱にも関わらず菊池武雄へ「春本」等を届けるために賢治がわざわざ吉祥寺に行ったということは妙な話だと思っていたが、当時ちゑは吉祥寺の姉の家に住んでいた等ということもあり得るから、これでますますこの思考実験も現実味を帯びてきたぞ。
そのついでに調子に乗って言えば、場合によっては、この東藏宛書簡〔395〕中の「廿日夜烈しく発熱致し…熱納まるを待ちてどこかのあばらやにてもはいり」は賢治の方便であった可能性もあるということも視野に入れる必要があるかもしれん。
荒木 どういうことだ?
吉田 他でもない、そうすれば少なくとも取り敢えず家に戻らなくてもよいことになるから実質的な「家出」ができるだろう。裏を返せば、この東藏宛書簡は、実質的に賢治は三回目の「家出」をする覚悟であったということの一つの傍証となりそうな気もする。
鈴木 それはちょっと論理の飛躍で、無理筋だと思うがな。う~む、段々何が何だかわからなくなってきたぞ。
荒木 え~と、昭和3年の上京は「逃避行」と言えなくもない。一方今回の昭和6年の上京は「東北採石工場技師」になってから約7ヶ月後の仕事に行き詰まりを見せ始めた頃の上京だし、少なくとも直ぐに花巻に戻ることは考えていなかったそれだ。そういや羅須地人協会の活動の場合も約7ヶ月で頓挫した。
鈴木 しかも昭和3年の場合は田植え前後の、昭和6年の場合は稲刈り前後の共に農繁期の古里を離れての上京だ。だから、賢治の場合には、少しやってみて少し問題にぶつかったならば直ぐに放り出し、そこから逃避してしまうという性向がどうやらありそうで、確かに同じ構図がこの2つにはあるな。
荒木 ところでその「家出」だが、最初のは何となくわかるが…。
吉田 もちろん最初の一回目は、
その時頭の上の棚から御書が二冊共ばつたり背中に落ちました。さあもう今だ。今夜だ。時計を見たら四時半です。汽車は五時十二分です。すぐに臺所へ行つて手を洗ひ御本尊を箱に納め奉り御書と一緒に包み洋傘を一本持つて急いで店から出ました。
<『宮澤賢治素描』(関登久也著、共榮出版)47pより>
という大正10年1月の衝動的で突発的な「家出」。
二回目が、これもまた突如花巻農学校の職を辞して下根子桜で暮らしを始めたことも、確たる見通しもないままのそれだったのだから僕に言わせれば実質的には「家出」で、これ。
そして三回目が、この昭和6年9月の上京だ。ただしほとんどの人はそうは思わんだろうけどな。
荒木 いや、三回目も吉田に段々刷り込まれてきたせいか、それもありかなと思うようになってしまった。世の中、二度あることは三度あるとも言うしな。
吉田 あっそうそう。僕と似たことを小倉豊文がこう言っていたはずだ。
最後の上京にしても、その前後二回の家を出ての独立的生活にしても、賢治にとって実に思い出深いものであったろう。賢治はその都度命がけの「出家」を決行したのである。
<『「雨ニモマケズ手帳」新考』(小倉豊文著、東京創元社)47pより>
と。ただし、こちらは文字が逆で「出家」だけど。
鈴木 そうか、小倉も三回と見ていたのか。それも「命がけの」。なるほどな。いずれ、この三回の「家出」にしてもあるいは「出家」にしても、まさしく不羈奔放な賢治の面目躍如というところかな。
荒木 皮肉か?
鈴木 とんでもない、このような賢治だからこそあれだけの作品を書けたということだよ。あの『春と修羅』のようなものをスケッチ出来る人が今後現れることなど二度とないだろう。
荒木 確かにこうやって振り返ってみると、この時の上京は賢治<三回目の「家出」>というのは十分にあり得ることだ。
思考実験<賢治ちゑに結婚を申し込む>
吉田 さて思考実験の続きだが、昭和6年9月 賢治が東京に「家出」をしようと思ったのは、もちろんちゑと結婚しようと思ったからだ。
鈴木 確かにそう言われてみれば、『宮澤賢治』(佐藤隆房)や『宮澤賢治と三人の女性』によれば、
伊藤さんと結婚するかも知れません
と賢治がほのめかし、ちゑのことを
ずつと前に話があつてから、どこにも行かないで待つてゐるといはれると、心を打たれますよ。
と認識し、しかも、
禁欲は、けつきよく何にもなりませんでしたよ、その大きな反動がきて病氣になつたのです
と悔いていたようだから、この頃になると賢治は独身主義を棄て、賢治はちゑならば
自分のところにくるなら、心中のかくごで
来てくれると思っていた節もあり、この頃の賢治はいよいよちゑと結婚しようと決意した、という可能性はないとは言えない。
荒木 しかも森の「『三原三部』の人」によれば、
けれどもこの結婚は、世の中の結婚とは一寸ちがつて、一旦からだをこわした私ですから、日常生活をいたわり合う、ほんとうに深い精神的なものが主となるでせう。
<『宮澤賢治と三人の女性』(森荘已池著、人文書房)115p~より>
というようなところまでも賢治は考えていたようだからな。
吉田 一方、昭和3年の「逃避行」とも見られる上京の場合と同じように、東北採石工場の仕事も約7ヶ月が過ぎた頃からその仕事も行き詰まってきたのでそこから逃れたくなったこともあって、賢治はちゑとの結婚を決意、東京に出て「東北砕石工場」の代理店を開いて化粧煉瓦を売ったりしながら生計を立て、「日常生活をいたわり合」いながらちゑと一緒に暮らそうと計画した。そしていよいよ昭和6年9月19日、化粧煉瓦を詰めたトランクを持って花巻を後にした。
荒木 どうだべがな?
吉田 まあまあ、単なる思考実験だ。続けよう。
もちろん、上京した賢治はいの一番にちゑの許を訪ねてその決意をちゑに伝え、結婚しようと切り出した。ところが、「ずつと前に私との話があつてから、どこにもいかないで居るというのです」と認識していたのは賢治の方だけ。先に明らかにしたように、一方のちゑはもはや賢治と結婚するつもりは全くなかったからきっぱりと断った。
荒木 しかも兄七雄が急逝したばかりだからなおさらに、きっぱりとその申し出を断ったということもありかな。
吉田 それもあると思うし、我が身を擲ってきたスラム保育を続けたいという強い意志と信念もあったんじゃないのかな。
ただし、賢治の方は予想だにしなかったちゑの拒絶にすっかり打ちのめされてしまった。しかし賢治とすれば「家出」の覚悟だったから、今更直ぐさまおめおめと実家に戻るというわけにもいかず、貸屋探しを菊池武雄に依頼。
荒木 そうか。「家出」の覚悟だったからこそ当初は、上京して直ぐに熱発しても頑なに実家に戻ることを拒み、なおかつ東京で住む家まで探していたということか。
鈴木 それにしてもなあ、ちゑとならば結婚してもいいと覚悟を決めて折角「家出」までして来た賢治とすれば、それが完全に裏切られたと受け取っただろうな。
荒木 そこで賢治の心の中にちゑに対する憎しみがめらめらと燃え始めた。
吉田 そのこともあって緊張の糸が切れてしまった賢治は、その反動で、もともと体調不十分だったこともあって途端に熱発、床に伏した。
荒木 これで何もかも終わり、賢治は夢も希望も失ってしまってもはや生きる望みもなくなり、あの「遺書」を書いた。
吉田 なるほど、こうなってみると荒木のその見方もありかもな。たったあの程度の熱発で着京直後に「遺書」を書くのかということと、ちゑからの結婚拒絶で受けたショックで死にたくなって「遺書」を書いたということとを比べてみれば、後者の方が確かに説得力があるな。
荒木 なっ。
吉田 さて、連日の高熱で床に伏しながら賢治は今後のことに思いを巡らした。もはやちゑとの結婚計画も頓挫した、「家出」をする意味もなくなってしまった。当然東京にいる必要もなくなってしまった。切羽詰まってしまった。
鈴木 そこで、9月27日に賢治は父政次郎へ
もう私も終わりと思いますので最後にお父さんの御聲をきゝたくなつたから……
<『宮澤賢治の手帳 研究』(小倉豊文著、創元社)22pより>
と電話した。その時にどれほどの病状だったかはわからないにしても、精神的にはとことんまで追い詰められていたということだけはたしかであっただろう。
吉田 いやどうだか。賢治は泣きを入れただけのことかもしれないぞ。
とまれ、その電話を受けて父は即刻帰花するようにと厳命。賢治は後ろ髪引かれる思い、あるいは逆に「渡りに舟」だったかもしれないが、いずれにせよ帰花。実家にて病臥した。
鈴木 ちなみにこの時、花巻に戻った賢治は父政次郎に何と言ったか。小倉豊文は『「雨ニモマケズ手帳」新考』に、
賢治はこの時はじめて父に向って「我儘ばかりして済みませんでした。お許し下さい」という意味の言葉を発したという。
<『「雨ニモマケズ手帳」新考』(小倉豊文著、東京創元社)24pより>
と記している。
荒木 そっか、この謝罪の文言「我儘ばかりして済みませんでした。お許し下さい」がそのとおり事実であったとすれば、この時の賢治は「家出」という決意をして上京したという吉田の「私見」が、俄然説得力を持ってきたな。
思考実験<「聖女のさましてちかづけるもの」はちゑ>
さらに思考実験を続ける。
◇『二葉保育園』の保母としてのプライド
吉田 さて、花巻に戻った賢治は実家で病に伏せながら先にも引用したように、『雨ニモマケズ手帳』の実質的な一頁に「昭和六年九月廿日/再び/東京にて發熱。」というように、<三回目の「家出」>のことをまず書いた。そしてこの手帳を書き進めていくうちに、賢治とならば結婚してもいいとちゑの方も思っているものとばかりに思い込んでいた賢治だったが、実際に結婚を申し込んだところちゑからはけんもほろろに断られてしまったから、ちゑに一方的に裏切られてしまったという屈辱感が日に日に募ってきて病臥中の賢治を苛み、次第に溜まってくるフラストレーションがついに爆発、10月24日「なまなましい憤怒の文字」を連ねた〔聖女のさましてちかづけるもの〕を『雨ニモマケズ手帳』に書いてしまった。
荒木 つまり、再び持ち上がったちゑとの「結婚話」が伏線となってこの詩を詠ましめたというわけだ。したがって、
賢治が「聖女のさましてちかづけるもの」と詠んだ女性は巷間言われている露ではもちろんなくて、誰あろうちゑのことだった。
と、そう吉田は言いたいのだ。
吉田 そういうこと。
鈴木 実は賢治は、当時ちゑが勤めていた『二葉保育園』のことや、ちゑがそこでどのようなことをしていたのかということをある程度知っていたと思うんだな。
荒木 何だ藪から棒に。
鈴木 実は、『光りほのかなれど―二葉保育園と徳永恕』(上笙一郎・山崎朋子著、教養文庫)によれば、同園の創設者の野口幽香と森島美根は、当時東京の三大貧民窟随一と言われていた鮫河橋に同園を開いて、寄附金を募ってそれらを元にして慈善教育事業、社会事業としての貧民子女の保育等に取り組んでいたというんだな。
そして、野口も森島も敬虔なクリスチャンであり、ちゑが勤めていた頃の同園の実質的責任者は徳永恕はクリスチャンらしくないクリスチャンだったという。ちなみに、現在でも同園は「キリストの愛の精神に基づいて、健康な心とからだ、そしてゆたかな人間性を培って、一人ひとりがしっかりとした社会に自立していけることを目標としています」という理念を掲げている。
つまり当時のちゑは、スラム街の貧しい家の子どもたちのために保育実践等をしていた、いわば<セツルメントハウス>と言える『二葉保育園』に勤めていたんだ。
荒木 つい俺は今まで、『二葉保育園』とは普通の保育園だとばかり思っていたがそうではなかったんだ。同園はセツルメント活動をしてたのか。あっ、そうか腑に落ちたぞ。そういえば、
そのころちゑさんは、あるセッツルメントに働いていました。母子ホームです。
<『宮澤賢治と三人の女性』(森荘已池著、人文書房)118pより>
と森が述べていたがこのことを意味してたんだ。
吉田 だからか、森は同書で
そしてこの少女は…(筆者略)…兄の死んだあとは、東京の母子寮にその生活の全部、全身全霊をささげて働いた。
<『宮澤賢治と三人の女性』171pより>
とも述べている。
鈴木 そうそう、二葉保育園には母子寮があって、
恕のつくったこの二葉保育園の母の家は、近代日本における〈母子寮〉という社会福祉施設の嚆矢であった!
ということも前掲書では述べてあったから、おそらくちゑはその頃はこの「母子寮」にも勤めていたのだろう。
荒木 ということであれば、賢治はちゑがそのような所で働いていることはある程度知っていただろうから、ちゑが「聖女のさまして」見えたということは十分にあり得る。したがって、もしそのような女性から仮に裏切られてしまったと賢治が思い詰めたとすれば、まさに
ちゑ=聖女のさましてちかづけるもの
と言い募ってしまいたくなるのも理屈としては成り立つな。
鈴木 なお断っておきたいのだが、だからといってちゑが問題のある人だと私は言いたいわけでは毛頭ない。
それどころか、ちゑは「翔んでる女性」である一方で、『二葉保育園』ではスラム保育のセツルメント活動に取り組んでいただけではなくて、兄の看護のために伊豆大島に居た頃はこっそりと隣の老婆を助けたり、そこを去ってからもその老婆に毎月「5円」を送金し続けたりするような女性であったということだから、なかなかな人だ。
荒木 そっか、昭和3年6月の「伊豆大島行」の際に、ちゑが賢治と結婚しないと心に誓ったのは、この当時のちゑの生き方からすれば、「高等遊民」のような生き方をしていた賢治に惹かれることはなかったからか。確かに雲泥の差があるもんな、その生き方の姿勢に。
吉田 そうか、ちゑはそういうとても素晴らしい人だったんだ。一方では、ちゑは賢治をいわば「振った」という形に結果的にはなってしまったわけだから、後々いくら森が『あなたは、宮澤さんの晩年の心の中の結婚相手だつた』(『宮澤賢治と三人の女性』)116p)とちゑに迫っても、ちゑは賢治と結びつけられることをひたすら拒絶したのだと解釈できるわけだ。
鈴木 そうか、その拒絶はちゑの矜恃ゆえにだったと吉田は言いたいわけだな。確かにそう考えてみれば、ちゑの一連の言動はすんなりと納得できる。
荒木 なるほど、ちゑの『二葉保育園』の保母としてのプライドが賢治と結びつけられることをかたくなに拒絶させたというわけか。
◇関徳弥の『短歌日記』の位置づけ
吉田 さて、そろそろここに登場させたいのが例の関徳弥の『短歌日記』中の10月4日と6日の記述だ。この日記はほぼ間違いなく「昭和6年」のものであるということが僕らによって確かめられたから、そうなるとこの前後の時間的な流れは、
・昭和6年9月28日:東京で発病し、花巻に戻って病臥。
・ 同 年10月4日:「夜、高瀬露子氏来宅の際、母来り怒る。露子氏宮沢氏との結婚話」
・ 同 年10月6日:「高瀬つゆ子氏来り、宮沢氏より貰ひし書籍といふを頼みゆく」
・ 同 年10月24日:〔聖女のさましてちかづけるもの〕
・ 推定同時期 :〔最も親しき友らにさへこれを秘して〕
・ 同 年10月24?日:〔われに衆怨ことごとくなきとき〕
・ 同 年11月3日:〔雨ニモマケズ〕
となる。
荒木 ところで何んだ、この〔われに衆怨ことごとくなきとき〕とは? 今まで登場したことがなかったはずだが…。
吉田 すまんすまん、後で説明するからちょっと待ってくれ。とりあえず続けさせてくれ。
すると考えられるのが、賢治が帰花したのと相前後して小笠原牧夫と結婚する決意を固めた露が、昭和6年10月4日に花巻高等女学校時代からの友人であるナヲの許を訪ねてその旨を報告したということだ。
そこへたまたまナヲの母ヤスがやって来た。賢治はヤスの甥だ。その賢治に最近結婚話のトラブルがあったということをヤスは聞き知ってはいたのだがその詳細までは承知していなかったので、そのトラブル相手ちゑのことを露であると誤解してヤスは怒り、そんなことだったら、賢治があなた(露)にやったものを一切返せと迫った。そのやりとりを見ていた徳弥は、義母の性格を知っているがゆえに「女といふものははかなきもの也」と日記に記した。
鈴木 そうか、こういう流れであれば徳弥があの日記に「母来り怒る。露子氏宮沢氏との結婚話」と書いたことも頷ける。
吉田 一方、そう言われた露は、賢治からかつて貰っていた本を持参して翌々日また関の家にやって来て、この本を賢治に返して欲しいと、賢治の従妹でもあり露の友人でもあるナヲにお願いして帰って行った。
以上、鈴木の好きな思考実験を僕も真似てみた。
荒木 いいんじゃねぇ、なかなか説得力がある思考実験だった。こうなると逆に、矢っ張り徳弥の『短歌日記』は「昭和6年」に書かれたものであるということの真実味がますます増してきた。
鈴木 しかも、徳弥の『短歌日記』の記述内容がなかなかうまく当て嵌まっている。
荒木 なるほどな。帰花した賢治は病に伏せながら、折角<三回目の「家出」>をしてまでちゑと結婚しようと思って上京したというのに、ちゑに一方的に裏切られてしまったと受けとめた賢治は恨みと怨念が募っていった。そこへ、もしかすると露が小笠原牧夫と来年春結婚するという噂も耳に入ったりしてさらにダメージを受けた賢治は、すっかり打ちひしがれてしまった。
ますます募ってくる苛立ちに耐え切れず賢治は、帰花して約一ヶ月後、ちゑに対する恨みと憎しみを込めてとうとう〔聖女のさましてちかづけるもの〕を詠んでしまった、という可能性が少なからずあるということか。
だから、「聖女のさましてちかづくもの」は露ではなくて実はちゑである。確かに、露ではなくてちゑとした方がすんなりと解釈できるな。もしかするとこのことは思考実験にとどまらず、実際に十分あり得たことかもな。
◇「聖女のさましてちかづけるもの」は限りなくちゑ
吉田 ではここで思考実験は止めにして、ここからはオーソドックスな考察に戻ろう。
鈴木 了解。とはいえ、この実験によって 「聖女のさましてちかづけるもの」は露とは限らず、露以外の女性も考えられるということだけはもはや明らかになったと言える。
荒木 今までの思考実験で、その可能性が少なくとも否定できないことがはっきりしたのだからな。
吉田 とはいっても、その候補者はさしあたり露とちゑしかいないというのも現実だ。そしてそれぞれ、
・露 :「レプラ」と詐病までして賢治の方から拒絶したといわれている露に対して約4年後
・ちゑ:結婚するかもしれませんと賢治が言っていたちゑに対して約2ヶ月半後
となる。
さあ、ではどちらの女性に対して、例の「このようななまなましい憤怒の文字」を連ねた〔聖女のさましてちかづけるもの〕という詩を当て擦って詠むのかというと、その可能性は
ちゑ ≪ 露
となることは明らかだろう。
荒木 「約4年後」と「約2ヶ月半後」とを比べればそれは明らか。いくらなんでも「約4年後」までも相変わらず執念深く思い続けていることはなかなかいないし、普通でぎねえべ。
吉田 まあ、「聖女のさましてちかづけるもの」が露であるという可能性は否定しないが、そうでない可能性が、それもかなりの程度あるということが言える。したがって、
「聖女のさましてちかづけるもの」は限りなくちゑである。
ということは言える。
荒木 当然この可能性の方が極めて大なのだから、詩〔聖女のさましてちかづけるもの〕を用いて<仮説:高瀬露は聖女だった>の検証作業などやれない。検証以前である、となる。
鈴木 実は、「昭和6年」の場合に問題となるのはこの〔聖女のさましてちかづけるもの〕と、例の徳弥の『短歌日記』だったが、この日記のことも織り込んで既にここまで考察してきたから「昭和6年」に関しては以上で検証作業は終了。
荒木 ということは、「昭和6年」の場合も<仮説:高瀬露は聖女だった>は検証に耐えたわけだ。さあ、それじゃいよいよ残るは「昭和7年」だけだから早くそこに移るベ。
吉田 ちょ、ちょっと待て。ほらさっきの〔われに衆怨ことごとくなきとき〕のことがあったじゃないか。
荒木 やべぇ、そおそおそおだった。俺が質問したといのに情けない。
吉田 では。それは「雨ニモマケズ手帳」の32p~33pに書かれていて、小倉豊文によればここには、
◎われに
衆怨ことごとく
なきとき
これを怨敵
悉退散といふ
◎
衆怨
ことごとく
なし
<『「雨ニモマケズ手帳」新考』(小倉豊文著、東京創元社)116pより>
と書かれていて、小倉はどちらの頁も〔聖女のさましてちかづけるもの〕の書かれた日と同じ10月24日のものらしいと推測している。
そして、小倉は賢治がこの〔われに衆怨ことごとくなきとき〕をここに書き付けた理由を次のように解説している。
恐らく、賢治は「聖女のさましてちかづけるもの」「乞ひて弟子の礼とれる」ものが、「いまわが像に釘う」ち、「われに土をば送る」ように、恩を怨でかえすようなことありとも、「わがとり来しは、たゞひとすじのみちなれや」と、いささかも意に介しなかったのであるが、こう書き終わった所で、平常読誦する観音経の「念彼観音力衆怨悉退散」の言葉がしみじみ思い出されたことなのであろう。そして、自ら深く反省検討して「われに衆怨ことごとくなきとき、これを怨敵悉退散といふ」、われに「衆怨ことごとくなし」とかきつけたものなのであろう。
<『「雨ニモマケズ手帳」新考』(小倉豊文著、東京創元社)119p~より>
鈴木 そうかそういうステップをちゃんと踏んでいたのか。実は私は今まで、10月24日に詠まれた〔聖女のさましてちかづけるもの〕と、そのたった10日後に書かれたという〔雨ニモマケズ〕の間にある両極端とも思えるほどの賢治の心の振幅の大きさがどうしても理解できなかった。
ところが賢治は、〔聖女のさましてちかづけるもの〕を詠んだ後にそのことを実はしっかりと「自ら深く反省検討」し、そして〔雨ニモマケズ〕を詠んだということか。これでやっと腑に落ちた。
荒木 実は、賢治は感情の起伏が激しかったと俺も人づてに聞いていた。まあ、そこが天才の天才たる所以の最たるものの一つなのかもしれないのだが。少なくともこれら二つの間に〔われに衆怨ことごとくなきとき〕が書いてあったということならば、それならば「雨ニモマケズ」もありだな。
よし、これでまた《愛すべき賢治》にまた一歩近づけたような気がしてきた。
◇詩は単独では伝記研究の資料たり得ない
吉田 ところで、いつもの荒木なら
<仮説:高瀬露は聖女だった>を棄却する必要はないということになる。いやあ嬉しいな。
と言って抃舞していたはずなのに、今回の「昭和6年」の場合はなしか。
荒木 いやあ、おかしいと思うんだよ俺は。この前までは賢治周辺の人たちの証言や客観的な資料等に基づいて検証を行った来たのに、今回は詩によるものだったろ。
確かに、この詩はさておき、賢治の詩は素晴らしいものが多いということは俺でもわかる。しかしな、詩は所詮詩でしかないべ。創作の一つだ。だから端的に言えば、〔聖女のさまして近づけるもの〕に書いてある内容全てが事実であるとは言えないだろうに。
鈴木 いわゆる詩は還元できないというやつだな。だからこそ、もし詩を伝記の資料として使うのであればその裏を取ったり検証をしたりした上で使わねばならないのは当然だ。
吉田 ところが、この詩に関してはそのような為すべきことを為していないだけでなく、露はクリスチャンだ、クリスチャンは聖女だ、だからこの詩〔聖女のさましてちかづけるもの〕は露のことを詠んでいるんだというあまりにも杜撰すぎる論法が採られてしまっているとなれば、結果的には露のことをこの詩は<悪女>にしてしまったという責任の一端を免れられない。
鈴木 まあもちろん、この詩そのものにその責任があるわけではなく、そう理解した人の責任だけどね。
荒木 一方、実はそれは露ではなくてちゑである可能性が極めて大であるということを俺たちは導けたのだから、この詩を元にして<悪女>扱いされた節もある露にすれば踏んだり蹴ったりだ。濡れ衣もいいどこだべ。
吉田 確かにそうだが、かの小倉豊文でさえもこの〔聖女のさまして近づけるもの〕を引き合いに出して、「この詩を読むと、すぐに私はある一人の女性のことが想い出される」(『「雨ニモマケズ手帳」新考』(小倉豊文著、東京創元社)111p)と言って、これは露のことを詠んだのだと実質的に断定している。
あるいはまた、佐藤勝治でさえも例の「このようななまなましい憤怒の文字はどこにもない」と言いつつも、この詩は露のことを詠っているのだとつゆほども疑っていない。それは境忠一でさえもそう言えなくもないし、他の多くの人もおしなべてそのように認識し、これだけ賢治が憤怒を込めて詠っているくらいだから、露は相当な<悪女>だと単純に決めつけてしまうだろう。
荒木 しかしだよ、単に手帳に書かれた一篇の詩によってだぞ、その一枚の紙切れによって一人の人間の尊厳や人格が安易に全否定されるということは許されていいのが!
吉田 荒木が怒るのももっともだ。それもこれも、然るべき人たちがその裏付けも取らず、検証もせずに漫然と<悪女伝説>の再生産を繰り返してきたからだ。いかな賢治の詩といえども単独であっては「伝記研究」の資料たり得ないことは当たり前のことなのにさ。
鈴木 何かというと、それらしいことや不都合なことがあるといつもそれは露だと決めつけられてきた傾向がある。例えば、露であることが全く判然としていないのに「判然としている」と決めつけられた「昭和4年の書簡下書群」、そして今回の〔聖女のさまして近づけるもの〕の「聖女」、さらにはこの次の年に出てくる「悪口を言いふらした女性」、皆そうだ。
吉田 これらのことに鑑みれば、そこには明らかに何者かによるそれこそ「悪念」や「奸詐」があったということがもはや否定できなかろう。
荒木 おいおい憶測でそんな物騒なこと言ってもいいのか。ちょっとまずいよそれは。
吉田 実はある作家が、
もし硬い、高い壁と、そこに投げつけられて壊れる卵があるなら、たとえ壁がどんなに正しく、卵がどんなに間違っていても、私は卵の側に立つ。
<『朝日新聞、平成21年2月25日、斎藤美奈子・文芸時評』より>
と言ったということだが、僕は今このことを思い出している。
誰しも皆、自分が高い壁の側に立つとは言わないとは思うが、高い壁となって立っている人がいるのも紛れもない事実。そしてちょうどこの「卵」とは露、あるいはこの<仮説:高瀬露は聖女だった>のことかもしれない。
しかも、ここまで調べた来た限りにおいては「卵がどんなに間違っていても」どころか露の行為はほぼ間違っていないと言えるし、一方の壁については「壁がどんなに正しく」てもどころかかなり間違っていることがわかったのだから、少なくとも僕は「卵の側に立つ」。
荒木 何だよ突然に、それも一人だけかっこつけて。しかもそれって村上春樹のスピーチのパクリだべ。
鈴木 じゃじゃじゃ、すっかり吉田にしてやられたな。
荒木 なあに、さっき言い過ぎたからその照れ隠しだべ。
吉田 ばれたか。
鈴木 それでは、「昭和6年」に関わる検証結果をここで確認すれば、「そもそも詩を単独で伝記研究の資料として使うことには無理がある」ということを肝に銘じつつ、
詩〔聖女のさまして近づけるもの〕の内容によって、〈仮説:高瀬露は聖女だった〉を棄却する必要はない。
だ。これで「昭和6年」に関しての考察は一切終了。
荒木 ということは、<仮説:高瀬露は聖女だった>は相変わらず検証に耐え続けているということか。さしずめ検証に耐え続けている「卵」というところだな。それじゃ脆くて弱い「卵」よ、今はまだそうかも知れんがこの次の「昭和7年」も検証に耐え得れば、晴れて雛になって歩み始めることができて、そのうち空も飛べるかもしれんぞ、あと少し頑張れと願いつつ最後の年の検証作業に移ろうか。
 続きへ。
続きへ。前へ
 。
。 〝「聖女の如き高瀬露」の目次〟 へ。
〝「聖女の如き高瀬露」の目次〟 へ。 〝渉猟「本当の賢治」(鈴木守の賢治関連主な著作)〟へ。
〝渉猟「本当の賢治」(鈴木守の賢治関連主な著作)〟へ。 ”みちのくの山野草”のトップに戻る。
”みちのくの山野草”のトップに戻る。 。
。ある著名な賢治研究者が私(鈴木守)の研究に関して、私の性格がおかしい(偏屈という意味?)から、その研究結果を受け容れがたいと言っているという。まあ、人間的に至らない点が多々あるはずの私だからおかしいかも知れないが、研究内容やその結果と私の性格とは関係がないはずである。
おかしいと仰るのであれば、そもそも、私の研究は基本的には「仮説検証型」研究ですから、たったこれだけで十分です。私の検証結果に対してこのような反例があると、たった一つの反例を突きつけていただけば、私は素直に引き下がります。間違っていましたと。
一方で、私は自分の研究結果には多少自信がないわけでもない。それは、石井洋二郎氏が鳴らす、
あらゆることを疑い、あらゆる情報の真偽を自分の目で確認してみること、必ず一次情報に立ち返って自分の頭と足で検証してみること
という警鐘、つまり研究の基本を常に心掛けているつもりだからである。そしてまたそれは自恃ともなっている。そして実際、従前の定説や通説に鑑みれば、荒唐無稽だと言われそうな私の研究結果について、入沢康夫氏や大内秀明氏そして森義真氏からの支持もあるので、なおさらにである。
【新刊案内】
そのようなことも訴えたいと願って著したのが『このままでいいのですか 『校本宮澤賢治全集』の杜撰』(鈴木 守著、録繙堂出版、1,000円(税込み))

であり、その目次は下掲のとおりである。

現在、岩手県内の書店で販売されております。
なお、岩手県外にお住まいの方も含め、本書の購入をご希望の場合は葉書か電話にて、入手したい旨のお申し込みを下記宛にしていただければ、まず本書を郵送いたします。到着後、その代金として1,000円分(送料無料)の切手を送って下さい。
〒025-0068 岩手県花巻市下幅21-11 鈴木守 ☎ 0198-24-9813

























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます