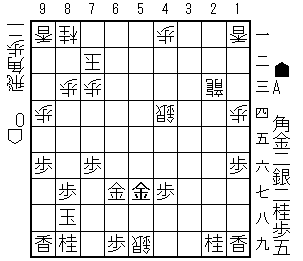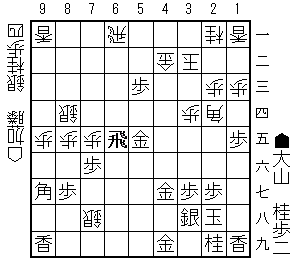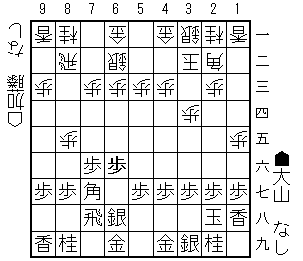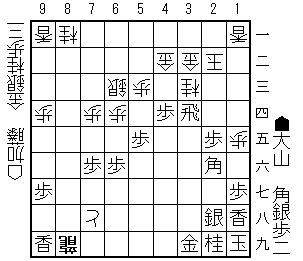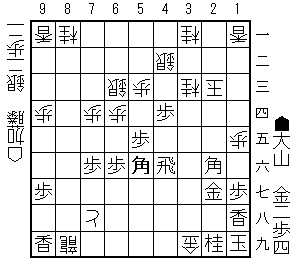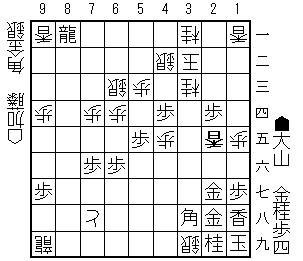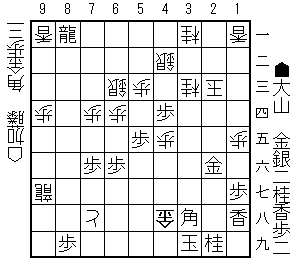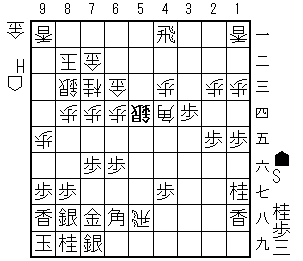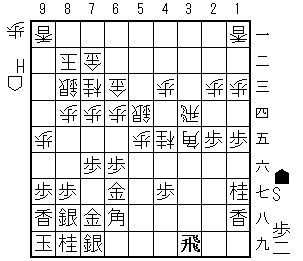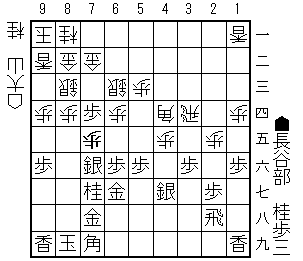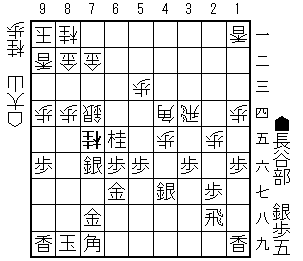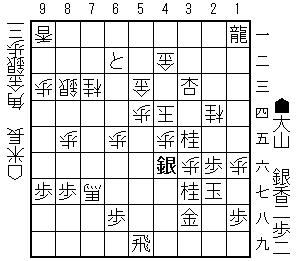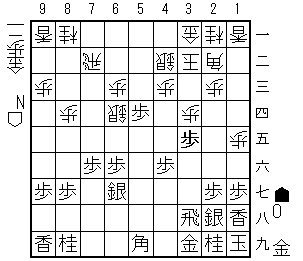昭和48年9月、石田和雄先生と第23期王将戦です。

大山先生の四間飛車に石田先生は棒銀。石田先生は急戦が多かったと思います。
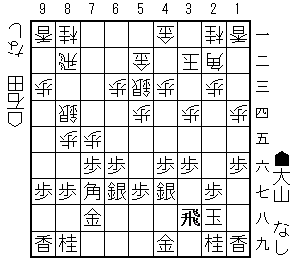
大山先生は得意のツノ銀から袖飛車。これを指すのは大山先生くらいです。玉が薄いので真似されません。

大山先生としては右から攻める(といっても単純ではないですが)ので左は低く受けます。
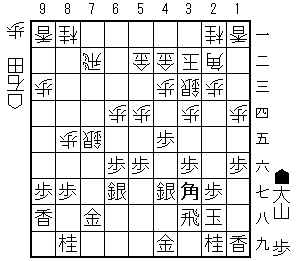
角を転回し、ここで石田先生の13角がよかったかどうか。74飛~73桂としたかった気がします。

46角とぶつけて角交換。

左は低く受けて

角、銀と打ちこまれたら危なく見えるのですが
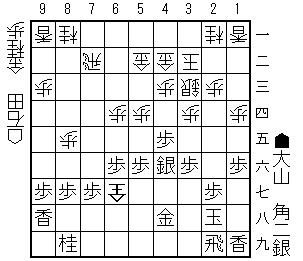
2枚換えで済めば互角のわかれです。
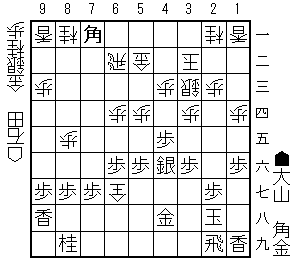
割打ちから馬を作れば2枚換えの損は減ります。
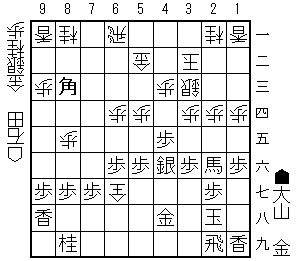
さらにもう一枚。これで大山先生が指しやすくなりました。
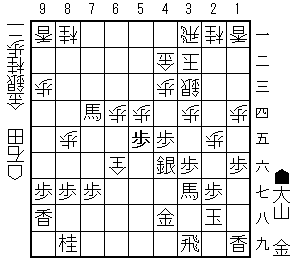
馬筋を生かした味の良い手です。ここで石田先生は端を攻めたのですが、どうにかして66の成銀を活用するほうが正しいのでしょう。馬2枚に対して66成銀と持ち駒銀桂が同等以上の働きがなければいけません。

端を攻めれば相当に見えるのですが、大山先生は受ける方針です。

飛車を使い端を受けるのは怖いのですが、馬があるから飛車は渡してもよいという考えです。

一度35歩として(これが怖い手です)24銀に14桂が手順です。これなら14同香しかありません。
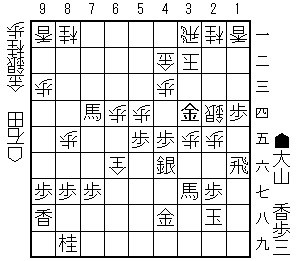
35の位を取られても空間に金を打てば少し大山先生がよいようです。でもここで33銀打ならまだ長かったはず。
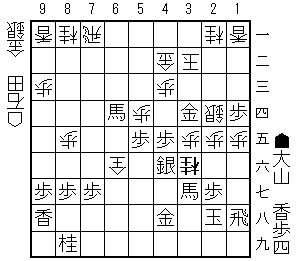
71飛は疑問手、さらに桂打は勢いですが
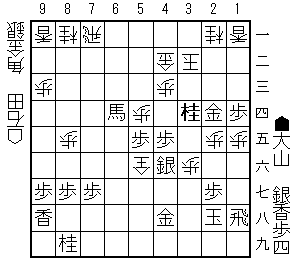
あっさり取って銀を払い桂馬を打てば受けがありません。
13角と出て46角から交換になったら大山先生が有利になりやすいのでしょう。2枚換えは2枚持ったほうがいいのですが、馬を作ればそうとも言えません。
まだ20代の石田先生をうまくあしらって攻めさせ、軽く反撃を決めたという将棋です。大山先生の手に無理がありません。
#KIF version=2.0 encoding=Shift_JIS
# ---- Kifu for Windows V7 V7.23 棋譜ファイル ----
手合割:平手
先手:大山9段
後手:石田和雄6段
手数----指手--
1 7六歩(77)
2 8四歩(83)
3 7八銀(79)
4 3四歩(33)
5 6六歩(67)
6 6二銀(71)
7 6八飛(28)
8 5四歩(53)
9 4八玉(59)
10 4二玉(51)
11 3八玉(48)
12 3二玉(42)
13 2八玉(38)
14 5二金(61)
15 3八銀(39)
16 1四歩(13)
17 1六歩(17)
18 4二銀(31)
19 6七銀(78)
20 7四歩(73)
21 4六歩(47)
22 8五歩(84)
23 7七角(88)
24 7三銀(62)
25 7八金(69)
26 5三銀(42)
27 3六歩(37)
28 8四銀(73)
29 4七銀(38)
30 7五歩(74)
31 3八飛(68)
32 4四銀(53)
33 5九角(77)
34 7六歩(75)
35 同 銀(67)
36 7二飛(82)
37 6七銀(76)
38 7五銀(84)
39 5六歩(57)
40 4二金(41)
41 9八香(99)
42 6四歩(63)
43 4五歩(46)
44 3三銀(44)
45 3七角(59)
46 1三角(22)
47 4六角(37)
48 同 角(13)
49 同 銀(47)
50 7六銀(75)
51 7七歩打
52 6七銀成(76)
53 同 金(78)
54 4七角打
55 3九飛(38)
56 5八銀打
57 4八金(49)
58 2九角成(47)
59 同 飛(39)
60 6七銀成(58)
61 6一銀打
62 6二飛(72)
63 5二銀成(61)
64 同 金(42)
65 7一角打
66 6一飛(62)
67 2六角成(71)
68 2四歩(23)
69 8三角打
70 3一飛(61)
71 7四角成(83)
72 4二金(52)
73 3九飛(29)
74 2五歩(24)
75 3七馬(26)
76 6六成銀(67)
77 5五歩(56)
78 1五歩(14)
79 同 歩(16)
80 1七歩打
81 同 香(19)
82 2四桂打
83 1九飛(39)
84 1六歩打
85 同 香(17)
86 同 桂(24)
87 同 飛(19)
88 1二香打
89 3五歩(36)
90 2四銀(33)
91 1四桂打
92 同 香(12)
93 同 歩(15)
94 3五歩(34)
95 3四金打
96 7一飛(31)
97 6四馬(74)
98 1五歩打
99 1八飛(16)
100 3六桂打
101 同 馬(37)
102 同 歩(35)
103 2四金(34)
104 5六成銀(66)
105 3四桂打
106 投了
まで105手で先手の勝ち

大山先生の四間飛車に石田先生は棒銀。石田先生は急戦が多かったと思います。
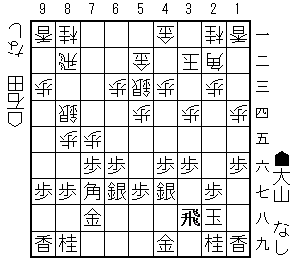
大山先生は得意のツノ銀から袖飛車。これを指すのは大山先生くらいです。玉が薄いので真似されません。

大山先生としては右から攻める(といっても単純ではないですが)ので左は低く受けます。
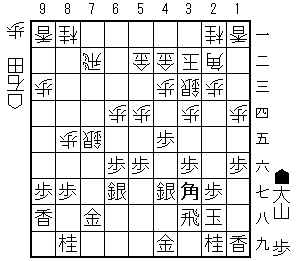
角を転回し、ここで石田先生の13角がよかったかどうか。74飛~73桂としたかった気がします。

46角とぶつけて角交換。

左は低く受けて

角、銀と打ちこまれたら危なく見えるのですが
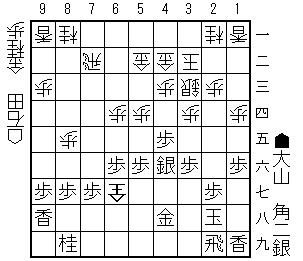
2枚換えで済めば互角のわかれです。
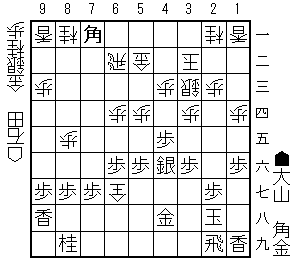
割打ちから馬を作れば2枚換えの損は減ります。
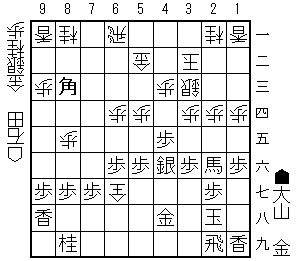
さらにもう一枚。これで大山先生が指しやすくなりました。
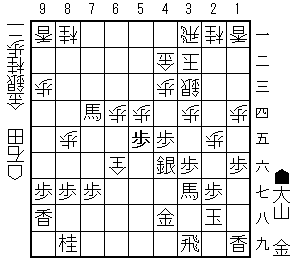
馬筋を生かした味の良い手です。ここで石田先生は端を攻めたのですが、どうにかして66の成銀を活用するほうが正しいのでしょう。馬2枚に対して66成銀と持ち駒銀桂が同等以上の働きがなければいけません。

端を攻めれば相当に見えるのですが、大山先生は受ける方針です。

飛車を使い端を受けるのは怖いのですが、馬があるから飛車は渡してもよいという考えです。

一度35歩として(これが怖い手です)24銀に14桂が手順です。これなら14同香しかありません。
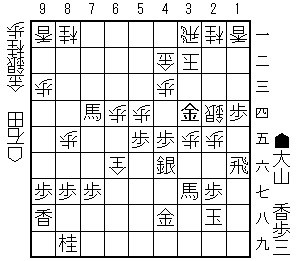
35の位を取られても空間に金を打てば少し大山先生がよいようです。でもここで33銀打ならまだ長かったはず。
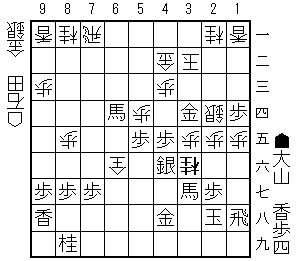
71飛は疑問手、さらに桂打は勢いですが
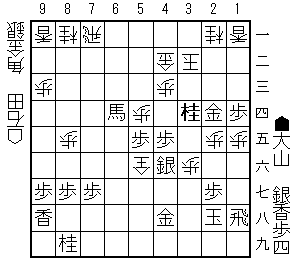
あっさり取って銀を払い桂馬を打てば受けがありません。
13角と出て46角から交換になったら大山先生が有利になりやすいのでしょう。2枚換えは2枚持ったほうがいいのですが、馬を作ればそうとも言えません。
まだ20代の石田先生をうまくあしらって攻めさせ、軽く反撃を決めたという将棋です。大山先生の手に無理がありません。
#KIF version=2.0 encoding=Shift_JIS
# ---- Kifu for Windows V7 V7.23 棋譜ファイル ----
手合割:平手
先手:大山9段
後手:石田和雄6段
手数----指手--
1 7六歩(77)
2 8四歩(83)
3 7八銀(79)
4 3四歩(33)
5 6六歩(67)
6 6二銀(71)
7 6八飛(28)
8 5四歩(53)
9 4八玉(59)
10 4二玉(51)
11 3八玉(48)
12 3二玉(42)
13 2八玉(38)
14 5二金(61)
15 3八銀(39)
16 1四歩(13)
17 1六歩(17)
18 4二銀(31)
19 6七銀(78)
20 7四歩(73)
21 4六歩(47)
22 8五歩(84)
23 7七角(88)
24 7三銀(62)
25 7八金(69)
26 5三銀(42)
27 3六歩(37)
28 8四銀(73)
29 4七銀(38)
30 7五歩(74)
31 3八飛(68)
32 4四銀(53)
33 5九角(77)
34 7六歩(75)
35 同 銀(67)
36 7二飛(82)
37 6七銀(76)
38 7五銀(84)
39 5六歩(57)
40 4二金(41)
41 9八香(99)
42 6四歩(63)
43 4五歩(46)
44 3三銀(44)
45 3七角(59)
46 1三角(22)
47 4六角(37)
48 同 角(13)
49 同 銀(47)
50 7六銀(75)
51 7七歩打
52 6七銀成(76)
53 同 金(78)
54 4七角打
55 3九飛(38)
56 5八銀打
57 4八金(49)
58 2九角成(47)
59 同 飛(39)
60 6七銀成(58)
61 6一銀打
62 6二飛(72)
63 5二銀成(61)
64 同 金(42)
65 7一角打
66 6一飛(62)
67 2六角成(71)
68 2四歩(23)
69 8三角打
70 3一飛(61)
71 7四角成(83)
72 4二金(52)
73 3九飛(29)
74 2五歩(24)
75 3七馬(26)
76 6六成銀(67)
77 5五歩(56)
78 1五歩(14)
79 同 歩(16)
80 1七歩打
81 同 香(19)
82 2四桂打
83 1九飛(39)
84 1六歩打
85 同 香(17)
86 同 桂(24)
87 同 飛(19)
88 1二香打
89 3五歩(36)
90 2四銀(33)
91 1四桂打
92 同 香(12)
93 同 歩(15)
94 3五歩(34)
95 3四金打
96 7一飛(31)
97 6四馬(74)
98 1五歩打
99 1八飛(16)
100 3六桂打
101 同 馬(37)
102 同 歩(35)
103 2四金(34)
104 5六成銀(66)
105 3四桂打
106 投了
まで105手で先手の勝ち