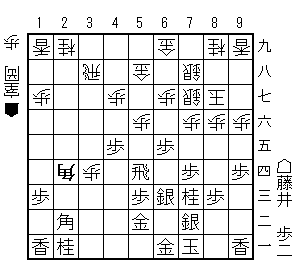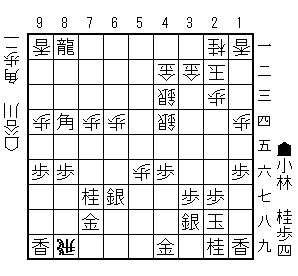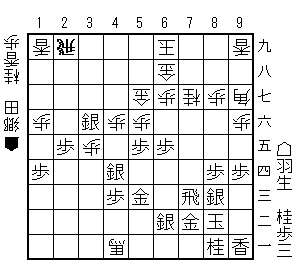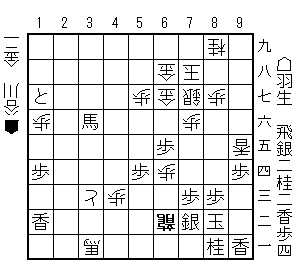明けましておめでとうございます。今年も名南将棋大会をよろしくお願いします。
3番煎じですが、また正月に書いた記事を加筆修正しました。参考にしていただければ幸いです。
<感想戦のリアル>
名南将棋大会でも感想戦の時間をもっと取りたいとは思うのですが、会場利用の終了時刻までは限られていますから、実際の運営は難しいです。下のクラスでは、自分の対局が終わると、早く次の対局をやりたいと急かされます。でもクラスが上になると、催促しないと次が始まらないです。感想戦の時間は棋力と比例するのでしょう。
中級者くらいまでは急所の局面だけでも正確に覚えていないので、駒を並べての感想戦ができないけれど、初段になれば駒を並べて感想戦ができるようになる、というくらいが標準的でしょうか。
棋譜を再現できるスキルをどうやって身につけるかなのですが、私は子供のころから定跡書を読むのが好きだったので、自然とできるようになったのだと思います。一般的にはプロの棋譜(実戦集など)を並べて覚える(暗譜する)ことが有効な訓練法でしょう。
しっかり感想戦ができると、より深いコミュニケーションが成り立つわけで、さらに楽しくなりますね。私は実戦よりも感想戦のほうが好きです。他人の将棋の感想戦であれこれ言うなんて面白すぎます。
今は太陽将棋研究会のオンライン例会で、対局30分60秒の後で、飽きるまで感想戦ができているのでとても感謝しています。
<感想戦で得られること>
人間同士で検討したって正解にはたどり着けないから不要であるという人もいるのですが、とんでもない誤解です。実際の対人の感想戦では相手に教えてもらう事もできます。強い人の考え方を聞くことは、自身の棋力が飛躍的に向上することにつながるのです。弱い人同士であっても、何を考えて指したのかを聞ければ、その情報を生かすこともできます。変化を一緒に考えることができますし、自分の気になっていた相手の手を、なぜ指さなかったのか聞くこともできます。自分が見送った指し手を相手がどう思うか聞いてみるのも良いでしょう。自分から何を考えていたか話してみると、相手も教えてくれるものです。
<一人感想戦で検討すること>
多くの対局では時間の制約があり、長い感想戦を許してもらえない事が多いですから、棋譜を覚えておくことがとても有用なスキルです。その日のうちに指した将棋を記録しておくのです。記録するには、Kif for Windowsを活用しています。スマホにアプリを入れておくのも良いでしょう。まだ棋力が低くて記憶できない方は、対局相手に断って対局中の盤駒の写真を撮っておけば並びやすいかもしれません。少数派ですが棋譜をつけながら対局される方もいます。オンライン対局ならば、棋譜を保存する機能がついていることが多いので、かなりやりやすいかもしれません。でもオンラインの相手は感想戦に興味のない人が多いのではないでしょうか。これはままなりません。
棋譜をつければ、一人でもしっかり感想戦や検討をすることができます。これはAIに意見を求める事もできます。ただし言葉で言ってはもらえませんから、自分なりに翻訳することです。
注意事項としては、棋譜を入力するとすぐにAIに答え(らしきもの)を確認したくなるのですが、自分で読み直して(対局と同じくらいは時間をかけたいところ)棋譜の分岐やコメントで記録して、自分なりに答えを出してからAIに尋ねるのです。その局面の最善手を聞くのではなくて、数手先までの読みを見て、どういう判断で選んだのかな、と推測しなければわからないのですが。
<一人感想戦の目標>
序盤ならば、定跡が使えたかどうか、間違って覚えていたならば修正できます。定跡を外れたのならば、どちらが外したか、なぜとがめられたか、とがめられなかったか、定跡をより深く理解することにつながります。新しい自分の定跡(変化や新手)を考えつくかもしれません。定跡を理解することで筋の良い指し手がわかるようになります。駒組みで作戦勝ちか作戦負けか、わかるようになってきます。
中盤ならば、仕掛けるべきか待つべきかのタイミング、方向性を確認します。手順よく攻められたかどうか。つぶされずに受けられたかどうか。自分は読みが優れていたか、感覚が優れていたかという特性が分かってくるでしょう。読み抜けがあったか、筋の悪い手を指さなかったか。成長のための課題が見えてくると思います。形勢判断に狂いはなかったか、それを元にした指し手の方向(大局観)は正しかったか。
終盤ならば、悪手を指さなかったかどうか。良い寄せ方ができたか、受けるべきところを受けたか。
どれが間違った手だったかよりも、なぜ自分が間違った選択をしたかを考えるほうが応用が利きます。その手筋を知らなかったのか。なぜ他の手がよく見えたのか。指さなかった手の可能性を考えていたかどうか。可能性のある相手の応手まで読んだ上で判断したかどうか。取捨選択で間違ったのなら、その理由は正しかったか。読みの間違いか、感覚の間違いか。これらは自分で考えたり対局心理を思い出したりしないと答えは出ません。
結論を元に、何が自分の課題なのかを洗い出します。その対応方法(訓練方法)を考えるまでが一人感想戦です。なぜ自分はそういう判断をしたのか、それは改善すべき弱点なのか、活かすべき個性なのか。そのあとの宿題として、自分の強み弱みを認識するところまで掘り下げたいところです。
<やってはだめなこと>
将棋に勝つことだけを目標にすること。負けてもすぐに次の対局を求め(自分が負けたことは認めたくないものです)、それで勝てばよいと逃げてしまうこと。
何も考えずに指すこと。
反省しないこと。
自分の棋譜を大切にしないこと。
<名南研究会>
名南でも毎月研究会を開くようになりました。棋譜を残すことを義務付けています。棋譜ファイルに保存して検討します。1週間後にAIで検討した結果を共有します。対局後、2~3日後、1週間後と3回は内容を検討できます。それぞれの段階で気づきがあります。
今年も将棋をいっぱい指して、少しでも強くなれますように。