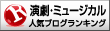RE滅鬼の刃 エッセーノベル
お祖父ちゃんと暮らすことになった最初の日、お祖父ちゃんが聞きました。
「どうだ、栞、これからはお祖父ちゃんの事『お父さん』て呼んでみるか?」
ショックでした。
なんと言っていいか分からなくて、俯いていたら涙が溢れてきて、両手をグーにして目をゴシゴシ拭きました。
それでも、涙は溢れてきて、その日初めて着た白のワンピースにポタポタ落ちてきて、シミになったらお母さんに怒られると思って、でも、もうお母さんに会うことは無くって、そう思ったら混乱して、ますます涙が止まらなくなって。
でも、声を上げて泣くことはしなかったですね。
声を上げて泣いたら、もう、張り詰めた髪の毛一本でもっているような心が壊れて、元に戻らなくなってしまいそうで、必死にこらえました。
お祖父ちゃんを『お父さん』と呼んでしまったら、二つの大事なものが二度と返ってこない。
一つは、おうち。子どもの言葉で『おうち』です。
家庭、ファミリー、絆、そういったものです。それが『お父さん』という言葉で永遠に消えてしまいそうな、そんな怖れを感じていました。たとえ100点満点でなくとも、おうちはおうちです。
ジブリの『ラピュタ』で、怖いシーンがありますね。
パズーとシータがムスカ大佐に追い詰められて、二人で飛行石を握って「「バルス」」って言うじゃないですか。
あれで、何百年、何千年続いたラピュタが分子結合を失ったみたいにバラバラになって落ちて行ってしまうじゃないですか。
あんな感じで、怖くて言えませんでした。
二つ目はお祖父ちゃんそのもの。
お祖父ちゃんを『お父さん』て呼んでしまったら『お祖父ちゃん』が居なくなってしまうじゃないですか。
わたしは、親の都合で、しょっちゅうお祖父ちゃんちに預けられていました。
お祖父ちゃんは、いつも優しくって、何かの拍子で誰かの胸で眠ってしまって、目が覚めた時、お祖父ちゃんだったらホッとしました。もっと昔はお祖母ちゃんも生きていて、よく、お祖父ちゃんとお祖母ちゃんに挟まれて寝ていたもんです。
お母さんでもよかったんですけどね。
お母さんの場合、目が覚めたら、そこから、もうよい子を演じなければならないので、ちょっとくたびれるんです。
お祖父ちゃんの姿をしたお父さん。そんなのは釈然としません。
でも、大きくなって少し分かりました。
友だちの中にお祖母さんと暮らしてる人が居たんです。その子が『お母さん』と呼んでいて、ちょっと「え? ええ?」って思って、その子は説明してくれました。
その子にも、そこには居ないお母さんにも、むろんお祖母さんにも、なにも問題はありません。
ただただ、居心地が悪いんです。
お祖父ちゃんを『お父さん』と呼んでしまったら、目の前にいるのは『お父さん』と呼ばれるお祖父ちゃんの姿をした怪物になってしまいます。
http://wwc:sumire:shiori○○//do.com
栞2号のドクロブログ☠!
なんで『お父さん』て呼ばなかったかって?
キモイからに決まってんじゃん。
ジジイと暮らすようになったのは五歳になってすぐだったと思う。
五歳っていうと、もう赤ちゃんじゃない。でしょ? 異議無いよね?
今ほど具体的にアレコレ知ってたわけじゃないけど、分ってたよ、これから大変だって。
もう一年くらい、ジジイとは、いっしょにお風呂に入ってなかったし。
お母さんは問題アリアリな人だったけど、そういうとこは、いっしょだったし。
ジジイのとこは、しょっちゅう来てたというか来させられてた。ま、家庭の事情ってやつさ。
でもさ、毎日ってわけじゃないよ。
お母さんは破滅的な性格だったけど、ドラマとかは、橋田寿賀子とか好きでさ、そういうのに憧れあるのよ。
渡る世間は鬼ばかりと笑いながら、渡る世間に鬼はなしとも願ってる。
世間の鬼は自分だと自覚しながら、自分の相手をしてくれる世間には鬼ではないと憧れてんのよ。
虫良過ぎ!
憧れてんだったら、自分ちをそうしろって思ったけどさ。ま、それは置いといて。
わたしもね、うちでは母親似の剥き出し幼女だったけど、ジジイんちじゃ仮面孫娘やってたわけ。
加齢臭は、ま、いいとして、ベタベタされんのは勘弁してよですよ。
いっしょにお風呂どころか、いっしょに洗濯もNG!
わたしがね、小五から洗濯してんのは、そういうことですよ。
家庭科の洗濯実習で手際がいいもんで、感心されて「あ、お祖父ちゃんと暮らしてますから」ってコソッと担任の先生に言ったら、EテレのMCてか、24時間テレビ的な微笑み返されてゲロ出そう。
そういや、24時間テレビも苦しいみたいね。もう何年も続かないでしょ?
わたしもね、こんな仮面孫娘、そう何年もやってるつもりないし。
あ、突然思い出した。安倍さんてさ、一発目と二発目の間に倒れてるよね。動画、何回も見たし。
弾が見つからないとか、現場検証が五日後って、もう終わってるでしょ。
ま、思っただけでさ、わたし的には、そういうことには目をつぶって、統○協会がーとか、テレビのワイドショー的に生きて生きればいいっす。