presented by hanamura ginza
はやいもので、もう 7 月ですね。
東京では、梅雨の中休みの良い天気がつづいています。
雨水をたっぷり吸い込んだ草花はすくすくと育ち、
木々の葉も繁りはじめ、早くも夏本番の気配です。
それでも風はまだ涼しく、
晴れた日には、公園でお弁当を広げている人たちの姿をよく見かけます。
公園に植えられた芝生は青々しく、
芝生を駆け回っている散歩中の犬たちも、
こころなしかはしゃいでいるように思えます。
さて、今日のお話はこの芝生(芝草)に関係があります。
現在、日本に生えている芝草には、
大きく分けて、日本芝と西洋芝の 2 種類があります。
日本芝は夏芝ともよばれ、
暑さに強いのですが、
冬になると、地上に出た草が枯れてしまいます。
一方、西洋芝は冬柴とも呼ばれ、
寒さに強いため、冬になっても青々としていますが、
夏になると枯れてしまう場合もあるようです。
芝草は、イネ科の植物で、
遠い昔から日本に自生していましたが、
すでに平安時代の頃には、
今日のように庭園にも植えられていたようです。
古来よりあるのはもちろん日本芝のほうで、
俳句の季語でも、青芝は夏をあらわし、
枯芝は冬をあらわすために用いられます。
広い範囲に生える芝草は、
葉の色が変化することで、
季節の移ろいが感じられるため、
遠い昔から、和歌や俳句の題材に用いられてきました。
万葉集や日本書紀にあらわされた和歌には、
芝草を詠んだ和歌がいくつか残されています。
また、平安時代には芝草についた露のことを「道芝の露」とよび、
儚いものという意味合いで使用しました。
この「道芝の露」は文様化され、
桃山時代の頃になると、
着物や調度品などの意匠に多く用いられるようになりました。
半円状の弓なりとなって描かれた芝草の上に、
小さな丸で露があらわされた意匠は、
「露芝(つゆしば)」文様とよばれるようになりました。
この時代につくられた能装束には、
露芝文様があらわされたものが多くあり、
それらの意匠からは、戦国の世の無常観が感じられます。
また道芝の露は、葉についた露がするりと落ちる様から、
するりと鋭く切れる日本刀を指す言葉としても、用いられました。
露芝文様は、江戸時代の小袖にも多く用いられています。
決して派手さはないのですが、
和の風情と美意識が感じられる露芝文様は、
江戸っ子たちにも人気があったのでしょう。

上の写真は、昭和初期頃につくられた帯地から
お仕立て直しをした名古屋帯です。
露芝文様に桔梗や萩、すすきなどの秋草が所々に
あらわされています。
すっと細い線で描かれた露芝は
涼感を誘うとともに清楚な秋草の美しさを引き立て、
意匠全体からは渋みのある和の風情が漂います。
本格的な夏はもうすぐそこまでやってきています。
ファッションの中でも、お着物はとくに周囲の方の目も楽しませるものですね。
やはり暑い季節には、涼やかな意匠が目を引くものです。
露芝があらわされた着物や帯で、涼感を演出するのも
素敵でしょう。
※上の写真の名古屋帯は 7 月 5 日に花邑 銀座店でご紹介予定の商品です。
●花邑 銀座店のブログ、「花邑の帯あそび」次回の更新は 7 月 11 日(木)
予定です。
帯のアトリエ 花邑-hanamura- 銀座店ホームページへ
↓




















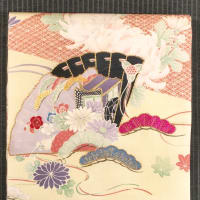
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます