本日は
お誕生日でございます。
ナスターシャ・キンスキーの(1960)
E・T・A・ホフマンの(1776)
史上最高のカストラートと讃えられたファリネッリの(1705)
それから
クラウス・ノミの。(1944)
1月24日の誕生花はブルースターという花なのだそうで。
他にもサフランですとか、フリージアですとか、オモトですとか、いろいろあるようでございますが
やっこさんには”オモト”より”ブルースター”の方が断然、似合いでございましょう。

どんなものであれ、ヤツについて書かれた文章を読むのは嬉しいもんでございます。
とりわけ喜ばしいのは、生前のノミを直接に知る人々の証言や
ヤツのことをまじめにアーティストとして評価する記事に出会った時でございます。
そう、
こちら のような。
ざっと訳させていただきますと、こんな内容でございます。
**********************
1983年、クラウス・ノミが「ゲイの癌」で亡くなった時
少数のファンや友達以外に、彼を知る人はほとんどいなかった。
スターを夢見てNYにやって来て、果たせず終わる。よくある話だ。
ノミ(本名スパーバー)はいろんな意味でクィア*だった。
(のろ注:クィア=不思議な、奇妙な、変な。近年はゲイやトランスジェンダーなどの性的マイノリティを包括的に指す言葉としても使われています)
同時代の、イーストヴィレッジ住まいのボヘミアンたちとも、全く違っていた。
しかも彼は天賦の才能を授かっていた。
ワイマール風の低音からファルセットの最高音にまで至る歌声だ。
しかし当時は、カウンターテナーの需要など無いに等しかった。
それでも時代のDIY(Do it yourself)精神にのっとり、彼は自分で自分の活躍の舞台を作り上げた。
その短いキャリアの間に、彼は旗ふりをつとめ、種々さまざまなフリークスたちの先頭に立って歩いた。
自身の両性具有性を前面に打ち出した、レトロ・未来派風のパフォーマンス。
ニューウェーブのバンドを従えた、シュトルム・ウント・ドラング*風のヴォーカルが
60年代のブリル・ビルディング・スタンダードやクラシックのアリアや、
癖の強いオリジナル曲とみごとなまでに渾然一体となっていた。
(*のろ注:”シュトルム~”は18世紀後半のドイツで勃興した革新的な文芸運動です。
適切なリンク先が見つけられませんでしたので、お手数ですが詳しくはWikipedia等をご参照くださいませ)
・・・
ノミが生前に出した2枚のアルバムは、彼の異世界的な魅力の一端を伝えてはいるものの
往々にして、ありきたりなバックトラックが、歌声の素晴らしさをかき消してしまっていた。
音質はひどくとも、残されたわずかなライヴ録音やライヴビデオの方が、ずっとよかったのだ。
つい先頃発売されたアルバム”Za Bakdaz”は、ノミに新たなアングルから光をあてた一枚だ。
いたずらっ子の実験のようでもあり、不思議な言葉で歌われた未完のオペラのようでもある。
音源は1979年ごろにホームスタジオで録音されたものだが
ノミの友人のページ・ウッドとジョージ・エリオットは、これに愛情のこもった修復を施してくれた。
このアルバムは、はるか遠い世界から届いた手紙のようだ。
そこでは、キッチュ(俗悪)とハイ・アート(純粋芸術)がガチンコで取っ組み合っているのだ。
**********************
どうですよ、どうですよ。
この下の文も訳していると日付を超えてしまいそうなので、とりあえず前半部分だけご紹介させていただきました。
(というかそれ以前に著作権問題にひっかかるのではないかと、現時点でもヒヤヒヤしているのでございますが汗)
お時間のある方はぜひとも”Act 1”以下の記事もお読みいただきたく存じます。
ノミの友人であったジョーイ・アリアスやページ・ウッドのお話が掲載されておりますので。
ワタクシの一番好きな一文は
Klaus was the art director of his life
クラウスは自分の 人生/生活 のアート・ディレクターだった
って所でございます。
ほんとにね、そうだったんだろうと思いますよ。ほんとに。
ヤツがいなくなってから、もう24年と5ヶ月もの歳月が流れたわけではございますが
Nomi isn't dead―Klaus Sperber is dead. And I think he'd have loved the idea of this character going on.
スパーバーは死んでしまったが、ノミは死んではいない。
それに、このキャラクターがずっと生き続けていくことを、彼も喜んだことだろう。
と いうわけで本日は
今も銀河のどこかを旅しているであろうクラウス・ノミの
64回目のバースデーでございます。
誕生日おめでとう、クラウス・ノミ。
お誕生日でございます。
ナスターシャ・キンスキーの(1960)
E・T・A・ホフマンの(1776)
史上最高のカストラートと讃えられたファリネッリの(1705)
それから
クラウス・ノミの。(1944)
1月24日の誕生花はブルースターという花なのだそうで。
他にもサフランですとか、フリージアですとか、オモトですとか、いろいろあるようでございますが
やっこさんには”オモト”より”ブルースター”の方が断然、似合いでございましょう。

どんなものであれ、ヤツについて書かれた文章を読むのは嬉しいもんでございます。
とりわけ喜ばしいのは、生前のノミを直接に知る人々の証言や
ヤツのことをまじめにアーティストとして評価する記事に出会った時でございます。
そう、
こちら のような。
ざっと訳させていただきますと、こんな内容でございます。
**********************
1983年、クラウス・ノミが「ゲイの癌」で亡くなった時
少数のファンや友達以外に、彼を知る人はほとんどいなかった。
スターを夢見てNYにやって来て、果たせず終わる。よくある話だ。
ノミ(本名スパーバー)はいろんな意味でクィア*だった。
(のろ注:クィア=不思議な、奇妙な、変な。近年はゲイやトランスジェンダーなどの性的マイノリティを包括的に指す言葉としても使われています)
同時代の、イーストヴィレッジ住まいのボヘミアンたちとも、全く違っていた。
しかも彼は天賦の才能を授かっていた。
ワイマール風の低音からファルセットの最高音にまで至る歌声だ。
しかし当時は、カウンターテナーの需要など無いに等しかった。
それでも時代のDIY(Do it yourself)精神にのっとり、彼は自分で自分の活躍の舞台を作り上げた。
その短いキャリアの間に、彼は旗ふりをつとめ、種々さまざまなフリークスたちの先頭に立って歩いた。
自身の両性具有性を前面に打ち出した、レトロ・未来派風のパフォーマンス。
ニューウェーブのバンドを従えた、シュトルム・ウント・ドラング*風のヴォーカルが
60年代のブリル・ビルディング・スタンダードやクラシックのアリアや、
癖の強いオリジナル曲とみごとなまでに渾然一体となっていた。
(*のろ注:”シュトルム~”は18世紀後半のドイツで勃興した革新的な文芸運動です。
適切なリンク先が見つけられませんでしたので、お手数ですが詳しくはWikipedia等をご参照くださいませ)
・・・
ノミが生前に出した2枚のアルバムは、彼の異世界的な魅力の一端を伝えてはいるものの
往々にして、ありきたりなバックトラックが、歌声の素晴らしさをかき消してしまっていた。
音質はひどくとも、残されたわずかなライヴ録音やライヴビデオの方が、ずっとよかったのだ。
つい先頃発売されたアルバム”Za Bakdaz”は、ノミに新たなアングルから光をあてた一枚だ。
いたずらっ子の実験のようでもあり、不思議な言葉で歌われた未完のオペラのようでもある。
音源は1979年ごろにホームスタジオで録音されたものだが
ノミの友人のページ・ウッドとジョージ・エリオットは、これに愛情のこもった修復を施してくれた。
このアルバムは、はるか遠い世界から届いた手紙のようだ。
そこでは、キッチュ(俗悪)とハイ・アート(純粋芸術)がガチンコで取っ組み合っているのだ。
**********************
どうですよ、どうですよ。
この下の文も訳していると日付を超えてしまいそうなので、とりあえず前半部分だけご紹介させていただきました。
(というかそれ以前に著作権問題にひっかかるのではないかと、現時点でもヒヤヒヤしているのでございますが汗)
お時間のある方はぜひとも”Act 1”以下の記事もお読みいただきたく存じます。
ノミの友人であったジョーイ・アリアスやページ・ウッドのお話が掲載されておりますので。
ワタクシの一番好きな一文は
Klaus was the art director of his life
クラウスは自分の 人生/生活 のアート・ディレクターだった
って所でございます。
ほんとにね、そうだったんだろうと思いますよ。ほんとに。
ヤツがいなくなってから、もう24年と5ヶ月もの歳月が流れたわけではございますが
Nomi isn't dead―Klaus Sperber is dead. And I think he'd have loved the idea of this character going on.
スパーバーは死んでしまったが、ノミは死んではいない。
それに、このキャラクターがずっと生き続けていくことを、彼も喜んだことだろう。
と いうわけで本日は
今も銀河のどこかを旅しているであろうクラウス・ノミの
64回目のバースデーでございます。
誕生日おめでとう、クラウス・ノミ。










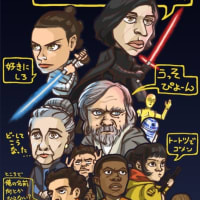
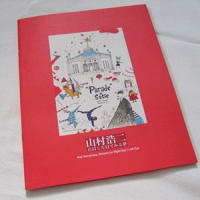
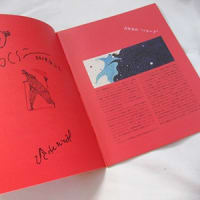
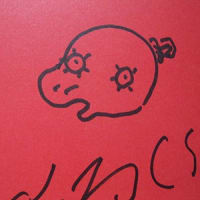
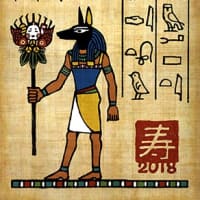





ご紹介のテキストはワタクシも読ませて頂いておりましたが、
英語が不自由な身ゆえ、例のロボット翻訳の不自由な日本語の前に少しばかり萎え萎えになっておりました。
とても判りやすく訳して下さって、本当にありがとうございます!!
後半の文章はノミさんの身近な人達によるもので、
ノミファンとしては大いに注目すべきテキストと思います。
(もちろん全体を通して良テキストと認識しております)
あの新しいCDは実は取り掛かってから10年の歳月を要したと、
製作者のジョージ・エリオット氏は教えてくれました。
フランスのノミファンは、継ぎ接ぎだらけの音なんてノミのアートを冒涜してる!と、
発表前にワタクシにメッセージを送ってきました。
なので、あちこちから賛否両論あっただろうというのは想像に難くありません。
しかしながら、出来上がったCDはノミさんの世界の創世記(仲間内でワイワイ言いながら作り上げていった)を垣間見るような、
それこそ、「THE NOMI SONG」で言うところの、
「彼の意図したものでないサンプル版」の逆のものであると思わざるを得ません。
(ただ、そのサンプル版というものを聴いてないので、本当のところはなんとも言いようがありませんが)
とにかく、ノミさんの真骨頂はLiveでのパフォーマンスと、
自らのアイデアを生かした音楽的アレンジに尽きるというのが大方の意見のようです。
ワタクシは非常に訓練された技術を持っているのにもかかわらず、
それに飽き足らず(そのままでは満足出来ずに、さらに過剰なまで)に子供のような茶目っ気を持って表現しようとしたノミさんの心意気に、
ノックアウトさせられてしまったのでした。
スミマセン、ちょっと飲み過ぎたみたいで文章が支離滅裂だと思います・・・。
まぁとにかく、ノミさんの誕生日は当日いろいろ動きがあって楽しかったです。
引用ばかりでたいしたことも語れませんで、申し訳ございませんでした。
実は"Za Bakdaz"の感想語りなどさせていただこうかと思っていたのですが
記事が間に合わなかったんでございます、ええ。
なんとか来月のノミ話でUPしたいと思っておりますが
万が一できなくてもどうぞお怒りんならないでくださいまし汗
>ロボット翻訳
あんまり使えませんよね。
ワタクシも英文読むのしんどいなーと思った時に使ったことがございますが
訳出された日本語をさらに意味の通じる日本語へと脳内翻訳しなければならず
結局よけいにしんどいということが判明したのでございました。
思えばノミを知ってから2年と少しになりますが
それ以来、必死でノミ関連の英文を読みあさったおかげで
だいぶ英文読解力がついたように思います笑
ノミさまさまでございます。
>フランスのノミファンは
そうなのですか?
ワタクシなどはヤツの声が聞けるってだけでも狂喜乱舞の態なんでございますが。
それどころか、ヤツの未発表音源ならば
今回のような素晴らしい作品に仕上げてくれなくってもいいから、
どんな断片でも、どんなに音が悪くてもいいから、
とにかく放出してほしい、耳に触れさせてほしいと思っております。
まあ、そんなもの出しやしないこってございましょうがね。
発売しても採算なんかとれないでしょうから。
そう思うとこの度の"Za Bakdaz"がいっそうありがたく思えて参ります。
>子供のような茶目っ気を持って
そうですね、全くそうですね。
舞台でのパフォーマンスにおいても
可笑しいほどにくそまじめな歌い方においても
カメラの前でも「素」の自分を隠しきれない、シャイな表情においても
そして、あの不器用な生き方においても
あまりにも 大人びていない 所が、ヤツの大きな魅力であろうと思います。
おお、飲み過ぎはいけません。
ってワタクシが言えた義理では全然ないんでございますが。
ちなみに当方、この日はイェーガーマイスターjager meisterを飲んでお祝いをいたしました。
そう、ノミが広告に使われてたあのお酒でございますよ。
気になったのでおたずねします。
Klaus Nomi, 2008, Kurzgeschichte von Sven Bremer
は、手に入るんでしょうか?小説らしいのです。
ご存じでしたら、教えてください。
毎晩御覧いただいているとは...甚だ恐縮でございます。
しげしげと更新できなくて申し訳ございません汗
おお、ノミさんにはまってしまわれたのですね。素晴らしい。
ヤツの歌声には中毒性がございますよね。
.....もっとものろの周辺の人々は残念ながら誰一人毒されませんでしたが。おかしいなあ。
もし未見でしたら、どうぞ映画『ノミ・ソング』も御覧くださいましね。
ますますヤツにはまること請け合いでございます。
それにしてもお誕生日がご一緒ですと!?
う う う う う 羨ましい......うぐぐぐ(悶絶)
お尋ねの小説は恥ずかしながら存じませんでしたので、ちと調べてみました。
しかしワタクシも、ドイツの若手作家Sven Bremerさんによる短編セミ・フィクションで、2008年に発売される、ということしか分かりませんでした。
ともあれ、引き続き注目したいと思います。
情報をどうもありがとうございました。
早々にお返事ありがとうございました。
マラーホフ氏がノミ様の曲で踊った動画が下記のアドレスで見られます。未見でしたらどうぞ!
http://www.nbs.or.jp/blog/news/contents/2008/02/post-15.html
マラーホフは去年、膝を39歳というダンサーとしては高齢になってから手術したのですが、最初の手術は失敗で再手術し、その後の経過は再手術後もあまり芳しくありませんでした。そのため、9月に予定されていた公演はキャンセルになり、本人は踊らないのを謝るためだけに遠いベルリンから来日しました。そんなわけで、今回の舞台に立てることが嬉しくて、復帰をテーマにした新作としてノミ氏の曲を選んだみたいです。
断片なりとも、見られるとは思っておりませんでした。
Cold Songだけかと思いきや、Wayward Sistersも使ってくだすったのですね。
これは嬉しうございますねえ。
ワタクシが知るかぎり、ノミの曲を使ったパフォーマンスでは
Cold Songばかりが使われてまいりましたので。
バレエのことは何も存じませんけれども、
一瞬一瞬が綿密に造られた彫刻であるかのような、指先つま先まで隙のない身体の美しさに見ほれてしまいました。
陳腐な言い方しかできなくてまことに申し訳ないのですが、ベルヴェデーレのアポロン像が動いているようではございませんか。
公演のキャンセルを謝るためにわざわざ来日してくださったとは、なんと律儀な。
ファンを大切になさるかたなのですね。
復帰をテーマにした作品にノミの曲をお選びになったというのは、マラーホフさんが手術をなさったのがノミの没した年齢と同じ39歳の折りであることと関係してらっしゃるのかしらん。
それにしても、手術からの復帰とは...あのパフォーマンスの背後には尋常ならぬ努力と精神力が秘められているのですね。
なぜ復帰がテーマの曲にノミさんの曲を選んだのかは、私もわからないです。39歳という年齢に関係するのかもわかりません。(振り付けは他の人の名前になっていますが、曲は自分で選んで渡したそうです。)
マラーホフさんはマリア・カラスのファンで彼女のCDやDVDは全部持っているけど、今回カラスは選ばなかったんだな。と思うだけです。でも、お陰で私はノミさんを知る事が出来たので、これはすごい宝ものを貰った気持ちです。いろいろと大人買いしてしまいました。
you tubeなどで画像を見て、恥じらいのあるあの表情にいちだんと深くはまってしまった感じです。私には、ピュアで可愛く見える~~。
話は変わりますが、ドイツの本、手に入るように私も尽力します。
オフステージのノミの見せる表情はほんとに、まるで恥ずかしがりの子供のようで、実に可愛いですね。ワタクシもあの表情でいっそうどっぷりはまってしまったクチです。
ノミ小説、せめてタイトルがわかるといいんですがねえ。
ワタクシもチェックを怠らぬようにいたしますが、ayumi様、入手された折りには当のろやにもご一報くださったら至極幸いでございます。
のろさまは表現力がすごいですね。
新書館発行のダンスマガジンの5月号に今回ノミさんの曲を選んだ理由が少し出ていましたので、もし、お時間がありましたら、立ち読みしてみてください。019ページです。私が引用するとなんだか色つけちゃいそうなので、直に読んでいただきたく思いました。
このインタビュー中に出てくるドイツのテレビのドキュメンタリーも見たいですね。誰かがYouTubeにアップロードしてるれることを祈って。
頭にノミさんの声がこだましている私です。
ノミにまつわることが少しでも載っているとなればもういても立ってもいられず、さっそく仕事帰りに書店を3件ハシゴしたのですが・・・ダンスマガジン、置いてなかったんでございます
図書館も5時で閉まってしまうし
ちょっぴりハートブロークンな夕べでございました。
5月号ということは、向こうひと月は書店に置いてありそうではありますが、出来るかぎり早急にお目にかかりたいと思っております。
頭にノミさんの声がこだましていらっしゃると?それは素晴らしい。その勢いで夢にでも出て来てくれれば、もっけの幸いじゃござんせんか。
時々、ヤツのあまりにもキョーレツな印象にショックを受けたかたの「夢に出て来そう」という感想を目にしますけれども、どうしてなかなか、出て来てはくれないんでございます。
もしayumiさんの所へヤツが来てくだすったら、のろん所にもちょっとは顔を出してやるように、言ってくださいましよ。笑