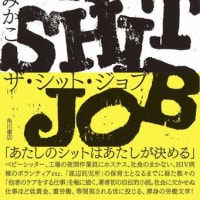小林惠子『江南出身の卑弥呼と高句麗から来た神武』(現代思潮新社、2011年)
 小林惠子の日本古代史シリーズ第1巻である。タイトル通り、3世紀の日本(列島)と朝鮮(半島)と中国のことをさまざまな史書を解読して解明した本で、卑弥呼や神武と呼ばれることになる人々のことが書かれている。
小林惠子の日本古代史シリーズ第1巻である。タイトル通り、3世紀の日本(列島)と朝鮮(半島)と中国のことをさまざまな史書を解読して解明した本で、卑弥呼や神武と呼ばれることになる人々のことが書かれている。
この人の本はいつも登場人物が多すぎて、混乱することが多いのだが、それ以上に、高句麗の王だった東川王が戦に敗北して、列島の越(当時は東倭と呼ばれていた)から日本に来て、さらに北九州を支配していた卑弥呼を破り、トヨを女王に立てて、東遷を開始し、吉備にいた間に死去し、息子が王になってさらに大和地方に東遷を進めたというような話は、本当に刺激的というほかない。
神武の東遷といっても、通常言われているものは264年頃のものだが、これは第三次の東遷で、それ以前に一世紀頃に月氏がスクナヒコナを破った第二次東遷もある。
日本に入ってきたのは、だいたい3つの方面(朝鮮東部やその北から日本海を渡って、今の越に入ってきた部族、朝鮮南部から壱岐島を通って北九州に入ってきた部族、沖縄諸島を北上して種子島から九州に入ってきた部族)で、彼らが入り乱れて、日本の各地を支配していた時代である。
卑弥呼の邪馬台国はどこにあったのかという人気の話題についても著者の考えが説明されているが、この人によれば、卑弥呼は一人ではなかったこと、奄美大島に邪馬台国があったが、後には北九州(伊都国)に移ったという。
それにしてもスケールの大きな話で、一つ疑問に思うのは、1万や2万の大軍という話が出てくるが、そんな輸送力がこの時代にあったのだろうか?陸続きならいざしらず、日本海を渡るなんてできたのだろうか?人間だけではない。馬もいるし、食料その他もそれだけの人数分を確保するというのは、たいへんなことだと思うのだが。
そして、中国での出来事が、朝鮮に影響を与え、それがさらに列島に影響を及ぼすという連鎖があまりに速いテンポで描かれていることだ。あの時代にそんなに情報が飛び交っていたのか(人的行き来があったのか)という疑問が湧き上がるほどだ。まるで現代の政治情勢を見ているような気になる。
この「日本古代史シリーズ」を順番に読んでいく予定だ。
 小林惠子の日本古代史シリーズ第1巻である。タイトル通り、3世紀の日本(列島)と朝鮮(半島)と中国のことをさまざまな史書を解読して解明した本で、卑弥呼や神武と呼ばれることになる人々のことが書かれている。
小林惠子の日本古代史シリーズ第1巻である。タイトル通り、3世紀の日本(列島)と朝鮮(半島)と中国のことをさまざまな史書を解読して解明した本で、卑弥呼や神武と呼ばれることになる人々のことが書かれている。この人の本はいつも登場人物が多すぎて、混乱することが多いのだが、それ以上に、高句麗の王だった東川王が戦に敗北して、列島の越(当時は東倭と呼ばれていた)から日本に来て、さらに北九州を支配していた卑弥呼を破り、トヨを女王に立てて、東遷を開始し、吉備にいた間に死去し、息子が王になってさらに大和地方に東遷を進めたというような話は、本当に刺激的というほかない。
神武の東遷といっても、通常言われているものは264年頃のものだが、これは第三次の東遷で、それ以前に一世紀頃に月氏がスクナヒコナを破った第二次東遷もある。
日本に入ってきたのは、だいたい3つの方面(朝鮮東部やその北から日本海を渡って、今の越に入ってきた部族、朝鮮南部から壱岐島を通って北九州に入ってきた部族、沖縄諸島を北上して種子島から九州に入ってきた部族)で、彼らが入り乱れて、日本の各地を支配していた時代である。
卑弥呼の邪馬台国はどこにあったのかという人気の話題についても著者の考えが説明されているが、この人によれば、卑弥呼は一人ではなかったこと、奄美大島に邪馬台国があったが、後には北九州(伊都国)に移ったという。
それにしてもスケールの大きな話で、一つ疑問に思うのは、1万や2万の大軍という話が出てくるが、そんな輸送力がこの時代にあったのだろうか?陸続きならいざしらず、日本海を渡るなんてできたのだろうか?人間だけではない。馬もいるし、食料その他もそれだけの人数分を確保するというのは、たいへんなことだと思うのだが。
そして、中国での出来事が、朝鮮に影響を与え、それがさらに列島に影響を及ぼすという連鎖があまりに速いテンポで描かれていることだ。あの時代にそんなに情報が飛び交っていたのか(人的行き来があったのか)という疑問が湧き上がるほどだ。まるで現代の政治情勢を見ているような気になる。
この「日本古代史シリーズ」を順番に読んでいく予定だ。