梅雨空の6月20日、何十年も前の知人たちが6人、稲武まで草木染め講習に参加するために来てくれました。
この日用意した染め材料は、稲武特産のタカキビの殻と、朝、庭で採取した桑の葉です。
タカキビを鍋に入れるときに、殻だと思っていたものが、実はほとんど実ばかりなのに気がつきました。もったいないと思いましたが、取替えに帰る時間はありません。前にタカキビのぬかをもらって煮出したら、やけに茶色い色が出たことを思い出し、せっかく知人たちが遠くから来てくれたのに、あのぱっとしない色が出たら、つまらないなとおもいながら、それでも多ければいいだろうと、いつもの1.5倍くらいの量を煮出しました。

すると、なんととってもあざやかな赤みが出ました! 真ん中2枚は絹。朱色です。手前と向こうは木綿。ピンクがかった茶色になりました。いつもよりかなり鮮明な色です。

タカキビの殻染めは、殻の部位によるのか、赤みが勝つときと茶色みが勝つときとがあります。でも、この日は実全体を煮出したので、美しい色が出たのでしょう。

実はちゃんと食べられました。ぜいたくな染めになりました。

桑の葉は、ソーダ灰を加えて緑葉染めにしました。1回目の染め液では黄色。2回目で黄緑色が、3回目で薄いけれど冴えたエメラルドグリーンになるのが普通なのですが、この日は2回目の緑がもっともきれい。ところが、絹のスカーフを銅の媒染液に入れたあと、3回目の染め液に戻したとたん、グレーになってしまいました。麻とレーヨンの混紡のスカーフは、同じ工程を経ても色の変化はありません。なぜか、絹のみグレーに。
あわてて、また銅の媒染駅に戻すと、緑色に変わりました。ただし、もとの緑色とは違って深い色合いです。青いような緑色のような灰色のような複雑な趣のある色です。緑青のような色といっていいかもしれません。面白いので、染液と媒染液とに何度も交互につけました。

手前が何度も繰り返した絹のスカーフ。むこう3枚は染め液に戻さずに洗いに入った布。微妙な違いが写真でもわかります。
草木染めは、化学反応を起こしてさまざまな色が生まれるのですが、化学に弱い私には、魔法みたいに思えます。どの色も、それぞれ味わい深く、再会した知人たちにも喜んでもらえました。2回煮出したタカキビの実は、まだ色が相当出そうだったので、一人に持って帰ってもらいました。彼女は、昔の絹の着物の裏地をこのタカキビで染めてパジャマにするのだとか。出来上がったパジャマを、ぜひ見たいものです。
この日用意した染め材料は、稲武特産のタカキビの殻と、朝、庭で採取した桑の葉です。
タカキビを鍋に入れるときに、殻だと思っていたものが、実はほとんど実ばかりなのに気がつきました。もったいないと思いましたが、取替えに帰る時間はありません。前にタカキビのぬかをもらって煮出したら、やけに茶色い色が出たことを思い出し、せっかく知人たちが遠くから来てくれたのに、あのぱっとしない色が出たら、つまらないなとおもいながら、それでも多ければいいだろうと、いつもの1.5倍くらいの量を煮出しました。

すると、なんととってもあざやかな赤みが出ました! 真ん中2枚は絹。朱色です。手前と向こうは木綿。ピンクがかった茶色になりました。いつもよりかなり鮮明な色です。

タカキビの殻染めは、殻の部位によるのか、赤みが勝つときと茶色みが勝つときとがあります。でも、この日は実全体を煮出したので、美しい色が出たのでしょう。

実はちゃんと食べられました。ぜいたくな染めになりました。

桑の葉は、ソーダ灰を加えて緑葉染めにしました。1回目の染め液では黄色。2回目で黄緑色が、3回目で薄いけれど冴えたエメラルドグリーンになるのが普通なのですが、この日は2回目の緑がもっともきれい。ところが、絹のスカーフを銅の媒染液に入れたあと、3回目の染め液に戻したとたん、グレーになってしまいました。麻とレーヨンの混紡のスカーフは、同じ工程を経ても色の変化はありません。なぜか、絹のみグレーに。
あわてて、また銅の媒染駅に戻すと、緑色に変わりました。ただし、もとの緑色とは違って深い色合いです。青いような緑色のような灰色のような複雑な趣のある色です。緑青のような色といっていいかもしれません。面白いので、染液と媒染液とに何度も交互につけました。

手前が何度も繰り返した絹のスカーフ。むこう3枚は染め液に戻さずに洗いに入った布。微妙な違いが写真でもわかります。
草木染めは、化学反応を起こしてさまざまな色が生まれるのですが、化学に弱い私には、魔法みたいに思えます。どの色も、それぞれ味わい深く、再会した知人たちにも喜んでもらえました。2回煮出したタカキビの実は、まだ色が相当出そうだったので、一人に持って帰ってもらいました。彼女は、昔の絹の着物の裏地をこのタカキビで染めてパジャマにするのだとか。出来上がったパジャマを、ぜひ見たいものです。


















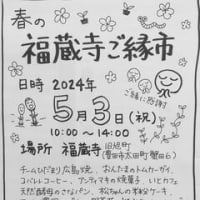







草木染って不思議。魔法のようだね。ブログたのしく 読んでいます。