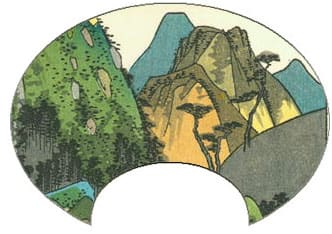為吉の家は、路地裏の長屋であった。長屋表の井戸端では、カミさん連中が大声で下世話の話に夢中になり、下衆な笑いを上げていた。
「為吉兄ちゃん、居てはりますか?」
カミさん連中は、三太の声を聞いて、一瞬静かになり、すぐに家の中で為吉の声がした。
「ああ、三太さんか?」
「そうや、約束通り来ました」
「ちょっとそこで待ってください」
「うん、わかった」
暫くすると、為吉が口をモゴモゴさせながら出てきた。
「朝飯の最中やったのか?」
「そうや、待たせてごめん」
カミさん連中が、三太に無遠慮な視線を送る。
「わい、待っとくさかい、最後まで食べて来いや」
「いや、もう済んだ」
為吉は、戸口で振り返り、「三太さんだ」と、紹介した。為吉の母親が黙って頭を下げた。
「母ちゃん、いってくるわ」
三太と連れあって長屋を後にした。カミさん連中に、爆発したような笑い声が起こっていた。
「失礼なおばはんたちや」
「まず、わいを連れ込んだ神社の森へ行こう」
「何をするの」
「神様に、お礼を言うのや、為吉兄ちゃんを、こんなええ子にしてくれたお礼や」
「恥ずかし」
森では、あの時と同じように、木々のてっぺんに向かって柏手を打ち、恭しくお辞儀をした。
「次は、お父っちゃんが行きそうな酒処や、兄ちゃん知っているやろ」
「うん、安酒場の天狗屋だ」
店に入り、店主に尋ねてみると、一時は毎日来ていたが、ここ十日以上は来ていないと言う。
「おっちゃん、有難う」
店主に礼を言って、外にでた。
「次は、石川島の寄り場や、兄ちゃんのお父っちゃんは、きっと寄り場にいると思う」
「持ち金が無くなったのだろう」
寄り場へ行くと、そこに居た人足たちに片っ端から尋ねまわった。
「嘉蔵という三十過ぎの人足を知りまへんか?」
「さあ、知らんな」
「そんな名前、聞いたことない」
「元、植木職人の手伝いをしていた男だすが」
「うーん、知らんな」
為吉と三太は、寄り場内を探しまわったが見つからなかった。
「ここと違うところへ行きはったのかな」
「もしかしたら、偽名を使っているのかも知れません」
「そうか、偽名だすか」
名前だけでは埒(らち)があかないので、植木職、木登りが得意、高い所を恐がらない男だと言って探すことにした。
探し続けると、平気で高所での作業が出来る男が網にかかった。その男は、弥太と名乗り、鳶職の手伝いをしているのだそうである。三太達は、弥太の今日の仕事場を訊き、行ってみることにした。
遠目ではあるが、丸木の柱をするするっと登っていく男を見つけ、為吉が叫んだ。
「あっ、お父うだ」
二人は駆け寄ってみた。また柱を伝って降りてきた男を見て、為吉が駆け寄った。
「お父う、こんな処で働いていたのか」
「為吉、わしを探しに来たのか、済まん」
為吉は男泣きに泣いている。
「お父う、帰ってきてくれよ、お願いだ」
「植木職の仕事をしくじって、お前達を食わすことが出来なくなったのだ」
為吉は三太に袖をクイクイと引っ張られて、父親に紹介した。
「この子は三太と言って、霊感占い師だ、この子がここへ連れてきてくれた」
嘉蔵は、三太に向かって黙って頭を下げた。
「この子が奉公しているお店の旦那様が、植木職の親方と、お父うがしくじった家に、一緒に行って謝ってやると言ってくれたのだ」
「有り難いが、もうダメだろう、親方はカンカンに怒っていた」
「たとえダメでも、旦那さんやこの子が、お父うを立ち直らせてくれる」
「三太さん有難う、お店の旦那様にもお礼を言っていたと伝えてくだせえ」
「伝えまへん、おじさんが直に言ってください」
「そんな恥晒しなことをさせねぇでくれ」
「大丈夫、旦那様はわいと同じく上方の人間で、それはもう気さくな人だす」
結局、今日の日当は京橋銀座の福島屋亥之吉が払ってくれると言って、鳶の仕事を昼までで打ち切り、嘉蔵は三太と倅の為吉に付いて福島屋まで来た。
「おっちゃん、遠慮しないで店に入って」
そう言っても、嘉蔵は外でもじもじしている。
「何や? 三太か? 嘉蔵さんを連れて来たのか?」
「へえ、それが客やないからと遠慮して入りません」
「そうか、それならわしが出て行こうか」
亥之吉は嘉蔵を見て言った。
「嘉蔵さん、とにかく家(うち)の前栽(せんざい)を見ておくなはれ、松の根元に何やら黒い虫がいるのだす」
「へい、見させて貰います」
嘉蔵は、店の裏へまわり、潜戸を開けて前栽に入り、松の根元を見ている。そこへ亥之吉が覗きに出て来た。
「何や気持ちの悪い毛虫みたなのが口から糸を出していますやろ」
「旦那様、これは松食虫と言いまして、放って置いたら松の木が枯れてしまいます」
「そうか、退治出来ますのか?」
「はい、根元を掘って、虫を焼き殺さねばなりません」
「そうか、ほんなら植木職の親方を呼びに行かせますよって、二人で退治しておくれ」
嘉蔵が慌てた。
「親方が来たら、また叱られます、わしはこれで失礼します」
「嘉蔵さん、帰ったらあきまへん、あんな年寄りひとりで穴が掘れまへんやろ」
「堪忍してください、また叱られたら、わし立ち直れません」
「何を子供みたいなことを言うているのや、腹を括りなはれ」
三太に指示して、植木屋の親方を呼びに行かせた。
親方が、押っ取りがたなで駆けつけてきた。
「旦那さん、松の木がどうかしましたか?」
「へえ、根元に松食虫がわいているのやそうな」
「誰がそんな事を言いました」
親方は周りを見回して、嘉蔵がこの場にいるのに気付いた。
「嘉蔵、来ていたのか」
「へい、福島屋さんに呼ばれまして…」
嘉蔵、気恥ずかしいのか、恐れているのか、下を向いてもじもじしている。
「どれ、松食虫かどうか調べてみよう」
親方、持ってきた円匙(えんし)で穴を掘ろうとしたが、土が硬くて掘れなかった。
「嘉蔵、黙って見てないで、代わって掘ってくれ」
「へい、承知しました」
嘉蔵が穴を掘ると、くろい毛虫がぼろぼろと出てきた。
「ほんとうだ、これは松食虫だ」
嘉蔵は、落ち葉と枯れ草を集めて火を熾し、虫を一匹一匹摘まみ上げると、火の中へ放り込んだ。
「明日、もう少し掘って、竹酢をふり掛けてみましょう、酢を嫌って出てくるかもしれません」
亥之吉は嘉蔵の肩に手をかけ、親方に向かっていった。
「もう、嘉蔵さんを許してあげたらどうだす?」
「へい、わしは遠に許しとります、わしはもう年寄りです、嘉蔵に植木屋を任せようと思っております」
「親方、許してもらえるのですか」
「だから言っているだろ、遠に許していると」
「有難うございます」
「嘉蔵、いまからしくじったお客に詫びにいこう」
親方は少しにっこりとした。
「約束だすさかい、わしも付いて行って、先様に許してくれるように頼みます」
「有難うございます、三太さんも有難う」
嘉蔵の目が潤んでいるように見えた。
先様は、亥之吉の知人であった。
「この嘉蔵さんが、しくじったそうで、わたいも謝ります、どうぞ嘉蔵さんを許してやってください」
先様は、慌てて亥之吉の肩を掴んだ。
「福島屋さん、頭を上げてください」実はと、その後のことを明かしてくれた。
「嘉蔵さんが切った枝を割ってみたら、カミキリムシの幼虫がでてきて、放っておいたらどうせ枯れる枝だとわかりました」
「嘉蔵さんは、それが分かっていて枝を切り落としたのですね」
「はい」
「怒って、悪いことをしました、庭木の手入れは、嘉蔵さんにお任せします」
この後、嘉蔵が植木職の親方を継ぎ、また、完三という二十歳前の男を手伝いに雇い、為吉にも手伝わせた。嘉蔵一家は、親方の土地を借りて建てた屋敷に移り、大々的に客を増やしていった。子供の居ない親方夫婦は、嘉蔵の子供を孫のように可愛がり、為吉と将棋をさすのが楽しみとなった。
「ご隠居さんと将棋をさしても、いつも俺に負けている」
為吉は辟易しながらも、我慢して付き合っているようであった。
第七回 植木屋嘉蔵(終) -次回に続く- (原稿用紙12枚)
「シリーズ三太と亥之吉」リンク
「第一回 小僧と太刀持ち」へ
「第二回 政吉の育ての親」へ
「第三回 弁天小僧松太郎」へ
「第四回 与力殺人事件」へ
「第五回 奉行の秘密」へ
「第六回 政吉、義父の死」へ
「第七回 植木屋嘉蔵」へ
「第八回 棒術の受け達人」へ
「第九回 卯之吉の災難」へ
「第十回 兄、定吉の仇討ち」へ
「第十一回 山村堅太郎と再会」へ
「第十二回 小僧が斬られた」へ
「第十三回 さよなら友達よ」へ
「第十四回 奉行の頼み」へ
「第十五回 立てば芍薬」へ
「第十六回 土足裾どり旅鴉」へ
「第十七回 三太の捕物帳」へ
「第十八回 卯之吉今生の別れ?」へ
「第十九回 美濃と江戸の師弟」へ
「第二十回 長坂兄弟の頼み」へ
「第二十一回 若先生の初恋」へ
「第二十二回 三太の分岐路」へ
「第二十三回 遠い昔」へ
「第二十四回 亥之吉の不倫の子」へ
「第二十五回 果し合い見物」へ
「第二十六回 三太郎、父となる」へ
「第二十七回 敵もさるもの」へ
「第二十八回 三太がついた嘘」へ
「第二十九回 三太の家出」へ
「第三十回 離縁された女」へ
「第三十一回 もうひとつの別れ」へ
「第三十二回 信濃の再会」へ
「最終回 江戸十里四方所払い」へ
次シリーズ 江戸の辰吉旅鴉「第一回 坊っちゃん鴉」へ
「為吉兄ちゃん、居てはりますか?」
カミさん連中は、三太の声を聞いて、一瞬静かになり、すぐに家の中で為吉の声がした。
「ああ、三太さんか?」
「そうや、約束通り来ました」
「ちょっとそこで待ってください」
「うん、わかった」
暫くすると、為吉が口をモゴモゴさせながら出てきた。
「朝飯の最中やったのか?」
「そうや、待たせてごめん」
カミさん連中が、三太に無遠慮な視線を送る。
「わい、待っとくさかい、最後まで食べて来いや」
「いや、もう済んだ」
為吉は、戸口で振り返り、「三太さんだ」と、紹介した。為吉の母親が黙って頭を下げた。
「母ちゃん、いってくるわ」
三太と連れあって長屋を後にした。カミさん連中に、爆発したような笑い声が起こっていた。
「失礼なおばはんたちや」
「まず、わいを連れ込んだ神社の森へ行こう」
「何をするの」
「神様に、お礼を言うのや、為吉兄ちゃんを、こんなええ子にしてくれたお礼や」
「恥ずかし」
森では、あの時と同じように、木々のてっぺんに向かって柏手を打ち、恭しくお辞儀をした。
「次は、お父っちゃんが行きそうな酒処や、兄ちゃん知っているやろ」
「うん、安酒場の天狗屋だ」
店に入り、店主に尋ねてみると、一時は毎日来ていたが、ここ十日以上は来ていないと言う。
「おっちゃん、有難う」
店主に礼を言って、外にでた。
「次は、石川島の寄り場や、兄ちゃんのお父っちゃんは、きっと寄り場にいると思う」
「持ち金が無くなったのだろう」
寄り場へ行くと、そこに居た人足たちに片っ端から尋ねまわった。
「嘉蔵という三十過ぎの人足を知りまへんか?」
「さあ、知らんな」
「そんな名前、聞いたことない」
「元、植木職人の手伝いをしていた男だすが」
「うーん、知らんな」
為吉と三太は、寄り場内を探しまわったが見つからなかった。
「ここと違うところへ行きはったのかな」
「もしかしたら、偽名を使っているのかも知れません」
「そうか、偽名だすか」
名前だけでは埒(らち)があかないので、植木職、木登りが得意、高い所を恐がらない男だと言って探すことにした。
探し続けると、平気で高所での作業が出来る男が網にかかった。その男は、弥太と名乗り、鳶職の手伝いをしているのだそうである。三太達は、弥太の今日の仕事場を訊き、行ってみることにした。
遠目ではあるが、丸木の柱をするするっと登っていく男を見つけ、為吉が叫んだ。
「あっ、お父うだ」
二人は駆け寄ってみた。また柱を伝って降りてきた男を見て、為吉が駆け寄った。
「お父う、こんな処で働いていたのか」
「為吉、わしを探しに来たのか、済まん」
為吉は男泣きに泣いている。
「お父う、帰ってきてくれよ、お願いだ」
「植木職の仕事をしくじって、お前達を食わすことが出来なくなったのだ」
為吉は三太に袖をクイクイと引っ張られて、父親に紹介した。
「この子は三太と言って、霊感占い師だ、この子がここへ連れてきてくれた」
嘉蔵は、三太に向かって黙って頭を下げた。
「この子が奉公しているお店の旦那様が、植木職の親方と、お父うがしくじった家に、一緒に行って謝ってやると言ってくれたのだ」
「有り難いが、もうダメだろう、親方はカンカンに怒っていた」
「たとえダメでも、旦那さんやこの子が、お父うを立ち直らせてくれる」
「三太さん有難う、お店の旦那様にもお礼を言っていたと伝えてくだせえ」
「伝えまへん、おじさんが直に言ってください」
「そんな恥晒しなことをさせねぇでくれ」
「大丈夫、旦那様はわいと同じく上方の人間で、それはもう気さくな人だす」
結局、今日の日当は京橋銀座の福島屋亥之吉が払ってくれると言って、鳶の仕事を昼までで打ち切り、嘉蔵は三太と倅の為吉に付いて福島屋まで来た。
「おっちゃん、遠慮しないで店に入って」
そう言っても、嘉蔵は外でもじもじしている。
「何や? 三太か? 嘉蔵さんを連れて来たのか?」
「へえ、それが客やないからと遠慮して入りません」
「そうか、それならわしが出て行こうか」
亥之吉は嘉蔵を見て言った。
「嘉蔵さん、とにかく家(うち)の前栽(せんざい)を見ておくなはれ、松の根元に何やら黒い虫がいるのだす」
「へい、見させて貰います」
嘉蔵は、店の裏へまわり、潜戸を開けて前栽に入り、松の根元を見ている。そこへ亥之吉が覗きに出て来た。
「何や気持ちの悪い毛虫みたなのが口から糸を出していますやろ」
「旦那様、これは松食虫と言いまして、放って置いたら松の木が枯れてしまいます」
「そうか、退治出来ますのか?」
「はい、根元を掘って、虫を焼き殺さねばなりません」
「そうか、ほんなら植木職の親方を呼びに行かせますよって、二人で退治しておくれ」
嘉蔵が慌てた。
「親方が来たら、また叱られます、わしはこれで失礼します」
「嘉蔵さん、帰ったらあきまへん、あんな年寄りひとりで穴が掘れまへんやろ」
「堪忍してください、また叱られたら、わし立ち直れません」
「何を子供みたいなことを言うているのや、腹を括りなはれ」
三太に指示して、植木屋の親方を呼びに行かせた。
親方が、押っ取りがたなで駆けつけてきた。
「旦那さん、松の木がどうかしましたか?」
「へえ、根元に松食虫がわいているのやそうな」
「誰がそんな事を言いました」
親方は周りを見回して、嘉蔵がこの場にいるのに気付いた。
「嘉蔵、来ていたのか」
「へい、福島屋さんに呼ばれまして…」
嘉蔵、気恥ずかしいのか、恐れているのか、下を向いてもじもじしている。
「どれ、松食虫かどうか調べてみよう」
親方、持ってきた円匙(えんし)で穴を掘ろうとしたが、土が硬くて掘れなかった。
「嘉蔵、黙って見てないで、代わって掘ってくれ」
「へい、承知しました」
嘉蔵が穴を掘ると、くろい毛虫がぼろぼろと出てきた。
「ほんとうだ、これは松食虫だ」
嘉蔵は、落ち葉と枯れ草を集めて火を熾し、虫を一匹一匹摘まみ上げると、火の中へ放り込んだ。
「明日、もう少し掘って、竹酢をふり掛けてみましょう、酢を嫌って出てくるかもしれません」
亥之吉は嘉蔵の肩に手をかけ、親方に向かっていった。
「もう、嘉蔵さんを許してあげたらどうだす?」
「へい、わしは遠に許しとります、わしはもう年寄りです、嘉蔵に植木屋を任せようと思っております」
「親方、許してもらえるのですか」
「だから言っているだろ、遠に許していると」
「有難うございます」
「嘉蔵、いまからしくじったお客に詫びにいこう」
親方は少しにっこりとした。
「約束だすさかい、わしも付いて行って、先様に許してくれるように頼みます」
「有難うございます、三太さんも有難う」
嘉蔵の目が潤んでいるように見えた。
先様は、亥之吉の知人であった。
「この嘉蔵さんが、しくじったそうで、わたいも謝ります、どうぞ嘉蔵さんを許してやってください」
先様は、慌てて亥之吉の肩を掴んだ。
「福島屋さん、頭を上げてください」実はと、その後のことを明かしてくれた。
「嘉蔵さんが切った枝を割ってみたら、カミキリムシの幼虫がでてきて、放っておいたらどうせ枯れる枝だとわかりました」
「嘉蔵さんは、それが分かっていて枝を切り落としたのですね」
「はい」
「怒って、悪いことをしました、庭木の手入れは、嘉蔵さんにお任せします」
この後、嘉蔵が植木職の親方を継ぎ、また、完三という二十歳前の男を手伝いに雇い、為吉にも手伝わせた。嘉蔵一家は、親方の土地を借りて建てた屋敷に移り、大々的に客を増やしていった。子供の居ない親方夫婦は、嘉蔵の子供を孫のように可愛がり、為吉と将棋をさすのが楽しみとなった。
「ご隠居さんと将棋をさしても、いつも俺に負けている」
為吉は辟易しながらも、我慢して付き合っているようであった。
第七回 植木屋嘉蔵(終) -次回に続く- (原稿用紙12枚)
「シリーズ三太と亥之吉」リンク
「第一回 小僧と太刀持ち」へ
「第二回 政吉の育ての親」へ
「第三回 弁天小僧松太郎」へ
「第四回 与力殺人事件」へ
「第五回 奉行の秘密」へ
「第六回 政吉、義父の死」へ
「第七回 植木屋嘉蔵」へ
「第八回 棒術の受け達人」へ
「第九回 卯之吉の災難」へ
「第十回 兄、定吉の仇討ち」へ
「第十一回 山村堅太郎と再会」へ
「第十二回 小僧が斬られた」へ
「第十三回 さよなら友達よ」へ
「第十四回 奉行の頼み」へ
「第十五回 立てば芍薬」へ
「第十六回 土足裾どり旅鴉」へ
「第十七回 三太の捕物帳」へ
「第十八回 卯之吉今生の別れ?」へ
「第十九回 美濃と江戸の師弟」へ
「第二十回 長坂兄弟の頼み」へ
「第二十一回 若先生の初恋」へ
「第二十二回 三太の分岐路」へ
「第二十三回 遠い昔」へ
「第二十四回 亥之吉の不倫の子」へ
「第二十五回 果し合い見物」へ
「第二十六回 三太郎、父となる」へ
「第二十七回 敵もさるもの」へ
「第二十八回 三太がついた嘘」へ
「第二十九回 三太の家出」へ
「第三十回 離縁された女」へ
「第三十一回 もうひとつの別れ」へ
「第三十二回 信濃の再会」へ
「最終回 江戸十里四方所払い」へ
次シリーズ 江戸の辰吉旅鴉「第一回 坊っちゃん鴉」へ