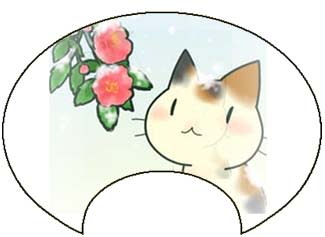北町奉行所与力、長坂清三郎の子息で兄の清心、弟の清之助が二人で三太の元へやって来た。聞けば三太に頼みごとがあると言う。
「お父上に言われて挨拶に来たというのは嘘だすな」
どうも可笑しいと最初から思っていた三太である。
「済みません、いきなりお願いするのも気が引けたもので…」
「もう、友達になったのだすから、何でも言ってください」
清心は恥ずかしそうに語った。父の長坂清三郎から、三太が幼くして他人の心が読めたり、強いのは三太に守護霊が憑いているからだと聞いていた。そのことを寺子屋(手習指南所)の筆子(生徒)に吹聴したところ、守護霊など居る訳がないと「嘘つき」呼ばわりされたのだ。そのことを師匠に告げ口され、清心は師匠から注意を受けた。
「清心、それはお前の妄想であろう、この世の中に霊など存在しないのだよ」
「これは、わたしの父上から聞いたことで、父上は嘘など申しません」
清心は、師匠相手に強情を張った為に、その日は屋敷に帰された。
「帰って反省しなさい、もう嘘はつかないと誓う決心がつくまで、指南所に来なくてもよろしい」
師匠にきつく言われて、清心は悔し泣きをしながら屋敷に戻り、その足で弟を連れて三太の元を訪れたのだと語った。
三太は困った。寺子屋が開いている時間は、三太の一番忙しい頃である。お店の女将が三太の外出を許す訳がない。
「新さん、何か良い思案はありませんか?」
『何とかして行ってやりやしょうぜ、清心さんが可哀想じゃありませんか』
「うん」
暖簾を分けて女将のお絹が出てきた。
「おや、三太にお客さまだすか」
「へえ、長坂清三郎様のお坊ちゃんたちだす」
「これは、これはようこそ、女将の絹だす、長坂さまには色々とお世話になっとります」
ここぞとばかり、三太がしゃしゃり出た。
「その長坂清三郎さまのお使いでみえたのだすが、明日昼ごろわいに来て貰いたいそうだす、わいには仕事がおますので、今、お断りしようかと…」
お絹が、三太の言葉を遮った。
「何を言っていますのや、長坂さまのお頼みを断ってどうしますのや、行きなはれ、行って長坂さまのお役に立って来なはれ」
三太は、長坂兄弟の方に顔を向けて、ぺろりと舌を出した。
「女将さんもああ言ってくれました、明日寺子屋が開いている時間に、わいが行ってあげまひょ、場所と先生の名前を教えておくなはれ」
長坂兄弟が通う寺子屋は、私塾のようであった。その名を藪坂手習い所(てならいしょ-)と言い、藪坂兼功という学者が設立したもので、師範の中に兼功の一子で藪坂冠鷹(かんよう)という二十歳前の先生が居た。この先生が長坂清心の手習いの師である。
「先生に会いたいと、子供が来ています」
年少筆子が冠鷹に伝えに来た。
「この手習いが終わったら会いましょう、待って貰いなさい」
だが、三太は既に付いて来ていた。
「手習いの邪魔をして悪いのだすが、わいは時間がありまへん、それに筆子の皆にもわかってほしいのだす」
「さようか、では仕方がなかろう、用件を申してみよ」
「長坂清心さんが話した守護霊のことだす」
「わたしはそんなものは居ないと清心を嗜めましたが…」
「居る証明をする為に参りました」
「ほう、居ると申すのか?」
「へえ、わいに憑いて居ます」
「手妻か、他人の心を惑わす妖術ではないのか?」
「では、守護霊に人の魂を抜いて貰いますので、誰か一人此処へよこしてください」
冠鷹は、筆子の一人を指名して、三太の元へ行かせた。
「それから、先生も此処へ来てください、魂を抜かれた人が倒れて頭を打たないように護ってください」
「わかった」
冠鷹は三太の前で筆子を後ろから抱き抱えるようにして三太の指示を待った。別段、祈祷をするでもなく、怪しげな手付きで催眠を誘うでもなく、三太は黙って立っていたが、やがて冠鷹に抱えられた少年は気を失って先生に身を委ねた。
「なるほど、これは守護霊の仕業ではなく、妖術の一種であろう」
三太は、首を左右に振った。
「こんなのでは、信用できまへんか?」
「信用できぬ」
「では、先生の心を読んでみましょう」
「今度は読心術か?」
「こんな子供の術で、人様の心が読めましょうか」
守護霊新三郎は、冠鷹に憑いた。
三太は、冠鷹に向かって囁いた。
「先生、いま悩みを抱えているでしょう?」
「ほう、悩みとな」
「それを筆子の皆さんの前で話してもよろしいか?」
冠鷹は、それをハッタリと見たらしく、笑って「どうぞ」と、言ってしまった。
「先生には好きな女子(おなご)が居ますやろ」
「一人や二人の好きな人くらい誰でも居るであろう」
「ちゃいますがな、惚れて、惚れて、惚れぬいた女子だす」
冠鷹は、筆子達にも分かる位に、ぱっと顔を紅らめた。
「その女は、同心の子女で、椿さんと言います」
「ま、待ってくれ、誰にそんなことを聞いたのだ」
「先生は、誰にも喋ったことはないでしょう? 先生の心に教えて貰ったのだす」
冠鷹の心は明らかに動揺しているのに、まだ疑っているようで、懸命に三太が当て推量で言っているのだと思おうとしている。
「先生、椿さんにまだ心の内を話していませんね、それどころか普通に話し掛けてもいないじゃないですか、そんなふうじゃ、他の男に奪われまっせ」
冠鷹は黙り込んでしまった。
「先生、しっかりしなはれ、今日手習いが終わったら、椿さんに会いに行きまひょ、わいの守護霊に椿さんの心を読んで貰います、なるべく早く終わってくださいよ」
こうなっては、冠鷹先生形無しである。筆子たちは囃し立てるし、頭の中は椿のことで一杯になり、手習いなど有ったものではない。
早々に手習いを終えると、三太と共に椿の屋敷に向かった。筆子たちが、そっと跡を付けてきたのは言うまでもない。
うまい具合に、椿が屋敷から出てきた。どうやら買い物に行くらしい。
「あら先生、今日は」
椿はすれ違いざまに挨拶だけをして、恥ずかしそうに下を向いて行き過ぎようとした。その時、守護霊新三郎が椿に移った。
「冠鷹先生、安心しなはれ、椿さんも先生のことが好きのようだす」
「ほんとうかっ」
冠鷹の顔が、明るくなった。
「椿さんを追っ掛けて、話をしてきなはれ、椿さんはそれを待ち焦がれています」
「どんな話をすればよいのだ?」
「そんなこと、子供に訊いてどうしますのや、この際やから、いきなり胸の内を打ち明けてもよろしいやろ、早く行きなはれ」
冠鷹は駆けて行った。三太が立ち止まって二人の様子を見ていると、どうやら旨くいったらしく、そのまま二人は並んで街角を曲がって消えた。筆子たちが「わーっ」と、その後を追って、やはり角に消えた。その中に、長坂清心も居た。
「あほくさ、とんだ仲立ちや、わいも早くおとなに成ろ」
三太は、そのままサッサと店に帰ってきた。
「女将さん、ただ今」
「三太か、遅かったやないか、どこか他所の小僧さんと話をしとったのやろ」
「違います、男と女の仲立ちをしていました」
「何や? それ」
「女将さん、おとなって他愛ないものだすなァ」
「何があったのや?」
「寺子屋の冠鷹という先生が、好きになった女子が居るのに、よう話し掛けへんのだす」
「それで三太が仲立ちを…」
「へえ」
「何と生意気なことを…」
「女将さんも、好きな男が出来たらわいが仲立ちしてやりますで」
「あほ、そんなことしたら死罪や」
第二十一回 若先生の初恋(終) -次回に続く- (原稿用紙11枚)
「シリーズ三太と亥之吉」リンク
「第一回 小僧と太刀持ち」へ
「第二回 政吉の育ての親」へ
「第三回 弁天小僧松太郎」へ
「第四回 与力殺人事件」へ
「第五回 奉行の秘密」へ
「第六回 政吉、義父の死」へ
「第七回 植木屋嘉蔵」へ
「第八回 棒術の受け達人」へ
「第九回 卯之吉の災難」へ
「第十回 兄、定吉の仇討ち」へ
「第十一回 山村堅太郎と再会」へ
「第十二回 小僧が斬られた」へ
「第十三回 さよなら友達よ」へ
「第十四回 奉行の頼み」へ
「第十五回 立てば芍薬」へ
「第十六回 土足裾どり旅鴉」へ
「第十七回 三太の捕物帳」へ
「第十八回 卯之吉今生の別れ?」へ
「第十九回 美濃と江戸の師弟」へ
「第二十回 長坂兄弟の頼み」へ
「第二十一回 若先生の初恋」へ
「第二十二回 三太の分岐路」へ
「第二十三回 遠い昔」へ
「第二十四回 亥之吉の不倫の子」へ
「第二十五回 果し合い見物」へ
「第二十六回 三太郎、父となる」へ
「第二十七回 敵もさるもの」へ
「第二十八回 三太がついた嘘」へ
「第二十九回 三太の家出」へ
「第三十回 離縁された女」へ
「第三十一回 もうひとつの別れ」へ
「第三十二回 信濃の再会」へ
「最終回 江戸十里四方所払い」へ
次シリーズ 江戸の辰吉旅鴉「第一回 坊っちゃん鴉」へ
「お父上に言われて挨拶に来たというのは嘘だすな」
どうも可笑しいと最初から思っていた三太である。
「済みません、いきなりお願いするのも気が引けたもので…」
「もう、友達になったのだすから、何でも言ってください」
清心は恥ずかしそうに語った。父の長坂清三郎から、三太が幼くして他人の心が読めたり、強いのは三太に守護霊が憑いているからだと聞いていた。そのことを寺子屋(手習指南所)の筆子(生徒)に吹聴したところ、守護霊など居る訳がないと「嘘つき」呼ばわりされたのだ。そのことを師匠に告げ口され、清心は師匠から注意を受けた。
「清心、それはお前の妄想であろう、この世の中に霊など存在しないのだよ」
「これは、わたしの父上から聞いたことで、父上は嘘など申しません」
清心は、師匠相手に強情を張った為に、その日は屋敷に帰された。
「帰って反省しなさい、もう嘘はつかないと誓う決心がつくまで、指南所に来なくてもよろしい」
師匠にきつく言われて、清心は悔し泣きをしながら屋敷に戻り、その足で弟を連れて三太の元を訪れたのだと語った。
三太は困った。寺子屋が開いている時間は、三太の一番忙しい頃である。お店の女将が三太の外出を許す訳がない。
「新さん、何か良い思案はありませんか?」
『何とかして行ってやりやしょうぜ、清心さんが可哀想じゃありませんか』
「うん」
暖簾を分けて女将のお絹が出てきた。
「おや、三太にお客さまだすか」
「へえ、長坂清三郎様のお坊ちゃんたちだす」
「これは、これはようこそ、女将の絹だす、長坂さまには色々とお世話になっとります」
ここぞとばかり、三太がしゃしゃり出た。
「その長坂清三郎さまのお使いでみえたのだすが、明日昼ごろわいに来て貰いたいそうだす、わいには仕事がおますので、今、お断りしようかと…」
お絹が、三太の言葉を遮った。
「何を言っていますのや、長坂さまのお頼みを断ってどうしますのや、行きなはれ、行って長坂さまのお役に立って来なはれ」
三太は、長坂兄弟の方に顔を向けて、ぺろりと舌を出した。
「女将さんもああ言ってくれました、明日寺子屋が開いている時間に、わいが行ってあげまひょ、場所と先生の名前を教えておくなはれ」
長坂兄弟が通う寺子屋は、私塾のようであった。その名を藪坂手習い所(てならいしょ-)と言い、藪坂兼功という学者が設立したもので、師範の中に兼功の一子で藪坂冠鷹(かんよう)という二十歳前の先生が居た。この先生が長坂清心の手習いの師である。
「先生に会いたいと、子供が来ています」
年少筆子が冠鷹に伝えに来た。
「この手習いが終わったら会いましょう、待って貰いなさい」
だが、三太は既に付いて来ていた。
「手習いの邪魔をして悪いのだすが、わいは時間がありまへん、それに筆子の皆にもわかってほしいのだす」
「さようか、では仕方がなかろう、用件を申してみよ」
「長坂清心さんが話した守護霊のことだす」
「わたしはそんなものは居ないと清心を嗜めましたが…」
「居る証明をする為に参りました」
「ほう、居ると申すのか?」
「へえ、わいに憑いて居ます」
「手妻か、他人の心を惑わす妖術ではないのか?」
「では、守護霊に人の魂を抜いて貰いますので、誰か一人此処へよこしてください」
冠鷹は、筆子の一人を指名して、三太の元へ行かせた。
「それから、先生も此処へ来てください、魂を抜かれた人が倒れて頭を打たないように護ってください」
「わかった」
冠鷹は三太の前で筆子を後ろから抱き抱えるようにして三太の指示を待った。別段、祈祷をするでもなく、怪しげな手付きで催眠を誘うでもなく、三太は黙って立っていたが、やがて冠鷹に抱えられた少年は気を失って先生に身を委ねた。
「なるほど、これは守護霊の仕業ではなく、妖術の一種であろう」
三太は、首を左右に振った。
「こんなのでは、信用できまへんか?」
「信用できぬ」
「では、先生の心を読んでみましょう」
「今度は読心術か?」
「こんな子供の術で、人様の心が読めましょうか」
守護霊新三郎は、冠鷹に憑いた。
三太は、冠鷹に向かって囁いた。
「先生、いま悩みを抱えているでしょう?」
「ほう、悩みとな」
「それを筆子の皆さんの前で話してもよろしいか?」
冠鷹は、それをハッタリと見たらしく、笑って「どうぞ」と、言ってしまった。
「先生には好きな女子(おなご)が居ますやろ」
「一人や二人の好きな人くらい誰でも居るであろう」
「ちゃいますがな、惚れて、惚れて、惚れぬいた女子だす」
冠鷹は、筆子達にも分かる位に、ぱっと顔を紅らめた。
「その女は、同心の子女で、椿さんと言います」
「ま、待ってくれ、誰にそんなことを聞いたのだ」
「先生は、誰にも喋ったことはないでしょう? 先生の心に教えて貰ったのだす」
冠鷹の心は明らかに動揺しているのに、まだ疑っているようで、懸命に三太が当て推量で言っているのだと思おうとしている。
「先生、椿さんにまだ心の内を話していませんね、それどころか普通に話し掛けてもいないじゃないですか、そんなふうじゃ、他の男に奪われまっせ」
冠鷹は黙り込んでしまった。
「先生、しっかりしなはれ、今日手習いが終わったら、椿さんに会いに行きまひょ、わいの守護霊に椿さんの心を読んで貰います、なるべく早く終わってくださいよ」
こうなっては、冠鷹先生形無しである。筆子たちは囃し立てるし、頭の中は椿のことで一杯になり、手習いなど有ったものではない。
早々に手習いを終えると、三太と共に椿の屋敷に向かった。筆子たちが、そっと跡を付けてきたのは言うまでもない。
うまい具合に、椿が屋敷から出てきた。どうやら買い物に行くらしい。
「あら先生、今日は」
椿はすれ違いざまに挨拶だけをして、恥ずかしそうに下を向いて行き過ぎようとした。その時、守護霊新三郎が椿に移った。
「冠鷹先生、安心しなはれ、椿さんも先生のことが好きのようだす」
「ほんとうかっ」
冠鷹の顔が、明るくなった。
「椿さんを追っ掛けて、話をしてきなはれ、椿さんはそれを待ち焦がれています」
「どんな話をすればよいのだ?」
「そんなこと、子供に訊いてどうしますのや、この際やから、いきなり胸の内を打ち明けてもよろしいやろ、早く行きなはれ」
冠鷹は駆けて行った。三太が立ち止まって二人の様子を見ていると、どうやら旨くいったらしく、そのまま二人は並んで街角を曲がって消えた。筆子たちが「わーっ」と、その後を追って、やはり角に消えた。その中に、長坂清心も居た。
「あほくさ、とんだ仲立ちや、わいも早くおとなに成ろ」
三太は、そのままサッサと店に帰ってきた。
「女将さん、ただ今」
「三太か、遅かったやないか、どこか他所の小僧さんと話をしとったのやろ」
「違います、男と女の仲立ちをしていました」
「何や? それ」
「女将さん、おとなって他愛ないものだすなァ」
「何があったのや?」
「寺子屋の冠鷹という先生が、好きになった女子が居るのに、よう話し掛けへんのだす」
「それで三太が仲立ちを…」
「へえ」
「何と生意気なことを…」
「女将さんも、好きな男が出来たらわいが仲立ちしてやりますで」
「あほ、そんなことしたら死罪や」
第二十一回 若先生の初恋(終) -次回に続く- (原稿用紙11枚)
「シリーズ三太と亥之吉」リンク
「第一回 小僧と太刀持ち」へ
「第二回 政吉の育ての親」へ
「第三回 弁天小僧松太郎」へ
「第四回 与力殺人事件」へ
「第五回 奉行の秘密」へ
「第六回 政吉、義父の死」へ
「第七回 植木屋嘉蔵」へ
「第八回 棒術の受け達人」へ
「第九回 卯之吉の災難」へ
「第十回 兄、定吉の仇討ち」へ
「第十一回 山村堅太郎と再会」へ
「第十二回 小僧が斬られた」へ
「第十三回 さよなら友達よ」へ
「第十四回 奉行の頼み」へ
「第十五回 立てば芍薬」へ
「第十六回 土足裾どり旅鴉」へ
「第十七回 三太の捕物帳」へ
「第十八回 卯之吉今生の別れ?」へ
「第十九回 美濃と江戸の師弟」へ
「第二十回 長坂兄弟の頼み」へ
「第二十一回 若先生の初恋」へ
「第二十二回 三太の分岐路」へ
「第二十三回 遠い昔」へ
「第二十四回 亥之吉の不倫の子」へ
「第二十五回 果し合い見物」へ
「第二十六回 三太郎、父となる」へ
「第二十七回 敵もさるもの」へ
「第二十八回 三太がついた嘘」へ
「第二十九回 三太の家出」へ
「第三十回 離縁された女」へ
「第三十一回 もうひとつの別れ」へ
「第三十二回 信濃の再会」へ
「最終回 江戸十里四方所払い」へ
次シリーズ 江戸の辰吉旅鴉「第一回 坊っちゃん鴉」へ