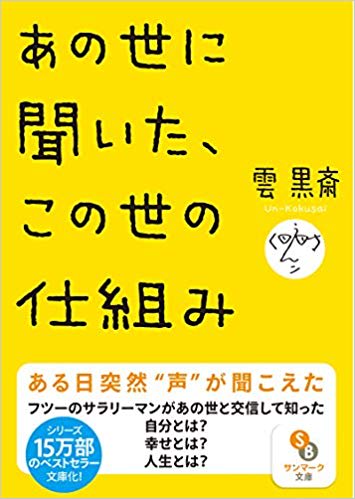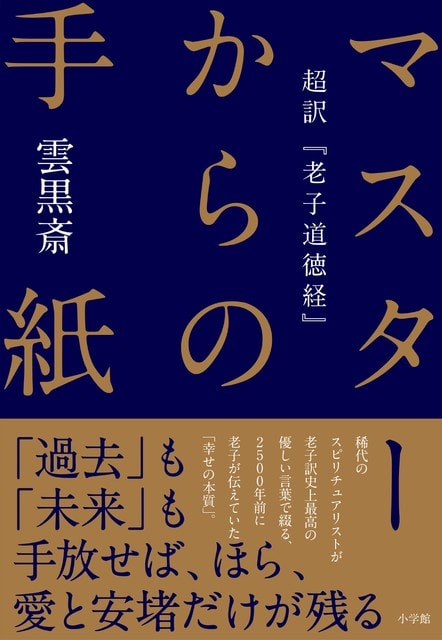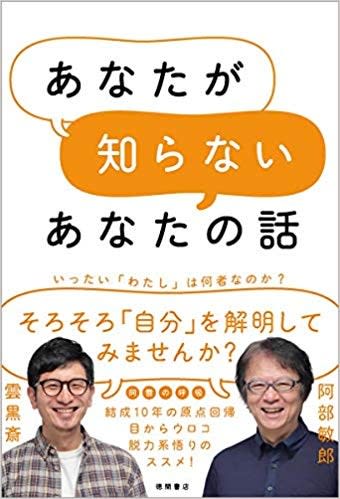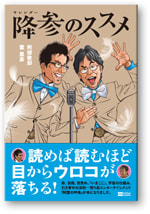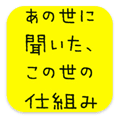2025年、gooブログのサービス終了に伴い、noteへお引越ししました。
あの世に聞いた、この世の仕組み
不還向・不還果
※初めての方はこちら「プロローグ」、「このblogの趣旨」からお読みください。
********************************************
先ほどこのブログを読み返してみたところ…
なんとまぁ、ちゃんとした記事らしい記事を書いていたのは、もう1カ月も前のことだったのね…
大変長らくお待たせしました。
いよいよ「悟りの階梯」のお話に戻りましょう。
これまでの話を振り返りますと、「四向四果」の説明から入りまして、それから「預流向・預流果」、「一来向」、「一来果」までご紹介しました。
で、この後の流れとしては、「一来果」以降の「不還向・不還果」、「阿羅漢向・阿羅漢果」をご説明するのが筋だとは思うのですが、実は、僕はこれらのことについては、簡単にご紹介するぐらいしかできません。
その理由は大きく2つ。
ひとつめ。
「一来果」レベルまでの経験があれば、「存在の仕組み」を理解できているはずなので、すでに「苦しみ」などからは自分の意思で離れる事ができているんです。
後は、自分の成すべき事(思考に基づく行為ではなく、あり方に基づく行為)を行っていくだけと言うことが理解できているので(その姿勢その物が修行であることを理解出来ているので)新たな情報や指針は、あまり必要がないはずです。
ふたつめ。
僕自身が経験出来ていないレベルの話だから。
経験していないんだから、「こういうものです」なんて語れるはずがありません。
実体験が伴っているなら、その経験に沿って、色々な比喩や表現法を考えることができますが、経験していないものを表現することは不可能です。
できるのは、先人の残してくれた情報を、「今現在の僕の解釈」でご紹介することだけです。
~「今現在の僕の解釈」でご紹介する~
これが大きな問題なんです。
レベルの低い者が、自分より高いレベルの世界を語る。
それは、例えるなら小学生が「大学生とは如何なるものか」を語るようなモノ。
どうにもこうにも無理があります。明確に語れるはずがないんです。
どう頑張っても、小学生(僕)が「大学生のお兄ちゃんが、こう言ってました。」的なお話しかできません。
それだって、どこまで正確なものかなんて、わかったもんじゃありません。
本当は、「阿羅漢果」の話を説明できるのは、「阿羅漢」だけなんです。まぁ、当たり前の話なんだけど。
そういうわけで、この先は、以上の事を予めご了承のうえ、ご覧下さい。
【不還向(ふげんこう)・不還果(ふげんか)】
ここでご紹介する「不還果」が、以前「お釈迦様シリーズ」でご紹介したアーラーラ・カーラーマ先生、ウッダカ・ラーマ・プッタ先生のレベルです。
つまり、お釈迦様登場以前、「最高地点」と考えられていた境地の段階。
この「不還果」に入るためには、最低限もう一度「無我」を体験しないといけないそうです。
そこに達する為には、それまでの「一瞬の無我体験」をさらに上回る「圧倒的な禅定体験」が鍵になるのだそう。
と、いうことは、このレベルに達するには、瞑想を習熟して、自らの意志で自由に「禅定」に入るだけの、心の落ち着きが必要になるということです。
一来果以降、日々の生活の中で、いかに自分の煩悩に気付き、それを滅することができているかということが、如実に表れてしまいます。
我々が日々生活している俗世間(六道の世界)と、禅定を通して経験できる梵天界とでは、相当なレベルの違い、大きな壁があるそうです。
さて、この「禅定(五感に頼らず・思考に流されず・意識が研ぎ澄まされ心が純粋にはたらく状態/三昧・寂静の境地)」に入って天界を遙かに超えた梵天界(色界・無色界)に達するとどうなるのでしょうか。
煩悩的には、「預流果」で消えた「有身見」、「疑」、「戒禁取」に加え、「激しい欲」と「激しい怒り」が消えるのだそうです。
っていうか、なんですの。「激しい欲」と「激しい怒り」って。。。
このレベルを持ってしても、やはり「チョットした欲」とか「軽い怒り」はあるってことなのね…
_| ̄|○ 煩悩、おそるべし…
これじゃぁやっぱり「一来果」とそんなに変わらないじゃない…って思っていたら、
ありましたよ奥さん。「一来果」と「不還果」の決定的な違いが!
…
すんません。本日時間切れです…
つづきは後日。
 ←これって、激しい欲? チョットした欲?
←これって、激しい欲? チョットした欲?
********************************************
先ほどこのブログを読み返してみたところ…
なんとまぁ、ちゃんとした記事らしい記事を書いていたのは、もう1カ月も前のことだったのね…
大変長らくお待たせしました。
いよいよ「悟りの階梯」のお話に戻りましょう。
これまでの話を振り返りますと、「四向四果」の説明から入りまして、それから「預流向・預流果」、「一来向」、「一来果」までご紹介しました。
で、この後の流れとしては、「一来果」以降の「不還向・不還果」、「阿羅漢向・阿羅漢果」をご説明するのが筋だとは思うのですが、実は、僕はこれらのことについては、簡単にご紹介するぐらいしかできません。
その理由は大きく2つ。
ひとつめ。
「一来果」レベルまでの経験があれば、「存在の仕組み」を理解できているはずなので、すでに「苦しみ」などからは自分の意思で離れる事ができているんです。
後は、自分の成すべき事(思考に基づく行為ではなく、あり方に基づく行為)を行っていくだけと言うことが理解できているので(その姿勢その物が修行であることを理解出来ているので)新たな情報や指針は、あまり必要がないはずです。
ふたつめ。
僕自身が経験出来ていないレベルの話だから。
経験していないんだから、「こういうものです」なんて語れるはずがありません。
実体験が伴っているなら、その経験に沿って、色々な比喩や表現法を考えることができますが、経験していないものを表現することは不可能です。
できるのは、先人の残してくれた情報を、「今現在の僕の解釈」でご紹介することだけです。
~「今現在の僕の解釈」でご紹介する~
これが大きな問題なんです。
レベルの低い者が、自分より高いレベルの世界を語る。
それは、例えるなら小学生が「大学生とは如何なるものか」を語るようなモノ。
どうにもこうにも無理があります。明確に語れるはずがないんです。
どう頑張っても、小学生(僕)が「大学生のお兄ちゃんが、こう言ってました。」的なお話しかできません。
それだって、どこまで正確なものかなんて、わかったもんじゃありません。
本当は、「阿羅漢果」の話を説明できるのは、「阿羅漢」だけなんです。まぁ、当たり前の話なんだけど。
そういうわけで、この先は、以上の事を予めご了承のうえ、ご覧下さい。
【不還向(ふげんこう)・不還果(ふげんか)】
ここでご紹介する「不還果」が、以前「お釈迦様シリーズ」でご紹介したアーラーラ・カーラーマ先生、ウッダカ・ラーマ・プッタ先生のレベルです。
つまり、お釈迦様登場以前、「最高地点」と考えられていた境地の段階。
この「不還果」に入るためには、最低限もう一度「無我」を体験しないといけないそうです。
そこに達する為には、それまでの「一瞬の無我体験」をさらに上回る「圧倒的な禅定体験」が鍵になるのだそう。
と、いうことは、このレベルに達するには、瞑想を習熟して、自らの意志で自由に「禅定」に入るだけの、心の落ち着きが必要になるということです。
一来果以降、日々の生活の中で、いかに自分の煩悩に気付き、それを滅することができているかということが、如実に表れてしまいます。
我々が日々生活している俗世間(六道の世界)と、禅定を通して経験できる梵天界とでは、相当なレベルの違い、大きな壁があるそうです。
さて、この「禅定(五感に頼らず・思考に流されず・意識が研ぎ澄まされ心が純粋にはたらく状態/三昧・寂静の境地)」に入って天界を遙かに超えた梵天界(色界・無色界)に達するとどうなるのでしょうか。
煩悩的には、「預流果」で消えた「有身見」、「疑」、「戒禁取」に加え、「激しい欲」と「激しい怒り」が消えるのだそうです。
っていうか、なんですの。「激しい欲」と「激しい怒り」って。。。
このレベルを持ってしても、やはり「チョットした欲」とか「軽い怒り」はあるってことなのね…
_| ̄|○ 煩悩、おそるべし…
これじゃぁやっぱり「一来果」とそんなに変わらないじゃない…って思っていたら、
ありましたよ奥さん。「一来果」と「不還果」の決定的な違いが!
…
すんません。本日時間切れです…
つづきは後日。
 ←これって、激しい欲? チョットした欲?
←これって、激しい欲? チョットした欲?コメント ( 12 ) | Trackback ( )
一来果
※初めての方はこちら「プロローグ」、「このblogの趣旨」からお読みください。
********************************************
さて、それでは次なるステップ「一来果(いちらいか)」へ向けてお話を続けていきましょう。
「預流果」までは、何かを切っ掛けとした偶然や説法など、いわゆる「外的要因」によって迎えることも可能でしたが、ここから先は「自力」でしか進めません。
日々の精進(一来向)と瞑想修行が必要になります。(「必要となります」とは言っても、義務でも強制でもありません。ごく自然に、そういう姿勢になっていきます。)
また、「瞑想修行」と聞くとどこか仰々しいですが、あまり難しくは考えないでください。
「ゆっくりと、心をなだめてあげる。」まずは、そのぐらいの気持ちで捉えていただければいいかと思います。
欲や怒り、妄想など、日々自分の心を掻き乱しているあれこれを静め、精神状態がスーっと落ち着いてくると、徐々に思考が明晰になり、智慧(真理を見極める認識力)が現れてくるのを感じることが出来ます。
その心の落ち着きが、ある一定のラインまで静まると、もう一度あの時の「無我(私がいない)」という瞬間が訪れます。
2度目の内的体験。それによって真理に対する確信が、よりいっそう高まります。
「ああ、やっぱり! あの気付きは、間違いでも、勘違いでも、気のせいでもなかった!」
これを「一来果」と言います。
さて、前段階の「預流果」では、「有身見・疑・戒禁取」の3つの煩悩が消えました。
「一来果」を迎えると、どうなるのでしょうか。
「貪欲(欲)・瞋恚(怒り)・愚痴(無知)」の『三毒(三大煩悩)』、それらが弱くなります。
…
…
…
「え?」
…
いえ、ですから、「欲・怒り・無知」が弱まります。
…
「何かの煩悩が消えるのではなく、弱まるだけ?」
…
はい。それだけ…ですが、なにか?
…
「地味…ですね。」
…
ええ。地味ですね。
地味ですが、何かを死に物狂いで追いかけることもなく、誰かや何かに必死にしがみつくこともなく、執拗に怒り続けることもなく、しつこく悲しみ続けることもなく、思考がクリアで何事にも要領よく対応できる様になっているので、以前と比べると、格段に幸せになっています。
自分の「あり方」がハッキリしているので、誰かや何かに流されることも減っていきます。
物事の因果関係を明確に捉えられるようになっていくので、物事がスムーズに進むようになり、強く望まなくとも、希望は自然と叶っていきます。
穏やかに、朗らかでいられるようになります。
煩悩が薄れれば薄れるほど、自由になっていくことを実感しているので、自ずと修行も進みます。
…
「あぁ。そう言われると、なんだか幸せそうでいいですね。」
でしょ?
でも、そうとはいえ、やっぱり「修行段階」であることには間違いありません。
ですから、この段階で死んでしまったとしたら…
「死んでしまったとしたら!?」
もう一度、人間界に生まれてくることが確定します。
「どうしてですか?」
まだ完全に悟っているわけではないですし、この上の段階「不還果(ふげんか)」の様に梵天界へ遊びに行くこともできません。
完全な悟りのために、もう一度「再挑戦」しなければならないんです。
そのためにもう一度だけ輪廻しなければならないのですが、人間界より下の世界は、修行の必要性を感じない愚かな世界ですし、天界は「楽」を感受するだけの世界ですから修行にはなりません。
ですから、その修行のためには、人間界が必要なんです。
もう一度だけ、人間界に来る必要があるので「一来果」と言います。
 ←地味な作業にご協力お願いします。
←地味な作業にご協力お願いします。
********************************************
さて、それでは次なるステップ「一来果(いちらいか)」へ向けてお話を続けていきましょう。
「預流果」までは、何かを切っ掛けとした偶然や説法など、いわゆる「外的要因」によって迎えることも可能でしたが、ここから先は「自力」でしか進めません。
日々の精進(一来向)と瞑想修行が必要になります。(「必要となります」とは言っても、義務でも強制でもありません。ごく自然に、そういう姿勢になっていきます。)
また、「瞑想修行」と聞くとどこか仰々しいですが、あまり難しくは考えないでください。
「ゆっくりと、心をなだめてあげる。」まずは、そのぐらいの気持ちで捉えていただければいいかと思います。
欲や怒り、妄想など、日々自分の心を掻き乱しているあれこれを静め、精神状態がスーっと落ち着いてくると、徐々に思考が明晰になり、智慧(真理を見極める認識力)が現れてくるのを感じることが出来ます。
その心の落ち着きが、ある一定のラインまで静まると、もう一度あの時の「無我(私がいない)」という瞬間が訪れます。
2度目の内的体験。それによって真理に対する確信が、よりいっそう高まります。
「ああ、やっぱり! あの気付きは、間違いでも、勘違いでも、気のせいでもなかった!」
これを「一来果」と言います。
さて、前段階の「預流果」では、「有身見・疑・戒禁取」の3つの煩悩が消えました。
「一来果」を迎えると、どうなるのでしょうか。
「貪欲(欲)・瞋恚(怒り)・愚痴(無知)」の『三毒(三大煩悩)』、それらが弱くなります。
…
…
…
「え?」
…
いえ、ですから、「欲・怒り・無知」が弱まります。
…
「何かの煩悩が消えるのではなく、弱まるだけ?」
…
はい。それだけ…ですが、なにか?
…
「地味…ですね。」
…
ええ。地味ですね。
地味ですが、何かを死に物狂いで追いかけることもなく、誰かや何かに必死にしがみつくこともなく、執拗に怒り続けることもなく、しつこく悲しみ続けることもなく、思考がクリアで何事にも要領よく対応できる様になっているので、以前と比べると、格段に幸せになっています。
自分の「あり方」がハッキリしているので、誰かや何かに流されることも減っていきます。
物事の因果関係を明確に捉えられるようになっていくので、物事がスムーズに進むようになり、強く望まなくとも、希望は自然と叶っていきます。
穏やかに、朗らかでいられるようになります。
煩悩が薄れれば薄れるほど、自由になっていくことを実感しているので、自ずと修行も進みます。
…
「あぁ。そう言われると、なんだか幸せそうでいいですね。」
でしょ?
でも、そうとはいえ、やっぱり「修行段階」であることには間違いありません。
ですから、この段階で死んでしまったとしたら…
「死んでしまったとしたら!?」
もう一度、人間界に生まれてくることが確定します。
「どうしてですか?」
まだ完全に悟っているわけではないですし、この上の段階「不還果(ふげんか)」の様に梵天界へ遊びに行くこともできません。
完全な悟りのために、もう一度「再挑戦」しなければならないんです。
そのためにもう一度だけ輪廻しなければならないのですが、人間界より下の世界は、修行の必要性を感じない愚かな世界ですし、天界は「楽」を感受するだけの世界ですから修行にはなりません。
ですから、その修行のためには、人間界が必要なんです。
もう一度だけ、人間界に来る必要があるので「一来果」と言います。
 ←地味な作業にご協力お願いします。
←地味な作業にご協力お願いします。コメント ( 38 ) | Trackback ( )
一来向
※初めての方はこちら「プロローグ」、「このblogの趣旨」からお読みください。
********************************************
「ねぇねぇ、黒斎さん。なんで最近仏教の話ばっかりなん?」
そんな事を思われていそうな昨今、皆様いかがお過ごしでしょうか。
書いている自分でさえ、「これじゃあ、なんか布教活動してる人みたいだなぁ…」と感じつつ、何かと筆の進まない感じになっている黒斎(AKB48所属)です。こんにちは。
うん。そうだよね。
このタイミングでこのブログに辿り着いた人だったら、思いっきり「あ、なに?ここって仏教サイト?」ってなっちゃうよね。
今更こんな事言うのも何なんだけど、僕、別に仏教の話をしたいわけじゃないんですよ。
他の宗教の根本で語られていることも、大切な事は一緒だし。
でもね、このことを理論的に説明しようと思ったら、古今東西見渡してみても、お釈迦様の話に敵うモノは他に見あたらないんです。
もうね、完璧に理論体系が完成されてるんです。仏教って。
こういう比較をするのもなんなんだけど、例えば、仏教とキリスト教を比べた場合…
お釈迦様って、「知的でクール。真理を論理的に語る。」というような感じで、
イエス様って、「情熱的で誠実。真理を詩的に語る。」という感じなんです。
同じ事を語るのでも、アプローチの仕方が全く違うの。
お釈迦様の語り口は「科学的」、かたやイエス様の語り口は「芸術的・文学的」。
これを「論理」という観点で比べると、やっぱり「科学的」な語りの方が向いているワケです。
勿論「芸術的・文学的」な語りが悪いって事じゃないですよ。それはそれで長所がいっぱいあります。
でも、どうしても「芸術的」な語り方では、「通約不可能性」が高まってしまうので、「受け取り方次第」で、本質が揺れてしまうんですね。
どちらかというと、科学的に根拠を示す事ができたり、「こうだから、こうなるでしょう?」と弁証法的に語られた方が、的確な理解に繋がりやすいと思うんです。
仏教は、そういう理由で、理論体系がシッカリしているからお話(説明)しやすいんです。
そんなこんなで、ここのところの記事はやたらと仏教づいてます。
…ってこうやって言い訳しても、やっぱりなんか仏教の肩を持つ人みたいになっちゃうかな…
まぁ、いいや。
さて、言い訳はこのぐらいにして、ここらで先日のお話の続きを書きますね。
「預流果」は、ホントに凄いことでも、偉いことでもないんです。
どちらかというと、「なんで今までこんな簡単で単純なことに気付けなかったんだろう。」って思うぐらいのことです。
前記事のコメント欄を拝見したら、コタさんがこの意味を掴むことが出来たようです。(そのコメントを拝見した時、とっても嬉しくて、ちょっと涙が出ました。)
その「気付き」を得ると、「因縁(原因・条件に基づく、その結果)」という言葉の本質を、「体験」として理解できます。
「そうか、“今の自分(結果)”があるのは、こうこうこういう理由(原因・条件)があったからなんだ!」
「現実」を形づくる、その「仕組み」を知ってしまうので、必然的にそれまで自分を苦しめていた「原因」を突き止めてしまいます。
「ああ!ほんとだ!これまで自分が苦しんできた全ての原因は、私の煩悩(欲・怒り・無知)だ!」
そうなると、もう後戻りはできません。
自分が不幸になる原因を知ってしまったので、もう、それを続けようとは思えなくなるんです。
あとは、これまで自分を苦しめてきた「原因」と「条件」を捨てていくだけです。
「よっしゃ!自分を苦しめるのはもう止めた!これからは、自分を苦しめてきた原因をどんどん捨てて行くぞ!」
その姿勢(あり方)の事を『一来向(いちらいこう)』と言います。
「預流果」を迎えると、もれなくついてきます。
 ←はい。僕はまだ続けます。
←はい。僕はまだ続けます。
********************************************
「ねぇねぇ、黒斎さん。なんで最近仏教の話ばっかりなん?」
そんな事を思われていそうな昨今、皆様いかがお過ごしでしょうか。
書いている自分でさえ、「これじゃあ、なんか布教活動してる人みたいだなぁ…」と感じつつ、何かと筆の進まない感じになっている黒斎(AKB48所属)です。こんにちは。
うん。そうだよね。
このタイミングでこのブログに辿り着いた人だったら、思いっきり「あ、なに?ここって仏教サイト?」ってなっちゃうよね。
今更こんな事言うのも何なんだけど、僕、別に仏教の話をしたいわけじゃないんですよ。
他の宗教の根本で語られていることも、大切な事は一緒だし。
でもね、このことを理論的に説明しようと思ったら、古今東西見渡してみても、お釈迦様の話に敵うモノは他に見あたらないんです。
もうね、完璧に理論体系が完成されてるんです。仏教って。
こういう比較をするのもなんなんだけど、例えば、仏教とキリスト教を比べた場合…
お釈迦様って、「知的でクール。真理を論理的に語る。」というような感じで、
イエス様って、「情熱的で誠実。真理を詩的に語る。」という感じなんです。
同じ事を語るのでも、アプローチの仕方が全く違うの。
お釈迦様の語り口は「科学的」、かたやイエス様の語り口は「芸術的・文学的」。
これを「論理」という観点で比べると、やっぱり「科学的」な語りの方が向いているワケです。
勿論「芸術的・文学的」な語りが悪いって事じゃないですよ。それはそれで長所がいっぱいあります。
でも、どうしても「芸術的」な語り方では、「通約不可能性」が高まってしまうので、「受け取り方次第」で、本質が揺れてしまうんですね。
どちらかというと、科学的に根拠を示す事ができたり、「こうだから、こうなるでしょう?」と弁証法的に語られた方が、的確な理解に繋がりやすいと思うんです。
仏教は、そういう理由で、理論体系がシッカリしているからお話(説明)しやすいんです。
そんなこんなで、ここのところの記事はやたらと仏教づいてます。
…ってこうやって言い訳しても、やっぱりなんか仏教の肩を持つ人みたいになっちゃうかな…
まぁ、いいや。
さて、言い訳はこのぐらいにして、ここらで先日のお話の続きを書きますね。
「預流果」は、ホントに凄いことでも、偉いことでもないんです。
どちらかというと、「なんで今までこんな簡単で単純なことに気付けなかったんだろう。」って思うぐらいのことです。
前記事のコメント欄を拝見したら、コタさんがこの意味を掴むことが出来たようです。(そのコメントを拝見した時、とっても嬉しくて、ちょっと涙が出ました。)
その「気付き」を得ると、「因縁(原因・条件に基づく、その結果)」という言葉の本質を、「体験」として理解できます。
「そうか、“今の自分(結果)”があるのは、こうこうこういう理由(原因・条件)があったからなんだ!」
「現実」を形づくる、その「仕組み」を知ってしまうので、必然的にそれまで自分を苦しめていた「原因」を突き止めてしまいます。
「ああ!ほんとだ!これまで自分が苦しんできた全ての原因は、私の煩悩(欲・怒り・無知)だ!」
そうなると、もう後戻りはできません。
自分が不幸になる原因を知ってしまったので、もう、それを続けようとは思えなくなるんです。
あとは、これまで自分を苦しめてきた「原因」と「条件」を捨てていくだけです。
「よっしゃ!自分を苦しめるのはもう止めた!これからは、自分を苦しめてきた原因をどんどん捨てて行くぞ!」
その姿勢(あり方)の事を『一来向(いちらいこう)』と言います。
「預流果」を迎えると、もれなくついてきます。
 ←はい。僕はまだ続けます。
←はい。僕はまだ続けます。コメント ( 18 ) | Trackback ( )
解脱
※初めての方はこちら「プロローグ」、「このblogの趣旨」からお読みください。
********************************************
前回、『悟り』とは、「預流果」を皮切りに、煩悩が順に消えていき、煩悩が消えた分だけ智慧(真理を見極める認識力)が現れていく現象のことを言います、というお話をしました。
今日は、これを別な表現でお話したいと思います。
「悟りの階梯が進み、煩悩が消えた分だけ智慧(真理を見極める認識力)が現れていく」と言うことは、同時に「輪廻の回数が減っていく」というコトを意味します。
こういうコトを言うと、「もし自分が死んでも、また生まれてきたい。」と思っている方から見たら、「冗談じゃない!生まれ変わりの回数が減ってしまうというなら、悟りたくなんてない!」と拒絶されてしまいそうですね。
でも、「何度生まれ変わっても、生まれることが出来る世界は“苦しみの世界”ですよ。」と言われたらどう思います?
「あ、そういうことならもう結構です。苦しみの世界には留まりたくありません。」と、そうなりますよね。
『解脱(げだつ)を目指す』とは、そういうことなんです。
「天国」や「地獄」という言葉を聞くと、どこか「死んだ後に魂が帰る世界」というような印象があるかと思います。
ですが、本当は違うんです。
僕たちは、今すでに、それらの世界のどこかに存在しています。
(とはいえ、本当の意味の「天国」に存在している人は、残念ながらこの地球にはいません。)
僕たちは、その苦しみの強弱はあれど、例外なく「苦しみを生む世界」の中に生きているんです。
「苦しみを生む世界に繰り返し生まれてくる」と言っても、それは「行いが悪かったからこその天罰」ということではありません。
誰のせいでもなく、自分の自由意思において、そこに留まっているんです。自ら苦しみを選択しているんです。
自分の自由意思によって「不自由」や「苦悩」を選択するという、なんとも馬鹿げたことをしているのが人間。
その愚かさのコトを仏教では『愚痴(無知)』と言います。そう。「煩悩」の一つですね。
苦しみを生む原因の一つは、「自分で自分を苦しめているという事実に気づかない愚かしさ」というワケです。
さて、先ほど触れた「苦しみを生む世界」を、さらに6階層(または5階層)に分け、その世界をカテゴライズしましょう。
それが、仏教で言うところの『六道(五道)』です。
下のランクから順に、「地獄界・餓鬼界・畜生界・(阿修羅界)・人間界・天界」となります。
ランクが下がるほど苦しみは深くなり、ランクが上がるほど苦しみは軽くなります。
仏教に詳しくなくても、どこかで聞いたことありますでしょ?
また、この「六道」については、「いまここ塾」の阿部さんが連載をされていたのでご存じの方も多いと思います。
※とてもわかりやすく六道のコトを教えてくれていますので、ご一読をオススメします。
「地獄界」 「餓鬼界」 「畜生界」 「人間界」 「阿修羅界」 「天界」
「自分の望みが思いどおりに叶う世界」、そんな世界のコトを、「天国」と捉えている方も多いかと思います。
上記六道の「天界」は、まさにそういう、満足感・達成感に溢れた世界。
ですが、この「天界」も実は本当の意味での「天国」ではありません。せいぜい「自我」が喜びを得る程度の「疑似天国」なんです。
「天」とはいえど、まだまだそこには「自我」があり、「欲」に元ずく世界ゆえ、苦しみの種は残っています。
満足感・達成感を維持しようと、そこに「執着(欲)」が生まれた途端、一時の幸福感もつかの間、あっという間に下の次元へ落ちてゆくこととなります。
『解脱』は、この疑似天国も超えた世界への飛翔を意味します。
…
さて、以上の話を踏まえて、再度「悟りの階梯」のお話へと戻っていきましょう。
…
っていうか、やっぱこのシリーズ、なんか堅っ苦しくない?
 ←大丈夫?まだ行ける?
←大丈夫?まだ行ける?
********************************************
前回、『悟り』とは、「預流果」を皮切りに、煩悩が順に消えていき、煩悩が消えた分だけ智慧(真理を見極める認識力)が現れていく現象のことを言います、というお話をしました。
今日は、これを別な表現でお話したいと思います。
「悟りの階梯が進み、煩悩が消えた分だけ智慧(真理を見極める認識力)が現れていく」と言うことは、同時に「輪廻の回数が減っていく」というコトを意味します。
こういうコトを言うと、「もし自分が死んでも、また生まれてきたい。」と思っている方から見たら、「冗談じゃない!生まれ変わりの回数が減ってしまうというなら、悟りたくなんてない!」と拒絶されてしまいそうですね。
でも、「何度生まれ変わっても、生まれることが出来る世界は“苦しみの世界”ですよ。」と言われたらどう思います?
「あ、そういうことならもう結構です。苦しみの世界には留まりたくありません。」と、そうなりますよね。
『解脱(げだつ)を目指す』とは、そういうことなんです。
「天国」や「地獄」という言葉を聞くと、どこか「死んだ後に魂が帰る世界」というような印象があるかと思います。
ですが、本当は違うんです。
僕たちは、今すでに、それらの世界のどこかに存在しています。
(とはいえ、本当の意味の「天国」に存在している人は、残念ながらこの地球にはいません。)
僕たちは、その苦しみの強弱はあれど、例外なく「苦しみを生む世界」の中に生きているんです。
「苦しみを生む世界に繰り返し生まれてくる」と言っても、それは「行いが悪かったからこその天罰」ということではありません。
誰のせいでもなく、自分の自由意思において、そこに留まっているんです。自ら苦しみを選択しているんです。
自分の自由意思によって「不自由」や「苦悩」を選択するという、なんとも馬鹿げたことをしているのが人間。
その愚かさのコトを仏教では『愚痴(無知)』と言います。そう。「煩悩」の一つですね。
苦しみを生む原因の一つは、「自分で自分を苦しめているという事実に気づかない愚かしさ」というワケです。
さて、先ほど触れた「苦しみを生む世界」を、さらに6階層(または5階層)に分け、その世界をカテゴライズしましょう。
それが、仏教で言うところの『六道(五道)』です。
下のランクから順に、「地獄界・餓鬼界・畜生界・(阿修羅界)・人間界・天界」となります。
ランクが下がるほど苦しみは深くなり、ランクが上がるほど苦しみは軽くなります。
仏教に詳しくなくても、どこかで聞いたことありますでしょ?
また、この「六道」については、「いまここ塾」の阿部さんが連載をされていたのでご存じの方も多いと思います。
※とてもわかりやすく六道のコトを教えてくれていますので、ご一読をオススメします。
「地獄界」 「餓鬼界」 「畜生界」 「人間界」 「阿修羅界」 「天界」
「自分の望みが思いどおりに叶う世界」、そんな世界のコトを、「天国」と捉えている方も多いかと思います。
上記六道の「天界」は、まさにそういう、満足感・達成感に溢れた世界。
ですが、この「天界」も実は本当の意味での「天国」ではありません。せいぜい「自我」が喜びを得る程度の「疑似天国」なんです。
「天」とはいえど、まだまだそこには「自我」があり、「欲」に元ずく世界ゆえ、苦しみの種は残っています。
満足感・達成感を維持しようと、そこに「執着(欲)」が生まれた途端、一時の幸福感もつかの間、あっという間に下の次元へ落ちてゆくこととなります。
『解脱』は、この疑似天国も超えた世界への飛翔を意味します。
…
さて、以上の話を踏まえて、再度「悟りの階梯」のお話へと戻っていきましょう。
…
っていうか、やっぱこのシリーズ、なんか堅っ苦しくない?
 ←大丈夫?まだ行ける?
←大丈夫?まだ行ける?コメント ( 26 ) | Trackback ( )
預流向・預流果
※初めての方はこちら「プロローグ」、「このblogの趣旨」からお読みください。
********************************************
さて、それではさっそく悟りの階梯を、順を追ってみていきましょう。
前回、解脱までの道のりは、4つの「向(目標)」と4つの「果(到達)」の合わせて8段階、というお話をしました。
・預流向(よるこう)
-----------------------------------
・預流果(よるか)
・一来向(いちらいこう)
・一来果(いちらいか)
・不還向(ふげんこう)
・不還果(ふげんか)
・阿羅漢向(あらかんこう)
・阿羅漢果(あらかんか)
前回は足し算的に「8段階」と説明してしまいましたが、「階梯(段階・レベル)」という意味で厳密に捉え直すと「4段階+1(預流向)」です。
と、申しますのも、一つでも「果(到達)」に辿り着くと、そこに次なる目標(向)が必然的についてくるからです。
【悟りの4段階+1】
準備段階:「預流向(よるこう)」
第一段階:「預流果(よるか)」と「一来向(いちらいこう)」のワンセット
第二段階:「一来果(いちらいか)」と「不還向(ふげんこう)」のワンセット
第三段階:「不還果(ふげんか)」と「阿羅漢向(あらかんこう)」のワンセット
最終段階:「阿羅漢果(あらかんか)」
という具合。
『悟り』とは、「預流果」を皮切りに、煩悩が順に消えていき、煩悩が消えた分だけ智慧(真理を見極める認識力)が現れていく現象のことを言います。
ですから、一口に「悟り」と言っても、そのレベルは人によって大きく異なります。
預流果、一来果、不還果と順に一つずつ段階を進み、阿羅漢果で完成します。
『自分を苦しめている諸悪の根源は、己の持つ煩悩。それ以外の理由はない。』
このことをハッキリと理解し、「よし、煩悩を消して、真理を見極めよう。」と、シッカリと真理に向かう姿勢のことを「預流向(よるこう)」と言います。
ちなみに「預流(よる)」とは、「完全な悟り(阿羅漢果)へ向かう聖なる流れに身を預ける」という意味だそうです。
その目標に向かうから「預流向」。
ここでは、まだ悟りを目指しているだけの状態ですので、まだ「悟り」とは言えません。(そういう意味も込めて、「預流向」と「預流果」の間に線を入れさせていただきました。)
では、その一線を越え、「預流果」を迎えるとどうなるのでしょうか。
以前、煩悩は数え切れないほどある、というお話をさせていただきました。
大きく分けると「貪欲(欲)」・「瞋恚(怒り)」・「愚痴(無知)」の3種類。
それに「慢(傲慢)」・「見(邪見)」・「疑(疑い)」を加えて『六大煩悩』。
それらを細分化していくと、有名な「108」に、それをさらに細分化すると数千、数万とキリがなくなっていきます。
その膨大な数の煩悩の中から、「預流果」で消える煩悩は…
1.有身見(うしんけん)
2.疑(ぎ)
3.戒禁取(かいごんじゅ)
…
…
…
え? それだけ?
…
はい。それだけです。
膨大な数の煩悩のうち、たった3つだけなんです。
無くなった煩悩はたった3つだけですから、まだまだ悩みも苦しみも膨大に残っています。
怒りもするし、泣きもするし、ヘマもしますし、凹みもします。
ですが、たった3つとはいえ、悟りを決定づける大切な3つです。
では、その3つを順に見ていきましょう。
1.有身見(うしんけん)
この煩悩は、「貪欲(欲)」でも「瞋恚(怒り)」でもありません。「愚痴(無知)」「見(邪見)」のカテゴリーに属する煩悩です。
これまで色々な形でお話してきた『「私」という独立した存在がある。』という錯覚のことを指す煩悩です。
ほんの一瞬でも、「無常」「無我」を知識としてではなく、体験として納得した時、「有身見」という邪見(因果の道理を無視する誤った考え方)は消え、「ああ、実際には“私”は実在しないんだ!」という理解と共に「無常・無我」という智慧が現れるんです。
そして、「有身見」が無くなると同時に、必然的に無くなる煩悩が2つあります。
それが「疑」と「戒禁取」です。この2つも「有身見」と同じく「愚痴(無知)」のカテゴリーの煩悩です。
2.疑(ぎ)
読んで字の如く「疑い」を意味します。
「疑」という煩悩が無くなるということは、「真理(諸行無常・諸法無我・因縁等)に対しての疑いが無くなる。」という意味です。
「有身見」が無くなったことによって、一瞬でも真理を「体験」しているため、当然それに対しての疑いがなくなります。
先日の「アハ体験」の例で言えば、「ああ!ホントにイエスが描かれていたんだ!」と納得できると、「アハ体験」以前にあった、「え~?こんなワケのわからない模様の中に、何が見えるって言うの?」という疑いは、絵が見えたと同時に消え去ります。
そんなニュアンスで捉えてください。
3.戒禁取(かいごんじゅ)
「戒禁取」は、しきたりや作法・儀式、無意味な修行や苦行等に対してこだわりをもってしまう煩悩(無知)のコトです。
槍のチンコ巻きとかは、まぁ、普段見ることはないにせよ、世の中には、ありがたい宗教的意義がありそうな修行や奇行が沢山あります。
ここ日本でも多く見受けられる「お祭り」や「火渡り」、「滝行」なんかも、この中に含まれます。
線香を何本立てろとか、戒名をどうしろこうしろとか、神社参拝やお墓参りの際は手を何回叩けとか、○○を供えろとか、日々「○○○○○」と唱えろとか、数珠は右手で持て、いや、左手だとか、そう言った「しきたり」や「儀式」にこだわるのも「戒禁取」です。
宗教的なコトだけではなく、事故に遭わないよう、家を出る時は靴は右足から履くとか、試合前にはユニフォームは右袖から着るとか、そういう、いわゆる「ジンクス」なども「戒禁取」です。
真理に触れるという経験をほんの一瞬でもすると、そういったあれこれは、エゴ(自我)が作った勝手な決まり事、文化以上の意味があるわけではないとわかるので、そういったものにこだわったり、ありがたがる気持ちがなくなります。
もちろん、それらの文化にも伝統や出来上がった背景などがありますから、無理に壊したり、蔑ろにするのも考え物です。
文化は、あくまで文化。ですから、人様に迷惑を掛けないのであれば、何をしていても自由です。
「ここではそういう決まりだ」と言われるのなら、それに従う方がいい。そこから余計な“いざこざ”は生まれません。
ですが、「私の行っている、この儀式こそが唯一の真実。こうでなければならない。」とそこにこだわりが生まれているなら「戒禁取」です。
そういうことにこだわる人、またこだわりを強要する人は、真理という自由さの中で生きているのではなく、自我が作ったルール・習慣に縛られ、自らの意思で不自由を選択した人です。
…
さて、「預流果」によって消える煩悩は上記の3つのみです。
ですから、いくら「煩悩が消えた」と言っても、数ある煩悩のうち、「無知」に関する基本的な3つだけですので、まだまだ欲深な気質も、何かとカリカリイライラするような怒りっぽい性格もそのまま残っているんです。
とはいえ、「諸行無常(全ては変わり続ける)」「諸法無我(実際には“私”は実在しない)」というコトが理解できていますから、一種「諦め」に似た気持ちが生まれ、それまであった「執着」は、徐々に力を弱めていきます。
この「預流果」。
実は、特別な何かを行わなくても、到達できることがあります。
修行も瞑想も不要です。
ある日突然不意に訪れる様なこともありますし、しっかりとした指導者の説法によって迎えることも可能です。
最初の準備段階、「預流向」をすっ飛ばして、いきなり「ガツン!」と来ることもあるんです。
ただ…
何の予備知識も無いままに迎えてしまうと、結構うろたえてしまいますし、僕と同じように「預流向」をすっ飛ばして経験する場合には、ある独特な条件が必要な様です。
その独特な条件とは…
「絶望(地獄を見る)」という経験です。
まぁ、手っ取り早いと言えば手っ取り早いんですが、あまりにも痛すぎるし、リスクが高いので、この方法はオススメできません。
きちんと、順序を守って「預流向」から入られることをオススメいたします。
 ←こんなマニアックな話でも、ついてこられますか?(最近難し過ぎると妻からダメだしを食らってます。)
←こんなマニアックな話でも、ついてこられますか?(最近難し過ぎると妻からダメだしを食らってます。)
********************************************
さて、それではさっそく悟りの階梯を、順を追ってみていきましょう。
前回、解脱までの道のりは、4つの「向(目標)」と4つの「果(到達)」の合わせて8段階、というお話をしました。
・預流向(よるこう)
-----------------------------------
・預流果(よるか)
・一来向(いちらいこう)
・一来果(いちらいか)
・不還向(ふげんこう)
・不還果(ふげんか)
・阿羅漢向(あらかんこう)
・阿羅漢果(あらかんか)
前回は足し算的に「8段階」と説明してしまいましたが、「階梯(段階・レベル)」という意味で厳密に捉え直すと「4段階+1(預流向)」です。
と、申しますのも、一つでも「果(到達)」に辿り着くと、そこに次なる目標(向)が必然的についてくるからです。
【悟りの4段階+1】
準備段階:「預流向(よるこう)」
第一段階:「預流果(よるか)」と「一来向(いちらいこう)」のワンセット
第二段階:「一来果(いちらいか)」と「不還向(ふげんこう)」のワンセット
第三段階:「不還果(ふげんか)」と「阿羅漢向(あらかんこう)」のワンセット
最終段階:「阿羅漢果(あらかんか)」
という具合。
『悟り』とは、「預流果」を皮切りに、煩悩が順に消えていき、煩悩が消えた分だけ智慧(真理を見極める認識力)が現れていく現象のことを言います。
ですから、一口に「悟り」と言っても、そのレベルは人によって大きく異なります。
預流果、一来果、不還果と順に一つずつ段階を進み、阿羅漢果で完成します。
『自分を苦しめている諸悪の根源は、己の持つ煩悩。それ以外の理由はない。』
このことをハッキリと理解し、「よし、煩悩を消して、真理を見極めよう。」と、シッカリと真理に向かう姿勢のことを「預流向(よるこう)」と言います。
ちなみに「預流(よる)」とは、「完全な悟り(阿羅漢果)へ向かう聖なる流れに身を預ける」という意味だそうです。
その目標に向かうから「預流向」。
ここでは、まだ悟りを目指しているだけの状態ですので、まだ「悟り」とは言えません。(そういう意味も込めて、「預流向」と「預流果」の間に線を入れさせていただきました。)
では、その一線を越え、「預流果」を迎えるとどうなるのでしょうか。
以前、煩悩は数え切れないほどある、というお話をさせていただきました。
大きく分けると「貪欲(欲)」・「瞋恚(怒り)」・「愚痴(無知)」の3種類。
それに「慢(傲慢)」・「見(邪見)」・「疑(疑い)」を加えて『六大煩悩』。
それらを細分化していくと、有名な「108」に、それをさらに細分化すると数千、数万とキリがなくなっていきます。
その膨大な数の煩悩の中から、「預流果」で消える煩悩は…
1.有身見(うしんけん)
2.疑(ぎ)
3.戒禁取(かいごんじゅ)
…
…
…
え? それだけ?
…
はい。それだけです。
膨大な数の煩悩のうち、たった3つだけなんです。
無くなった煩悩はたった3つだけですから、まだまだ悩みも苦しみも膨大に残っています。
怒りもするし、泣きもするし、ヘマもしますし、凹みもします。
ですが、たった3つとはいえ、悟りを決定づける大切な3つです。
では、その3つを順に見ていきましょう。
1.有身見(うしんけん)
この煩悩は、「貪欲(欲)」でも「瞋恚(怒り)」でもありません。「愚痴(無知)」「見(邪見)」のカテゴリーに属する煩悩です。
これまで色々な形でお話してきた『「私」という独立した存在がある。』という錯覚のことを指す煩悩です。
ほんの一瞬でも、「無常」「無我」を知識としてではなく、体験として納得した時、「有身見」という邪見(因果の道理を無視する誤った考え方)は消え、「ああ、実際には“私”は実在しないんだ!」という理解と共に「無常・無我」という智慧が現れるんです。
そして、「有身見」が無くなると同時に、必然的に無くなる煩悩が2つあります。
それが「疑」と「戒禁取」です。この2つも「有身見」と同じく「愚痴(無知)」のカテゴリーの煩悩です。
2.疑(ぎ)
読んで字の如く「疑い」を意味します。
「疑」という煩悩が無くなるということは、「真理(諸行無常・諸法無我・因縁等)に対しての疑いが無くなる。」という意味です。
「有身見」が無くなったことによって、一瞬でも真理を「体験」しているため、当然それに対しての疑いがなくなります。
先日の「アハ体験」の例で言えば、「ああ!ホントにイエスが描かれていたんだ!」と納得できると、「アハ体験」以前にあった、「え~?こんなワケのわからない模様の中に、何が見えるって言うの?」という疑いは、絵が見えたと同時に消え去ります。
そんなニュアンスで捉えてください。
3.戒禁取(かいごんじゅ)
「戒禁取」は、しきたりや作法・儀式、無意味な修行や苦行等に対してこだわりをもってしまう煩悩(無知)のコトです。
槍のチンコ巻きとかは、まぁ、普段見ることはないにせよ、世の中には、ありがたい宗教的意義がありそうな修行や奇行が沢山あります。
ここ日本でも多く見受けられる「お祭り」や「火渡り」、「滝行」なんかも、この中に含まれます。
線香を何本立てろとか、戒名をどうしろこうしろとか、神社参拝やお墓参りの際は手を何回叩けとか、○○を供えろとか、日々「○○○○○」と唱えろとか、数珠は右手で持て、いや、左手だとか、そう言った「しきたり」や「儀式」にこだわるのも「戒禁取」です。
宗教的なコトだけではなく、事故に遭わないよう、家を出る時は靴は右足から履くとか、試合前にはユニフォームは右袖から着るとか、そういう、いわゆる「ジンクス」なども「戒禁取」です。
真理に触れるという経験をほんの一瞬でもすると、そういったあれこれは、エゴ(自我)が作った勝手な決まり事、文化以上の意味があるわけではないとわかるので、そういったものにこだわったり、ありがたがる気持ちがなくなります。
もちろん、それらの文化にも伝統や出来上がった背景などがありますから、無理に壊したり、蔑ろにするのも考え物です。
文化は、あくまで文化。ですから、人様に迷惑を掛けないのであれば、何をしていても自由です。
「ここではそういう決まりだ」と言われるのなら、それに従う方がいい。そこから余計な“いざこざ”は生まれません。
ですが、「私の行っている、この儀式こそが唯一の真実。こうでなければならない。」とそこにこだわりが生まれているなら「戒禁取」です。
そういうことにこだわる人、またこだわりを強要する人は、真理という自由さの中で生きているのではなく、自我が作ったルール・習慣に縛られ、自らの意思で不自由を選択した人です。
…
さて、「預流果」によって消える煩悩は上記の3つのみです。
ですから、いくら「煩悩が消えた」と言っても、数ある煩悩のうち、「無知」に関する基本的な3つだけですので、まだまだ欲深な気質も、何かとカリカリイライラするような怒りっぽい性格もそのまま残っているんです。
とはいえ、「諸行無常(全ては変わり続ける)」「諸法無我(実際には“私”は実在しない)」というコトが理解できていますから、一種「諦め」に似た気持ちが生まれ、それまであった「執着」は、徐々に力を弱めていきます。
この「預流果」。
実は、特別な何かを行わなくても、到達できることがあります。
修行も瞑想も不要です。
ある日突然不意に訪れる様なこともありますし、しっかりとした指導者の説法によって迎えることも可能です。
最初の準備段階、「預流向」をすっ飛ばして、いきなり「ガツン!」と来ることもあるんです。
ただ…
何の予備知識も無いままに迎えてしまうと、結構うろたえてしまいますし、僕と同じように「預流向」をすっ飛ばして経験する場合には、ある独特な条件が必要な様です。
その独特な条件とは…
「絶望(地獄を見る)」という経験です。
まぁ、手っ取り早いと言えば手っ取り早いんですが、あまりにも痛すぎるし、リスクが高いので、この方法はオススメできません。
きちんと、順序を守って「預流向」から入られることをオススメいたします。
 ←こんなマニアックな話でも、ついてこられますか?(最近難し過ぎると妻からダメだしを食らってます。)
←こんなマニアックな話でも、ついてこられますか?(最近難し過ぎると妻からダメだしを食らってます。)コメント ( 30 ) | Trackback ( )
| « 前ページ | 次ページ » |