人は死を前に最も敬虔な気持ちになると思う。
人は生まれながらにして差別を持って生まれる。社会的には貴賎貧富、老若男女、健康不健康などなどあって、生きるのが辛く、悩みは尽きないのが人生であるが、死は全ての者にとって平等である。
それが私が人間を観察するとき、語るときの最後の砦でもある。
さらに、人はどんな死に方をするかも予測できない。死が直ちにくる場合、比較的時間がある場合など様々である。
「死は時を選ばず、時を待たず、死は前からばかりではなく、ゆっくりと気づかぬように後ろからも迫ってくる」。
そのことは虚弱な幼少期を過ごした私の実感でもあり、私の人生観でもある。
人はその死に臨んで社会的な鎧を脱いで裸になる。何一つ持っていけない。だから死に臨んで発した言葉には裸の人間性が現れ、嘘や意地や誇張もない。その人の本当の姿が表現される。だから私は辞世の句など、賢者が最後に発した言葉が好きだ。
当ブログは恐れ多くも吉田兼好の徒然草から表題を借用している。
「徒然草のメインテーマ」は「死生観」である。所々に兼好は死生観をちらつかす。
その兼好法師の辞世の句は以下である。
◉かへり来ぬ 別れをきてもなげくかな 西にとかつは 祈るものから (兼好法師)
師は「徒然草』第七段で、「四十に足らぬほどにて死なんこそ、 めやすかるべけれ」と述べている。 人生五十年よりさらに短い四十歳が目標だった、という。死亡時推定年齢は七十歳であるが、はっきりとしない。彼が生きた鎌倉時代、庶民が四十歳まで生きるのは容易ではなかった。軽い風邪でもあっけなく命を落とし、至る所に餓死と病死のむくろが転がっていた。鴨長明の方丈記の中にこの辺の事情が詳しく描写されている。
死は日常の中に当たり前のようにあった。だから、兼好法師を貫いていたのは、世捨て人に共通なのであるが、無常観だった。
だから、「生きているということを、日々楽しまないでよいものか・・・」と述べ「死を憎まば、生を愛すべし。存命の喜び、日々に楽しまざらんや(第九十三段)」と言っている。「一瞬一瞬、人は生きている。その一瞬、一瞬を、二度と帰らぬものとして楽しみ充実させるのだ」と。
このことは、以下の句にも共通する。
◉おもしろきこともなき世をおもしろく (高杉晋作)
人は誰でも、いつかは死が訪れることは知っている。だが、その死が、予測していない時にときに、突然やってくる。
◉つひに行く 道とはかねて聞しかど 昨日今日とは 思はざりしを (在原業平)
◉つひに行く 道とはかねて聞しかど 昨日今日とは 思はざりしを (在原業平)
もう一つ。
◉風さそふ 花よりもなほ我はまた 春の名残を いかにとやせん ( 浅野長矩)
これは私が最も気に入っている句。江戸城松の廊下抜刀し、即日切腹となった。風に誘われて散る桜は名残り惜しいが、それよりも、切腹して散っていく自分が残念でならない・・・。
切腹の命が下って数時間、いろいろ考えるべきことがあっただろうがその間に作り上げたなんて信じられない。

















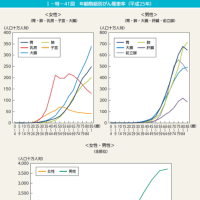


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます