いま、私は終活の最中である。今まで収集した書籍や音源、庭木なども対象に身辺整理を進めている。終活の対象はまず物品が対象になるが、自分の死に方を考えながら残りの生き方をじっくり考えることも終活の一つのありようと考える。
最近、私は人の死に様を考えるときに自殺、自死の意義について勉強を始めていて、内外の文献等を集めている。私は決して自殺、自死を礼賛するものではないが、全否定するものでもない。私にとっての可能性?勿論ゼロとは言い切れない。
私は「いのちは自分のもの、死ぬ権利もある」と思っている。安楽死を含め「死に方を選べる社会が到来すればいい」と思う。わが国では社会的にコンセンサスは得られないだろう。高齢化社会、多死社会を迎えやっと生きる事の意義が問われ始めてきたレベルである。
一方、生物学者の池田清彦早大教授は、「いのちは自分の所有物ではない。だから、死ぬ権利はない」と述べている。
---------------------------------------------------------------------------
わが国には自殺自死の歴史が積み重ねられている。出版物も多い。
まだ途中までしか読んでいないが、モーリス・パンゲ著「自死の日本史」には以下の例を引いて日本人の精神論を展開している。
■ 安徳天皇を抱いて海に身を投げた二位尼 ■ 鎌倉幕府滅亡時の6千人余の武士の切腹 ■ 千利休 ■ 浅野内匠頭 ■ 大石内蔵助と四十七士 ■ 西郷隆盛 ■ 乃木希典 ■ 芥川龍之介 ■ 太宰治 ■ 川端康成 ■ 特攻隊の心情 ■ 三島由紀夫
この著作は読み進めるのが楽しみである。
---------------------------------------------------------------------------
資料検索の過程で「須原一秀」という哲学者を知った。
氏は65歳で神社で頸動脈を切ったあと首を吊って自死を遂げた、とされている。
著作等を通じ自死を礼賛し、そのとおり死んだという点はすごいと思う。 その著作を取り寄せて読んでみた。
須原氏は、本著作の中で「死の受容」について考察した精神科医、キューブラー・ロスの例を挙げ、人は老化すれば変わりうるので、そうなる前に対応せよ、と述べる。
また、割腹の三島由紀夫、飛び降りの伊丹十三、刑死したソクラテスの例を挙げ仔細に検証している。氏はこの三者は迫り来る老醜への嫌悪から死に向かった、と断言する。
須原氏は「中高年の男女よ、心身の衰えを自覚したら、躊躇せずに自殺せよ」と呼びかけており、自身がどう考えていたかわからないが、私は須原氏が挙げた3人が、迫り来る老醜への嫌悪から自死願望を持っていたとは到底思えない。3人には死ぬべき別な事情があったのだ、と思う。
では、須原氏自身は何で死んだのか。本当に老醜を嫌っていたのか、哲学者が加齢の意義をどう考えていたのか?
頸動脈を切って首吊り自殺した、とされるが動脈を切ってから首吊りができたのか?とも思う。「老醜」、「自殺」について考察しすぎて自らを心理的に追い込んだのかも知れない。しかし、実際に自殺という行動にうつした哲学者の思考過程は、論旨に乱暴な部分は多々あるものの、一つの考え方として容認出来るし、自ら実践したという点でひたむきさ、迫力がある。
しかしながら、私の立場から言えば、加齢による精神・身体の変化は不幸なことではなく、そのことを味わう事に人生の意義があり、楽しみだ、とおもう。従って、老醜を嫌悪して自ら元気なうちに命を絶つという行動には直接的には結びつかない、と思うから須原氏には同意できない。
少なくとも私たちは、死を思う行為から遠ざかるべきではない。そのことを教えてくれる著作である。
最近、私は人の死に様を考えるときに自殺、自死の意義について勉強を始めていて、内外の文献等を集めている。私は決して自殺、自死を礼賛するものではないが、全否定するものでもない。私にとっての可能性?勿論ゼロとは言い切れない。
私は「いのちは自分のもの、死ぬ権利もある」と思っている。安楽死を含め「死に方を選べる社会が到来すればいい」と思う。わが国では社会的にコンセンサスは得られないだろう。高齢化社会、多死社会を迎えやっと生きる事の意義が問われ始めてきたレベルである。
一方、生物学者の池田清彦早大教授は、「いのちは自分の所有物ではない。だから、死ぬ権利はない」と述べている。
---------------------------------------------------------------------------
わが国には自殺自死の歴史が積み重ねられている。出版物も多い。
まだ途中までしか読んでいないが、モーリス・パンゲ著「自死の日本史」には以下の例を引いて日本人の精神論を展開している。
■ 安徳天皇を抱いて海に身を投げた二位尼 ■ 鎌倉幕府滅亡時の6千人余の武士の切腹 ■ 千利休 ■ 浅野内匠頭 ■ 大石内蔵助と四十七士 ■ 西郷隆盛 ■ 乃木希典 ■ 芥川龍之介 ■ 太宰治 ■ 川端康成 ■ 特攻隊の心情 ■ 三島由紀夫
この著作は読み進めるのが楽しみである。
---------------------------------------------------------------------------
資料検索の過程で「須原一秀」という哲学者を知った。
氏は65歳で神社で頸動脈を切ったあと首を吊って自死を遂げた、とされている。
著作等を通じ自死を礼賛し、そのとおり死んだという点はすごいと思う。 その著作を取り寄せて読んでみた。
須原氏は、本著作の中で「死の受容」について考察した精神科医、キューブラー・ロスの例を挙げ、人は老化すれば変わりうるので、そうなる前に対応せよ、と述べる。
また、割腹の三島由紀夫、飛び降りの伊丹十三、刑死したソクラテスの例を挙げ仔細に検証している。氏はこの三者は迫り来る老醜への嫌悪から死に向かった、と断言する。
須原氏は「中高年の男女よ、心身の衰えを自覚したら、躊躇せずに自殺せよ」と呼びかけており、自身がどう考えていたかわからないが、私は須原氏が挙げた3人が、迫り来る老醜への嫌悪から自死願望を持っていたとは到底思えない。3人には死ぬべき別な事情があったのだ、と思う。
では、須原氏自身は何で死んだのか。本当に老醜を嫌っていたのか、哲学者が加齢の意義をどう考えていたのか?
頸動脈を切って首吊り自殺した、とされるが動脈を切ってから首吊りができたのか?とも思う。「老醜」、「自殺」について考察しすぎて自らを心理的に追い込んだのかも知れない。しかし、実際に自殺という行動にうつした哲学者の思考過程は、論旨に乱暴な部分は多々あるものの、一つの考え方として容認出来るし、自ら実践したという点でひたむきさ、迫力がある。
しかしながら、私の立場から言えば、加齢による精神・身体の変化は不幸なことではなく、そのことを味わう事に人生の意義があり、楽しみだ、とおもう。従って、老醜を嫌悪して自ら元気なうちに命を絶つという行動には直接的には結びつかない、と思うから須原氏には同意できない。
少なくとも私たちは、死を思う行為から遠ざかるべきではない。そのことを教えてくれる著作である。

















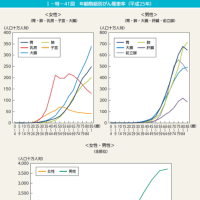


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます