従来、知るのが不可能であったことが、科学の進歩で可能になって来た。
結果を知ったらどうするか、難しい決断が迫られるようになった。検査を受けるか否かは自由だから自己責任と言えばそれまでだが、そのためには自分でも判断できるほどの正確な知識と決断力が必要である。
新型出生前診断は、無侵襲的出生前遺伝学的検査とも呼ばれるが、そのような検査の一つである。妊婦の血液中には、微置だが遊離のDNAが流れている。妊娠中は、自分のDNAだけでなく、胎児のDNAもある程度混じっている。妊婦の血漿中にある遊離DNAのから胎児の遺伝子を解析し、胎児の染色体や遺伝子を調べる検査である。確定診断には侵襲的な羊水検査が必要となる。
日本国内では2013年4月より、日本医学会の認定・登録委員会により認定された施設で検査が始まった。現在は71施設で行われている。対象者は超音波検査などで胎児の染色体異常の可能性が示唆された妊婦や高齢妊婦とされている。指針案の段階では35歳以上の妊婦と年齢が定義されていたが、その後年齢条項は削除された。
費用は健康保険の適応がなく自費扱いとなり、日本では20万円程度の負担となる。
一般的に、高齢出産では胎児異常が増えていく。晩婚化、不妊治療の増加を背景に、新出生前診断のニーズが高まっている。受診者が3年間で3万入超に上ることが各地の病院でつくる研究チームの集計で分かった。
おなかの子の状態を知りたいというのは、多くの夫婦の願いであろう。だが、異常が分かった場合には極めて重い選択に直面する。受診し、染色体異常の疑いで羊水検査に進み、異常が確定したうちの94%、394人が人工妊娠中絶を選択したそうだ。随分中絶例が多いように思われるが、異常があれば中絶と考えて検査を受けているだろうから、高率になるのは理解できる。一方、異常の可能性が高いことが告げられても出産を決意した6%の人たちは、どれだけ悩んだことだろうか。
検査の偽陽性が10%あるという。こんな中「産むか、否か」の是非を他人が問うのは酷だ、と思う。「産まない選択をした夫婦のことを、誰が責めることができるか」、私は言えない、と思う。
「産む」という選択をした家族には、多大な自助努力が求められるのが現状である。生まれてくる子供、その両親・家族を継続的に支える社会の仕組みが十分とは言えない。検査する病院に適切なカウンセリング体制があることが実施要件の一つであるが、社会のバックアップ体制はそれを裏付けてはいない。
実に重い選択が課せられる。
結果を知ったらどうするか、難しい決断が迫られるようになった。検査を受けるか否かは自由だから自己責任と言えばそれまでだが、そのためには自分でも判断できるほどの正確な知識と決断力が必要である。
新型出生前診断は、無侵襲的出生前遺伝学的検査とも呼ばれるが、そのような検査の一つである。妊婦の血液中には、微置だが遊離のDNAが流れている。妊娠中は、自分のDNAだけでなく、胎児のDNAもある程度混じっている。妊婦の血漿中にある遊離DNAのから胎児の遺伝子を解析し、胎児の染色体や遺伝子を調べる検査である。確定診断には侵襲的な羊水検査が必要となる。
日本国内では2013年4月より、日本医学会の認定・登録委員会により認定された施設で検査が始まった。現在は71施設で行われている。対象者は超音波検査などで胎児の染色体異常の可能性が示唆された妊婦や高齢妊婦とされている。指針案の段階では35歳以上の妊婦と年齢が定義されていたが、その後年齢条項は削除された。
費用は健康保険の適応がなく自費扱いとなり、日本では20万円程度の負担となる。
一般的に、高齢出産では胎児異常が増えていく。晩婚化、不妊治療の増加を背景に、新出生前診断のニーズが高まっている。受診者が3年間で3万入超に上ることが各地の病院でつくる研究チームの集計で分かった。
おなかの子の状態を知りたいというのは、多くの夫婦の願いであろう。だが、異常が分かった場合には極めて重い選択に直面する。受診し、染色体異常の疑いで羊水検査に進み、異常が確定したうちの94%、394人が人工妊娠中絶を選択したそうだ。随分中絶例が多いように思われるが、異常があれば中絶と考えて検査を受けているだろうから、高率になるのは理解できる。一方、異常の可能性が高いことが告げられても出産を決意した6%の人たちは、どれだけ悩んだことだろうか。
検査の偽陽性が10%あるという。こんな中「産むか、否か」の是非を他人が問うのは酷だ、と思う。「産まない選択をした夫婦のことを、誰が責めることができるか」、私は言えない、と思う。
「産む」という選択をした家族には、多大な自助努力が求められるのが現状である。生まれてくる子供、その両親・家族を継続的に支える社会の仕組みが十分とは言えない。検査する病院に適切なカウンセリング体制があることが実施要件の一つであるが、社会のバックアップ体制はそれを裏付けてはいない。
実に重い選択が課せられる。

















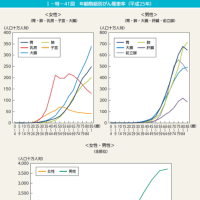


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます