つい先日、1月10日、地方紙である秋田魁新聞、シニア川柳投稿欄に「老害の 人の本読み フテ腐る」が掲載された。おそらく内館牧子氏の著作を読んで、自らの老害に気付き、著者の鋭い指摘に不快な気分を味わったのであろう。
「老害の人」は内館牧子氏の著作の題名である。
氏の高齢者を扱った作品に「終わった人」内館牧子著 「終わった人」 講談社 (2015年9月) 単行本 378ページ、「すぐ死ぬんだから」 、「今度生まれたら」などがある。
内容は、実にリアルかつユーモラス。 高齢者の前向きな姿、周囲の迷惑感を存分に表現されており、私は楽しむことができた。
私も日常から老害の被害者である。同時に私自身も老害をふり撒く加害者になっていないかとの恐れを抱いている。いや、私は絶対に老害加害者ではあり得ない、とも思っている。
高齢者に何度も同じ話を聞かされて閉口するのは誰にでもある経験だろう。普段、高齢の患者さんの診療に携わる私は、「病気の話より昔話に付き合う時間の方が長い」という悩みを抱える。もっと医者らしく付き合ってほしいものだ、との悩みが若い時からあった。最近は「どうせ、先がみじかい老齢医師だから、まあイッカ・・」と諦めムードである。
そのような老害関連の感情に切り込んで小説に仕立てた著者の目のつけどころは、誠に鋭い。
本作の主人公は古いタイプの元会社社長85歳であるが、自らの会社の若いスタッフに人生を語りたくて仕方がない。会社に出かけては社員相手に説教をする。後継ぎ世代の娘と婿養子の現社長はイライラしながらも無視できず、葛藤の日々を送る。
しかも、主人公は自宅にも俳句自慢や絵画自慢、遅刻常習者など、さまざまな「老害」仲間を連れてくる。会社での主人公の説教や、自宅の中でも家族内の会話が延々と語られるが、家の中で最も主人公を理解しているのは18歳の男の孫である。
これから読む方もあろうから、内容はこの程度にしておく。
私は読了して、爽快な気持ちになった。
高齢者の姿、特徴を存分に確認し、溜飲を下げた。
物語中の「老害の人」たちが80歳前後であるのに対し、困惑する娘世代は60歳前後。つまり、「老害を振りまく老人の話に、プレ老人がイラつく」という構図である。そう考えれば、無邪気でパワフルな「老害」を振りまく方々の姿は次の自分の姿である。プレ老人世代の抱く焦燥感は、将来の自分自身への恐れと戒めからくるものに違いない。
どんな人も若いままではいられない。体だけでな脳細胞だって老化する。「子供笑うな来た道じゃ、年寄り笑うな行く道じゃ」はけだし名言である。
次の世代の人は「不快だが将来の自分の姿かもしれない。先が長いわけでなし、多少のことは大目に見よう」と言いたくなる。若い世代の人は「言った後の人間関係の不愉快さ」を味わいたくなくてクレームはつけられない。
かくして、老害者達は表立っては誰からも非難されず、野放し状態になる。だから老害者達は体力知力が衰えるまで実にイキイキしている。
私は超高齢者の活躍が前面に出るのを是としない。
社会を見る限りにおいては、日本の社会は時代遅れの旧体制、男性社会、老人社会の状況であり、不快に思っている。すなわち男性害・老害の社会である。しつこいが、私はそれを是、としない。
私は、老害の人にはなるまいと組織の内規に沿ってスッパリ引退した。現役引退後は自身を恥じて言を慎み社会的にはほぼ隠蔽生活に入った。
こんなことを言うのも老害にあたるか??注意しなければ・・・。

















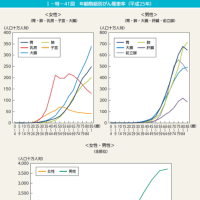


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます