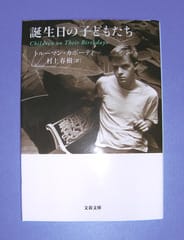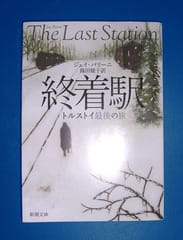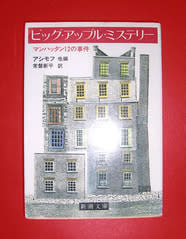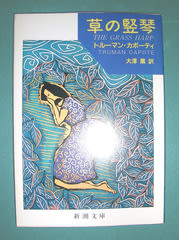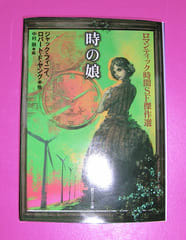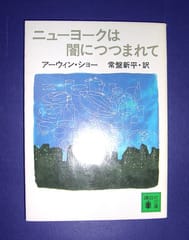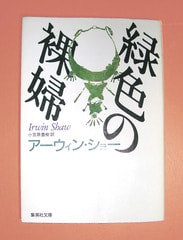GOD'S LITTLE ACRE 

1933年 アースキン・コールドウェル
エミール・ゾラの『大地』のような、剥き出しの欲望や金への渇望が
痛々しいほどに激しく描かれているのかと思いきや…
なんつーか、少しは理性で押さえんかい! と怒り出したくなる内容でしたね
『大地』と決定的に違うと(あくまで私が)思うのは
そこに漂う “ どうしようもない感じ ” の強さです。
『大地』では、現在の生活のため、子どもの将来のため、生産量の落ちた土地から
少しでも多くの収入を得るために、家族で激しい土地の奪い合いが展開されます。
そのためには嫁の妹にだって手をだして言いなりにさせてやる! という
荒々しいやり口だって躊躇せず選びます。
なんだけど『神の小さな土地』ではね…
金鉱掘りに全てをかけて、農園を食いつぶしてしまった父を持つウォールデン父子と
その家族たちが主人公です。
父タイ・タイは15年間一家の土地という土地で穴を掘り続けています。
バックとショウはそんな父親の手伝いに明け暮れ、これまた作物を作りませんでした。
バックの妻グリゼルダはものすごい美女で、タイ・タイの自慢の嫁です。
次女ダーリング・ジルは男好きで悪い噂が絶えません。
長男ジム・レスリーは金持ちで病気持ちの女と結婚し、貧しい実家には近づこうとしません。
長女ロザモンドは良い娘ですが、結婚して夫一筋です。
その夫ウィルは工場で働く職人ですが1年以上ストライキを続けています。
で、内容はものすごくはしょるんだけど…
タイ・タイはダーリング・ジルに求婚しているスウィントの情報のおかげで
今度こそ金鉱が見つかると思って、ロザモンドとウィルを手伝いに呼び寄せようと考えます。
冬が越せないので、ジム・レスリーにお金を借りようとも考えます。
それでウィルもジム・レスリーも、バックの妻グリゼルダに完全に参ってしまうわけですね。
自分に妻がいてもグリゼルダに夫がいてもおかまいなし、
「手に入れてやる!」と公言して憚らないばかりか
ウィルにいたっては嫁の前で彼女を押し倒しちゃう始末。
ダーリング・ジルは、姉ロザモンドの夫ウィルの男前ぶりにやられてしまって
姉が目を離した隙にベッドにもぐりこんじゃうし
押し倒されちゃったグリゼルダも「本当に探していた男はウィルだったわ」てな感じで
夫のことも忘れてスト破りについていく有様…
妻ロザモンドは「それでこそウィル!」と惚れ直しちゃうのよ、どう思う?
ジム・レスリーはグリゼルダを奪いに銃を持って実家に乱入する…て
もう無茶苦茶でしょー
問題は、彼らのどうしようもない衝動と本能のみの行動が理解できるか、
これはそうしちゃっても仕方が無いと思えるか、なんですが
わたしゃさっぱりわからんよ。
百歩譲ってどうしても人の嫁を手に入れたいとしましょうよ。
でもなにも “ 直ちに ” じゃなくたっていいのでは? 皆が寝静まるまで待ってみませんか?
もちろん他にもテーマはあるのよ、金鉱のこととか、また工場で働きたいとかさ。
でもそこにもあまりギリギリの崖っぷち感がないんですよね。
物語のラストでは、兄弟・義理の兄弟入り乱れての惨劇を招くのですが
哀しさも力強さも何も感じませんでした。
ドリフとか吉本新喜劇で最後にドタバタドタ~って終わるじゃない?
むしろあんな情景が頭に浮かんじゃいましたよ。
発売時センセーションを巻き起こしたと言われるこの物語…
Weblioによれば “ センセーショナル ” の語意には
あざとい、えげつない、興味本位の、などの意味があるみたいです。
この『神の小さな土地』はうっすらとそんな感じを受けた本でした。
欲望のはけ口、やり場の無い怒り、みなぎる力の象徴などなどの吐露を
すべてセックスでかたずけちゃってるような気がしてなりません。
一番手っ取り早いと言ってしまえばそれまでなんだが…


1933年 アースキン・コールドウェル
エミール・ゾラの『大地』のような、剥き出しの欲望や金への渇望が
痛々しいほどに激しく描かれているのかと思いきや…
なんつーか、少しは理性で押さえんかい! と怒り出したくなる内容でしたね

『大地』と決定的に違うと(あくまで私が)思うのは
そこに漂う “ どうしようもない感じ ” の強さです。
『大地』では、現在の生活のため、子どもの将来のため、生産量の落ちた土地から
少しでも多くの収入を得るために、家族で激しい土地の奪い合いが展開されます。
そのためには嫁の妹にだって手をだして言いなりにさせてやる! という
荒々しいやり口だって躊躇せず選びます。
なんだけど『神の小さな土地』ではね…
金鉱掘りに全てをかけて、農園を食いつぶしてしまった父を持つウォールデン父子と
その家族たちが主人公です。
父タイ・タイは15年間一家の土地という土地で穴を掘り続けています。
バックとショウはそんな父親の手伝いに明け暮れ、これまた作物を作りませんでした。
バックの妻グリゼルダはものすごい美女で、タイ・タイの自慢の嫁です。
次女ダーリング・ジルは男好きで悪い噂が絶えません。
長男ジム・レスリーは金持ちで病気持ちの女と結婚し、貧しい実家には近づこうとしません。
長女ロザモンドは良い娘ですが、結婚して夫一筋です。
その夫ウィルは工場で働く職人ですが1年以上ストライキを続けています。
で、内容はものすごくはしょるんだけど…
タイ・タイはダーリング・ジルに求婚しているスウィントの情報のおかげで
今度こそ金鉱が見つかると思って、ロザモンドとウィルを手伝いに呼び寄せようと考えます。
冬が越せないので、ジム・レスリーにお金を借りようとも考えます。
それでウィルもジム・レスリーも、バックの妻グリゼルダに完全に参ってしまうわけですね。
自分に妻がいてもグリゼルダに夫がいてもおかまいなし、
「手に入れてやる!」と公言して憚らないばかりか
ウィルにいたっては嫁の前で彼女を押し倒しちゃう始末。
ダーリング・ジルは、姉ロザモンドの夫ウィルの男前ぶりにやられてしまって
姉が目を離した隙にベッドにもぐりこんじゃうし
押し倒されちゃったグリゼルダも「本当に探していた男はウィルだったわ」てな感じで
夫のことも忘れてスト破りについていく有様…
妻ロザモンドは「それでこそウィル!」と惚れ直しちゃうのよ、どう思う?
ジム・レスリーはグリゼルダを奪いに銃を持って実家に乱入する…て
もう無茶苦茶でしょー

問題は、彼らのどうしようもない衝動と本能のみの行動が理解できるか、
これはそうしちゃっても仕方が無いと思えるか、なんですが
わたしゃさっぱりわからんよ。
百歩譲ってどうしても人の嫁を手に入れたいとしましょうよ。
でもなにも “ 直ちに ” じゃなくたっていいのでは? 皆が寝静まるまで待ってみませんか?
もちろん他にもテーマはあるのよ、金鉱のこととか、また工場で働きたいとかさ。
でもそこにもあまりギリギリの崖っぷち感がないんですよね。
物語のラストでは、兄弟・義理の兄弟入り乱れての惨劇を招くのですが
哀しさも力強さも何も感じませんでした。
ドリフとか吉本新喜劇で最後にドタバタドタ~って終わるじゃない?
むしろあんな情景が頭に浮かんじゃいましたよ。
発売時センセーションを巻き起こしたと言われるこの物語…
Weblioによれば “ センセーショナル ” の語意には
あざとい、えげつない、興味本位の、などの意味があるみたいです。
この『神の小さな土地』はうっすらとそんな感じを受けた本でした。
欲望のはけ口、やり場の無い怒り、みなぎる力の象徴などなどの吐露を
すべてセックスでかたずけちゃってるような気がしてなりません。
一番手っ取り早いと言ってしまえばそれまでなんだが…