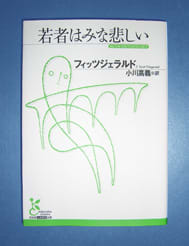PILGRIMS 

1997年 エリザベス・ギルバート
読んでいる時には「女性が書いているわりには男っぽいなぁ」と思っていましたが
読後はやはり女性らしい物語の数々だったと感じています。
舞台が、アメリカの、どちらかというと田舎、あるいはハイウェイ沿いに思える話が多くて
つい、テンガロンハットとかブーツの男性が屯する酒場とか
二の腕逞しい大型トレーラーの運転手が座って大きなホットドッグをほおばるカフェを
勝手に想像しながら読んでいたのが、男らしく思えた要因かもしれません。
表題『巡礼者たち』は農場主に雇われた19歳の少女とその家の息子の
仲間意識なのか恋なのか…という微妙な心情を描いた秀作ですが
それはおいといて、好きだったお話しをいくつか紹介します。
『トール・フォークス(Tall Falks)』
エレンの店トール・フォークスと、別居中の夫トミーの店ラディ・ナット・ハウスは
道をはさんで営業していて、常連たちが行き来し、お互いに繁盛していました。
しかしトミーの店は潰れ、トップレスバーがオープンしました。
エレンが甥と偵察に行くと、常連たちが皆そのバーに勢揃いしていました。
たぶん小さな町なんだと思うんですが、以前従業員だった女性も向かいに移り
常連も向かいに取られ…なんてことが続けばエレンの店も将来どうなるか…
物語の中ではエレンは落ち着いていますが、ちょっとした言動に焦りが見える気がします。
しかし、トップレスだからって長年通った店に背を向けるとは…男の人って…
『デニー・ブラウンの知らなかったこと
(The Many Things That Denny Brown Did Not Know)』
15歳のデニー・ブラウンの両親は看護士でした。
その夏、デニーはなぜかかつていじめられていたラッセルと親しくなり
ラッセルの姉ポーレットとこっそり恋人同士になりました。
ある日ポーレットが水疱瘡にかかり、デニーは父親譲りの看護をします。
いじめを克服して友人になる少年たち、父親の仕事を見直す息子…
テーマから見ればいい話なんですけど、道徳番組的な展開はなく
主人公が夏のけだるさに流されているうちに大人になりました、という感じです。
“ 人生の岐路 ” と言いますが、気付かぬ内に岐路を越えていたってこともありますよね。
『最高の妻(The Finest Wife)』
惚れっぽくて恋愛を繰り返したローズは一番好きな男性と結婚し43年後に死別しました。
70歳近くなっていたローズは幼稚園バスの運転手になりました。
ある日、子どもたちが表れないかわりに老人たちが次々バスに乗って来ます。
彼らは皆ローズのかつての恋人でした。
小説では、恋愛遍歴の多い女性はなにかと不幸なラストを迎えることが多いのですが
この物語のラストはすごくハッピーに思えました。 こんな最後を迎えたい…
私はまわりがなんと言おうと、本人が「幸せだ」と思える人生が送れればいいと思うのよね。
ブログで女性の歴史を書いてますが、後の世で悪女だとかおばかさんだとか言われようと
生きているうちに幸せな思いをした人はそれでいいと思うのですよ。
そうですねぇ…
作者が特定のパーソナリティーに肩入れしていないような気がします。
確かに面白い短篇集には様々な人物やシチュエーションが登場するものですが
エリザベス・ギルバートの場合は徹底しているような気がします。
扱っているテーマには、社会的な問題や世間をにぎわす話題はほとんんどありません。
主人公のまわりで起きていることだけを、ほぼ時系列で書いています。
執着心がないのか、公平なのか、利己的なのか、平和主義なのか…
とにかく、雑念無く話の世界に入り込むことができました。
時系列だし文章は読み易いのですが、だからといって簡単な物語ではありません。
主人公の気持がはっきりしないまま話が進行し、成り行きっぽくラストを迎え
そのラストもすっきりしない…というスタイルで
ちゃんとした起承転結が存在しないと嫌な人には向かないかもしれません。
好き嫌いはあるかもね… 私は今のところ好きと嫌いのど真ん中にいる状態です。


1997年 エリザベス・ギルバート
読んでいる時には「女性が書いているわりには男っぽいなぁ」と思っていましたが
読後はやはり女性らしい物語の数々だったと感じています。
舞台が、アメリカの、どちらかというと田舎、あるいはハイウェイ沿いに思える話が多くて
つい、テンガロンハットとかブーツの男性が屯する酒場とか
二の腕逞しい大型トレーラーの運転手が座って大きなホットドッグをほおばるカフェを
勝手に想像しながら読んでいたのが、男らしく思えた要因かもしれません。
表題『巡礼者たち』は農場主に雇われた19歳の少女とその家の息子の
仲間意識なのか恋なのか…という微妙な心情を描いた秀作ですが
それはおいといて、好きだったお話しをいくつか紹介します。
『トール・フォークス(Tall Falks)』

エレンの店トール・フォークスと、別居中の夫トミーの店ラディ・ナット・ハウスは
道をはさんで営業していて、常連たちが行き来し、お互いに繁盛していました。
しかしトミーの店は潰れ、トップレスバーがオープンしました。
エレンが甥と偵察に行くと、常連たちが皆そのバーに勢揃いしていました。
たぶん小さな町なんだと思うんですが、以前従業員だった女性も向かいに移り
常連も向かいに取られ…なんてことが続けばエレンの店も将来どうなるか…
物語の中ではエレンは落ち着いていますが、ちょっとした言動に焦りが見える気がします。
しかし、トップレスだからって長年通った店に背を向けるとは…男の人って…
『デニー・ブラウンの知らなかったこと
(The Many Things That Denny Brown Did Not Know)』

15歳のデニー・ブラウンの両親は看護士でした。
その夏、デニーはなぜかかつていじめられていたラッセルと親しくなり
ラッセルの姉ポーレットとこっそり恋人同士になりました。
ある日ポーレットが水疱瘡にかかり、デニーは父親譲りの看護をします。
いじめを克服して友人になる少年たち、父親の仕事を見直す息子…
テーマから見ればいい話なんですけど、道徳番組的な展開はなく
主人公が夏のけだるさに流されているうちに大人になりました、という感じです。
“ 人生の岐路 ” と言いますが、気付かぬ内に岐路を越えていたってこともありますよね。
『最高の妻(The Finest Wife)』

惚れっぽくて恋愛を繰り返したローズは一番好きな男性と結婚し43年後に死別しました。
70歳近くなっていたローズは幼稚園バスの運転手になりました。
ある日、子どもたちが表れないかわりに老人たちが次々バスに乗って来ます。
彼らは皆ローズのかつての恋人でした。
小説では、恋愛遍歴の多い女性はなにかと不幸なラストを迎えることが多いのですが
この物語のラストはすごくハッピーに思えました。 こんな最後を迎えたい…
私はまわりがなんと言おうと、本人が「幸せだ」と思える人生が送れればいいと思うのよね。
ブログで女性の歴史を書いてますが、後の世で悪女だとかおばかさんだとか言われようと
生きているうちに幸せな思いをした人はそれでいいと思うのですよ。
そうですねぇ…
作者が特定のパーソナリティーに肩入れしていないような気がします。
確かに面白い短篇集には様々な人物やシチュエーションが登場するものですが
エリザベス・ギルバートの場合は徹底しているような気がします。
扱っているテーマには、社会的な問題や世間をにぎわす話題はほとんんどありません。
主人公のまわりで起きていることだけを、ほぼ時系列で書いています。
執着心がないのか、公平なのか、利己的なのか、平和主義なのか…
とにかく、雑念無く話の世界に入り込むことができました。
時系列だし文章は読み易いのですが、だからといって簡単な物語ではありません。
主人公の気持がはっきりしないまま話が進行し、成り行きっぽくラストを迎え
そのラストもすっきりしない…というスタイルで
ちゃんとした起承転結が存在しないと嫌な人には向かないかもしれません。
好き嫌いはあるかもね… 私は今のところ好きと嫌いのど真ん中にいる状態です。










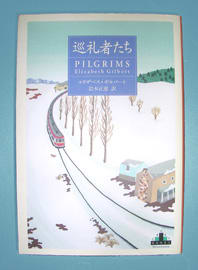
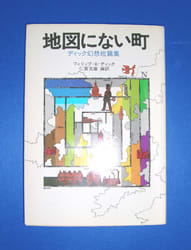


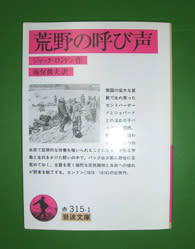

 リードがついてるからまだいいようなものの…
リードがついてるからまだいいようなものの…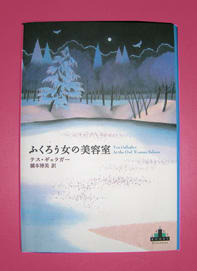

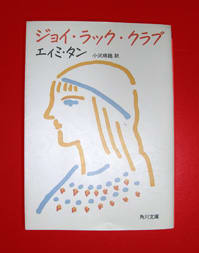

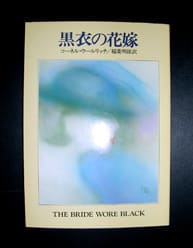





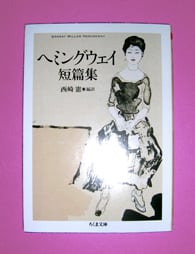





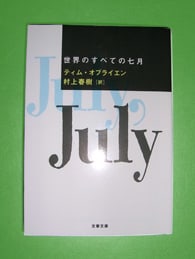

 難しいわぁ…
難しいわぁ… 余談です
余談です 印は作品の善し悪しではなくて、私の好き度メモみたいなものなんですが
印は作品の善し悪しではなくて、私の好き度メモみたいなものなんですが