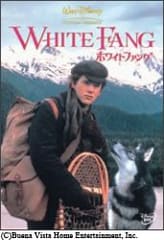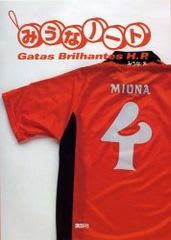ネットの世界にはいろいろふざけたサイトがあるもので、たとえば”世界の三面記事”なんてブログは、なかなか秀逸と言いますかしょうもないといいますか、いやまいったね、と言いましょうか。そのムチャクチャさに徹した姿勢、まことに端倪すべからざるものがあります。
要するに”東スポ”ですな。世界のあちこちから到底信じられないようなニュースを探してきてはブログにアップしている。
集まった記事のタイトルだけを記しても、”スピード違反のトレーラーを止めてみたら、荷台から20個以上の人間の生首が ”とか、”病院の霊安室で92才老女の遺体と屍姦した24才検査技師 ”とか、”ジェルキング -- ペニスの長さ・外周を3 - 8cm 大きくする体操”とか、まったくこんなアホな話を良く思いつくものだ、そして良く集めたものだと呆れるばかり。
最近の”ヒット作”は、”ボルネオ島でオランウータンが人間相手の売春を強要されている”ってのなんですが。
まあ、いうまでもなくオランウータンと性交したがる男なんて、そうはいない訳で、こんな話をまともに信じる方がおかしいんですが。しかも”オランウータン売春”が好評で客が引きもきらず、なんて内容なんだから、ますます疑わしい。
ところがこれ、なんと某ソーシャルネットワーキングサービス内の某コミュニティで、この話をメンバー全員、本気に取ってしまったんですな。
話が本物かどうかなんて検証も省いてメンバー各氏、このアホ・ストーリーをいきなり全面的に信じてしまい、感傷モードやら義憤モードに入って、「胸が痛いです」「ボニー、ごめんね」とかクソ甘いコメントを次々に書き連ねている。あ、ボニーってのは問題のオランウータンの名です。
世の中には疑う事を知らない人っているんですねえ。あそこのサイトに載ってる他のニュースも全部本気で読んでるんでしょうか、あのヒトビトは。 信じてるんでしょうねえ、オランウータンの話をあれだけ簡単に信じ込んでしまったくらいですから。
大丈夫か、訳の分からないインチキ宗教とかサギとかにそのうち引っかからないようにしろよ・・・
PS.
以上が昨日までの話。
今夜、そのコミュを覗いてみたら、オランウータンに関するトピは削除されてました。理由説明は無し。
メンバーが現実を見る理性を獲得し、そのトピを恥じたがゆえの処置であれば少しは救われるけど・・・どうなんでしょうねえ。
下に、”ブログ・世界の三面記事”掲載の問題の記事を全文引用します。
~~~~~
○売春宿で客を取る裸のオランウータン
<インドネシア発> 「ボルネオ・オランウータン・サバイバル・ファウンデーション」*に保護されているポニーは、数奇な運命を辿ってきたオランウータンである。実は、彼女はここに連れて来られる前まで、売春宿で人間を相手に体を売っていたのだ。
(*1999年に発足した同基金は、ペットとして捕獲されたり、山火事等で親をなくしたオランウータンを森に戻す活動をしている。)
ポニーが発見されたのは、ボルネオ島にある小さな村(元記事によると、どうやら売春に特化した村であるようだ)の売春宿で、彼女はくさりで壁につながれ、マットレスの上に横たわっていたという。
オランウータンは、赤茶けた少し長めの毛に覆われた動物であるが、ポニーは、体中の毛を剃られ丸裸だった。
男性が近づくと、彼女はくるりと背を向け、お尻を突き出したかと思うと、ぐるぐる回し始め、セックスを誘うような素振りをしたという。保護された時、彼女は6、7才であったと推定されるが、それまで長期にわたり売春宿の女性経営者(マダム)の元にいたようだ。
基金側はポニーを助け出そうとしたのだが、マダムは、ポニーは皆に可愛がられ、稼ぎもいいからと引き渡しを頑に拒否。ポニーは宝くじの当選番号を引いたりしたこともあり、幸運をもたらす存在として見られていたというのも、断る理由の一つだったようだ。
売春宿には、もちろん女性たちも働いていたが、オランウータンとセックスするという物珍しさから、そこを訪れる客の多くはポニーを指名したという。
当時、ポニーは毛を一日おきに剃られていたため、皮膚はただれ、吹き出物だらけだった。あらわになった地肌を蚊は容赦なく刺し、痒くてたまらない彼女は蚊の刺し傷を掻き続け、そこからばい菌に感染した。その上、指輪やネックレスまで身に付けさせられていた。ポニーは見るに耐えない状態だったという。
ポニーをそこから救い出そうと、基金のワーカーたちは森林警備官と地元の役人たちを引き連れ、一年にわたり何度も売春宿に足を運んだが、その度村人たちに妨害された。彼らは銃と毒が塗られたナイフをちらつかせ、ワーカーたちを脅したそうだ。
最終的にAK-47(自動小銃)で武装した35人の警官が出動し、やっとオランウータンを救出することができた。ポニーがつながれていたくさりをワーカーたちがはずそうとした時、マダムは、「私のベビーを連れて行かないで!」と、泣き叫んだという。
インドネシアにはこのケースのような動物虐待を裁く法的処罰がなく、ポニーを囲っていたマダムらは何のおとがめも受けていない。
http://omoroid.blog103.fc2.com/blog-entry-151.html