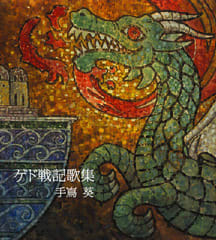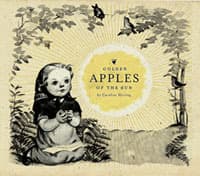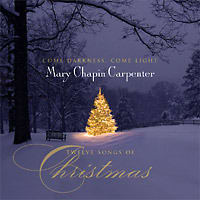今、マリアンヌ・フェイスフルのデビュー当時のアルバムが欲しくてね。でも、内外ともに絶版状態みたいで手に入らず、くさっているのである。なんだこれは。
デビュー当時のフェイスフルって、結構可憐なフォーク調のものを歌ういい感じの歌手だったんだね。ロリ系のさ。こっちは彼女をリアルタイムで知ってはいたけど、ストーンズのメンバーとのあれこれとかそんなものばかり興味を持ってしまい、彼女がどんな音楽をやっていたか、興味を持つ機会もなかった。でも今調べてみると、なかなか面白い内容のアルバムを出しているんだよ。
特に、「ノース・カントリー・メイド」っていうアルバム、これが欲しくて。なかなか泣かせる選曲でね。あ、そう来たか、みたいな曲が並んでいる。
まあ、詳しくはそちらで勝手に調べて欲しいんだが。うん、きっとあなたも欲しくなるに違いないって。
で、さあ、このアルバムなんて、通販サイトになんというか”売り切れ”の表示さえないんだ。「この盤があったんだけど売り切れです」じゃなくて、その存在の痕跡さえ残っていない。そんなに売りたくないか、通販サイトもさ。
とか言ってるけど、ますます悔しいのは、何年か前に”デッカ・イヤーズ”って彼女のボックスものが出ていて、実は”フォーク期”のフェイスフルは、これを買っておけば一網打尽だったんだよな。全部手に入っていた。まったくねえ・・・よくある話でさ。その価値に気が付いた時には、もう思いっきり絶版なんだよな。
ねえ、なんとかならんか、レコード会社よ?
デビュー当時のフェイスフルって、結構可憐なフォーク調のものを歌ういい感じの歌手だったんだね。ロリ系のさ。こっちは彼女をリアルタイムで知ってはいたけど、ストーンズのメンバーとのあれこれとかそんなものばかり興味を持ってしまい、彼女がどんな音楽をやっていたか、興味を持つ機会もなかった。でも今調べてみると、なかなか面白い内容のアルバムを出しているんだよ。
特に、「ノース・カントリー・メイド」っていうアルバム、これが欲しくて。なかなか泣かせる選曲でね。あ、そう来たか、みたいな曲が並んでいる。
まあ、詳しくはそちらで勝手に調べて欲しいんだが。うん、きっとあなたも欲しくなるに違いないって。
で、さあ、このアルバムなんて、通販サイトになんというか”売り切れ”の表示さえないんだ。「この盤があったんだけど売り切れです」じゃなくて、その存在の痕跡さえ残っていない。そんなに売りたくないか、通販サイトもさ。
とか言ってるけど、ますます悔しいのは、何年か前に”デッカ・イヤーズ”って彼女のボックスものが出ていて、実は”フォーク期”のフェイスフルは、これを買っておけば一網打尽だったんだよな。全部手に入っていた。まったくねえ・・・よくある話でさ。その価値に気が付いた時には、もう思いっきり絶版なんだよな。
ねえ、なんとかならんか、レコード会社よ?