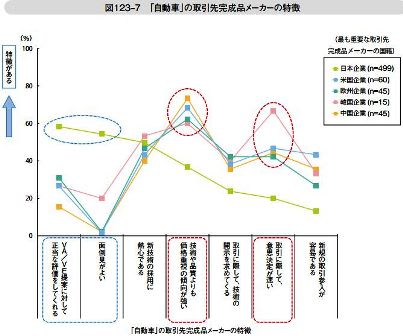おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。
昨日は2013年度ものづくり白書 109ページの「TOTO(株)の“知財のピラミッド”」をみましたが、今日は112ページの「標準の種類」をみます。
国際標準とは、製品の品質、性能、安全性、寸法、試験方法などに関する国際的な取決めのことで、主な標準の種類としては、デファクト標準、フォーラム標準、デジュール標準に分類されます。

wikipediaによると、市場における競争や広く採用された「結果として事実上標準化した基準」をデファクトスタンダードといい、ISO、DIN、JISなどの国際標準化機関等により定められた標準をデジュールスタンダードと呼ぶそうです。
経緯は白書本文に譲るとして、自社技術を国際標準化させることのメリットは製品市場の拡大と製造コストダウン、他社との製品共通化や技術移転が容易となる点であり、デメリットは他社の参入が容易となり、製品価格が低下する点が挙げられます。
重要なことは、単に自社技術を標準化するだけでは自社の利益にはつながらないことから、あらかじめ自社のコア技術を特定し、コア技術はクローズ化により利益の源泉とする一方、コア技術以外はオープン化により全体としての市場拡大を図り、市場の拡大と利益確保が両立する仕組みを作るなどの知財マネジメントと連携させることです。
得意とする自動車、カメラ、電化製品をはじめ、脱原発に向けた自然エネルギーなど、日本のものづくりのグローバル化のKFS(成功の鍵)になるということですね。
昨日は2013年度ものづくり白書 109ページの「TOTO(株)の“知財のピラミッド”」をみましたが、今日は112ページの「標準の種類」をみます。
国際標準とは、製品の品質、性能、安全性、寸法、試験方法などに関する国際的な取決めのことで、主な標準の種類としては、デファクト標準、フォーラム標準、デジュール標準に分類されます。

wikipediaによると、市場における競争や広く採用された「結果として事実上標準化した基準」をデファクトスタンダードといい、ISO、DIN、JISなどの国際標準化機関等により定められた標準をデジュールスタンダードと呼ぶそうです。
経緯は白書本文に譲るとして、自社技術を国際標準化させることのメリットは製品市場の拡大と製造コストダウン、他社との製品共通化や技術移転が容易となる点であり、デメリットは他社の参入が容易となり、製品価格が低下する点が挙げられます。
重要なことは、単に自社技術を標準化するだけでは自社の利益にはつながらないことから、あらかじめ自社のコア技術を特定し、コア技術はクローズ化により利益の源泉とする一方、コア技術以外はオープン化により全体としての市場拡大を図り、市場の拡大と利益確保が両立する仕組みを作るなどの知財マネジメントと連携させることです。
得意とする自動車、カメラ、電化製品をはじめ、脱原発に向けた自然エネルギーなど、日本のものづくりのグローバル化のKFS(成功の鍵)になるということですね。