塩田明彦の「監督ノート」にサティアンから出てきた子どもたちの瞳にポルポト派の少年兵士のそれをなぞらえているのを見て、やはりそうかと思った。文化大革命の実験を現実化しようとした壮大な破滅的企て、それが76年から79年までカンプチアでなされたクメール・ルージュ=ポルポト派のなしたことだった。そして、ポルポト派が重視した教育政策(あれが教育であったか、政策であったかはさて措くとしても)の柱は、子どもを親から引き離し、子どもが「主体的に」親の世代を断罪する力を持つことにあった。何がしかのブルジョアジーに染まった大人より何ものにも染まっていない子どもこそ「民主」カンプチアを支える豊富な人材であったからだ。このような極端な集団主義、空想主義が瓦解したのは言うまでもないが、あの時ポルポト派の兵士であった子どももその後の内戦、新カンプチア建国の中でより現実社会に順応し、もうオンカー(党)の子どもではないだろう。しかし、現在の社会が子どもを私有財産化しすぎる中で ー 一人っ子政策の中国も、塾とゲームに子育て?を全て預ける日本も、モノのごとく暴力をふるい時に死に至らしめるアメリカも ー 子どもの私有財産化を否定したポルポト派の理想主義は、人権という概念からは逸脱するけれど何かしら新鮮な感じがする。
振り返ってみるとカナリアの子どもたち。光一は母親の入信に引きずられニルヴァーナ(オウム真理教を模していることは言うまでもない)で生活、「社会性」をつけず成長したならば、光一を引っ張る由希は母を亡くした後父親から暴力を振るわれ、援助交際で小遣いを稼ぐ恐ろしく「社会性」に長けた存在。彼・彼女をこうしたのは大人の身勝手、無責任というのはた易いが、彼らにとって過酷であるのはお金がないことではない、食べるものがないことでもない、信頼できる人間がそばにいないことでもない。彼らが自分の道を自分で選べなかったことなのだ。
ところがニルヴァーナで活動していた大人たちも自分で自分の道を選んだ結果そうなったのか?いや、自分で自分の道を選ぶことのできる人間などそう多くはないのかもしれない。そうであっても「死」より「生」に価値があると思える間は、変わりゆく存在としての人間に塩田監督が可能性を託したのは、実は外の世界を一切拒否するかのような光一の射抜くような眼差しだったのかもしれない。
振り返ってみるとカナリアの子どもたち。光一は母親の入信に引きずられニルヴァーナ(オウム真理教を模していることは言うまでもない)で生活、「社会性」をつけず成長したならば、光一を引っ張る由希は母を亡くした後父親から暴力を振るわれ、援助交際で小遣いを稼ぐ恐ろしく「社会性」に長けた存在。彼・彼女をこうしたのは大人の身勝手、無責任というのはた易いが、彼らにとって過酷であるのはお金がないことではない、食べるものがないことでもない、信頼できる人間がそばにいないことでもない。彼らが自分の道を自分で選べなかったことなのだ。
ところがニルヴァーナで活動していた大人たちも自分で自分の道を選んだ結果そうなったのか?いや、自分で自分の道を選ぶことのできる人間などそう多くはないのかもしれない。そうであっても「死」より「生」に価値があると思える間は、変わりゆく存在としての人間に塩田監督が可能性を託したのは、実は外の世界を一切拒否するかのような光一の射抜くような眼差しだったのかもしれない。


















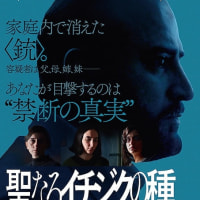





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます