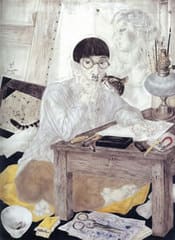モエレ沼公園にはぜひ行ってみたいと思う。イサム・ノグチがそのグランドデザインの集大成とも言えるべき作品を遺し、それが死後実現されたからだけというわけではない。写真や映像でしか見たことはないが、モエレ沼公園はなにかしら惹かれるものがあるのだ、なにかこう、子どもが奈良の若草山の芝生にごろごろとでんぐり返りをするような、大人になってもそれを体験したいような、広く、あたたかく、なだらかな雰囲気がモエレ沼にはあふれているような気がしたのだ。そしてそこにはニューヨークのイサム・ノグチ美術館にはない尊大ではなく壮大な雰囲気を感じるのだ。
一方、イサム・ノグチがブランクーシの影響を多大に受けているというのは気がついていた。幾何学的、工業的ともまみえる大理石、あるいはブロンズの作品はおよそロダンが築いた近代社会を迎える人間の懊悩や、近代以前の人間の本来的に持つ苦悩(それがダンテの神曲に最大限負ったとしても)を表現した「近代彫刻」をも超えているのは明らかだ。
ただ、ボッチョーニらの未来派でもなくブランクーシはいわば人が持つ(と信じたい、あるいは信じたい)とされるある種の「崇高さ」に賭けたのだ、と思える。「空間の鳥」を(ポンピドーセンター)は、鳥ではない。磨きぬかれた尖状の黄金色に輝くブロンズが鳥であるわけがない。が、あの突き抜けた方向性、今にも飛び立たんとする躍動感は紛れもなく鳥なのだ。
イサム・ノグチの作品はブランクーシと違い、躍動感で勝負したものは少ないと思える。しかし逆に大地に拘ったのかもしれない。イサム・ノグチの作品には太陽や「無限」をモチーフにしたものが多い。日本人の父親、アメリカ人の母親のもとに生まれ、常に自己の依るべきところ、立ち位置を模索した彼のアイデンティファイを想像し、作品課題に探すことは容易い。が、イサム・ノグチは本当に自己のアイデンティティ・クライシス故に太陽や大地に回答を求めたのか。否。
後年彼の手がけたプレイグラウンドは多い。そのどれもが直線の中に曲線が見事に融和しているのがわかる。ガウディやバッサーと違うところだ。曲線=自由ばかりであると人間はときに不安だ。人間はときに直線=管理を心地よいと思うし、またそれがないと不安なときもある。しかしノグチが直線=管理から放たれようとした生き方、時に曲線世界に生きるということ、こそグランドデザインの発想の源ではなかったか。
そこには国家や偉い人たちなど思惑など超えた自然とのつきあいが展望されてるとというのは言い過ぎだろうか。モエレ沼公園はもともとゴミ埋め立て地である。
一方、イサム・ノグチがブランクーシの影響を多大に受けているというのは気がついていた。幾何学的、工業的ともまみえる大理石、あるいはブロンズの作品はおよそロダンが築いた近代社会を迎える人間の懊悩や、近代以前の人間の本来的に持つ苦悩(それがダンテの神曲に最大限負ったとしても)を表現した「近代彫刻」をも超えているのは明らかだ。
ただ、ボッチョーニらの未来派でもなくブランクーシはいわば人が持つ(と信じたい、あるいは信じたい)とされるある種の「崇高さ」に賭けたのだ、と思える。「空間の鳥」を(ポンピドーセンター)は、鳥ではない。磨きぬかれた尖状の黄金色に輝くブロンズが鳥であるわけがない。が、あの突き抜けた方向性、今にも飛び立たんとする躍動感は紛れもなく鳥なのだ。
イサム・ノグチの作品はブランクーシと違い、躍動感で勝負したものは少ないと思える。しかし逆に大地に拘ったのかもしれない。イサム・ノグチの作品には太陽や「無限」をモチーフにしたものが多い。日本人の父親、アメリカ人の母親のもとに生まれ、常に自己の依るべきところ、立ち位置を模索した彼のアイデンティファイを想像し、作品課題に探すことは容易い。が、イサム・ノグチは本当に自己のアイデンティティ・クライシス故に太陽や大地に回答を求めたのか。否。
後年彼の手がけたプレイグラウンドは多い。そのどれもが直線の中に曲線が見事に融和しているのがわかる。ガウディやバッサーと違うところだ。曲線=自由ばかりであると人間はときに不安だ。人間はときに直線=管理を心地よいと思うし、またそれがないと不安なときもある。しかしノグチが直線=管理から放たれようとした生き方、時に曲線世界に生きるということ、こそグランドデザインの発想の源ではなかったか。
そこには国家や偉い人たちなど思惑など超えた自然とのつきあいが展望されてるとというのは言い過ぎだろうか。モエレ沼公園はもともとゴミ埋め立て地である。