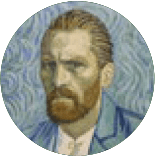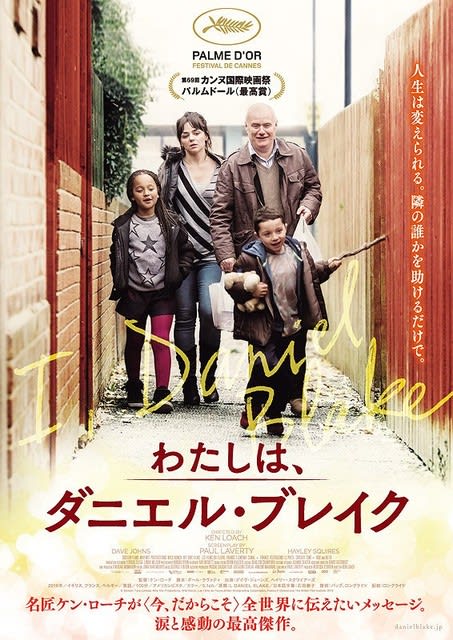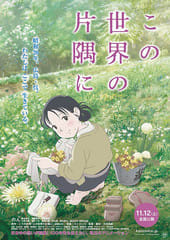「A」や「FAKE」で知られる映像作家の森達也さんがドキュメンタリーであるからといって作者の作為や意図が全く入らないことはあり得ない旨述べていたことを思い出した。
「ゲッベルスと私」もナチスの宣伝相であったゲッベルスの秘書(タイピスト)であったポムゼルの語りや、挿入される映像に監督が改めて脚色したことはないだろう。しかし、ポムゼルに対するインタビューのどの部分を映画として残し、その合間のどこにどんな映像を挟むかという編集作業に監督の問題意識や考え方が反映されるのは当然だろう。だからといって、本作がナチスの暴政やポムゼルの個人責任を問うプロパガンダ作品ではない。
ポムゼルは「ドイツ国民全員に(ホロコーストの)責任があるとするなら私にもある」と。それは日本の「一億総懺悔」に通じるものがある。一部の重い責任をうすめて―日本では当然大日本帝国を総攬していた天皇ヒロヒトであろう―その時の国民全員に被害国(民)に責任があるとする立場は結局一人ひとりの責任を問わないことになってしまう。また、1945年当時の1億人には植民地であった朝鮮半島や台湾などの人も含まれる。この人らには日本内地から「一億総懺悔」と括られる謂れはない。これは本作でもオーストリア人にとってナチスに加担した責任が明確に示されていて不評だとの傾向に通じる。そう一介の市民は国家権力の被害者であることは感じていても、侵略、圧殺した他国の市民に対して加害者であることには自覚的にはなれない。その無自覚さは容易に次代の他国民圧殺や国内の外国人やマイノリティに対する差別に結びつきやすい。そして差別は戦争を生む。
クレーネス監督とヴァイゲンザマー監督は言う。「この映画は決して歴史についての映画ではありません。むしろ、現代についての映画なのです。(中略)一番怖いことは、私たちが政治や社会について無関心になってしまうことです。この映画は戦争における個人の責任についても語っています。邦題『ゲッベルスと私』(原題はA German Life)の〝私〟とはあなたのことでもあるのです。もし、あなたが彼女の立場だったら、どうしていましたか?」
「戦争法」をはじめ、着々と強権国家づくりがなされるこの国では、市民レベルでは(それ以上かもしれないが)ヘイトスピーチもまかりとおる。「あなたが彼女の立場だったら、どうしていましたか?」を反芻すべき作品である。