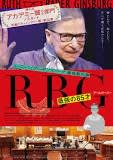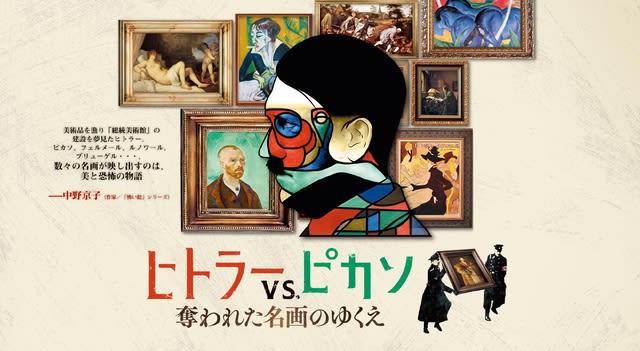映画の背景を最初知らなかったので、中東のどの国か分からなかった。けれど女性がブルカなどのイスラムの厳格な装いをしていなかったこと、多くの移民が暮らしている下層の街であることが窺い知れ、レバノンではと感じた。的中したが、それを自慢したいわけではない。シリアからの難民が隣国に多く流れているとか、その生活実態がきついものであるとか聞いていたかもしれないのに、それくらい、レバノンの現状に疎かったということだ。
ゼインは12歳くらい。親が出生届を出していないから、法的には存在しないのだ。ゼインには兄弟がたくさんいる。が、年下ばかりだ。この理由(わけ)はすぐに知れる。ゼインと仲よかったすぐ下の妹、サハルが生理が始まった途端、結婚させられるのだ。レバノンでも11歳での結婚はもちろん合法ではないが、結婚相手はゼインが両親を訴えた法廷で「11歳の結婚は私の地方では普通です。そしてサハルは“十分熟していました”」と言い放つ。ゼインの親が貧困のため、サハルの結婚相手から鶏1羽を受け取ったこと、サハルが未熟な体で妊娠、出血死したこと、自分も出て行けと言われたこともあり、ゼインは両親を訴える。「世話できないなら産むな」と。
ゼインもサハルもその下の子供達も働き通しだ。街で、自家製ジュースを売り、薬物をしたした衣類を刑務所で売りさばき、ゼインは家主の店(主人はサハルを娶ることになる)で配達もこなす。もちろん学校には行っていない。両親も移民で仕事をしていない。やっていることといえば子作りだけ。そしてサハルより年上の姉らは「児童婚」を強いられていたのをゼインは見ていたのだ。
本作が提起する問題はいくつもある。シリアなどの移民が隣国レバノンに押し寄せているのに無為無策であること。そもそもそのように国を捨てる移民が大量発生するシリア内戦の解決が米露を始めとする国際社会が見出せていないこと、レバノン国内の移民の居住地域をスラム化させている現状、そして(レバノンでももちろん違法で、レバノンはキリスト教徒が多く、イスラム原理主義勢力が強いわけではないのに)児童婚をゆるしている国内状況など。一つひとつが解決するには多大な労力を要すると思うが、本作はだから撮られたのだろう。知ってほしいと。
監督・脚本・主演(ゼインの弁護士役)をこなしたナディーン・ラバキーはフィクションである本作をドキュメンタリーに見えるがごとく徹底的にリサーチして仕上げたという。そしてゼインを始め、ゼインを助けるエチオピア移民のラルヒ、ゼインの両親、サハルなどすべて本業の役者ではない。ゼインが出生届けがないのに弁護士の奔走などで身分証明を得て、北欧に移住(もちろん映画の両親ではない)したのは事実なのである。
日本でも児童虐待が問題視されている。その多くは直接的暴力や、ネグレクト、そして主に父親から女児に対する性虐待の事例だ。そもそも親の養育能力が欠けているのをソーシャルワーカーや児相が懸命に(多くの場合、そうに違いない)ケアしていたのに、そこから漏れた事案が悲惨なことになっている。この国では、学校に行かせず、児童婚を強いる案件はさすがにないと思っていたら、やはり学校に行っていない子どももいるそうだ。公教育を受けるべきかどうかはさておき、教育を受ける権利は憲法にも規定されており、親が教育に関心を持たない事例は確実にある。であるから、親の教育力(とその背景にある貧困、自己評価の低さなど)を無視して、テストの結果が悪い学校には予算配分を減らすなどいう大阪府・市の姿勢は現実と原因を理解していないなにものでもないのである。
しかしゼインの逞しさには恐れいる。突然ラルヒが帰ってこなくなり(不法就労で拘束された)、その子ヨナスの面倒を見、現金収入を得ようとする機知と実行力は、移民を「移民でない」と見えない存在にしようとしている日本社会では想像を超えている。だからと言って自己責任力の最たるものとしてのゼイン的な生き方が子どもに求められる社会も健全とは言えないだろう。自立とはかくも難しい課題であって、それが求められる年齢と背景を考えさせるのが本作の魅力だ。