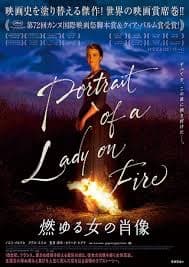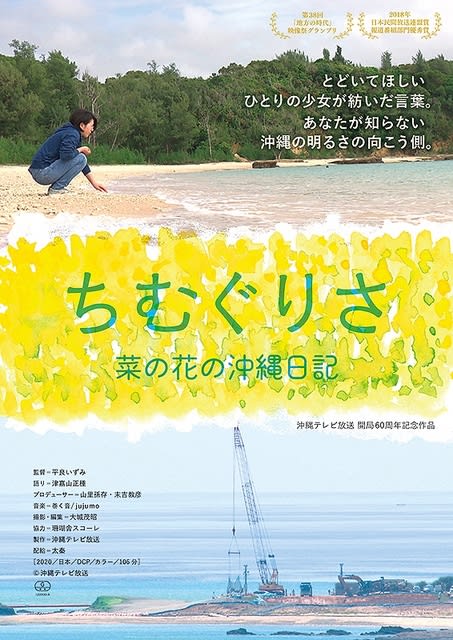定住地を持たず流浪する民の呼び名は数多ある。イスラエル建国まで祖国を持たない、あるいはそれ以外の地に生きるユダヤ人を代表するディアスポラ。かつてはジプシーと呼ばれたが現在はロマ、あるいは地名由来のボヘミアン。マッチョな人気ダンス・ヴォーカル・グループ名でなく本来の意味は逃亡者、亡命者のエグザイル。そして遊牧民や流浪する人をさすノマド。
私はホームレスではなくハウスレス。財産としてのハウスはないが、居場所としてのホームはある。夫を亡くし、企業城下町だったネバダ州のエンパイアは街から企業が去ると、ファーンも住居を失い、キャンピングカーでの生活となるが、昔の教え子の子どもから「あなたはホームレス?」と訊かれ毅然と答える。教員まで勤めたファーンは別に家を探せばいいのではないかと思えるが。ファーンには豊かに暮らしている妹やファーンに好意を抱きノマド仲間だったが、息子と和解し大きな家に住まうデイヴィッドも彼女に部屋を提供しようとする。が、ファーンはもう車以外のベッドでは眠れない。そしてそのような困難な生活にあっても働くことを諦めない。ファーンが季節労働で雇われるアマゾンの巨大な配送センター。多くのノマドも働くのは雇用中は駐車場が保証されるから。テーマパークの食堂、モールの掃除。細切れの労働では多くの収入は得られない。しかし、ノマド仲間の多くは、安定した職を得てハウスに住みたいと考えているようにも見えない。そこには一言では言い表せない過去を引きずり、資産の象徴たるハウスを持つ束縛からは解放されたいと考えるから。
原作は『ノマド 漂流する高齢者たち』(ジェシカ・ブルーダー)で、著者は実際にノマドと3年間暮らし、数百人のノマドに取材したルポを著した。ファーンを演じるアカデミー賞俳優フランシス・マクドーマンド以外の登場人物はほとんど実在のノマドである。ハウスの束縛から解放されたい人たちと前述したが、実際の暮らしは厳しい。車ゆえの厳しい環境。冷暖房、食事、洗濯、排泄、病気になった時など生活の基本条件から、駐車場、車のメインテナンスと現金収入は不可欠だ。だからノマドは気楽な「遊牧民」ではなくて、流浪を余儀なくされた資本主義社会ゆえの「垢」なのだ。
ファーンが妹の家族に世話になった際、集った者が不動産で儲ける話をすると「借金させて家を売りつけるなんて」と反論する。そこにはリーマンショックの影が見える。そして画面をクリックすればすぐに商品が送られてくるアマゾンの仕組みもこういった期間労働、使い捨て労働によって成り立っているという事実を見せつける。そう、本作は優れてアメリカの現実を描いているのだ。持てるものと持たざる者。そこで表面的には描かれていないかに見えるのは、弱肉強食、格差社会という世界最強・最大の資本主義国アメリカの本質であって、個で抗えるものではない。だから、心の中だけでもファーンは自由であり続けるのだ。それを支えるのがキャンピングカーという小さなお城しか失うものを持たない寄る辺なきノマドの仲間たちである。いや、ファーンは言う。自分は心残りを引きずり、それを乗り越えられないからノマドを生きるのだと。自立して誇りあるノマド、に見えるファーンとて不安と戦い続ける高齢者(劇中では61歳)に過ぎないのだ。
ファーンと実在のノマドたちに密着したカメラは、社会の矛盾を直接的に突く構成とはなっていない。その点を、さこうますみは「ケン・ローチだったとしたら、また別の描き方をしただろう」と指摘する(『週刊金曜日』1321号 2021.3.19)。確かにケン・ローチなら格差社会に壊され、時に命を奪われる主人公にしたかもしれない。しかし、「ミナリ」の脚本・監督のリー・アイザック・チョンといい、本作のクロエ・ジャオといいアジアがルーツの監督ではアメリカ映画も見せるものがある。ハリウッドへの偏見?を捨てて今後も期待したい。