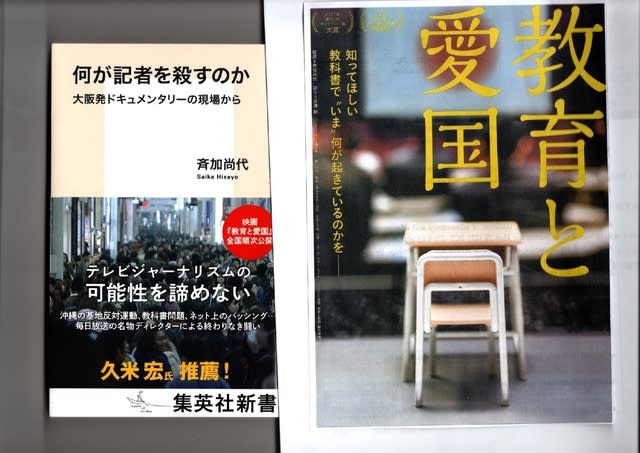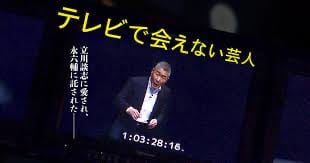是枝裕和監督は「家族であることとないこと」と「家族でいることといないこと」を描くのが本当にうまい。家族とは他人である異性が結合し、子をもうけ、血縁関係が基本であるとの「理想の」「伝統的で」「健全な」家族像を疑うことから始まる。現にDVや児童遺棄などの問題は血縁家族から発生していることが多い。しかし、是枝監督が問うのは、理想の家族とは何かではなく、一人ひとりの人間がどの時点で家族を形成、意識していくかという点にあり、それを世間=多数派の他者が「そんなものは、家族ではない」という決めつけを打ち消すところにあると思う。
「誰も知らない」(2004)では、子ども置き去り事件を、「そして父になる」(2013)では、新生児取り違えを、そして「万引き家族」(2018)では、血縁のない一家の擬似家族ぶりを描いた。そして本作は赤ちゃんポストである。
日本では熊本慈恵病院のただ一ヶ所だけで運営されている通称「赤ちゃんポスト」(慈恵病院では「こうのとりのゆりかご」)は、韓国では3ヶ所あり、保護数も日本より圧倒的に多い。日本より少子化がはるかに進む韓国で(合計特殊出生率は0.81、2021年)、授かった命を手放さなければならない境遇の母親が多い事実と、その命をなんとか守ろうとする国を挙げての取り組みに驚かされる。しかし、もちろん綺麗事ではない。
本作でカンヌ映画祭主演男優賞を得た名優ソン・ガンホ演じるサンヒョンは、自身親から遺棄された過去を持つドンス(カン・ドンウォン)と赤ちゃんポストに託された子どもを売るベイビー・ブローカー。赤ちゃんを取り戻したい母親ソヨン(イ・ジウン)は、彼らと共に買い手探しの奇妙な旅に出る。途中でドンスの育った施設の子どもヘジンも加わり、ロードムービーが展開する。児童売買の現場を押さえようと彼らを追う刑事スジン(ペ・ドゥナ)は何か重い屈託を抱えていて。配役と場面ごとの間の妙に唸っているうちに、事態はとんでもない方向へ。そう、血縁関係も、もともとなんの関係もなく、感情や利害の対立さえあった人たちが「家族」になってゆくのだ。しかし、当然犯罪がらみ、警察に追われる「家族」は「家族」として成就はしない。
あらためて「家族」とはなんだろう。私ごとで恐縮だが、筆者はある資格官職として勤めていた。資格には一般的に試験通過が必要で、多くの場合、その資格を得るためには研修もあり、研修を終わった者だけが官職を名乗ることができた。しかし、私は試験に通ったから、研修を終えたからその官職を名乗れるのではなく、その官職名で呼ばれ、働いているうちにその官職となるのだと常々感じていたし、若い人にもそう伝えていた。家族も同じようなものではないだろうか。「家族」として見なされると同時に、実感することと、その「家族」の一員であることを自身が受け入れていく過程そのものが「家族」であると。そう「家族」は「家族」になってゆくのだ。だから、「家族」と見なされていることだけにすがり、その家族間にずれや軋轢が生じると容易に壊れるものでもあると。異性、年長と年少、血縁などの属性は関係ない。
同性カップルの権利や、出自の不明なままの内密出産の法的保護など「多様な家族像」という一言には納めきれない現実もまた、「これが家族です」という定義づけを不明にし、その意味をも問い直す。日本では独り世帯が増加し、高齢者の「独居」も増加の一途だ。しかし、「家族」を上記血縁や同居の有無に囚われることなく、緩やかな人間関係の上で再定義するならば、悲惨な実態とイメージは薄れるのではないか。ところが、カンヌで同時期に賞を取った早川千絵監督の「PLAN75」が上映中で、日本では「家族」どころか「無用な」人間を減らす試みが現在進行形に見えるのが恐ろしい。