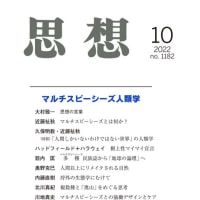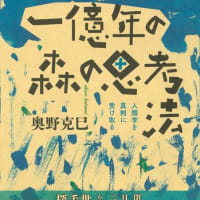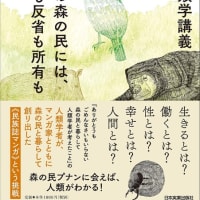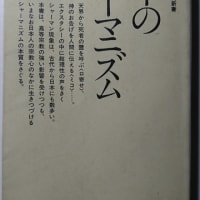本発表の目的は、マレーシア・サラワク州のブラガ川流域に半定住する、狩猟を主生業とする約500人のプナン(Penan)の動物と人間をめぐる関係の輪郭を民族誌的に描き出すことを踏まえて、自然と社会という主題に対して一つの見通しを示すことである。本発表では、ボルネオ島、マレー半島、東インドネシア一帯で広く行われているとされ、東南アジア民族学において、「雷複合(thunder complex)」と呼びならわされてきた観念と実践を取り上げる。フォースによれば、「その複合の中心には、禁止事項、とりわけ、動物の扱い方を含む禁止事項が、嵐を招き、その結果として、洪水や稲妻によって、ときには、石化によって罰を与えられるという考えがある」。
本発表で取り上げるプナン社会においても、動物に対する人間のまちがったふるまいが、雷雨や大雨、洪水などの天候の激変を引き起こすと考えられている。人間のまちがったふるまいに怒った動物の魂が天空へと駆け上がり、雷神にその怒りを届け、雷神の怒りが雷鳴となって鳴り響き、雷雨や大水を引き起こすと考えられている。そうした制御不能な天候の激変に対しては、それが起きた時点でそれを鎮めるための儀礼が行われ、また、人間の粗野な動物の扱いがその原因であると考えられるため、動物に対して、まちがったふるまいをしないために、禁忌が実践され、人間と動物の間の近接が禁止されてきた。
本分科会は、民族誌を手がかりとして自然と社会の二元論を考えることを目指している。それに応じるために、本発表では、どのように人間が、民族誌的な実践の場面において、動物と相互交渉しているのかに焦点をあてたい。プナンの行動の現実を、できる限り、生き生きとした民族誌のなかに描き出したいと思う。そのため、以下では、エピソードを中心とした口頭発表を試みる。そうした民族誌の全体性の先に、プナンにおける動物と人間の関係のあり方、とりわけ、それらの近接の禁止というタブーの意味と魂の連続性に関して、一つの見方を提示することを目指している。
以下では、順に、ジャネ、発表者(プナン名:ブラユン)、ドム、ティマイ、発表者の一人称の表現による世界理解を示す。
◆登場人物リスト
・ジャネ・・・プナンの長老(1.の語り)
・ブラユン・発表者のこと(2.5.の語り)
・ドム・・・プナン人のハンター(3.の語り)
・ラセン・・プナン人のハンター
・ティマイ・プナン人のハンター(4.の語り)
1.長老ジャネの話、夜、狩猟キャンプにて
「よく聞いておきなさい。生きているもののうち人が捕まえようとしたときに逃げようとするものにはすべて魂がある。イノシシ、シカ、マメジカ、リーフモンキー、ブタオザル、テナガザル、マレーグマ、ジャコウネコ、ヤマアラシ、センザンコウだけでなく、地を這うもの(ヘビ)、サイチョウやスミゴロモなどの飛ぶもの(鳥)、泳ぐもの(魚)、トカゲやカエル、蟲でも、捕まるのを恐れて逃げようとするものにはすべて魂がある。魚には捕まえようとしても逃げないものもいるから、魂のないものもいることになる。要は、われわれ人だけではない、魂があるのは。だが、ジャングルのなかにいる吸血ヒル、あれには魂はない。捕まえようとするときにでもただただ血を吸うばかりで逃げようとはしない。ヒルは、枯葉から生まれてくると言われている。だからジャングルにはあんなにたくさんのヒルがいるのだ。それらは、次から次へと出てくる。ヒルには魂がないから、焼き殺そうが切り刻もうがかまわない。しかし、魂を持つ生き物に対しては、人はふるまいに十分に気をつけなければならない。人は魂を持つ生き物に対して、まちがったふるまいをしてはならない。子どもたちがよくそうしているように、狩りでしとめた動物と戯れるなんてもってのほかだ。プナンはしとめた動物はすばやく解体して料理して食べるだけである。そのさい、しとめた動物の本当の名前を口にしてはいけない。生きていてもすでに死んでいても、動物を前にしたら、その動物を別名(ngaran dua)で呼ばなければならない。belengang(サイチョウ)はbale ateng(赤い目) に、kelasi(赤毛リーフモンキー)はkaan bale(赤い動物)に、palang alut(ジャコウネコ)はkaan merem(夜の動物)にというふうに )。人がまちがったふるまいをすると動物の魂は天空へと駆けのぼる。すると雷神は怒って雷鳴を轟かせ大雨を降らせ洪水を起こして、わたしたちに禍をもたらすのだ。大水や洪水。場合によっては、雷神は人を石に変えたり、大地を真っ赤に染めるほど血を流したりする。赤土の大地は、そのようにして、人の血で染まったのだ。よく覚えておくのだ。動物の扱いには十分に注意せよということを。」
2.発表者の回想、翌朝、狩猟に出かける
わたしは長老ジャネの言葉を聞いているうちに、うとうととし、そのまま蚊帳のなかに入って眠ってしまった。夜が明ける少し前に、男たちの放屁とそれをめぐる笑い声で目が覚めた。狩猟キャンプの朝は早い。朝6時前の夜が明ける前に男たちは起きていつ何時にでもこの場から立ち退くことができるように荷物をコンパクトにまとめる。それは古からの移動民のならわしだ。
5人のハンターと彼らに同行するわたしは皆飲み物も食べ物もいっさい口にせず夜が明け始めた山道を駆け上がった。なぜ狩猟に行く前には何も飲んだり食べたりしないのかというわたしの問いかけに最年長の男はぽつりとそれが「プナンのやり方なのだ」と答えた )。わたしはもっとも近場のジャングルに入って獲物を探すというラセンとドムについてゆくことにした。
ほどなく鬱蒼としたジャングルのなかに入った。ジャングルのなかに入り込んだ途端、わたしの脳裏にはプナンの神話世界が浮かんできた。この地上に何もなかった時代、蛙の神ジャウィが事物であれ生き物であれ、あらゆるものに名を付けた。蛙の神によってあらゆる事物や生き物が生み出された。まず言葉が先にあったのだ。その原初の時代、マレーグマだけに尾があった。見てくれがいいと他の動物がマレーグマのところに尻尾をもらいに来た。マレーグマは次々にそれを惜しみなく与えた。最後にテナガザルが来たときにはマレーグマにはもう他の動物に与える尾が残っていなかった。それで今日マレーグマとテナガザルにだけ尻尾がない。そのようにして神話のなかで、マレーグマは惜しみなく与えるという道徳規範をヒトに教えてくれたのである。そのころには、動物もヒトのように話し、ふるまっていた。ジャングルにはそうした神話の世界が息づいている。
ジャングルを歩いていると前方の木の上で小動物のようなものがちょろちょろと動いているのが見えた。ドムはわたしにあれはリスだと教えてくれた。ムジサイチョウが高い樹々の上を飛んでゆく。はばたく雄大な羽音が聞こえる。樹上高くサルの類が葉をざわつかせている。それらは人間と同じように何かに反応して動く。魂をもっている。プナンはこうも言う。動物とヒトは見かけがちがっていても、それほどちがいはないと。解体してその内部を覗いてみるならば、動物も人間も同じように心臓 、脳、肝臓 をもっている。それゆえにクネップ=心をもっている )。その意味で、動物は、人間と同じように、再帰的な主体として現われる 。
3.ドムの狩猟行、昼、ジャングルにて
その日は、ジャングルのなかにはイノシシシの真新しい足跡はほとんど見あたらなかった。遠くの峰からリーフモンキーの鳴き声が聞こえてきた。クゥオークゥオークゥオクゥオクゥオクゥオクゥオ。おれたちは、ジャングルのなかを歩いても歩いても、お目当てのイノシシには出くわさなかった。新しい足跡さえ見あたらない。ラセンとおれは、そのうちにイノシシではなくてリーフモンキーやブタオザルなどを狙撃しようと考えるようになった。ちょうど樹上の動物や小動物をしとめるための散弾も2発ある。われわれは下を向いて足跡を見て歩くよりも、樹上に目を凝らしながらジャングルのなかを歩き回るようにした。遠くでクロカケスがさえずっている。トゥアイトゥトアイトゥトゥアイトゥトアイトゥ。ジャングルのなかには陽射しは届かないので天空の様子は分からないが、どうやら雨が降るようだ。そうクロカケスが教えている。木の上で何かが動いているのを察知した。さきほど遠くで葉を揺らしていたブタオザルのようだ。距離にして、ここから200メートルほど先の樹上だ。ラセンは猟銃の筒に散弾銃を補填して、音を立てないように小走りで獲物がいるほうへと近づいて行った。ブタオザルの集団はどうやら危険を察知して、警戒しはじめたようである。ブタオザルはヒトが放つ匂いに対して敏感だ。甲高い声を上げて逃げようとする。樹から樹へと飛び移り始めた。そのときである。ドゥドーン。前方に一発の銃声が響いた。急いで駆けつけると地上からブタオザルがズドンと落ちてきた。散弾が何発か命中したのだ。見るとそのブタオザルのメスは血をたらたらと流しながら虫の息だった。それを見て、ラセンは、何のためらいもなく、即座に山刀の反対側で頭をコツンと強く叩いて息の根を止めた。もってきた籐の籠に獲物を畳み込んで、おれがその獲物を担いで帰ることになった。
1時間くらいかけてジャングルを出ると、ジャングルの外は、クロカケスが教えてくれたように、土砂降りの雨だった。ブタオザルの魂が名前を呼ばれて怒らないように、おれたちはその獲物をウムンという別名で呼んだ )。ラセンとブラユンとおれは、その後しばらくして狩猟キャンプに到着した。5時間ほど歩き回って獲物はこのブタオザル一頭だけだった。狩猟に出かけた仲間のうちキャンプに戻ったのはわれわれ3人が最初だった。 おれはすぐに炭火で火を起こした。薪を割っているときに、そばにいたブラユンがカメラを取り出してその獲物を撮影しようとしていた。おれは手を止めて、それがよく写るようにと両手を持ち上げてポーズを取った。その様子を見て、タバコを吸っていたラセンはゲラゲラと笑った。おれは調子に乗ってその獲物にいろんなポーズを取らせた。ラセンとおれはしばらくの間笑い転げた。ブラユンはその間パシャパシャと写真を写していた。馬鹿騒ぎが一段落するとおれはその肉を解体して中華鍋のなかにぶちこんで、ブタオザルの肉のスープをつくった。
4.ティマイの唱えごと、夜、激しい雷雨のなかで
Iteu ulie amie padie melakau, puun ateng menigen, saok todok kat, selue pemine mena kaan, uyau, apah, panyek abai telisu bogeh, keledet baya buin belengang dek ngelangi
戻ってきたぞ兄弟たちよ、獲物はまったく獲れなかった、何も狩ることができなかった。嘘を言えば父と母が死ぬだろう。ブタの大きな鼻、かつてイノシシだったマレー人、トンカチの頭のようなブタの鼻、大きな目のシカ。夜に光るシカの目、ワニ、ブタ、サイチョウ、ニワトリが鳴いてやがる・・・!
ラセンたちとは別の猟場に出かけたおれたち4人のメンバーは、獲物が得られなかったときのつねとして、動物に対する「怒りのことば」を唱えながら、手ぶらで狩猟キャンプに戻ってきた。朝っぱらから夕方までジャングルを歩き回って、結局、おれたちには獲物がなかったのだ。運がなかった。今日のおかずはラセンがしとめたブタオザルの肉だけだ。いや獲物があるだけましなほうかもしれない。
ドムがつくったブタオザルの肉のスープをおかずにして、サゴヤシの澱粉を囲んで皆で食事をした。食事を終えて水浴びをしたころには陽はどっぷりと暮れた。小屋がけで蝋燭の火を灯したときに突然遠くで稲光がした。グォグォグォーン。つづいて遠くで物凄い雷鳴が轟いた。空を見上げると一面に低く雲が垂れ込めている。雷鳴は鳴り響いていた。雷神が怒っている。しだいに雷鳴の回数が増え、その音量が大きくなって、雷雨はこちらのほうに近づいてきているようだった。その瞬間、突風が吹いて蝋燭の灯が消えてしまった。まったくの闇の空間。天空をつんざく稲妻がわれわれに一瞬光を与えた。ドムがあわてて木の切れ端を寄せ集めて壁をつくって蝋燭に火を灯した。そのとき、大粒の雨が降り始めた。よりいっそうがなりたてるように轟く雷鳴。グォグォグォグォーン。土砂降りの雨と稲光。雷神の怒りはおさまらない。おれにはピンと来た。昼間、ラセンとドムがブタオザルにポーズを取らせてゲラゲラ笑ったというではないか。それがこの嵐と雷雨を引き起こしたにちがいない。ブタオザルの魂がラセンとドムのふるまいに怒って、天空の雷神のもとに駆け上がったのである。おれは髪の毛を引きちぎってそれを燃やしながら、雷雨のなかに飛び出して天に向かって唱えた。
Baley Gau, baley Lengedeu. Akeu pani ngan kuuk baley Gau, baley Lengedeu. Ia maneu liwen anah medok ineh . Mau kuuk liwen mau kuuk pengewak baley Gau baley Lengedeu. Ia maneu liwen Berayung gamban medok. Dom Lasen mala ineh maneu kuuk seli liwen. Pengah akeu menye bok mena kau baley Gau, baley Lengedeu. Mau kela baley gau, baley Lengedeu
雷神よ稲光の神よ。おれはあんた、雷神と稲光の神と話している。嵐を起こすのは、ブタオザルのせい。雷神よ稲光の神よ、嵐を起こすのを止めておくれ。嵐を起こすのは、ブラユンがブタオザルの写真を撮影したから。ドムとラセンがそれを笑って、そのことがあんたの気に障って嵐を起こしたんだ。おれはあんたのために髪の毛を燃やした。雷神よ稲光の神よ、止めておくれ!
しばらくすると、その激しい雨は小振りとなり、雷鳴ともどもしだいにおさまった。
5.発表者の解釈、夜、寝ながら唱えごとを聞いて
わたしは狩猟キャンプのなかで雨がかからないようにうずくまってティマイの唱えごとを録音しながら聞いていた。激しい雨音でよく聞き取れないが、祈願文のなかで、わたしの名前がひんぱんに語られている。どうやら、昼間の写真撮影でブタオザルにポーズを取らせてあざ笑ったことが、その嵐と雷雨を引き起こしたとティマイは考えたようだ。ドムとラセンとわたしの3人が、しとめられたブタオザルに対してまちがったふるまいをしてしまったのである。長老ジャネのいう戒めを破ってしまったのだ。ティマイは、ブタオザルの魂はその粗野なふるまいに腹を立て、天空へと飛び立ち、雷神が怒ってわたしたちに罰を与えたと推論したようである。
プナンにとって、ブタオザルを含めて、動物は人間と同じように魂を持ち、人間と同じように心で怒りを感じる存在である。そこでは、動物と人間は「身体性(physicality)」は異なるが、同じような「内面性(interiority)」をもつ存在として捉えられている )。そのように、プナンにとって、動物と人間は、内面性(魂)を分かちもつ点で、きちっと切り分けられるような存在ではない。自然のなかでは、すべての現象や事物に平等の地位が与えられており、とりわけ、生き物に関しては、一頭の動物であれ一人の人間であれどんなものにも優先権はない。そういったことが、動物も人間と同じように魂をもつとプナンが言うことで示されているのではないだろうか。いずれにせよ、動物と人間の間に大きな違いはない。
他方で、人間は動物を狩って、食べて生きてゆかなければならない。そのとき、人間にとって対象となる動物との間で、身体性と内面性に、どのような変化が起きているのだろうか。ここでは仮に、動物を殺して食べるという行動の背景には、人間と動物の間で、身体の物質性の点では類似しているが、内面性については異なる(=魂を認めない)という見方が成り立つと考えてみよう。動物を人間と同じ魂をもつ存在と見なしていては、人は、日々動物を殺害することに抵抗感を感じるはずだ。したがって、自然主義に拠りながら、人間と動物には魂の連続性はないという見方をベースにして、人間は、道具と技術を用いて、一方的に、動物を殺害し、解体・料理して食べることが可能になる。言い換えれば、人間が、獲物である動物に対面する場合には、動物と人間の魂の連続性が断ち切られ(=内面性が分断され)、動物が人間にとって操作と加工の対象(=死せるマテーリア)となる。
しかし、はたして、プナンにとって、動物と人間の魂の連続性(=内面性の類似)という価値は、狩猟から食へのプロセスにおいて、魂の非連続性(=内面性の違い)へと変更されるのだろうか。どうやら、そう単純なものではないようである。プナンはよく、獲物はすばやく解体・料理しなければならないという。その間に、まちがったふるまいをして、魂をもつ動物を怒らせないためである。また、獲物を前にしてその動物に言及しなければならない場合には、プナンは、その動物の名の代わりに別名を用いて動物を怒らせないようにする。そうした諸規範の実践をつうじて、動物と人間の魂の連続性の価値それ自体は、いっこうに変更されることがない。つまり、プナンは、動物と近接しなければならない場合において、決められたふるまいをつうじて、動物と人間の間に魂の連続性があること、すなわち、それらが内面的に類似しているという原則を維持しようと努めているように見える。
別の角度から述べれば、プナンは、動物と人間の魂の連続性という大原則を揺るがせにしないために、動物をあざ笑ってはならないであるとか、獲物はすばやく解体料理しなければならないであるとか、種の名前を呼んではならないというような、動物に向き合ったときの禁忌実践を複雑に発達させ、動物と人間の間の近接を禁じてきたのである。そのように理解すれば、プナン人たちは、そうした存在論の底に、人間と大部分の間(多くの動物を含む)は、同じように再帰的な主体であることを認めているという事実が浮かび上がる。
最後に、こうしたプナンの人間と動物をめぐる民族誌には、自然と社会の二元論思考を再検討する上で、いったいどのような意味があるのだろうか。いましがた述べたように、プナンにとって、人間と動物は、ともに魂をもち、内面的に類似している。そこでは、魂をもつことにより、人間と間が同じ主体的存在、一つの主体として立ち現われる。その主原則が大きく崩れることがないように、動物をめぐる禁忌が行われ、人間と動物の近接が禁止されていた。そうした考え方は、部分的に、ヴィヴェイロス・デ・カストロのいう、「単一の文化、多数の自然」から成る「多自然主義(multinaturalism)」の考え方に近いものである )。
多自然主義は、人間と間が等しく主体=文化であることをベースにして、「単一の自然、多数の文化」から成る「多文化主義(multiculturalism)」という知の枠組みの組み換えの可能性に開かれている。多文化主義とは、自然という共有世界を想定し、文化は多様だとする、欧米近代に主流の考え方である。そこでは、身体と物質の客観的な普遍性が確認された上で、精神と意味の主観的な特殊性が確認される。それに対して、多自然主義では、文化あるいは主体が普遍の形式であって、自然や客体が特殊の形式となる。「西洋の多文化主義が公共政策としての相対主義なら、アメリカ先住民の観点主義者のシャーマニズムは、宇宙論的なポリティクスとしての多自然主義である」 。多文化主義では、それぞれの文化の主体である人間同士が交渉し、一方、多自然主義では、人間、動物、精霊などがそれぞれ主体的存在として社会宇宙を構成し、交渉にあたる。
自然と社会の二元論思考は、単一の自然を想定し、社会を構成する人間主体だけに精神を与えてきた。これまでのところ、人間だけに精神を与えるような考え方を批判的に乗り越えるために、人間と間を同位のアクターとして位置づける理論が提起されてきている。そうした理論的課題の検討状況の進行を見やりながら、人類学者はこれまで、多文化主義から出発することで、そのバイアスによって、人間と間が、同じように主体であるような多自然主義的な状況について語りうる方法をもち合わせてこなかったのではないだろうか。民族誌に基礎を置きながらこうした問題に取り組んできた、ヴィヴェイロス・デ・カストロやデスコーラらの議論に合流しながら、人間と間を同時に再帰的な主体的存在であると捉えるような人びとの民族誌の詳細な検討をつうじて、自然と社会の二元論思考を問い直すための議論だけでなく、そのおおもとのところにある西洋思考の再検討の議論にも接近してゆくことが、今後に残された課題である。
第44回日本文化人類学会(立教大学)分科会(2010.6.12.)
「自然と社会の民族誌:動物と人間の連続性」 (代表:田所聖志、東京大学&奥野克巳、桜美林大学)のうち、奥野克巳「ボルネオ島狩猟民プナン社会における動物と人間~近接の禁止と魂の連続性~【エピソード・ヴァージョン】」の発表原稿