気がつくとけっこう読んでた.ここ2ヶ月で.で忘れないうちに、っていうか、すでに記憶がうっすらとしている本も幾つかあるのだが、読んだ本について書いておこうと思う.まず、伊坂幸太郎の『死神の精度』は、生の世界と死の世界が、死神を介して交錯する物語で、こういう想像力は好きだし、エンターテインメントとしてはなかなかのものであるのだが、それを読んだ同じ時期に読んだ、同じ短編連作として、道尾秀介の『光媒の花』の出来のほうが数段よかったと感じた.道尾は人物の造型、蝶や花などのモノの配置を含めて、表現が実に実にうまいのだ.彼の最新文庫本で、直木賞を受賞した『月と蟹』も、そのあとすぐに読んでみたいと思い立って買って読んでみたが、道尾は、大人たちの欲動を下の方から見つめながら、少年と少女たちの心の動きを描くのが実に巧みなのだと思う.とにかく、稀有な作家だ.おっと、道尾さんに話は傾いてしまったが、その前に、ある方から、とにかく凄い、現代のディケンズだ、今年読んだ本のなかで一番だという話を聞いて、ジョン・アーヴィングの『未亡人の一年』(上)(下)を読んでみた.うなったね、この本には.二人の息子を交通事故で亡くした傷心のマリアンを深く愛するようになった16歳のエディ、その後マリアンは失踪するが、エディは、当時4歳だったルースに30年以上の時を経て再会する.物語の流れのなかで、家族とその友人たちの物語がつづられる.かなり部厚い本なのに、スイスイ引き込まれて読んでしまう.そんな圧巻のアメリカ文学に対抗して、日本にも凄いのがあった、と思えたのは、菊池寛の『父帰る/恩讐の彼方に』である.卒論の合宿で来月に訪ねる予定なので、高松出身の作家の本を読んでおこうと提案して読んだのであるが、いや~、すごい、すさまじい.上役を叩き斬って逐電した男がやがて悔い改めて僧となり、人が何人も転落死している難所にある岩を、21年もの間掘りつづけるという「恩讐の彼方に」だけでなく、バカ殿一代記とでもいうべき「忠直卿行状記」、芸を磨くために恋をしかけた「藤十郎の恋」など、「菊池寛」という文学的才能を新たに発見したように思う.その一方で、塩野七生の『チェーザレ・ボルジアあるいは優雅なる冷酷』は、実に美しげな題に惹かれて読みはじめたものの、う~ん、なんじゃ、この15世紀末のイタリアの歴史小説は・・・。で、本年度の芥川・直木賞関連作品を三冊。まずは、いとうせいこうの『想像ラジオ』は、被災地が生み出した文学の流れのなかに位置づけられるのだと思う。樹の上に引っかかった死者によるラジオ放送は、死者からのリクエストや死者とのやり取りで、想像上のものとして行われ、その意味で、文字という視覚と想像上のラジオの聴覚が絶妙に小説のなかで絡み合っている.その死者の声は、やがて、生きている最愛の妻に届く.読んでいる最中に、この本が賞を取るではないかと思ったが、第149回芥川賞受賞作は、開けてみると、藤野可織の『爪と目』だった.それはまた、爪=わたし、目=父の愛人であり、亡くなった母の後の継母の対比が、流麗な文章のなかに描かれる美しい作品だった.これにはけっこう納得.そして、直木賞は、桜木紫乃の『ホテルローヤル』が選出された.それは、北海道のさびれたラブホテルを舞台とする連作短編で、どうやら、桜木さんは、実家がその名前でラブホテルを経営していたとかで、性愛という行動を裏側から見てみたところの哀切のようなものを感じさせてくれた.というところで、ちょっと休んで、39冊目に、そう、39というと何の関係もないが、クイーンの”39”という曲があって、個人的にはたいそう好きなのであるが.その次に、姫野カオルコの『リアル・シンデレラ』を読んだが、これは、一人で読んだというのではなく、読書会に参加させてもらって、その場でああでもない、こんなことではないかなどと言いながら読んだのであるが、倉島泉という不思議な、あるいは不思議への傾いてゆく女性をめぐる物語は、多種多様な意見を交わすうちに、本を読むことそのものへの喜びみたいなものへと誘われる経験であったような気がしたのである.で、今年になってから40冊目にあたるのは、これも目の前にある興味にそそられて読んだのであるが、司馬遼太郎の『草原の記』である.それは、チンギス・ハーンの息子オゴタイ、20世紀を生きた一人のモンゴル人女性を描きだしている、なかなかに味わい深い本であった.いまのところそんな感じで、来週からモンゴルへ飛ぶ.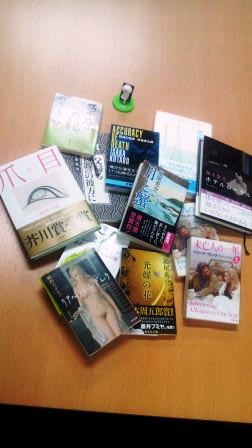
最新の画像[もっと見る]










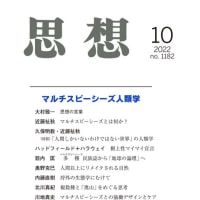

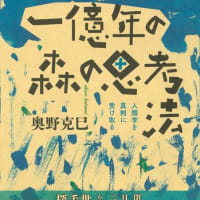
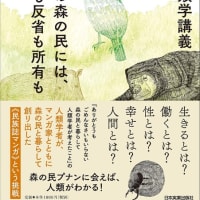



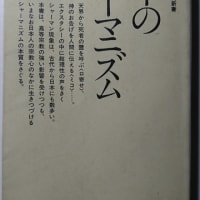


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます