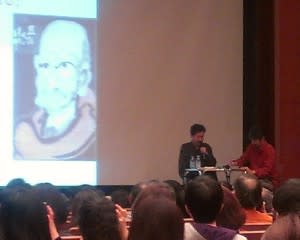〇国立劇場 2月雅楽公演『舞楽:太平楽(たいへいらく)一具/大曲 古鳥蘇(ことりそ)』(2月25日、14:00~)
毎年、この時期に行われる宮内庁式部職楽部の舞楽公演に行ってきた。今年は私の大好きな「太平楽」が演じられると聞いて、絶対に行きたいと思った。
「太平楽」は左方(オレンジ色を着る)の式舞。私は、たぶん今上天皇の御即位十年記念の宮内庁楽部公演(1999年)が初見、2012年の『四天王寺の聖霊会 舞楽四箇法要』公演が二度目、2013年に『天理大学雅楽部 北海道公演』でも見ている。国家の慶事には必ず演じられる舞で、人気も高いのだと思う。
プログラムの解説によると、「調子」「道行(朝小子/ちょうこし)」「破(武昌楽/ぶしょうらく)」「急(合歓塩/がっかえん)」「急 重吹/しげぶき」から構成される大曲で、今回は全曲を通して演奏されるが、一般にはその一部を省略することが多いとのこと。確かに、今回、思ったより長い感じがした。
「文化デジタルライブラリー」の解説を参考にすると、舞人が入場する前の前奏曲が「調子」。次に「道行」の演奏に合わせて、鉾を携えた四人の舞人たちが舞台に上がる。「破」(ゆるやかなリズム)では、前半、鉾を床に横たえて空手で舞う。両手とも人差指と中指だけをピンと伸ばしたかたちを崩さない。剣印とか刀印とかいうのだそうだ。途中からは鉾を持って舞う。「急」(速いリズム)では、再び鉾を横たえ、太刀を抜いて舞う。雅楽にしては、かなり動きが速い。最後は、再びゆるやかなリズムに戻り、鉾を掲げ、大地を踏み固めて退場。
さすが宮内庁楽部で、衣装は豪華絢爛であった。優雅なオレンジ色の長い裾(きょ)、純白の沓(くつ)、そして金銀の鎧・兜がキラキラ光る。プログラムに楽部の方が体験談を書いているが、兜と頭の間に空間があるので、鐘の真下にいるような状態になり「ゴーン」と音が鳴り響いて聞こえるとか、鎧は革製の小札(こざね)で出来ているので動くと「ミシミシ」軋む音がするとか、舞台に立たなければ分からない苦労がしのばれて興味深かった。動物の顔をした肩喰(かたくい)、帯喰(おびくい)は、舞人によって違う顔形をしているのだそうだ。二階席からでは、とても判別できなかったけれど、覚えておこう。
「古鳥蘇」は右方高麗楽。たぶん初めて見た。右方だから緑色の衣装で登場すると思っていたら、緑色の袍は肩脱ぎしていて、下襲の袖口のオレンジ色が目立つ。巻纓老懸の武官の冠。六人舞。長い袖をひらめかせながら、深く腰を落として、ゆっくり左右に移動しながら舞う。六人が順々に退場して、これで終わりかと思ったら、二人が何か不思議な得物を持って再登場した。長煙管の先に白い毛が植わった、細い払子のようにも見えるもので、後参桴(ごさんばち)というのだそうだ。これを振りながら二人で舞って終わった。
毎年、この時期に行われる宮内庁式部職楽部の舞楽公演に行ってきた。今年は私の大好きな「太平楽」が演じられると聞いて、絶対に行きたいと思った。
「太平楽」は左方(オレンジ色を着る)の式舞。私は、たぶん今上天皇の御即位十年記念の宮内庁楽部公演(1999年)が初見、2012年の『四天王寺の聖霊会 舞楽四箇法要』公演が二度目、2013年に『天理大学雅楽部 北海道公演』でも見ている。国家の慶事には必ず演じられる舞で、人気も高いのだと思う。
プログラムの解説によると、「調子」「道行(朝小子/ちょうこし)」「破(武昌楽/ぶしょうらく)」「急(合歓塩/がっかえん)」「急 重吹/しげぶき」から構成される大曲で、今回は全曲を通して演奏されるが、一般にはその一部を省略することが多いとのこと。確かに、今回、思ったより長い感じがした。
「文化デジタルライブラリー」の解説を参考にすると、舞人が入場する前の前奏曲が「調子」。次に「道行」の演奏に合わせて、鉾を携えた四人の舞人たちが舞台に上がる。「破」(ゆるやかなリズム)では、前半、鉾を床に横たえて空手で舞う。両手とも人差指と中指だけをピンと伸ばしたかたちを崩さない。剣印とか刀印とかいうのだそうだ。途中からは鉾を持って舞う。「急」(速いリズム)では、再び鉾を横たえ、太刀を抜いて舞う。雅楽にしては、かなり動きが速い。最後は、再びゆるやかなリズムに戻り、鉾を掲げ、大地を踏み固めて退場。
さすが宮内庁楽部で、衣装は豪華絢爛であった。優雅なオレンジ色の長い裾(きょ)、純白の沓(くつ)、そして金銀の鎧・兜がキラキラ光る。プログラムに楽部の方が体験談を書いているが、兜と頭の間に空間があるので、鐘の真下にいるような状態になり「ゴーン」と音が鳴り響いて聞こえるとか、鎧は革製の小札(こざね)で出来ているので動くと「ミシミシ」軋む音がするとか、舞台に立たなければ分からない苦労がしのばれて興味深かった。動物の顔をした肩喰(かたくい)、帯喰(おびくい)は、舞人によって違う顔形をしているのだそうだ。二階席からでは、とても判別できなかったけれど、覚えておこう。
「古鳥蘇」は右方高麗楽。たぶん初めて見た。右方だから緑色の衣装で登場すると思っていたら、緑色の袍は肩脱ぎしていて、下襲の袖口のオレンジ色が目立つ。巻纓老懸の武官の冠。六人舞。長い袖をひらめかせながら、深く腰を落として、ゆっくり左右に移動しながら舞う。六人が順々に退場して、これで終わりかと思ったら、二人が何か不思議な得物を持って再登場した。長煙管の先に白い毛が植わった、細い払子のようにも見えるもので、後参桴(ごさんばち)というのだそうだ。これを振りながら二人で舞って終わった。