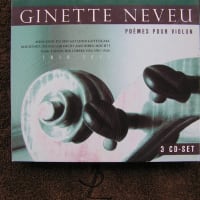その昔、「ジャック・ランスロ」というクラリネット奏者がいた。
新聞の三面記事の下の方にちょっとした死亡欄があって次のような記事を切り抜いて保存している。
ジャック・ランスロさん(仏のクラリネット奏者)
7日、心不全で死去、88歳。
フルート奏者の故ジャン・ピエール・ランパル氏と並び、フランスの管楽器界を代表する存在だった。浜中浩一、横川晴児両氏をはじめ、日本でも多くの後進を育成。楽器の改良にも貢献した。
享年88歳とはなかなかの長寿を全うしたことになる。世界に誇る日本人男性の平均寿命でさえ81歳なんだから。
「管楽器奏者は肺活量がモノをいうので若い頃からその辺を鍛えていたのが長生きの原因ではないか」というのが自分の憶測。
名著「西方の音」(五味康祐著)に、フランス人に管楽器の名手が多いのはフランス語の発音(唇や舌の使い方)が管楽器の演奏にマッチしていて幼児の頃から訓練されているからなんて記載があったのをふと思い出した。
そういえばポピュラー音楽のジャンルに入るが、トランペット奏者の「ジャン・クロード・ボレリー」もフランス人。
さて、ランスロといえばモーツァルトの「クラリネット協奏曲」(K622)が有名で、これは同じフランス出身のフルート奏者ランパルの「フルートとハープのための協奏曲」(K299)とカップリングになっているCD盤がある。

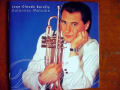
ただし演奏曲目としては「フルートと・・・」の方が有名で、これは昔から極め付きの名曲、名演(ランパル~ハープのラスキーヌ~パイヤール指揮)とされていて、モーツァルト・ファンでこのCDを持っていない人はモグリであると断言しても差し支えないほど。
作品の方は旅先での母親の死という悲運に見舞われたパリ時代(二度目)の22歳のときのもので、ある貴族とその娘さんが共演するための曲目として作曲を依頼されたもので典雅で叙情的な旋律、とりわけ第二楽章は筆舌に尽くしがたいほどの美しい調べ。
さて、肝心のランスロによるクラリネット協奏曲の方だがこれもいい演奏だとは思うが、ひと昔前はレオポルト・ウラッハ(ウィーン)の演奏したものが極上とされていた。しかし、惜しいことに録音年次が古くてこれはモノラル録音。
両方の演奏ともにずっと以前に購入して既に聴いてそれなりの感想を持ってはいるのだが、その頃とは随分とオーディオ装置も変わったことだしと久しぶりに聴き比べてみた。
クラリネットは柔らかく甘美な響きを持ち、聴き手をほのぼのとした気分に誘い込みながら自然と森の情景の詩人にしてしまう不思議な楽器である。


左が「クラリネット協奏曲、右が「クラリネット五重奏曲」。
やはり当時聴いたときと同じ印象で音質(録音)は劣るものの晩年のモーツァルトの内面的な渋さ、あのオペラ「魔笛」にも共通した「うら淋しさ」と「透明感」を求めるとなるとウラッハに一日の長があるように思う。
特に第二楽章のアダージョの深く精神的な味わいは「モーツァルトが死の近いことを予感しつつ作曲した辞世の歌」とされているが、いたずらに感傷に流されることなくふくよかでゆったりとしたクラリネットの音色が自然に拡がっていくのはウラッハならではの枯淡の境地。
ウラッハ以後のクラリネット奏者では、ランスロも含めてプリンツ、ライスター、シュミードルなどの名手がいるが個人的にはちょっと物足りない。
近年ではどういうアーティストがいるんだろうかと思って手持ちの「ウィーンフィル・ベルリンフィル最新パーフェクトガイド」(音楽の友社刊)をひも解いてみると、現在はウィーン・フィルの首席が当年とって34歳の気鋭ダニエル・オッテンザマーで、ブルリンフィルではヴェンツェル・フックスだ。
両者とも、新たにCDを購入するほどのこともないと思うので「NHKの音楽館」(Eテレ)や早朝の「BSプレミアム」が頼りだけど、おそらく登板は望み薄でしょうね(笑)。
この内容に共感された方は励ましのクリックを →