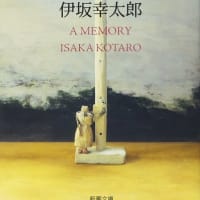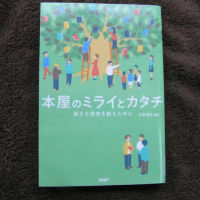日常茶飯事のように、DAC、プリアンプ、パワーアンプ、あるいはケーブルを入れ替えながら「ああでもない、こうでもない」とオーディオを毎日楽しんでいるが、その結果を、つまり「どういう音質になったのか」をいざブログに書こうとなると、いつも困り果ててしまう。
一番大切なポイントなのに、どう表現したらいいのか・・(笑)。
正確に表現できない「もどかしさ」をいつも感じているが、これが「嗅覚」や「味覚」となると様相が一変する。
たとえば「思索紀行」(立花 隆)の中の「ワインの香りと味」についての表現なんか実に豊かなんですよね~。
抜き書きしてみると、
✰ ワインのプロの間では試飲の仕方が完全に様式として確立されている。そして言葉で匂いと味わいを表現しなければならない。さらには、その表現力をどれだけ身に付けているかで「匂いと味きき」の能力が試される。
✰ 匂いの表現方法にはなんと百種以上ある。たとえば天然の香りが次々にあげられ、初めはたいてい花の香りから始まる。スミレ、ジャスミンなど、あらゆる花の名前が登場してきて、次に果物の香りとしてリンゴ、イチゴさらにはアーモンドなどのナッツ類も登場する
ほかにも、本書では「味覚」「嗅覚」の表現の豊かさについて事細かに述べられているが、それに比べて「聴覚=音質」の表現の難しさについて嘆かざるを得ない。
たとえば「スミレの香りみたいな音」といってもチンプンカンプンですよね(笑)。
したがって「音の表現」についてもワインのように様式として確立し、もっと豊かで感覚的に分かりやすい表現ができないものだろうかと、いつも思う。
ちなみに、オーディオ誌などで「音質」に関して常用される言葉としてアトランダムに挙げると「光沢」「色艶」「彫琢」「奥行き感」「スケール感」「透明感」「いぶし銀」「色気」「音像定位」「原音」などで、ほかにもいろいろありそうだがすぐには思い浮かばない。
そもそも、味覚細胞や嗅覚細胞には対象となる超微粒子が直接触れてくるが、聴覚細胞に届くのはせいぜい「空気の波」に過ぎないのだから仕方がないのかもしれませんね。
ちなみに「チャットGPT」で「音質を表現する言葉」で、打ち込んでみたら次のような文章が出てきましたよ。
「音質を表現する言葉には以下のようなものがあります。
1 クリアな :音がクリアで透明感があることを表現する
2 暖かい :音が柔らかく、心地よい印象を与えることを表現する
3 明瞭な :音が明確で聞き取りやすいことを表現する
4 豊かな :音が豊かで奥行きがあることを表現する
5 ナチュラルな :音が自然で加工されていないような印象を与えることを表現する
6 ダイナミックな :音がダイナミックでパワフルな印象を与えることを表現する
7 フラットな :音が平坦で特に強調された周波数がないことを表現する
8 ディテールが豊富な :音の細かなディテールが豊富で聴き手に細部まで伝わることを表現する
9 サウンドステージが広い :音の広がりが広く、空間的な印象があることを表現する
10 サウンドバランスが良い :音のバランスが良く楽器や声がバランスよく聞こえることを表現する」
とまあ、以上のとおりです。
単に「いい音だ」と片付けるよりも、これら10項目に亘って言及するとかなり具体的なイメージが湧いてくる気がしますよ。
「チャットGPT」・・、なかなか捨てたもんじゃないとは思いませんかね~(笑)。
この内容に共感された方は励ましのクリックを →