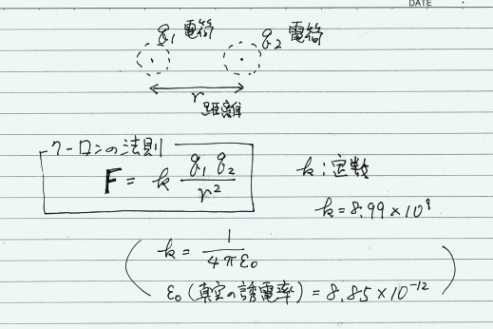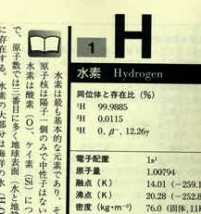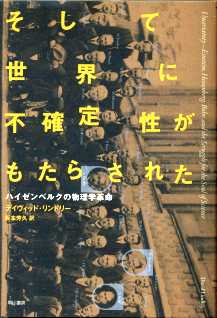中野サンプラザ。
中野サンプラザは中野駅の北口すぐにあります。写真のとおり、△形の建物です。
僕が東京に出てきて最初に住んだ街が中野。ずいぶん昔の話ですが。 僕の住んだ部屋は中野駅の南側にあって、中野公会堂や堀越高校の近くでした。
引っ越してきた翌日の朝に僕は、中野サンプラザの横にある中野区役所に転入届けを出しに行き、ついでに中野サンプラザの中に入ってみました。
この建物の一階は広いフロアになっていて、ガラス張りなので明るい光が燦燦と入ってきます。(←そうか、だから「サンプラザ」なのね!) 今はどうなっているか知りませんが、奥にプレイガイドがあり、窓側にはソファーが広々と並んでいました。
さて僕はそのソファーに座り煙草をとりだして…、向こう側にはカップルが座っていましたが…「んん!?」 なんと、男が、女の腹や胸を触りながら、おだやかに会話しているじゃあ~りませんか! 午前中の、こんなに明るい光のなかで!
それは…? あり、なのか?
「う、うーん…。 東京って、すごいところだ。」
と、心の中で僕は感想をもらしました。 (東京っていったって、人が多いだけのことさ)、基本的にそのように考えていた僕は、(いや自分が間違っていた、考えを改めねばならぬ)とこの時、悟ったのです!!
しばし休憩して、さあ帰ろう、と立ち上がったとき、フロアの真ん中にある階段から、ぞろぞろと制服姿の男女が出てきました。堀越高校の制服でした。 この日、中野サンプラザの大ホールで入学式が行われていたようです。
以上、中野サンプラザのおもいで話でした。
そうそう、数年前、ここで将棋を指しました。 アマ竜王戦(東京都予選)だったかな…、2連敗で悄然…(笑)。 さすが東京…、強いわ。
その日のサンプラザの大ホールでは、「古武術発表会」なるものが開催されており、無料だったので、ちょっと見学。 それからラーメン食べて帰りました。

中野サンモール。 これも北口。
つまりはどこにでもある商店街なのですが、この奥に例の「中野ブロードウェイ」があり、それが中野サンモールの特別なところ。 「まんだらけ」には住んでいた当時も数回行ったことがありますが、当時はまだ小さなまんが専門の古本屋にすぎず、中野も現在のようなフィギアのメッカではまだありませんでした。
その「中野ブロードウェイ」に行ってみました。 初体験のようなもの。

撮影許可を得て、ショーケースを写す。
ヒーロー達…いや、ヒーローのコピー達…。
うーん、彼らにとってしあわせな場所とはどこなのか?

せっかくなので、1コ、買う。 ミクラスじゃ~、¥350。
カプセル怪獣とは、そもそも何なのか、誰かおしえてくれぬかの~。
余談ですが、サンプラザ中野の北のこのあたりには、「二人組の警官」の幽霊がよく出ます。――というのは半分ウソで、幽霊ではなく、「リアル警官二人組」にちょくちょく出会います。僕の友人が当時そのあたりに住んでいまして、遊びに行く途中、僕もよく出会いました。東京はなんて警官が多いところか、と僕はおどろきました。 一日に何度も出会うのですから!
これにはカラクリがあるのでした。 というのは、昔、陸軍中野学校(←スパイ養成学校!)がこのあたりに在りまして、その流れで、警官の学校とか寮とかそのようなものがそこにあったのでした。 今はどうなのか、とか、詳しいことは知りません。
中野サンプラザは中野駅の北口すぐにあります。写真のとおり、△形の建物です。
僕が東京に出てきて最初に住んだ街が中野。ずいぶん昔の話ですが。 僕の住んだ部屋は中野駅の南側にあって、中野公会堂や堀越高校の近くでした。
引っ越してきた翌日の朝に僕は、中野サンプラザの横にある中野区役所に転入届けを出しに行き、ついでに中野サンプラザの中に入ってみました。
この建物の一階は広いフロアになっていて、ガラス張りなので明るい光が燦燦と入ってきます。(←そうか、だから「サンプラザ」なのね!) 今はどうなっているか知りませんが、奥にプレイガイドがあり、窓側にはソファーが広々と並んでいました。
さて僕はそのソファーに座り煙草をとりだして…、向こう側にはカップルが座っていましたが…「んん!?」 なんと、男が、女の腹や胸を触りながら、おだやかに会話しているじゃあ~りませんか! 午前中の、こんなに明るい光のなかで!
それは…? あり、なのか?
「う、うーん…。 東京って、すごいところだ。」
と、心の中で僕は感想をもらしました。 (東京っていったって、人が多いだけのことさ)、基本的にそのように考えていた僕は、(いや自分が間違っていた、考えを改めねばならぬ)とこの時、悟ったのです!!
しばし休憩して、さあ帰ろう、と立ち上がったとき、フロアの真ん中にある階段から、ぞろぞろと制服姿の男女が出てきました。堀越高校の制服でした。 この日、中野サンプラザの大ホールで入学式が行われていたようです。
以上、中野サンプラザのおもいで話でした。
そうそう、数年前、ここで将棋を指しました。 アマ竜王戦(東京都予選)だったかな…、2連敗で悄然…(笑)。 さすが東京…、強いわ。
その日のサンプラザの大ホールでは、「古武術発表会」なるものが開催されており、無料だったので、ちょっと見学。 それからラーメン食べて帰りました。

中野サンモール。 これも北口。
つまりはどこにでもある商店街なのですが、この奥に例の「中野ブロードウェイ」があり、それが中野サンモールの特別なところ。 「まんだらけ」には住んでいた当時も数回行ったことがありますが、当時はまだ小さなまんが専門の古本屋にすぎず、中野も現在のようなフィギアのメッカではまだありませんでした。
その「中野ブロードウェイ」に行ってみました。 初体験のようなもの。

撮影許可を得て、ショーケースを写す。
ヒーロー達…いや、ヒーローのコピー達…。
うーん、彼らにとってしあわせな場所とはどこなのか?

せっかくなので、1コ、買う。 ミクラスじゃ~、¥350。
カプセル怪獣とは、そもそも何なのか、誰かおしえてくれぬかの~。
余談ですが、サンプラザ中野の北のこのあたりには、「二人組の警官」の幽霊がよく出ます。――というのは半分ウソで、幽霊ではなく、「リアル警官二人組」にちょくちょく出会います。僕の友人が当時そのあたりに住んでいまして、遊びに行く途中、僕もよく出会いました。東京はなんて警官が多いところか、と僕はおどろきました。 一日に何度も出会うのですから!
これにはカラクリがあるのでした。 というのは、昔、陸軍中野学校(←スパイ養成学校!)がこのあたりに在りまして、その流れで、警官の学校とか寮とかそのようなものがそこにあったのでした。 今はどうなのか、とか、詳しいことは知りません。
















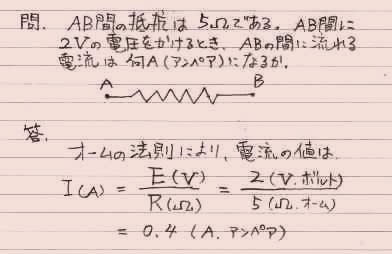

 キャベンディッシュの原稿
キャベンディッシュの原稿