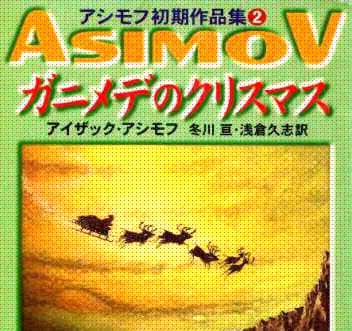ケアルである。 SFファンでありながら、ケアルを知らないなんてことはあるはずがない、ていうくらいに有名な猫型宇宙怪物、それがケアルである。
この怪物はヴァン・ヴォークトの『宇宙船ビーグル号の冒険』に登場する。この本は、僕が「SF」というものを読むようになったきっかけをつくってくれた本でもある。(そのことは、以前に述べた。)
この『宇宙船ビーグル号の冒険』はいくつかの宇宙怪物(ベム)が登場するが、その最初に出てくるのが「ケアル」。
〔 … 巨大な前脚がおののいて、かみそりのように鋭い爪の一本一本がむき出しになった。肩から生えた太い触手が、緊張してゆれている。猫に似た大きな顔を左右に揺ゆすると、ケアルは耳の代りにある毛のような巻きひげを必死に震わせ、…〕
これは創元SF文庫のものから。 ところが今では早川書房からも出ていて、そっちでは「クァール」となっている。原文は「Couerl」らしいから、クァールが近いのだろうけど、昔読んだ人は皆「ケアル」で慣れ親しんできていると思う。こういう大事なところは統一してほしいものだ。「ケアル」と「クァール」では、別の生き物のように感じるよ。
〔遠い地平線のはるか上空に、一つの小さな光る点が現われたのである。その点はみるみる大きくなり、巨大な金属の球となった。超大型の、球状をした宇宙船だった。磨きあげた銀のように、光る球体は、ケアルの頭上を風を切って通過したが、減速していることがはっきりわかる。 … 〕
これが宇宙船ビーグル号だ。科学者、軍人を1000人乗せて、宇宙探査をしている。
ビーグル号は、下の文庫本のカバー絵を見てもわかるように、球形、つまり真ん丸のカタチをした宇宙船なのだ。
〔ケアルののどは激しいかわきに息づまり、イドの振動を発散する、このいかにも弱々しい生物たちに襲いかかって、叩きつぶしてやりたい衝動が、彼の目をくらませた。〕
「イド(細胞原形質)」というのが、唯一のケアルの食料で、この惑星の生き物がほとんどすべて息絶えてしまったので、ケアル自身も飢えて死んでしまうところだった。そこに、宇宙船がやってきた。その宇宙船から「いかにも弱々しい生物たち」が出てきた。彼らのイドを食いたい! (ケアルの食料になるイドは殺したばかりの生物にしか存在しないのだ。)
ケアルには知性もあった。おとなしい大きな猫のふりをして人間に近づいて宇宙船に入りこむ。
知性があるというのは、しかし、その程度ではない。宇宙船を乗っ取って運転することだってしちゃうのだ。肩の触手で、機械の改造だってできちゃう。
ケアルの能力はそれだけじゃない。物質の、原子の配列だって変えてしまう。壁を溶かしたり、逆に、超金属に変質させたり…。
そんな、すご~い、黒猫ちゃんなのだ。

このケアルの話が、ヴァン・ヴォークトのデビュー作にして出世作『黒い破壊者』(『Black Destroyer』)なのだ。これは<アスタウンディング・サイエンスフィクション>1939年7月号に載った。しかもこの雑誌の表紙絵もこの話を元に描かれた絵になっている。SFファンはこのかつていなかったタイプの宇宙猫に興奮し、この年、ヴォークトは人気NO.1作家となった。
つまりケアルは、夏目漱石においての、あの「名前のない猫」のようなフシギ猫なのである。それはSF黄金期の幕開けを告げるためにやってきた宇宙怪物であった、ともいえる。
ずっと後で、ヴォークトの宇宙怪物のこのシリーズが、『宇宙船ビーグル号の冒険』として一冊の本になった。日本語でこれが読めるようになったのは、1960年代のことになる。
さて、野田昌宏というSF作家がいる。今年6月に74歳で死んでしまったから、いた、というべきところだが。 元々本職はTVプロデューサーで、『開けポンキッキ』を創ったのがこの人。麻生太郎現総理のいとこでもある。
この野田昌宏さん、SFファンの間では「野田大元帥」などと呼ばれていたが、彼の書いた『スペースオペラの読み方』という本の中に、アイザック・アシモフと会った時のことが書かれているので以下に紹介しよう。
1969年7月27日、アポロ11号によって遂に人類は月面に到達した。その時、ニューヨークの新聞紙に載ったアイザック・アシモフのコメントは次のようなものだったそうだ。
「ゴダードよ、今、われわれは月にいる!」
これを知ったときは涙が出そうになった、と野田さんは書いている。
ゴダードとは、アメリカのロケットの父とよばれる人で、少年時代にウェルズのSF小説を読んでロケットを月まで飛ばすことを夢見てそれを実現することを生涯の目的とし、1926年に液体燃料によるロケットの最初の打ち上げ実験をした。わずか10数メートルの飛行だが、これが始まりだった。その後、マスコミからの批判もあったが、彼はロケット打ち上げへの情熱を失うことはなかった。しかし、宇宙への夢は実現することなく、1945年にその生涯を閉じた…ゴダードとはそういう人である。
それで、野田昌宏さんのTV番組の制作会社テレワークが、その人類月面到達の特集番組を作ることになったとき、そのメインキャラとしてアイザック・アシモフを使いたい、と野田さんは考えたのだ。アシモフ氏との交渉の結果、その仕事の了解は得られた。
SFの熱烈なファンでもある野田さんは、仕事とは別に、あのアシモフと会えるというだけでも感激だ。しかし…、この仕事が始まる時、制作本部長がこう言ったという。
「アイザック・アシモフ氏は煙草が嫌いです。服に残っている煙草の煙も嫌がるそうです。スタッフ全員、明日は本番終了まで絶対禁煙を守ってもらいたい。アシモフはとても神経質な人で…」
野田昌宏は緊張しながらアシモフ邸へ向かった。チャイムを押してドアが開くと、そこには、あの写真で見た通りのアイザック・アシモフが立っていた!
そして居間に通され、さっそく打ち合わせ。 野田さんは資料を取り出した。
その時である!
「おッ!」
アシモフは鋭い声を挙げた。
「君はその雑誌まで持っているのか!」

「その雑誌」とは、<アスタウンディング・サイエンスフィクション>1939年7月号であった。そう、アシモフの『趨勢』が初めてジョン・W・キャンベルに認められて載り、ヴァン・ヴォークトの『黒い破壊者』のケアルと宇宙船が表紙絵を飾ったあの号である!
それをきっかけとして、アシモフと野田さんは、一気にうちとけた関係になったのである。野田昌宏さんは、それほどの筋金入りSFマニアなのだった。野田さんは、巨匠アシモフに向かって、言葉をほとばしらせた。もちろん英語で。自分たち日本のSFファンは、大戦後、腹をすかせた毎日の中で、アメリカ兵が読み捨てた紙くずの中から、SF雑誌を拾って読み、そうやって私はあなたのSF小説も知ったのですよ! 『われはロボット』や『宇宙気流』を! アシモフは、しみじみと頷きつつ、黙って野田さんの話を聞いてくれたという。
野田さんは心が震え、そして後でこう思ったそうだ。
“SF”しといてよかった…。
それからアシモフは、野田さんらを相手に、30分ほど、いろいろな話をしてくれた。そして「妻は若い時からずっと日本へ行きたいと言い続けているんだよ」とも言った。 野田さんが、それはいいですね、是非来てくださいと言うと、アシモフ 「それが君、私は飛行機が嫌いだし…」
アシモフは飛行機に乗れないのだ。高所恐怖症なのである。
そのことにアシモフ自身が気づいたのは、あのアイリーンとのデートの時である。恋に破れたアシモフは、口ひげを生やし、そして海に行った。ちなみに、アシモフは、ブルックリンに住んでいながら、この時20歳になって初めて海を見たのだという。自由の女神像のある港の風景は眺めていたが、広々とした外洋(大西洋)の海をそれまで見たことがなかったと。世間知らずのアシモフ青年にとって、それも「冒険」だったようだ。初めて海の水につかり、「大人になった気分」(←笑)を味わった。だが、彼は、その後も泳げるようにはならなかった。足を大地から離すことが恐かったから。
『アシモフ自伝』の中にも、<アスタウンディング>1939年7月号こそ、SF黄金時代の幕開けであったとはっきり書かれている。
ところで、ヴォークトの『宇宙船ビーグル号の冒険』はケアルに始まって、ほかにも地球には存在しえないような不思議な生命体が登場する。子どものときに僕がいちばん恐かったのが「イクストル」という怪物である。これは赤い怪物で、人間に卵を産みつけようとする。後の映画『エイリアン』の原型のような話である。
40年代のアメリカのSFの人気は、1にヴォークト、2にハインラインであったようだ。ところが、ヴァン・ヴォークトは、ハインラインやアシモフのように後に「巨匠」とはあまり呼ばれない。なぜか?
ヴォークトのSFは、そのSF的設定や心理描写が細やかなところが人気だった。そして発想が普通じゃない。
ヴォークトは『黒い破壊者』でデビュー後もその才能をいかんなく発揮、傑作を書き続けた。ところがだんだん「普通じゃない発想」がさらに加速して、わけがわからなくなり、本人も「科学」の枠を跳び越して、妙な「超科学」のような世界にはまり、そして偉大なSF編集長キャンベルまでそういうインチキ科学(超人類の誕生とか反重力の発明とかを本気で実現させようと考えていたのかも)にはまり、読者を宇宙の辺境に置き去りにしてしまったのである。 つまり、ヴォークトとキャンベルは、どうやら、「才能があふれすぎてしまった」ようである。脳みそが溶けかけてしまったのだろう。
この二人、存在自体が、まるで「遊星からの物体X」の怪物のようではないか。
◇ ◇ ◇ ◇
今年はこれでおしまい。また来年。
では、皆様、よいお年を。
この怪物はヴァン・ヴォークトの『宇宙船ビーグル号の冒険』に登場する。この本は、僕が「SF」というものを読むようになったきっかけをつくってくれた本でもある。(そのことは、以前に述べた。)
この『宇宙船ビーグル号の冒険』はいくつかの宇宙怪物(ベム)が登場するが、その最初に出てくるのが「ケアル」。
〔 … 巨大な前脚がおののいて、かみそりのように鋭い爪の一本一本がむき出しになった。肩から生えた太い触手が、緊張してゆれている。猫に似た大きな顔を左右に揺ゆすると、ケアルは耳の代りにある毛のような巻きひげを必死に震わせ、…〕
これは創元SF文庫のものから。 ところが今では早川書房からも出ていて、そっちでは「クァール」となっている。原文は「Couerl」らしいから、クァールが近いのだろうけど、昔読んだ人は皆「ケアル」で慣れ親しんできていると思う。こういう大事なところは統一してほしいものだ。「ケアル」と「クァール」では、別の生き物のように感じるよ。
〔遠い地平線のはるか上空に、一つの小さな光る点が現われたのである。その点はみるみる大きくなり、巨大な金属の球となった。超大型の、球状をした宇宙船だった。磨きあげた銀のように、光る球体は、ケアルの頭上を風を切って通過したが、減速していることがはっきりわかる。 … 〕
これが宇宙船ビーグル号だ。科学者、軍人を1000人乗せて、宇宙探査をしている。
ビーグル号は、下の文庫本のカバー絵を見てもわかるように、球形、つまり真ん丸のカタチをした宇宙船なのだ。
〔ケアルののどは激しいかわきに息づまり、イドの振動を発散する、このいかにも弱々しい生物たちに襲いかかって、叩きつぶしてやりたい衝動が、彼の目をくらませた。〕
「イド(細胞原形質)」というのが、唯一のケアルの食料で、この惑星の生き物がほとんどすべて息絶えてしまったので、ケアル自身も飢えて死んでしまうところだった。そこに、宇宙船がやってきた。その宇宙船から「いかにも弱々しい生物たち」が出てきた。彼らのイドを食いたい! (ケアルの食料になるイドは殺したばかりの生物にしか存在しないのだ。)
ケアルには知性もあった。おとなしい大きな猫のふりをして人間に近づいて宇宙船に入りこむ。
知性があるというのは、しかし、その程度ではない。宇宙船を乗っ取って運転することだってしちゃうのだ。肩の触手で、機械の改造だってできちゃう。
ケアルの能力はそれだけじゃない。物質の、原子の配列だって変えてしまう。壁を溶かしたり、逆に、超金属に変質させたり…。
そんな、すご~い、黒猫ちゃんなのだ。

このケアルの話が、ヴァン・ヴォークトのデビュー作にして出世作『黒い破壊者』(『Black Destroyer』)なのだ。これは<アスタウンディング・サイエンスフィクション>1939年7月号に載った。しかもこの雑誌の表紙絵もこの話を元に描かれた絵になっている。SFファンはこのかつていなかったタイプの宇宙猫に興奮し、この年、ヴォークトは人気NO.1作家となった。
つまりケアルは、夏目漱石においての、あの「名前のない猫」のようなフシギ猫なのである。それはSF黄金期の幕開けを告げるためにやってきた宇宙怪物であった、ともいえる。
ずっと後で、ヴォークトの宇宙怪物のこのシリーズが、『宇宙船ビーグル号の冒険』として一冊の本になった。日本語でこれが読めるようになったのは、1960年代のことになる。
さて、野田昌宏というSF作家がいる。今年6月に74歳で死んでしまったから、いた、というべきところだが。 元々本職はTVプロデューサーで、『開けポンキッキ』を創ったのがこの人。麻生太郎現総理のいとこでもある。
この野田昌宏さん、SFファンの間では「野田大元帥」などと呼ばれていたが、彼の書いた『スペースオペラの読み方』という本の中に、アイザック・アシモフと会った時のことが書かれているので以下に紹介しよう。
1969年7月27日、アポロ11号によって遂に人類は月面に到達した。その時、ニューヨークの新聞紙に載ったアイザック・アシモフのコメントは次のようなものだったそうだ。
「ゴダードよ、今、われわれは月にいる!」
これを知ったときは涙が出そうになった、と野田さんは書いている。
ゴダードとは、アメリカのロケットの父とよばれる人で、少年時代にウェルズのSF小説を読んでロケットを月まで飛ばすことを夢見てそれを実現することを生涯の目的とし、1926年に液体燃料によるロケットの最初の打ち上げ実験をした。わずか10数メートルの飛行だが、これが始まりだった。その後、マスコミからの批判もあったが、彼はロケット打ち上げへの情熱を失うことはなかった。しかし、宇宙への夢は実現することなく、1945年にその生涯を閉じた…ゴダードとはそういう人である。
それで、野田昌宏さんのTV番組の制作会社テレワークが、その人類月面到達の特集番組を作ることになったとき、そのメインキャラとしてアイザック・アシモフを使いたい、と野田さんは考えたのだ。アシモフ氏との交渉の結果、その仕事の了解は得られた。
SFの熱烈なファンでもある野田さんは、仕事とは別に、あのアシモフと会えるというだけでも感激だ。しかし…、この仕事が始まる時、制作本部長がこう言ったという。
「アイザック・アシモフ氏は煙草が嫌いです。服に残っている煙草の煙も嫌がるそうです。スタッフ全員、明日は本番終了まで絶対禁煙を守ってもらいたい。アシモフはとても神経質な人で…」
野田昌宏は緊張しながらアシモフ邸へ向かった。チャイムを押してドアが開くと、そこには、あの写真で見た通りのアイザック・アシモフが立っていた!
そして居間に通され、さっそく打ち合わせ。 野田さんは資料を取り出した。
その時である!
「おッ!」
アシモフは鋭い声を挙げた。
「君はその雑誌まで持っているのか!」

「その雑誌」とは、<アスタウンディング・サイエンスフィクション>1939年7月号であった。そう、アシモフの『趨勢』が初めてジョン・W・キャンベルに認められて載り、ヴァン・ヴォークトの『黒い破壊者』のケアルと宇宙船が表紙絵を飾ったあの号である!
それをきっかけとして、アシモフと野田さんは、一気にうちとけた関係になったのである。野田昌宏さんは、それほどの筋金入りSFマニアなのだった。野田さんは、巨匠アシモフに向かって、言葉をほとばしらせた。もちろん英語で。自分たち日本のSFファンは、大戦後、腹をすかせた毎日の中で、アメリカ兵が読み捨てた紙くずの中から、SF雑誌を拾って読み、そうやって私はあなたのSF小説も知ったのですよ! 『われはロボット』や『宇宙気流』を! アシモフは、しみじみと頷きつつ、黙って野田さんの話を聞いてくれたという。
野田さんは心が震え、そして後でこう思ったそうだ。
“SF”しといてよかった…。
それからアシモフは、野田さんらを相手に、30分ほど、いろいろな話をしてくれた。そして「妻は若い時からずっと日本へ行きたいと言い続けているんだよ」とも言った。 野田さんが、それはいいですね、是非来てくださいと言うと、アシモフ 「それが君、私は飛行機が嫌いだし…」
アシモフは飛行機に乗れないのだ。高所恐怖症なのである。
そのことにアシモフ自身が気づいたのは、あのアイリーンとのデートの時である。恋に破れたアシモフは、口ひげを生やし、そして海に行った。ちなみに、アシモフは、ブルックリンに住んでいながら、この時20歳になって初めて海を見たのだという。自由の女神像のある港の風景は眺めていたが、広々とした外洋(大西洋)の海をそれまで見たことがなかったと。世間知らずのアシモフ青年にとって、それも「冒険」だったようだ。初めて海の水につかり、「大人になった気分」(←笑)を味わった。だが、彼は、その後も泳げるようにはならなかった。足を大地から離すことが恐かったから。
『アシモフ自伝』の中にも、<アスタウンディング>1939年7月号こそ、SF黄金時代の幕開けであったとはっきり書かれている。
ところで、ヴォークトの『宇宙船ビーグル号の冒険』はケアルに始まって、ほかにも地球には存在しえないような不思議な生命体が登場する。子どものときに僕がいちばん恐かったのが「イクストル」という怪物である。これは赤い怪物で、人間に卵を産みつけようとする。後の映画『エイリアン』の原型のような話である。
40年代のアメリカのSFの人気は、1にヴォークト、2にハインラインであったようだ。ところが、ヴァン・ヴォークトは、ハインラインやアシモフのように後に「巨匠」とはあまり呼ばれない。なぜか?
ヴォークトのSFは、そのSF的設定や心理描写が細やかなところが人気だった。そして発想が普通じゃない。
ヴォークトは『黒い破壊者』でデビュー後もその才能をいかんなく発揮、傑作を書き続けた。ところがだんだん「普通じゃない発想」がさらに加速して、わけがわからなくなり、本人も「科学」の枠を跳び越して、妙な「超科学」のような世界にはまり、そして偉大なSF編集長キャンベルまでそういうインチキ科学(超人類の誕生とか反重力の発明とかを本気で実現させようと考えていたのかも)にはまり、読者を宇宙の辺境に置き去りにしてしまったのである。 つまり、ヴォークトとキャンベルは、どうやら、「才能があふれすぎてしまった」ようである。脳みそが溶けかけてしまったのだろう。
この二人、存在自体が、まるで「遊星からの物体X」の怪物のようではないか。
◇ ◇ ◇ ◇
今年はこれでおしまい。また来年。
では、皆様、よいお年を。