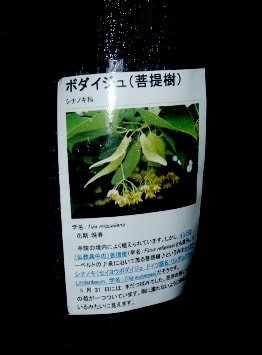1ヶ月前、医者に処方された机の引き出しの中の「目薬」のケースがかじられて中身がなくなっていた…。 なぜこれを狙う!?
一週間ほど前のある日、ラジオを聴こうとしたら機械が発動しない。調べたらコードが一部むき出しに!!
そして今日!
パソコンの「キー」が3つなくなっている!!!
おいおいおい! おいおい! おいっ!
こりゃあもう本格的に「ねずみ問題」をかんがえにゃならん。ここまで先延ばしにしてきたが…。
だけどねえ…。 僕は君達と話し合いがしたいよ。(それとも、既に‘戦争’は始まっているのかい?)
それにしても、ねずみって本当に「ちゅーちゅーちゅー」って鳴くんだねえ。
あれはどういう意味なんだろう…。
一週間ほど前のある日、ラジオを聴こうとしたら機械が発動しない。調べたらコードが一部むき出しに!!
そして今日!
パソコンの「キー」が3つなくなっている!!!
おいおいおい! おいおい! おいっ!
こりゃあもう本格的に「ねずみ問題」をかんがえにゃならん。ここまで先延ばしにしてきたが…。
だけどねえ…。 僕は君達と話し合いがしたいよ。(それとも、既に‘戦争’は始まっているのかい?)
それにしても、ねずみって本当に「ちゅーちゅーちゅー」って鳴くんだねえ。
あれはどういう意味なんだろう…。
この稿は、じつはすでに先々月に書いていたもの。なんとなくそのままにしていたのですが、やっと画をつけました。 (長いッスよ~。詰め込みすぎ…ですかね?)
「ノーチラス。 北緯。 90度。」というのは、世界的に有名なセリフなのだそうです。(僕はこの歳になるまで知りませんでしたが。)
アメリカの原子力潜水艦ノーチラス号がついに北極点に到達した時のアンダーソン艦長がワシントンに打った電報の言葉です。1958年8月3日のこと。
同じ年1958年の暮れ12月に、日本ではプラモデル「原子力潜水艦ノーチラス号」(1/300)が発売された。これが“日本初のプラモデル”なのだそうだ。発売したのは東京浅草のマルサン商店というブリキ玩具のメーカーで、「プラモデル」という言葉もそのメーカーがつくりだした。(世界では「プラスチック・モデル」という。) ただしこのプラモデル「ノーチラス号」はオリジナル製品ではなく、アメリカのラベール(レベル)社製(1953年発売)のコピー商品である。
値段は250円。
250円という値段では、子どもには買えない。
1958年といえば、昭和33年。あの映画『三丁目の夕日』の年で、東京タワーが建設途中である。翌昭和34年には初の週刊少年漫画誌『少年マガジン』と『少年サンデー』が誕生する。その値段は30円だった(はじめ『マガジン』は40円だったが、すぐに下げた)。
だから子どもにはこの「ノーチラス号」は高すぎる。 しかし“プラモデルブーム”の波は確実に近づいてきていたのだ。マルサン商店が「ノーチラス号」を発売しなかったとしても、2ヵ月後には、別のメーカーの潜水艦の模型が発売されていたはずである。
それがニチモ(日本模型)による「伊号潜水艦」である。こっちは、純国産プラモデルだ。 このニチモ「伊号潜水艦」は、年が明けて昭和34年の2月に発売された。 これは100円という値段で、そして、よく売れた。
続いて、三共模型、三和模型というメーカーが30円という低価格商品を売り出したから、ついに子供達のハートに一気に火が点いた。
さらに昭和35年11月には、イマイが「鉄人28号」を発売。 さらに田宮模型が参入、36年12月「パンサータンク」(ドイツ戦車)を発売し―――といった具合に昭和模型少年を熱狂させていったのである。
プラモデル(プラスチック・モデル)の発祥の地は、イギリスだという。
1936年にフロッグというメーカーが「ペンギン」という名のシリーズで1/72スケールのイギリスの爆撃機、戦闘機の模型を発売したのがはじまりだそうだ。「ペンギン」というのはつまり「飛ばない鳥」という意味のネーミングである。(イギリス式ユーモアってやつだね。)
大戦後、この熱はアメリカに飛び火して、アメリカでは飛行機にとらわれず、自動車や戦艦の模型が作られるようになったのであった。
ところで、本物のアメリカ製「原子力潜水艦ノーチラス号」のほうの話をしよう。この画期的な新式の潜水艦が建造されたのは1952年からで、1954年12月に進水。ついに「原子力潜水艦」が産声をあげたのである。「ノーチラス」と名付けられた。
「ノーチラス」はもちろん、ジュール・ベルヌ作『海底二万マイル』からとったネーミングである。「ノーチラス」とは「オウムガイ」のことだが、ジュール・ベルヌがこの小説の潜水艦にこの名前を付けたのには別の理由がある。アメリカのロバート・フルトン(もともとは画家だった)という人がいて、1800年に、「ノーチラス号」と名付けた潜水艦の設計図を書いて、フランス政府に売り込んだのである。もちろんこれはおもちゃではなく、本物の潜水艦の設計図である。ただしその売り込みは実らなかったが。 フルトンのこの潜水艦は3人乗り、動力は「手動式」であった。
さて、浅草マルサン商店の「原潜ノーチラス号」が発売された1958年、本物の原潜ノーチラス号は、ある‘挑戦’にトライしていた。(「サンシャイン作戦」と名付けられた。)
潜水艦によって、北極の氷の下を潜って、太平洋から大西洋まで通りぬけたのである。(ベーリング海峡→北極点→グリ-ンランド)
‘原子力’には酸素がいらない。これが画期的なことだった。「原子力」を手に入れることによって、ついに潜水艦は、永続的に潜ることを可能としたのである。そういう意味でも、『海底二万マイル』のノーチラス号並みの能力を、このとき人類はやっと手に入れたことになる。‘原子力’によって。
ただし、この「原子力潜水艦ノーチラス号」の水中での速度は、案外速くない? 20ノットほどだから、時速40キロ未満である。(それでも、大戦中の潜水艦の3倍の速度なのだ。) いやいや、船よりも速い。
この世界初の原子力潜水艦は、1980年に引退した。
‘原子力’―――(ウランの)「核分裂」が最初に発見されたのは、ベルリンの実験室である。
1938年12月ドイツ・ベルリンのオットー・ハーンと助手フリッツ・シュトラスマンの実験室でそれは起こった。予期せぬ結果が出た。ハーンは、その“不可解な結果”を手紙で物理学者のリーゼ・マイトナーに知らせ、「何が起こったのだろう?」と相談した。 マイトナーはもともとこのチームのメンバーで――というより、この核研究実験のチームを立ち上げたのは彼女(リーゼ・マイトナーは女性である)なのだ。オーストリア生まれのリーゼ・マイトナーは、ベルリンの街が大好きだったのだけれど、ユダヤの生まれだったために泣く泣くスウェーデンに亡命したばかりだった。
マイトナーは考えた。 彼女は自分達のベルリンの実験チームの実力を信頼していたから、ハーンの送ってきた実験結果にまちがいはないと、ハッキリ確信できた。
この(奇妙な)実験結果は“正しい”。 それならば、結論はこうだ。
「信じられないこと」が実際に起こったのだ!!
ウランの核が二つに割れたのだ!
しかし、なぜ“割れた”のか。そんなことがありえるのか? いや、すでにそれは起こったことなのだ! 物理学者としては、その理由を説明できなければならない…。
「ウラン235」は、「陽子92個、中性子143個」の核をもっている。この巨大な「核」を、たった1個の「中性子」がふたつに分割したのだ。(バリウムとクリプトンに。) そこにはどんな“物理学”が働いているのか?
リーゼ・マイトナーにとって、“物理学”は、恋人だった。
1938年のクリスマスの前日、コペンハーゲンからオットー・フリッシュがやってきた。フリッシュは、リーゼ・マイトナーの甥であり、彼もまた物理学者である。彼女は、フリッシュにハーンからの手紙を見せた。「信じられないな…。何かの間違いだ。」とフリッシュは言った。「でも、これが本当に起こったとしたら…どういうことが考えられるかしら?」 そんなことは起こらない、不可能だと言いながら、フリッシュはやがてそれを考えることに夢中になった。 二人は、「核が二つに割れた」その原理について考えた。「原子核は液滴のようなものではないか」とニールス・ボーア(デンマークの物理学者)が以前に発言したことを彼らは思い出していた。「液滴」…つまり「水の粒」のことだが、その「水の粒」が二つに割れるための条件はなんだろう?
…そのようにして「核分裂」の理論がそこで誕生したのである。場所はスウェーデン・クングエルブ村。
核は二つに割れ、そして、エネルギーが生まれる…。 F=m×c(2乗)、アルバート・アインシュタインの発見したあの式によれば、失われた質量の分だけエネルギーに変わるはずである…!!
そのエネルギー量は…
200000000eV !! (←2億電子ボルト)
二人が考え出した核分裂の理論より生じるエネルギー、アインシュタインの式から計算されるエネルギー、両者のその大きさがピタリと一致した!
フリッシュは、興奮した。
「ウラン核」は、割れる。
この重大な結論を、オットー・フリッシュは、デンマーク・コペンハーゲンへ戻り、ニールス・ボーアに伝えた…。
ボーアは、その時、アメリカへと旅立つ直前であった。(アインシュタインに会う予定があった。) ボーアは、フリッシュから‘それ’を聞くやいなや、自分の額を手でたたいて、こう叫んだ。「ああ、私たちはなんて馬鹿だったんだ!」 いつでも鋭い、ニールス・ボーア博士の偉大な直感力は、それが“正しい”と瞬時に認めたのであった。当時のヨーロッパの優秀な物理学者達をモヤモヤと悩ませていた「ウランの謎」、その答えがそこに示されたのだ。明解に。
「核分裂」の発見は、こうして1939年1月、ニールス・ボーアの口からアメリカ東海岸を中心にたちまち広がっていったのである。フリッシュ(とマイトナー)がそれを論文に書いて出すよりも前に。 「しまった…」と思ったがもう遅い。 ボーア博士はあわてて、フリッシュとマイトナーのために、その理論の優先権を確保しなければならなかった。
ボーアがアメリカでお喋りをしてる間に、フリッシュは、実験を行って確認した。 「ウラン核」は、ほんとうに、割れた。
フリッシュはその新しく見つかった現象に、「フィッション(核分裂)」と名前を付けて論文を書いた。
このベルリンでの核分裂は、「ウラン235」に「減速した中性子」を衝突させることで起こった。 この「ウラン235」と、「減速した中性子」というのが、絶妙な組み合わせだった。
というのは、まず、天然のウランはほとんどが「ウラン238」(99%)で、「ウラン235」はわずか0.7%しかない。そして「ウラン238」ではこのタイプの核分裂は起こらない。(「ウラン235」が重要なのだ、と気づいた最初の人は、ボーアである。)
そして、「減速した中性子」。 これはイタリア・ローマのエンリコ・フェルミ(後にアメリカに亡命)によって見いだされた画期的なアイデアであった。(これによってフェルミはノーベル賞を受賞した。) 中性子を、パラフィン(ろうそくの材料)を通過させることで「減速」するのである。「減速」しないと、やはりこの核分裂は起こらない。
この、「ウラン235」と、「減速した中性子」との組み合わせをベルリンチームは(別の目的をもって)たまたま実験したのだが、彼らの頭の中には(イタリアのフェルミのチームにも)、「核を二つに割る」などという予測図は、まったくなかったものなのであった。 実を言うと、ローマのフェルミの実験の中でもこの「核分裂」は起こっていたのだった。ただ、ドイツ人化学者ハーンの観察がとくべつにすぐれていたのである。エンリコ・フェルミは本物の天才だった。そもそも「ウランに中性子をぶつけると何かがおこる」と気づいて発表した最初の人物は彼なのだ。しかしもともとフェルミは“理論物理学者”で、突然に“実験物理学者”にかわったのは4年ほど前だった。ところがオットー・ハーンの実験者としての経験は40年ほどもあり、しかもフェルミとは違って“化学者”だった。物理の理論のことは深くはわからないが、化学分析は超一流だ。そうした条件が、ハーンに、この「大発見」をもたらしたのであろう。
フェルミらもハーンらも、じつは一生懸命、未知の「93番元素」を探していたのである。
‘それ’は、つまり、偶然に発見された‘パワー’だったのだ!
彼らが望んでいたわけではなかったのに、‘それ’は、その時、現われたのだ。(いま戦争がはじまろうとするその時に!)
もし、ハーン、シュトラスマン、マイトナーの実験チームがウランの「核分裂」を発見しなかったとしても、いずれそれは誰かが見つけたことだろう。(おそらくはエンリコ・フェルミが。)
だとしても、その発見が、何年か、あるいは何ヶ月か遅れたとしたら…
その場合は、広島、長崎に住む人々の運命も、確実に、違うものになっていたはずである。
さて、ところで、日本初のプラモデル「原子力潜水艦ノーチラス号」を発売したマルサン商店は、今は存在していません。 ただしその「金型」は現在童友社が所有しており、再発売もされたこともあるようです。 →これ
また、原寸大の原潜ノーチラス号と同じ頃に、手塚治虫の「アトム」も誕生しました。
「ノーチラス。 北緯。 90度。」というのは、世界的に有名なセリフなのだそうです。(僕はこの歳になるまで知りませんでしたが。)
アメリカの原子力潜水艦ノーチラス号がついに北極点に到達した時のアンダーソン艦長がワシントンに打った電報の言葉です。1958年8月3日のこと。
同じ年1958年の暮れ12月に、日本ではプラモデル「原子力潜水艦ノーチラス号」(1/300)が発売された。これが“日本初のプラモデル”なのだそうだ。発売したのは東京浅草のマルサン商店というブリキ玩具のメーカーで、「プラモデル」という言葉もそのメーカーがつくりだした。(世界では「プラスチック・モデル」という。) ただしこのプラモデル「ノーチラス号」はオリジナル製品ではなく、アメリカのラベール(レベル)社製(1953年発売)のコピー商品である。
値段は250円。
250円という値段では、子どもには買えない。
1958年といえば、昭和33年。あの映画『三丁目の夕日』の年で、東京タワーが建設途中である。翌昭和34年には初の週刊少年漫画誌『少年マガジン』と『少年サンデー』が誕生する。その値段は30円だった(はじめ『マガジン』は40円だったが、すぐに下げた)。
だから子どもにはこの「ノーチラス号」は高すぎる。 しかし“プラモデルブーム”の波は確実に近づいてきていたのだ。マルサン商店が「ノーチラス号」を発売しなかったとしても、2ヵ月後には、別のメーカーの潜水艦の模型が発売されていたはずである。
それがニチモ(日本模型)による「伊号潜水艦」である。こっちは、純国産プラモデルだ。 このニチモ「伊号潜水艦」は、年が明けて昭和34年の2月に発売された。 これは100円という値段で、そして、よく売れた。
続いて、三共模型、三和模型というメーカーが30円という低価格商品を売り出したから、ついに子供達のハートに一気に火が点いた。
さらに昭和35年11月には、イマイが「鉄人28号」を発売。 さらに田宮模型が参入、36年12月「パンサータンク」(ドイツ戦車)を発売し―――といった具合に昭和模型少年を熱狂させていったのである。
プラモデル(プラスチック・モデル)の発祥の地は、イギリスだという。
1936年にフロッグというメーカーが「ペンギン」という名のシリーズで1/72スケールのイギリスの爆撃機、戦闘機の模型を発売したのがはじまりだそうだ。「ペンギン」というのはつまり「飛ばない鳥」という意味のネーミングである。(イギリス式ユーモアってやつだね。)
大戦後、この熱はアメリカに飛び火して、アメリカでは飛行機にとらわれず、自動車や戦艦の模型が作られるようになったのであった。
ところで、本物のアメリカ製「原子力潜水艦ノーチラス号」のほうの話をしよう。この画期的な新式の潜水艦が建造されたのは1952年からで、1954年12月に進水。ついに「原子力潜水艦」が産声をあげたのである。「ノーチラス」と名付けられた。
「ノーチラス」はもちろん、ジュール・ベルヌ作『海底二万マイル』からとったネーミングである。「ノーチラス」とは「オウムガイ」のことだが、ジュール・ベルヌがこの小説の潜水艦にこの名前を付けたのには別の理由がある。アメリカのロバート・フルトン(もともとは画家だった)という人がいて、1800年に、「ノーチラス号」と名付けた潜水艦の設計図を書いて、フランス政府に売り込んだのである。もちろんこれはおもちゃではなく、本物の潜水艦の設計図である。ただしその売り込みは実らなかったが。 フルトンのこの潜水艦は3人乗り、動力は「手動式」であった。
さて、浅草マルサン商店の「原潜ノーチラス号」が発売された1958年、本物の原潜ノーチラス号は、ある‘挑戦’にトライしていた。(「サンシャイン作戦」と名付けられた。)
潜水艦によって、北極の氷の下を潜って、太平洋から大西洋まで通りぬけたのである。(ベーリング海峡→北極点→グリ-ンランド)
‘原子力’には酸素がいらない。これが画期的なことだった。「原子力」を手に入れることによって、ついに潜水艦は、永続的に潜ることを可能としたのである。そういう意味でも、『海底二万マイル』のノーチラス号並みの能力を、このとき人類はやっと手に入れたことになる。‘原子力’によって。
ただし、この「原子力潜水艦ノーチラス号」の水中での速度は、案外速くない? 20ノットほどだから、時速40キロ未満である。(それでも、大戦中の潜水艦の3倍の速度なのだ。) いやいや、船よりも速い。
この世界初の原子力潜水艦は、1980年に引退した。
‘原子力’―――(ウランの)「核分裂」が最初に発見されたのは、ベルリンの実験室である。
1938年12月ドイツ・ベルリンのオットー・ハーンと助手フリッツ・シュトラスマンの実験室でそれは起こった。予期せぬ結果が出た。ハーンは、その“不可解な結果”を手紙で物理学者のリーゼ・マイトナーに知らせ、「何が起こったのだろう?」と相談した。 マイトナーはもともとこのチームのメンバーで――というより、この核研究実験のチームを立ち上げたのは彼女(リーゼ・マイトナーは女性である)なのだ。オーストリア生まれのリーゼ・マイトナーは、ベルリンの街が大好きだったのだけれど、ユダヤの生まれだったために泣く泣くスウェーデンに亡命したばかりだった。
マイトナーは考えた。 彼女は自分達のベルリンの実験チームの実力を信頼していたから、ハーンの送ってきた実験結果にまちがいはないと、ハッキリ確信できた。
この(奇妙な)実験結果は“正しい”。 それならば、結論はこうだ。
「信じられないこと」が実際に起こったのだ!!
ウランの核が二つに割れたのだ!
しかし、なぜ“割れた”のか。そんなことがありえるのか? いや、すでにそれは起こったことなのだ! 物理学者としては、その理由を説明できなければならない…。
「ウラン235」は、「陽子92個、中性子143個」の核をもっている。この巨大な「核」を、たった1個の「中性子」がふたつに分割したのだ。(バリウムとクリプトンに。) そこにはどんな“物理学”が働いているのか?
リーゼ・マイトナーにとって、“物理学”は、恋人だった。
1938年のクリスマスの前日、コペンハーゲンからオットー・フリッシュがやってきた。フリッシュは、リーゼ・マイトナーの甥であり、彼もまた物理学者である。彼女は、フリッシュにハーンからの手紙を見せた。「信じられないな…。何かの間違いだ。」とフリッシュは言った。「でも、これが本当に起こったとしたら…どういうことが考えられるかしら?」 そんなことは起こらない、不可能だと言いながら、フリッシュはやがてそれを考えることに夢中になった。 二人は、「核が二つに割れた」その原理について考えた。「原子核は液滴のようなものではないか」とニールス・ボーア(デンマークの物理学者)が以前に発言したことを彼らは思い出していた。「液滴」…つまり「水の粒」のことだが、その「水の粒」が二つに割れるための条件はなんだろう?
…そのようにして「核分裂」の理論がそこで誕生したのである。場所はスウェーデン・クングエルブ村。
核は二つに割れ、そして、エネルギーが生まれる…。 F=m×c(2乗)、アルバート・アインシュタインの発見したあの式によれば、失われた質量の分だけエネルギーに変わるはずである…!!
そのエネルギー量は…
200000000eV !! (←2億電子ボルト)
二人が考え出した核分裂の理論より生じるエネルギー、アインシュタインの式から計算されるエネルギー、両者のその大きさがピタリと一致した!
フリッシュは、興奮した。
「ウラン核」は、割れる。
この重大な結論を、オットー・フリッシュは、デンマーク・コペンハーゲンへ戻り、ニールス・ボーアに伝えた…。
ボーアは、その時、アメリカへと旅立つ直前であった。(アインシュタインに会う予定があった。) ボーアは、フリッシュから‘それ’を聞くやいなや、自分の額を手でたたいて、こう叫んだ。「ああ、私たちはなんて馬鹿だったんだ!」 いつでも鋭い、ニールス・ボーア博士の偉大な直感力は、それが“正しい”と瞬時に認めたのであった。当時のヨーロッパの優秀な物理学者達をモヤモヤと悩ませていた「ウランの謎」、その答えがそこに示されたのだ。明解に。
「核分裂」の発見は、こうして1939年1月、ニールス・ボーアの口からアメリカ東海岸を中心にたちまち広がっていったのである。フリッシュ(とマイトナー)がそれを論文に書いて出すよりも前に。 「しまった…」と思ったがもう遅い。 ボーア博士はあわてて、フリッシュとマイトナーのために、その理論の優先権を確保しなければならなかった。
ボーアがアメリカでお喋りをしてる間に、フリッシュは、実験を行って確認した。 「ウラン核」は、ほんとうに、割れた。
フリッシュはその新しく見つかった現象に、「フィッション(核分裂)」と名前を付けて論文を書いた。
このベルリンでの核分裂は、「ウラン235」に「減速した中性子」を衝突させることで起こった。 この「ウラン235」と、「減速した中性子」というのが、絶妙な組み合わせだった。
というのは、まず、天然のウランはほとんどが「ウラン238」(99%)で、「ウラン235」はわずか0.7%しかない。そして「ウラン238」ではこのタイプの核分裂は起こらない。(「ウラン235」が重要なのだ、と気づいた最初の人は、ボーアである。)
そして、「減速した中性子」。 これはイタリア・ローマのエンリコ・フェルミ(後にアメリカに亡命)によって見いだされた画期的なアイデアであった。(これによってフェルミはノーベル賞を受賞した。) 中性子を、パラフィン(ろうそくの材料)を通過させることで「減速」するのである。「減速」しないと、やはりこの核分裂は起こらない。
この、「ウラン235」と、「減速した中性子」との組み合わせをベルリンチームは(別の目的をもって)たまたま実験したのだが、彼らの頭の中には(イタリアのフェルミのチームにも)、「核を二つに割る」などという予測図は、まったくなかったものなのであった。 実を言うと、ローマのフェルミの実験の中でもこの「核分裂」は起こっていたのだった。ただ、ドイツ人化学者ハーンの観察がとくべつにすぐれていたのである。エンリコ・フェルミは本物の天才だった。そもそも「ウランに中性子をぶつけると何かがおこる」と気づいて発表した最初の人物は彼なのだ。しかしもともとフェルミは“理論物理学者”で、突然に“実験物理学者”にかわったのは4年ほど前だった。ところがオットー・ハーンの実験者としての経験は40年ほどもあり、しかもフェルミとは違って“化学者”だった。物理の理論のことは深くはわからないが、化学分析は超一流だ。そうした条件が、ハーンに、この「大発見」をもたらしたのであろう。
フェルミらもハーンらも、じつは一生懸命、未知の「93番元素」を探していたのである。
‘それ’は、つまり、偶然に発見された‘パワー’だったのだ!
彼らが望んでいたわけではなかったのに、‘それ’は、その時、現われたのだ。(いま戦争がはじまろうとするその時に!)
もし、ハーン、シュトラスマン、マイトナーの実験チームがウランの「核分裂」を発見しなかったとしても、いずれそれは誰かが見つけたことだろう。(おそらくはエンリコ・フェルミが。)
だとしても、その発見が、何年か、あるいは何ヶ月か遅れたとしたら…
その場合は、広島、長崎に住む人々の運命も、確実に、違うものになっていたはずである。
さて、ところで、日本初のプラモデル「原子力潜水艦ノーチラス号」を発売したマルサン商店は、今は存在していません。 ただしその「金型」は現在童友社が所有しており、再発売もされたこともあるようです。 →これ
また、原寸大の原潜ノーチラス号と同じ頃に、手塚治虫の「アトム」も誕生しました。
この絵は東宝映画『海底軍艦』(1963年)より。 映画のこの「海底軍艦」は「轟天号(ごうてんごう)」と命名され、空を飛ぶこともできるし土中を進むこともできる万能巨大兵器である。デザインは小松崎茂。
さて、僕がこの稿で述べたいのは、その原作の『海島冒険奇譚 海底軍艦』のほうで、これが書かれたのは1900年。
こっちは空は飛ばない。 「潜水艦」であることが、最新未来兵器だった時代、である。
1900年といえば、まだ日露戦争も始まっていないし、夏目漱石もまだ小説を書いていない。日本にはまだ潜水艦などないし、ディーゼルエンジンもないし、ラジオもない。ライト兄弟はまだ世界初の飛行テストを行っていない。ラザフォードの「原子核の発見」も10年あとだ。
映画のほうはといえば、1960年代だから、すでに“原子力”というものが厳然として在り、日本は敗戦の苦しみを経験している。
つまりこのように、映画版と原作小説とでは時代状況がまったくちがう。だから内容もまた、まったく別のものであることをまず記しておく。 映画『海底軍艦』は、原作のタイトルと潜水艦のイメージだけを借りてつくったべつの物語なのである。
押川春浪(おしかわしゅんろう)が『海島冒険奇譚 海底軍艦』の作者である。
この話は、伊太利亜(イタリア)から始まる。 主人公は柳川という男(私)で世界一周の旅の途中、イタリアで旧友と偶然に会う。その旧友の妻と息子(日出男少年)が、母子だけで日本に帰国するという。主人公柳川も同じ汽船に乗って日本に帰るところだったので、柳川は友人に頼まれてその母子と船の旅を共にすることになる。
ところが出港前、白髪の老女がなぜか「今夜は不吉な夜だから行くのをやめよ」と泣く…。
船(弦月丸、げんげつまる)は、イタリアを出発。 地中海からスエズ運河を通り、紅海、そしてインド洋へ。
そこで謎の怪しい船‘海蛇丸(かいだまる)’におそわれる。
弦月丸は沈没――!!
いろいろあって、柳川と日出男少年は二人で海を漂流、その後無人島に漂着。
インド洋に浮かぶその無人島は、なんと日本の秘密海軍基地だった!!
そこで建造中だったのが、「海底軍艦」だったのである。この小説中では、“電光艇”と名付けている。
この「海底軍艦 電光艇」の動力源はなんだろうか?
〔「此倉庫には前申した、海底戦闘艇の動力の原因となるべき重要の化学薬液が、十二の樽に満されて納められているのです。実に此薬液こそ、海底戦闘艇の生命ともいうべき物です。」〕
なるほど、「12の化学薬液」が「海底軍艦」の秘密の動力源なのだ!!
押川春浪は、1876年愛媛県松山市生まれ。(つまり正岡子規や秋山真之と同じだ。)
彼の「年譜」がべらぼうに面白いので、その一部を以下に書き出してみる。
明治二十三年(1890) 14歳
上京して明治学院に入る。勉強はそっちのけで野球に熱中したので、父は目のとどく東北学院普通部に転校させた。 (中略) ミッション・スクールの洋風な点が性に合わず、西洋人の教師と大喧嘩したり、犬を殺して教室のストーブで煮て食べたり、長髪の同級生の髪に石油をかけて放火したりしたため、父の厳命で北海道に渡った。札幌農学校の入試に落ち、私費で同校の実習科に入学。原野を開拓するつもりだったが、いたるところ大木の林の一本一本を手作業で切る手間にうんざりして上京、水産講習所に入所。南氷洋で捕鯨事業にたずさわる夢があったが、次第に鯨の数も減少し、容易に捕らえることができないと知ると、それも嫌になった。(以下略)
明治三十一年(1898) 22歳
七月、東京専門学校(いまの早稲田大学)英文科卒業、引きつづき政治科に入学。この頃、借馬にまたがって意気揚々と神楽坂をのぼって交番近くまできたところ、馬が突然暴れ、とっさの気転で交番へ乗り入れた。内部は目茶苦茶になったが、巡査の力で馬をとめることができた。また、寄宿舎の屋根にとまっていた山鳩を、柔道三段の山田敬行と二人で鉄砲で撃ち落したのを渡せ渡せぬと争って舎監にしかられると、逆に舎監にくってかかり、逃げ出した舎監に向かって…(以下略)
明治三十三年(1900) 24歳
処女作『海島冒険奇譚海底軍艦』を執筆。 認められ、文武堂より出版。
どうです? ‘たいへんな男’でしょう? (ぜったいに友達になりたくない男、であるな。)
とほうもない豪傑であり、とほうもない駄目人間である。
押川春浪、どうやら実際に外国には行ったことがないようだ。 その後もずっとこのような冒険小説を書いたが、やはり一番面白いのがこの処女作の『海底軍艦』のようだ。 1916年、38歳没。
古典SF研究家横田順彌氏は、「押川春浪『海底軍艦』こそ、日本のSFのルーツである」としている。 ‘日本のSFは海底軍艦からはじまる’というわけだ。
押川春浪がこれを執筆し始めた時、「デュマのような面白いものを」という意識があったらしい。「デュマ」とは、19世紀フランスの作家アレクサンドル・デュマのことで、『三銃士』『モンテ・クリスト伯』などが代表作。ジュール・ベルヌは若い時にこのデュマの下で学んだことがある。
ところで、押川春浪『海底軍艦』には、「竜」とか怪物とかは出ません。 敵は、‘国籍不明’のなぞの海賊組織です。
日本帝国海軍と海賊軍は、インド洋にて大決戦! 7隻の海賊船団はいずれも撃沈! しかしその正体にはなにも触れず…。(それでいいのか? だいたい「海蛇丸」って日本語なのでは…??)
まあとにかく、大勝利した船団は意気揚々と日本へ向かう…。
そしてこの物語の最後は、
〔…右手に高く兜形の帽子を揚げて、今一度、諸君と共に大日本帝国万歳! 帝国海軍万歳を三呼しましょう。〕
と、締めくくられている。
さて、僕がこの稿で述べたいのは、その原作の『海島冒険奇譚 海底軍艦』のほうで、これが書かれたのは1900年。
こっちは空は飛ばない。 「潜水艦」であることが、最新未来兵器だった時代、である。
1900年といえば、まだ日露戦争も始まっていないし、夏目漱石もまだ小説を書いていない。日本にはまだ潜水艦などないし、ディーゼルエンジンもないし、ラジオもない。ライト兄弟はまだ世界初の飛行テストを行っていない。ラザフォードの「原子核の発見」も10年あとだ。
映画のほうはといえば、1960年代だから、すでに“原子力”というものが厳然として在り、日本は敗戦の苦しみを経験している。
つまりこのように、映画版と原作小説とでは時代状況がまったくちがう。だから内容もまた、まったく別のものであることをまず記しておく。 映画『海底軍艦』は、原作のタイトルと潜水艦のイメージだけを借りてつくったべつの物語なのである。
押川春浪(おしかわしゅんろう)が『海島冒険奇譚 海底軍艦』の作者である。
この話は、伊太利亜(イタリア)から始まる。 主人公は柳川という男(私)で世界一周の旅の途中、イタリアで旧友と偶然に会う。その旧友の妻と息子(日出男少年)が、母子だけで日本に帰国するという。主人公柳川も同じ汽船に乗って日本に帰るところだったので、柳川は友人に頼まれてその母子と船の旅を共にすることになる。
ところが出港前、白髪の老女がなぜか「今夜は不吉な夜だから行くのをやめよ」と泣く…。
船(弦月丸、げんげつまる)は、イタリアを出発。 地中海からスエズ運河を通り、紅海、そしてインド洋へ。
そこで謎の怪しい船‘海蛇丸(かいだまる)’におそわれる。
弦月丸は沈没――!!
いろいろあって、柳川と日出男少年は二人で海を漂流、その後無人島に漂着。
インド洋に浮かぶその無人島は、なんと日本の秘密海軍基地だった!!
そこで建造中だったのが、「海底軍艦」だったのである。この小説中では、“電光艇”と名付けている。
この「海底軍艦 電光艇」の動力源はなんだろうか?
〔「此倉庫には前申した、海底戦闘艇の動力の原因となるべき重要の化学薬液が、十二の樽に満されて納められているのです。実に此薬液こそ、海底戦闘艇の生命ともいうべき物です。」〕
なるほど、「12の化学薬液」が「海底軍艦」の秘密の動力源なのだ!!
押川春浪は、1876年愛媛県松山市生まれ。(つまり正岡子規や秋山真之と同じだ。)
彼の「年譜」がべらぼうに面白いので、その一部を以下に書き出してみる。
明治二十三年(1890) 14歳
上京して明治学院に入る。勉強はそっちのけで野球に熱中したので、父は目のとどく東北学院普通部に転校させた。 (中略) ミッション・スクールの洋風な点が性に合わず、西洋人の教師と大喧嘩したり、犬を殺して教室のストーブで煮て食べたり、長髪の同級生の髪に石油をかけて放火したりしたため、父の厳命で北海道に渡った。札幌農学校の入試に落ち、私費で同校の実習科に入学。原野を開拓するつもりだったが、いたるところ大木の林の一本一本を手作業で切る手間にうんざりして上京、水産講習所に入所。南氷洋で捕鯨事業にたずさわる夢があったが、次第に鯨の数も減少し、容易に捕らえることができないと知ると、それも嫌になった。(以下略)
明治三十一年(1898) 22歳
七月、東京専門学校(いまの早稲田大学)英文科卒業、引きつづき政治科に入学。この頃、借馬にまたがって意気揚々と神楽坂をのぼって交番近くまできたところ、馬が突然暴れ、とっさの気転で交番へ乗り入れた。内部は目茶苦茶になったが、巡査の力で馬をとめることができた。また、寄宿舎の屋根にとまっていた山鳩を、柔道三段の山田敬行と二人で鉄砲で撃ち落したのを渡せ渡せぬと争って舎監にしかられると、逆に舎監にくってかかり、逃げ出した舎監に向かって…(以下略)
明治三十三年(1900) 24歳
処女作『海島冒険奇譚海底軍艦』を執筆。 認められ、文武堂より出版。
どうです? ‘たいへんな男’でしょう? (ぜったいに友達になりたくない男、であるな。)
とほうもない豪傑であり、とほうもない駄目人間である。
押川春浪、どうやら実際に外国には行ったことがないようだ。 その後もずっとこのような冒険小説を書いたが、やはり一番面白いのがこの処女作の『海底軍艦』のようだ。 1916年、38歳没。
古典SF研究家横田順彌氏は、「押川春浪『海底軍艦』こそ、日本のSFのルーツである」としている。 ‘日本のSFは海底軍艦からはじまる’というわけだ。
押川春浪がこれを執筆し始めた時、「デュマのような面白いものを」という意識があったらしい。「デュマ」とは、19世紀フランスの作家アレクサンドル・デュマのことで、『三銃士』『モンテ・クリスト伯』などが代表作。ジュール・ベルヌは若い時にこのデュマの下で学んだことがある。
ところで、押川春浪『海底軍艦』には、「竜」とか怪物とかは出ません。 敵は、‘国籍不明’のなぞの海賊組織です。
日本帝国海軍と海賊軍は、インド洋にて大決戦! 7隻の海賊船団はいずれも撃沈! しかしその正体にはなにも触れず…。(それでいいのか? だいたい「海蛇丸」って日本語なのでは…??)
まあとにかく、大勝利した船団は意気揚々と日本へ向かう…。
そしてこの物語の最後は、
〔…右手に高く兜形の帽子を揚げて、今一度、諸君と共に大日本帝国万歳! 帝国海軍万歳を三呼しましょう。〕
と、締めくくられている。
日本の潜水艦は「伊号第1潜水艦」からはじまるようだ。 これは第一次世界大戦末期にドイツで製造中だった最新型の「U142型」の設計図を日本が手に入れて、ほぼその設計図どおりに造られたものらしい。主要部品もほとんどドイツ製。1923年着工、24年進水、26年竣工。
いま、僕は、映画『ローレライ』を観ながらこれを書いているが、これは第二次世界大戦末期の話で、ドイツ製の「伊号第57潜水艦」がその主役として登場する。 ただしこれはフィクションであるし、どうやら「伊号第57潜水艦」なるものは現実には存在しなかったようだ。 (ただし、「伊号第58潜水艦」は存在し働いた。)
潜水艦の発想は数千年前の昔からあったようだが、なかなか実用化はむつかしかった。19世紀においてさえ、潜水艦の動力は、「手動」であった。 海上の船とちがって「空気の問題」があって、蒸気機関をそのまま使うわけにはいかなかったからだ。(『海底二万マイル』のノーチラス号はネモ船長発明の新電池だったわけだが。)
それは当然で、蒸気機関は(SLを見ればわかるように)大量に「空気」が必要だし、「排気ガス」も捨てなければいけないが、それを海中にボコボコ出していたら、敵に居場所を知らせるようなもので、それでは潜水艦の意味がない。
Wikipediaによれば、「内燃機関を搭載した最初の潜水艦は、1900年に米国で建造されたホーランド潜水艦(水中排水量74t)である」ということである。そしてその後、潜水艦を大きく発達させたのはドイツである。第一次世界大戦後、世界各国は敗戦国ドイツの潜水艦を手に入れ、その技術を吸収した。日本もそれに遅れまいと機敏に動きドイツ潜水艦「U142型」の設計図を入手したわけである。
19世紀後半から20世紀前半にかけて、ドイツの「技術」は多くの面でたしかに世界トップにあったように思われる。(たとえば鉛筆がそうだった。)
とはいえ、当時の潜水艦は基本的には海上を進み、潜る時にはディーゼルエンジンは停止して電気に切り替える。ディーゼルだってやっぱり「酸素」を必要とするし「排気ガス」も出るからだ。
つまり、(ノーチラス号のように)海の中を自由にすいすい、というわけにはいかない。 「潜ることもできる戦艦」というのがほんとうの姿だろう。
さて、現代の潜水艦は無限に(ほんとうの無限ではないとしても)潜っていられると聞いたが、「空気の問題」はどう解決しているのだろうか?
(追記: 『ローレライ』の潜水艦は、「伊507」でした。)
追追記: 大きなまちがいを書いてしまったようです。どうやら日本初の潜水艦は1905年にアメリカから分解輸入した「第一潜水艦」が正しいようです。
いま、僕は、映画『ローレライ』を観ながらこれを書いているが、これは第二次世界大戦末期の話で、ドイツ製の「伊号第57潜水艦」がその主役として登場する。 ただしこれはフィクションであるし、どうやら「伊号第57潜水艦」なるものは現実には存在しなかったようだ。 (ただし、「伊号第58潜水艦」は存在し働いた。)
潜水艦の発想は数千年前の昔からあったようだが、なかなか実用化はむつかしかった。19世紀においてさえ、潜水艦の動力は、「手動」であった。 海上の船とちがって「空気の問題」があって、蒸気機関をそのまま使うわけにはいかなかったからだ。(『海底二万マイル』のノーチラス号はネモ船長発明の新電池だったわけだが。)
それは当然で、蒸気機関は(SLを見ればわかるように)大量に「空気」が必要だし、「排気ガス」も捨てなければいけないが、それを海中にボコボコ出していたら、敵に居場所を知らせるようなもので、それでは潜水艦の意味がない。
Wikipediaによれば、「内燃機関を搭載した最初の潜水艦は、1900年に米国で建造されたホーランド潜水艦(水中排水量74t)である」ということである。そしてその後、潜水艦を大きく発達させたのはドイツである。第一次世界大戦後、世界各国は敗戦国ドイツの潜水艦を手に入れ、その技術を吸収した。日本もそれに遅れまいと機敏に動きドイツ潜水艦「U142型」の設計図を入手したわけである。
19世紀後半から20世紀前半にかけて、ドイツの「技術」は多くの面でたしかに世界トップにあったように思われる。(たとえば鉛筆がそうだった。)
とはいえ、当時の潜水艦は基本的には海上を進み、潜る時にはディーゼルエンジンは停止して電気に切り替える。ディーゼルだってやっぱり「酸素」を必要とするし「排気ガス」も出るからだ。
つまり、(ノーチラス号のように)海の中を自由にすいすい、というわけにはいかない。 「潜ることもできる戦艦」というのがほんとうの姿だろう。
さて、現代の潜水艦は無限に(ほんとうの無限ではないとしても)潜っていられると聞いたが、「空気の問題」はどう解決しているのだろうか?
(追記: 『ローレライ』の潜水艦は、「伊507」でした。)
追追記: 大きなまちがいを書いてしまったようです。どうやら日本初の潜水艦は1905年にアメリカから分解輸入した「第一潜水艦」が正しいようです。
ノーチラス号とは?
19世紀にネモ船長がつくった潜水艦。(上の絵は映画版より)
では、その動力源は?
んー、んー、なんだっけ…??
というわけで、『海底二万マイル』(ジュール・ベルヌ作)を借りてきた。
きっと「蒸気力」だろうと思っていたら、違った。 「電池」だった!!
19世紀にネモ船長がつくった潜水艦。(上の絵は映画版より)
では、その動力源は?
んー、んー、なんだっけ…??
というわけで、『海底二万マイル』(ジュール・ベルヌ作)を借りてきた。
きっと「蒸気力」だろうと思っていたら、違った。 「電池」だった!!
カギムシ、という。
この生物は日本ではお目にかかれない。ミミズに足がはえたような妙な生物らしい。南半球にいるらしい。
この生物はどうやら「生きた化石」であるらしい。進化のカギを握り、太古の姿のままでその姿を保存してきた。 (だから日本名が「カギムシ」なのか…それはどうだろう? 興味のある方は自分で調べてください。)
カギムシの参考ブログ → http://umafan.blog72.fc2.com/blog-entry-740.html
http://ameblo.jp/oldworld/entry-10005755849.html
上の絵は、深海探査船チャレンジャー号の調査に参加したヘンリー・ノティッジ・モーズリーがケープタウン(南アフリカ)で見つけ研究したもので、ケープカギムシ(和名)である。この時のものは体長8cmだった。
このH・N・モーズリー(モーズレーと表記されることもある)ももちろん日本にやってきたことになるが(1875年)、彼らは神戸港に船を停泊した時、人力車に乗って京都まで行っている。 そしてこのモーズリーは京都で仲間とわかれ、単独で陸路東海道を旅している。あとで横浜で合流してチャレンジャー号に乗ることになるのだが、その東海道の旅路でモーズリーがおおいに感心したのが、同行した「田中」という名の書生だった。気の利くさっぱりした男で、夕方旅館に着くと、その日にあった体験などを俳句に読んでさらさらと帳面に筆記するのだった。モーズリーの目にはそれがとてもかっこよく映ったのだった。
さて、すでに前回記事に書いたことの繰り返しになるが、このH・N・モーズリーはイギリスに帰ってこのチャレンジャー号体験を『チャレンジャー号上の一博物学者の記録』として本にした。そして1891年帰らぬ人となる。
その時に3歳だった息子が、後に物理学者となり、「モーズリーの法則」を発見し、科学史に大きな貢献をすることになる。 名前は、ヘンリー・グウィン・ジェフリーズ・モーズリーである。
20世紀の初頭――。 アルゴンやネオンなど希ガスの発見。 キュリー夫人のポロニウム、ラジウムの発見。「新元素」が次々と現われ、メンデレーエフの周期律表の大部分が埋まってきた。 そうなると、残りの空白を埋める「新元素」を発見したいと化学者たちが考えるのは当然の成り行きといえた。
しかし、だれかが「新元素を発見しました!」と言っても、それが正しいのかどうか、それを判定するのがまた難しい。フクザツに混じり合っている物質の中から「それ」だけを分離し、性質を調べ、重量を測る――しかし、そのような新元素は元々微量にしかないものだから(それで発見に苦労しているのだから!)、スペクトルを調べるほどの量もとりだせないのだった。
なにか他にそれが何の元素であるか調べる便利な方法がないものか――。
あったのである。
それが「モーズリーの法則」である。
物質にエネルギーをあたえると「励起状態」というものになる。これは「反応しやすい状態」のことだが、その時にその物質の「電子」が軌道を移動しやすい状態になる。その「電子」がの軌道から軌道に移動するとき、その物質に特有の周波数の「X線」が発生することがわかってきた。それを「特性X線」というのだが、モーズリーはそれを研究した。そして直感と粘り強い研究の成果が「モーズリーの法則」という関係式となって表れたのだった。
この「モーズリーの法則」によって、「特性X線」の波長さえ調べればその物質の原子番号が判る、ようになったのだ!
つまり物質が発する‘特性X線’の波長は、「私の原子番号は○○です」と自己申告してくれているようなものだった。 (もっとも、私たちが今使っている「原子番号」というものは当時の化学の世界にはなく、これより50年後に正式に採用されたらしい。)
「モーズリーの法則」は、混乱していた物理・化学の世界を整理するのに多大な貢献となった。これを使えばその物質が何であるかを確認するための様々な分析作業がすべて省けるのである。
H・G・J・モーズリーがこの法則を発見したのは1913年、弱冠26歳の時である。 これはノーベル賞級の発見であったが、ノーベル賞委員会もそれは認めつつ、しかしまだ発表されたばかりであったし、それに若いモーズリーにはまだ未来がある。モーズリーほどの優秀な物理学者ならさらに重要な発見をする可能性もある。そう、いつだってノーベル賞は授与できるのだし、と思っていたようだ。
――ところが、そうではなかった。 翌年、モーズリーは死んでしまう。
モーズリー自身は、自分の発見した法則を使えば、まだ発見されていない「新元素」が発見できると意欲を燃やしていた。 いまだ未発見の元素は(これもモーズリーの法則のおかげではっきりしてきたのだが)、原子番号43、61、72、75が残っていた。
1914年、第一次世界大戦が始まる。 彼は陸軍に志願する。
そして27歳H・G・J・モーズリーは戦場に散った。 トルコ・ガリポリの戦い――彼の加わったイギリスの部隊は全滅だった。
ノーベル賞委員会は彼にノーベル賞を与えておかなかったことを悔やんだという。(この賞は死者に贈ることはできないのだ。)
モーズリーの戦死の報を聞き、彼の物理学の師であったアーネスト・ラザフォードは、大声を出して泣いたという。
3歳の時に父を亡くしたH・G・J・モーズリーと、A・ラザフォードの関係は仲の良い父子のような関係だったかもしれない。戦争が始まったその瞬間、ラザフォードとモーズリーはイギリス科学振興協会の会議のため海のむこうオーストラリアにいたのだった。
この生物は日本ではお目にかかれない。ミミズに足がはえたような妙な生物らしい。南半球にいるらしい。
この生物はどうやら「生きた化石」であるらしい。進化のカギを握り、太古の姿のままでその姿を保存してきた。 (だから日本名が「カギムシ」なのか…それはどうだろう? 興味のある方は自分で調べてください。)
カギムシの参考ブログ → http://umafan.blog72.fc2.com/blog-entry-740.html
http://ameblo.jp/oldworld/entry-10005755849.html
上の絵は、深海探査船チャレンジャー号の調査に参加したヘンリー・ノティッジ・モーズリーがケープタウン(南アフリカ)で見つけ研究したもので、ケープカギムシ(和名)である。この時のものは体長8cmだった。
このH・N・モーズリー(モーズレーと表記されることもある)ももちろん日本にやってきたことになるが(1875年)、彼らは神戸港に船を停泊した時、人力車に乗って京都まで行っている。 そしてこのモーズリーは京都で仲間とわかれ、単独で陸路東海道を旅している。あとで横浜で合流してチャレンジャー号に乗ることになるのだが、その東海道の旅路でモーズリーがおおいに感心したのが、同行した「田中」という名の書生だった。気の利くさっぱりした男で、夕方旅館に着くと、その日にあった体験などを俳句に読んでさらさらと帳面に筆記するのだった。モーズリーの目にはそれがとてもかっこよく映ったのだった。
さて、すでに前回記事に書いたことの繰り返しになるが、このH・N・モーズリーはイギリスに帰ってこのチャレンジャー号体験を『チャレンジャー号上の一博物学者の記録』として本にした。そして1891年帰らぬ人となる。
その時に3歳だった息子が、後に物理学者となり、「モーズリーの法則」を発見し、科学史に大きな貢献をすることになる。 名前は、ヘンリー・グウィン・ジェフリーズ・モーズリーである。
20世紀の初頭――。 アルゴンやネオンなど希ガスの発見。 キュリー夫人のポロニウム、ラジウムの発見。「新元素」が次々と現われ、メンデレーエフの周期律表の大部分が埋まってきた。 そうなると、残りの空白を埋める「新元素」を発見したいと化学者たちが考えるのは当然の成り行きといえた。
しかし、だれかが「新元素を発見しました!」と言っても、それが正しいのかどうか、それを判定するのがまた難しい。フクザツに混じり合っている物質の中から「それ」だけを分離し、性質を調べ、重量を測る――しかし、そのような新元素は元々微量にしかないものだから(それで発見に苦労しているのだから!)、スペクトルを調べるほどの量もとりだせないのだった。
なにか他にそれが何の元素であるか調べる便利な方法がないものか――。
あったのである。
それが「モーズリーの法則」である。
物質にエネルギーをあたえると「励起状態」というものになる。これは「反応しやすい状態」のことだが、その時にその物質の「電子」が軌道を移動しやすい状態になる。その「電子」がの軌道から軌道に移動するとき、その物質に特有の周波数の「X線」が発生することがわかってきた。それを「特性X線」というのだが、モーズリーはそれを研究した。そして直感と粘り強い研究の成果が「モーズリーの法則」という関係式となって表れたのだった。
この「モーズリーの法則」によって、「特性X線」の波長さえ調べればその物質の原子番号が判る、ようになったのだ!
つまり物質が発する‘特性X線’の波長は、「私の原子番号は○○です」と自己申告してくれているようなものだった。 (もっとも、私たちが今使っている「原子番号」というものは当時の化学の世界にはなく、これより50年後に正式に採用されたらしい。)
「モーズリーの法則」は、混乱していた物理・化学の世界を整理するのに多大な貢献となった。これを使えばその物質が何であるかを確認するための様々な分析作業がすべて省けるのである。
H・G・J・モーズリーがこの法則を発見したのは1913年、弱冠26歳の時である。 これはノーベル賞級の発見であったが、ノーベル賞委員会もそれは認めつつ、しかしまだ発表されたばかりであったし、それに若いモーズリーにはまだ未来がある。モーズリーほどの優秀な物理学者ならさらに重要な発見をする可能性もある。そう、いつだってノーベル賞は授与できるのだし、と思っていたようだ。
――ところが、そうではなかった。 翌年、モーズリーは死んでしまう。
モーズリー自身は、自分の発見した法則を使えば、まだ発見されていない「新元素」が発見できると意欲を燃やしていた。 いまだ未発見の元素は(これもモーズリーの法則のおかげではっきりしてきたのだが)、原子番号43、61、72、75が残っていた。
1914年、第一次世界大戦が始まる。 彼は陸軍に志願する。
そして27歳H・G・J・モーズリーは戦場に散った。 トルコ・ガリポリの戦い――彼の加わったイギリスの部隊は全滅だった。
ノーベル賞委員会は彼にノーベル賞を与えておかなかったことを悔やんだという。(この賞は死者に贈ることはできないのだ。)
モーズリーの戦死の報を聞き、彼の物理学の師であったアーネスト・ラザフォードは、大声を出して泣いたという。
3歳の時に父を亡くしたH・G・J・モーズリーと、A・ラザフォードの関係は仲の良い父子のような関係だったかもしれない。戦争が始まったその瞬間、ラザフォードとモーズリーはイギリス科学振興協会の会議のため海のむこうオーストラリアにいたのだった。
犬吠埼灯台は関東の最東端千葉県銚子市にある灯台です。 1874年11月初点灯。
犬吠埼灯台を描いて、それだけでは物足らないので何か船を描こうと思い、それでチャレンジャー号を描いてみました。
「チャレンジャー号」と聞くと、あのフロリダの空に砕けて散ったNASAのスペースシャトルを思い浮かべる人が多いだろう。でも、それではない。
このイギリスのチャレンジャー号が日本にやってきたのは1875年4月のことで、今から134年前のことになる。(つまり犬吠埼灯台が点灯した半年後だ。) この船は、「世界の深海の生物相を調べよう!」という壮大な計画の途中、日本に立ち寄ったのである。
先の9月、しょこたん中川翔子がしんかい6500に乗って海にもぐったらしい。僕はそのTV番組を見損ねてしまって残念に思っているが、この深海探査船チャレンジャー号は、そのしんかい6500のルーツともいえる船なのである。
さてチャレンジャー号の色々なことは後にまわして、まず、犬吠埼灯台の話をしよう。
いやなんです
あなたのいってしまふのが――
これは高村光太郎『智恵子抄』のいちばん最初にある詩「人に」のその冒頭の部分である。「あなた」というのはもちろん智恵子のことで、後に光太郎と結婚し、さらには精神をくずしていく…。 そんな妻智恵子のことを詩に綴ったものを集めた本が『智恵子抄』である。
上の「人に」の詩を書いたのは明治四十五年(1912年)七月、その場所というのが、この犬吠埼灯台のある場所なのである。この夏、二人はそこでデートをしたらしい。
「いやなんです」というのは、この時、実家のほうから智恵子に見合いの話が来ていて、それを光太郎が気にして、「どうか見合いを断ってほしい」とお願いしているのである。なんともカッコわるい、しかし、ストレートでわかりやすい詩である。
高村光雲の息子高村光太郎がアメリカ、ヨーロッパを旅した(アルバイトもしたようだ)のは1906年から1909年。 光太郎の芸術の友である萩原守衛(碌山)が死んだのが1910年。 そして1912年に長沼智恵子と出会う。長沼智恵子という人も芸術家で、日本女子大卒業後も実家(福島県)に帰らず画の勉強をしていたらしい。この当時28歳だった。
この犬吠埼での二人のデートは、“写生旅行”だったようだ。
犬吠埼に僕は行ったことがありませんが、灯台のある岬は“石切の鼻”と呼ばれ、付近には“幌掛岩”という奇怪な岩があるようです。 僕の描いたこの絵の向こう側は砂浜になっています。
そしてこの灯台は、135年の風雪に耐えてここに立っています。
犬吠埼灯台の施工者はリチャード・ヘンリー・ブラントン。 スコットランド(イギリス)からやって来ました。文献では彼のことはしばしば「日本の灯台の父」と紹介されています。
11月1日は灯台記念日なのだそうです。
それは日本ではじめて(洋式の)灯台の工事が着工された日が11月1日だったから。 日本の最初の洋式灯台は、東京湾の入り口の横須賀にある観音崎灯台で、1869年2月初点灯。 施行したのはフランス人F.L.ヴェルニー。 ただし観音崎灯台は今は3代目となっています。
アメリカの黒船来航によって、江戸幕府は強引に「開国」をすることになり、その時に交わした条約の中に、いくつかの場所に「灯台」を造るという約束があったのです。それで江戸幕府は、洋式の灯台を建築する技術者を派遣してもらうよう、フランスとイギリスにお願いしました。フランスからやって来たのがF.L.ヴェルニーでした。
それで、イギリスへの灯台技師派遣の話はスコットランドの「スティーブンソン兄弟社」のところに行きました。 そう、あの伝説の灯台技師ロバート・スティーブンソンの息子たちデヴィッドとトマスの会社です。(このトマス・スティーブンソンの息子が作家ロバート・ルイス・スティーブンソンで、『宝島』の作者。) トマスは、日本から灯台技師を送ってほしいという願いがくると、「それならこの男がいい」といって派遣したのがスコットランド人R・H・ブラントンというわけです。
そういうことで、ヴェルニーとブラントン、「日本の灯台の父」は、二人います。
彼らは明治時代に日本にやってきたいわゆる「お雇い外国人」ということになりますが、それらの外国人の中でも多かったのがスコットランド人だったようです。スコットランドは技術の輸出国だったんですね。(そういえば蒸気機関の発展はスコットランドで起こりましたね。)
さてそれでは、チャレンジャー号の話。
この深海探査船の大計画の団長としてやってきたのがやはりこれもスコットランド人のチャールズ・W・トムソン。エディンバラ大学教授。エディンバラ大学がこの学問調査の中心地となったのでした。
「海の底の生物相はいったいどうなっているのだろうか」
それが彼らの知りたいことだった。 地中海、北海、大西洋の海を調べた彼らは深まる謎をさらに調べるために、いっそ世界中の海の深海調査をしたらどうかと考えたのである。そして、実行した。さすが19世紀の世界の海を制覇していたイギリスだからこその発想と実行力であった。
世界の深海を調査する――その使命を担って、1872年12月イギリス・ポーツマス港を出港したチャレンジャー号は、大西洋、カリブ海を調べ、アフリカ南端ケープタウンを廻り、インド洋、南極海へ行く。 そこからオーストラリア、ニュージーランド、ニューギニア近郊の海を調査、そして次の目的地が日本であった。
この船には軍事的な目的はまったくなかったから、日本でも歓待を受けた。1875年4月11日、東京湾入りしたチャレンジャー号は、横浜でしばし休日を過ごし、その後、相模湾、瀬戸内海、そして最後に房総半島沖を調査した。
調査団メンバー達は日本が大変に気に入り、「ここにもう一度来たいと思わない人はいないだろう」と書いている。彼等は人力車の人夫に驚いた。どれだけ走ってもまったく疲れた様子をみせず、声をかければいつでもサワヤカに返事が返ってくるのである。
日本での最後の調査、房総半島沖でも彼らはたくさんの収穫(生物標本)を得ることになったが、その中でももっともインパクトのあるものが、巨大ヒドロポリプの発見であった。これは2メートルを越す巨大な生物で、このように海の底はワンダーにあふれた世界だったのだ。
そして1875年6月16日、チャレンジャー号はハワイに向けて出発したのであった。
深海探査船チャレンジャー号がイギリスに戻りついたのは1876年5月。じつに3年半の航海であった。
出発時、調査団、士官、一般水兵総勢243人――帰ってきた時には144人になっていた。その内6人が航海中に病気や事故で死亡、26人が不健康となって下船、そして61名の水兵が逃亡した。逃亡した水兵の多くは、南アフリカでのダイヤモンドラッシュ、オーストラリアでの金鉱ラッシュに飛びついた男達であった。
チャレンジャー号の深海調査団のメンバーには、団長のトムソン(博物学者)の他に3名の博物学者と1名の化学者がいた。そのうちの一人は、航海中に太平洋で病気になり命を落とした。
彼らが持ち帰った標本を記録しまとめる仕事が残っていたが、それは膨大なもので、彼らだけでは無理だった。イギリスだけでは人手が足らず他国の学者の協力も仰ぐこととなり、エディンバラ大学は海洋学の国際センターのようになった。その『チャレンジャー・レポート』が完成するまでにはなんと19年かかった。
C・W・トムソンは、しかし、その途中で亡くなった。1882年、52歳であった。
チャレンジャー号のメンバーの一人に博物学者ヘンリー・ノティッジ・モーズリーがいる。彼はこの海洋探検を『チャレンジャー号上の一博物学者の記録』として記し好評を得た。モーズリーがこの探検調査に参加したのは28歳の時、しかしこのモーズリーも1891年、47歳の若さで亡くなった。あとに三人の幼い子を残して。
そのうちの一番下の子どもは、まだ3歳だったが、やがて成長して物理学者となる。オックスフォード大学を出て、さらにアーネスト・ラザフォードのもとで学び、科学史における重要な発見をする。
それを、「モーズリーの法則」という。
ふーッ。 書きつかれたよ…。 (なにしてんだ、オレ?)
犬吠埼灯台を描いて、それだけでは物足らないので何か船を描こうと思い、それでチャレンジャー号を描いてみました。
「チャレンジャー号」と聞くと、あのフロリダの空に砕けて散ったNASAのスペースシャトルを思い浮かべる人が多いだろう。でも、それではない。
このイギリスのチャレンジャー号が日本にやってきたのは1875年4月のことで、今から134年前のことになる。(つまり犬吠埼灯台が点灯した半年後だ。) この船は、「世界の深海の生物相を調べよう!」という壮大な計画の途中、日本に立ち寄ったのである。
先の9月、しょこたん中川翔子がしんかい6500に乗って海にもぐったらしい。僕はそのTV番組を見損ねてしまって残念に思っているが、この深海探査船チャレンジャー号は、そのしんかい6500のルーツともいえる船なのである。
さてチャレンジャー号の色々なことは後にまわして、まず、犬吠埼灯台の話をしよう。
いやなんです
あなたのいってしまふのが――
これは高村光太郎『智恵子抄』のいちばん最初にある詩「人に」のその冒頭の部分である。「あなた」というのはもちろん智恵子のことで、後に光太郎と結婚し、さらには精神をくずしていく…。 そんな妻智恵子のことを詩に綴ったものを集めた本が『智恵子抄』である。
上の「人に」の詩を書いたのは明治四十五年(1912年)七月、その場所というのが、この犬吠埼灯台のある場所なのである。この夏、二人はそこでデートをしたらしい。
「いやなんです」というのは、この時、実家のほうから智恵子に見合いの話が来ていて、それを光太郎が気にして、「どうか見合いを断ってほしい」とお願いしているのである。なんともカッコわるい、しかし、ストレートでわかりやすい詩である。
高村光雲の息子高村光太郎がアメリカ、ヨーロッパを旅した(アルバイトもしたようだ)のは1906年から1909年。 光太郎の芸術の友である萩原守衛(碌山)が死んだのが1910年。 そして1912年に長沼智恵子と出会う。長沼智恵子という人も芸術家で、日本女子大卒業後も実家(福島県)に帰らず画の勉強をしていたらしい。この当時28歳だった。
この犬吠埼での二人のデートは、“写生旅行”だったようだ。
犬吠埼に僕は行ったことがありませんが、灯台のある岬は“石切の鼻”と呼ばれ、付近には“幌掛岩”という奇怪な岩があるようです。 僕の描いたこの絵の向こう側は砂浜になっています。
そしてこの灯台は、135年の風雪に耐えてここに立っています。
犬吠埼灯台の施工者はリチャード・ヘンリー・ブラントン。 スコットランド(イギリス)からやって来ました。文献では彼のことはしばしば「日本の灯台の父」と紹介されています。
11月1日は灯台記念日なのだそうです。
それは日本ではじめて(洋式の)灯台の工事が着工された日が11月1日だったから。 日本の最初の洋式灯台は、東京湾の入り口の横須賀にある観音崎灯台で、1869年2月初点灯。 施行したのはフランス人F.L.ヴェルニー。 ただし観音崎灯台は今は3代目となっています。
アメリカの黒船来航によって、江戸幕府は強引に「開国」をすることになり、その時に交わした条約の中に、いくつかの場所に「灯台」を造るという約束があったのです。それで江戸幕府は、洋式の灯台を建築する技術者を派遣してもらうよう、フランスとイギリスにお願いしました。フランスからやって来たのがF.L.ヴェルニーでした。
それで、イギリスへの灯台技師派遣の話はスコットランドの「スティーブンソン兄弟社」のところに行きました。 そう、あの伝説の灯台技師ロバート・スティーブンソンの息子たちデヴィッドとトマスの会社です。(このトマス・スティーブンソンの息子が作家ロバート・ルイス・スティーブンソンで、『宝島』の作者。) トマスは、日本から灯台技師を送ってほしいという願いがくると、「それならこの男がいい」といって派遣したのがスコットランド人R・H・ブラントンというわけです。
そういうことで、ヴェルニーとブラントン、「日本の灯台の父」は、二人います。
彼らは明治時代に日本にやってきたいわゆる「お雇い外国人」ということになりますが、それらの外国人の中でも多かったのがスコットランド人だったようです。スコットランドは技術の輸出国だったんですね。(そういえば蒸気機関の発展はスコットランドで起こりましたね。)
さてそれでは、チャレンジャー号の話。
この深海探査船の大計画の団長としてやってきたのがやはりこれもスコットランド人のチャールズ・W・トムソン。エディンバラ大学教授。エディンバラ大学がこの学問調査の中心地となったのでした。
「海の底の生物相はいったいどうなっているのだろうか」
それが彼らの知りたいことだった。 地中海、北海、大西洋の海を調べた彼らは深まる謎をさらに調べるために、いっそ世界中の海の深海調査をしたらどうかと考えたのである。そして、実行した。さすが19世紀の世界の海を制覇していたイギリスだからこその発想と実行力であった。
世界の深海を調査する――その使命を担って、1872年12月イギリス・ポーツマス港を出港したチャレンジャー号は、大西洋、カリブ海を調べ、アフリカ南端ケープタウンを廻り、インド洋、南極海へ行く。 そこからオーストラリア、ニュージーランド、ニューギニア近郊の海を調査、そして次の目的地が日本であった。
この船には軍事的な目的はまったくなかったから、日本でも歓待を受けた。1875年4月11日、東京湾入りしたチャレンジャー号は、横浜でしばし休日を過ごし、その後、相模湾、瀬戸内海、そして最後に房総半島沖を調査した。
調査団メンバー達は日本が大変に気に入り、「ここにもう一度来たいと思わない人はいないだろう」と書いている。彼等は人力車の人夫に驚いた。どれだけ走ってもまったく疲れた様子をみせず、声をかければいつでもサワヤカに返事が返ってくるのである。
日本での最後の調査、房総半島沖でも彼らはたくさんの収穫(生物標本)を得ることになったが、その中でももっともインパクトのあるものが、巨大ヒドロポリプの発見であった。これは2メートルを越す巨大な生物で、このように海の底はワンダーにあふれた世界だったのだ。
そして1875年6月16日、チャレンジャー号はハワイに向けて出発したのであった。
深海探査船チャレンジャー号がイギリスに戻りついたのは1876年5月。じつに3年半の航海であった。
出発時、調査団、士官、一般水兵総勢243人――帰ってきた時には144人になっていた。その内6人が航海中に病気や事故で死亡、26人が不健康となって下船、そして61名の水兵が逃亡した。逃亡した水兵の多くは、南アフリカでのダイヤモンドラッシュ、オーストラリアでの金鉱ラッシュに飛びついた男達であった。
チャレンジャー号の深海調査団のメンバーには、団長のトムソン(博物学者)の他に3名の博物学者と1名の化学者がいた。そのうちの一人は、航海中に太平洋で病気になり命を落とした。
彼らが持ち帰った標本を記録しまとめる仕事が残っていたが、それは膨大なもので、彼らだけでは無理だった。イギリスだけでは人手が足らず他国の学者の協力も仰ぐこととなり、エディンバラ大学は海洋学の国際センターのようになった。その『チャレンジャー・レポート』が完成するまでにはなんと19年かかった。
C・W・トムソンは、しかし、その途中で亡くなった。1882年、52歳であった。
チャレンジャー号のメンバーの一人に博物学者ヘンリー・ノティッジ・モーズリーがいる。彼はこの海洋探検を『チャレンジャー号上の一博物学者の記録』として記し好評を得た。モーズリーがこの探検調査に参加したのは28歳の時、しかしこのモーズリーも1891年、47歳の若さで亡くなった。あとに三人の幼い子を残して。
そのうちの一番下の子どもは、まだ3歳だったが、やがて成長して物理学者となる。オックスフォード大学を出て、さらにアーネスト・ラザフォードのもとで学び、科学史における重要な発見をする。
それを、「モーズリーの法則」という。
ふーッ。 書きつかれたよ…。 (なにしてんだ、オレ?)
三軒茶屋のこの三叉路に昔(江戸時代のことだ)、名前の通りに三軒の茶屋があって繁盛していたらしい。
村上春樹の『1Q84』の図書館の予約の順番がまわってきたので読んでいるのですが、その物語はこの場所――首都高速道路三号線の非常階段――から始まります。
主人公の青豆(女性30歳)がタクシーに乗りその中でFMラジオからヤナーチェック作曲の『シンフォニエッタ』という曲を聴く。その時に彼女は“ねじれた感覚”をもつ。彼女は渋谷へ行きたいのだが高速道路は混雑していてそのタクシーは進まない。運転手は、彼女に、非常階段があるということを知らせる。彼女はタクシーを降り、ハイヒールの靴を脱いで非常階段を降りる。そして田園都市線三軒茶屋駅にむかう。彼女の目的は渋谷のホテルにいる男に会いその男を暗殺すること――。
前回書いたように「オッターバ・コンブリオ」を聴きながらこのブログを書いています。
さっきは偶々ヤナーチェックの『落ち葉』(草かげの小径にて第1集 ~落ち葉)という曲が流れていました。秋の曲ということで。その後の曲はバッハ『アリア』。 僕はこの番組によってヤナーチェック(1854-1928チェコの作曲家)をはじめて聴きましたし、バッハの『アリア』は知っていても、いまだ『カノン』と区別がつきません。
でもそんなこととは関係なく、音楽はたのしめる…。 しかしもう少し心地良い環境で聴きたいものだと思っている。どうもこの部屋の‘ぐあい’が良くないのです。なにかが。なにかをどうにかせねばならん。
サティ『風変わりな美女(真面目な幻想曲)』という曲が面白い(タイトルも)。
1984年…か。
その年、僕はまだ東京に住んでいなかった。(あの日本航空御巣鷹山墜落事故は1985年。) だから「三軒茶屋」なんて地名も知らなかったのですが。

三軒茶屋キャロットタワーという建物です。

三軒茶屋将棋倶楽部。
ここはプロ棋士宮田利夫七段が席主をしている。
将棋道場というのはほんとに儲からない商売であるが、将棋のすきな人にとっては天国の休日が過ごせる。800円だか1000円だかで一日将棋が指せて、しかもこの三軒茶屋将棋倶楽部はコーヒー付きだ。それだけではない。そのコーヒーを現役プロ棋士(宮田七段)が運んできてくれるのだからすごい!
宮田利夫さんは故高柳敏夫の弟子だが(中原誠名人や島朗さん清水市代さんも高柳さんの弟子だ)、その高柳道場が昭和の時代に渋谷にあって、平成になってその道場が閉鎖になった。その後に渋谷に近いこの三軒茶屋に宮田さんがこの道場を立ち上げたということになる。
とはいえ、僕は最近さっぱり将棋を指していない。

↑
大原まり子さん(大阪府出身)は17歳の時に小説を書いてSFマガジンコンテストに応募したが落選した。その時に入選したのが新井素子さん(東京都練馬区出身)で、大原まり子と同学年。大原さんはちょっと自信を失い2年間小説を書かなかったが、再び応募してこんどは見事に入選。その作品が彼女のデビュー作となった『一人で歩いていった猫』。 僕は彼女の描くキラキラしてかっこよくそして悲しい宇宙物語が大好きだった。 彼女の「未来宇宙」では、「アディアプロトン機械帝国」と「調停者(人間)」の2大勢力が常に戦争を行っている。 その未来宇宙に、“天使の翼(これは機械の共生生物)を背にもった宇宙猫”を主人公とした話が『一人で歩いていった猫』である。 大原さんはヴァン・ヴォークトのSF小説の大ファンのようだ。
大原まりこがこれらの宇宙物語を書いた1980年代は、まだ「ソビエト連邦」が存在していた時代で、彼女の描く宇宙の‘2大勢力’という構図がその時代の影響をうけているというのが、今考えるとおもしろい。 上の写真でもいわゆる「聖子ちゃんカット」が流行っていた時代で、しかも「太い眉」ももてはやされ(石原真理子がその代表)、太眉の大原さんは時代のど真ん中を歩いていたわけだ。
大原さんは、東京の女子大に入学し卒業したが、大阪時代から「三軒茶屋」に憧れていたという。 …なぜだ?

村上春樹の『1Q84』の図書館の予約の順番がまわってきたので読んでいるのですが、その物語はこの場所――首都高速道路三号線の非常階段――から始まります。
主人公の青豆(女性30歳)がタクシーに乗りその中でFMラジオからヤナーチェック作曲の『シンフォニエッタ』という曲を聴く。その時に彼女は“ねじれた感覚”をもつ。彼女は渋谷へ行きたいのだが高速道路は混雑していてそのタクシーは進まない。運転手は、彼女に、非常階段があるということを知らせる。彼女はタクシーを降り、ハイヒールの靴を脱いで非常階段を降りる。そして田園都市線三軒茶屋駅にむかう。彼女の目的は渋谷のホテルにいる男に会いその男を暗殺すること――。
前回書いたように「オッターバ・コンブリオ」を聴きながらこのブログを書いています。
さっきは偶々ヤナーチェックの『落ち葉』(草かげの小径にて第1集 ~落ち葉)という曲が流れていました。秋の曲ということで。その後の曲はバッハ『アリア』。 僕はこの番組によってヤナーチェック(1854-1928チェコの作曲家)をはじめて聴きましたし、バッハの『アリア』は知っていても、いまだ『カノン』と区別がつきません。
でもそんなこととは関係なく、音楽はたのしめる…。 しかしもう少し心地良い環境で聴きたいものだと思っている。どうもこの部屋の‘ぐあい’が良くないのです。なにかが。なにかをどうにかせねばならん。
サティ『風変わりな美女(真面目な幻想曲)』という曲が面白い(タイトルも)。
1984年…か。
その年、僕はまだ東京に住んでいなかった。(あの日本航空御巣鷹山墜落事故は1985年。) だから「三軒茶屋」なんて地名も知らなかったのですが。

三軒茶屋キャロットタワーという建物です。

三軒茶屋将棋倶楽部。
ここはプロ棋士宮田利夫七段が席主をしている。
将棋道場というのはほんとに儲からない商売であるが、将棋のすきな人にとっては天国の休日が過ごせる。800円だか1000円だかで一日将棋が指せて、しかもこの三軒茶屋将棋倶楽部はコーヒー付きだ。それだけではない。そのコーヒーを現役プロ棋士(宮田七段)が運んできてくれるのだからすごい!
宮田利夫さんは故高柳敏夫の弟子だが(中原誠名人や島朗さん清水市代さんも高柳さんの弟子だ)、その高柳道場が昭和の時代に渋谷にあって、平成になってその道場が閉鎖になった。その後に渋谷に近いこの三軒茶屋に宮田さんがこの道場を立ち上げたということになる。
とはいえ、僕は最近さっぱり将棋を指していない。

↑
大原まり子さん(大阪府出身)は17歳の時に小説を書いてSFマガジンコンテストに応募したが落選した。その時に入選したのが新井素子さん(東京都練馬区出身)で、大原まり子と同学年。大原さんはちょっと自信を失い2年間小説を書かなかったが、再び応募してこんどは見事に入選。その作品が彼女のデビュー作となった『一人で歩いていった猫』。 僕は彼女の描くキラキラしてかっこよくそして悲しい宇宙物語が大好きだった。 彼女の「未来宇宙」では、「アディアプロトン機械帝国」と「調停者(人間)」の2大勢力が常に戦争を行っている。 その未来宇宙に、“天使の翼(これは機械の共生生物)を背にもった宇宙猫”を主人公とした話が『一人で歩いていった猫』である。 大原さんはヴァン・ヴォークトのSF小説の大ファンのようだ。
大原まりこがこれらの宇宙物語を書いた1980年代は、まだ「ソビエト連邦」が存在していた時代で、彼女の描く宇宙の‘2大勢力’という構図がその時代の影響をうけているというのが、今考えるとおもしろい。 上の写真でもいわゆる「聖子ちゃんカット」が流行っていた時代で、しかも「太い眉」ももてはやされ(石原真理子がその代表)、太眉の大原さんは時代のど真ん中を歩いていたわけだ。
大原さんは、東京の女子大に入学し卒業したが、大阪時代から「三軒茶屋」に憧れていたという。 …なぜだ?

これは芦花公園の菩提樹(ぼだいじゅ)。 菩提樹にもいろいろあって、これはシナノキ科、つまり中国菩提樹と呼ばれる種類らしい。
“菩提樹”というのは、ハート型の葉っぱで、良い香りがして、加工しやすいのでヨーロッパの人々にとってはたいへん親しみのある樹のようだ。
少しづつクラシック音楽の世界に興味をもってきている。きっかけはTBSラジオで1年前から、深夜3時より1時間『OTTAVA con brio』(オッターバ・コンブリオ)が放送されるようになり、時々聞くようになったことである。この番組のミュージック・ディレクター斉藤茂さんの話題のすすめかたに親しみを感じたということもある。この番組は元々はインターネットラジオ放送で毎日3時間半(18時~)ほどの番組で、放送後1週間の間はいつでも聞く事が出来る(無料である)。 それで僕はこの頃はPCをいじっている時はこの番組を聴きながら、ということが多い。
22日(木曜日、ただしTBSラジオでは金曜日深夜)の放送では(はじめから10分くらいの時間に)「ドイツ音楽と菩提樹」について斉藤茂さんが話していた。これは元々はある聴取者からの質問(2週間前)で、斉藤さんも「そういえばほんと菩提樹は音楽の中に登場しますね、なぜでしょうね?」と興味を持って、別の聴取者からの意見などもあったりして、どうやらこういうことらしいというような斉藤氏なりのまとめを話していた。その後で紹介された曲はマスネ(19世紀フランスの作曲家)の『組曲第7番:「アルザスの風景」 ~菩提樹の下で』。
僕にとっては、クラシック音楽は‘未知の新しい世界’で、とても新鮮だ。(そういえば『のだめカンタービレ』は完結したらしいね。)
興味がある方はこちらでどうぞ→『OTTAVA con brio』
(「OTTAVA con brio」とは「元気になる!」というような意味らしいです。)
そんな“菩提樹”の話を聞いて、たまたま上のような写真を何ヶ月か前に撮っていたことを思い出したので、それで今日の記事にしてみた。
「目覚めなければ…」と僕は感じている。
自分にとって‘目覚める’ということがどういうことなのか、半分くらいしかわからないのだが。
僕はずっと夢の中を旅しているように思っている。「目覚める」とは、夢の中の旅を終了して、リアルな世界に生きるということである。そのための準備をしなければ、と思っている。でも、「準備」とは、具体的に何をすることだろう…、そんなことを今はずっと考えている。「準備」のなかに、ブログを書くことをストップするということもあるかもしれない。
ブログを書くことで、僕の中ではいろいろなことが前にすすめた。有意義なことだった。自分のなかに、もやもやしたものがある。その正体を少しづつ明らかにしていく。そんな作業だった。それでも、もやもやしたものは、同じ割合で今もある。ブログに明らかにしたことは、「書きたいこと」その全体のうちの6分の1、つまり全体の1割7分くらいのような気がする。そして、書いても書いても、あとの8割3分ほどの「もやもや」の割合はいっこうにかわらないのだ。
そうなると、「量」で言えば、「明らかになる」分量よりも、「もやもや」の分量のほうがふえていくわけで、これでは…。
最近、コナン・ドイルの『ロストワールド(失われた世界)』を読んだ。これは怪獣映画のルーツとなる物語で、1912年に発表された。主人公はケンカ大好きの老教授チャレンジャー。彼はある詩人のスケッチブックを手にいれる。そこには“翼竜(プテラノドン)”が描かれていた…! チャレンジャー教授は、その怪物は、南アメリカのある地に生存していると確信し、若い新聞記者らとともに、冒険の旅に…。
現実世界での「恐竜の研究」の始まりは、1820年代のイギリス南部である。オックスフォード大学のバックランド教授(メガロサウルスの研究を発表)、医師ギデオン・マンテル(イグアノドンの歯を発見)、女性メアリーー・アニング(プレシオサウルス発見)の三人がその草分けである。
恐竜自体は、もちろんもっともっと昔に存在した。絶滅したのは6500年前…ではなく、6500万年前だ!!
(人類最古の芸術作品は3万5千年前だったが…、6500万前って…どんだけ~!?)
絶滅の原因でもっとも有力なのは、隕石(小惑星)衝突説だが、これはアルヴァレス父子が1980年(つい30年前のことだ)に発表したもの。彼らはたった一発(!)の小惑星の衝突の影響によって恐竜すべてがいっぺんに絶滅したと言ったのだ!
はじめはだれもそれを疑ったが、その後1992年メキシコ・ユカタン半島沖の海中にある直径190キロメートルの巨大クレーターが発見された! これを調べるとぴったり恐竜絶滅の時期と一致した(6498万年前)のだ! それは直径10キロメートルの小惑星が地球に時速4万キロメートルでの衝突によるものと推定された。今では、この小惑星のそのただ一回の衝突が恐竜を絶滅させたという説が最有力とされているそうだ。
アルヴァレス父子は、衝突後に生じる地上の温度変化を算出し、その温度変化によって恐竜は絶滅したとしたのだった。衝突後、膨大な量のチリが舞い上がり、何年にもわたって太陽を覆い隠す…すると地球の温度は低下する…。その寒さが恐竜たちを絶滅させた―――という。
「学ぶ」ということは、過去へ過去へとさかのぼって行くことらしい。学べば学ぶほど、こころは「過去へ」と飛んで行く…。
「過去へ飛ぶ」というのは、時間のながれに逆行するということである。現実のながれに自然に対応していくことが「リアルに生きる」ということであるなら、「学ぶ」という行為は、そこからどんどん離れていく行為となる。「学ぶ」のはおもしろいが、「現実」というものの手触りや温もりをわすれてしまいそうになって時々怖くなる。
自分はこれでいいのだろうか。幽霊になってしまってはいないだろうか。
どうやら、僕は、「学んで」いたようである。
ほんとうは、10代のときにしっかり「学んで」おくべきなのだ。「学んだ 」ことをリアルな世界で生かすつもりならば。旅は若い時のほうがいい。僕は、自分に、お前の学びたかったことはこういうことだろ、と納得させるために、そのために夢を見ていたのだと思っている。学びそこねた10代の自分に話しかけていたのだ。このブログを使って。
さあさあ、目覚めの準備をはじめよう。 (過去の空を飛ぶのはホドホドにして。)
まったく自信はないが、こうしていてもしかたがないから。 まず言葉にしてみる。
☆ ☆ ☆ ☆
《カテゴリー分類について、お詫び》
1年くらい前から、「しょうぎ」「つめしょうぎ」以外の内容は、すべて「はなし」のカテゴリーに入れています。(なにも考えずそうしています。)
ブログという形式は、過去にさかのぼって記事を読むのが大変ですよね。だから新しい読者のためにカテゴリーはしっかりまとめたほうが良いのですが、それがむつかしいのです。 僕の記事はもういろんな分野の内容を(煮込み料理のように)雑ぜて書くことに面白さを感じてしまったので、もう、分類しようがないのです。たとえば今回の記事も、植物なのか、音楽なのか、動物(恐竜)なのか、自分についてなのか、本なのか…。もはや、手におえません。御免なさい。
このブログ内でなにか興味のあるテーマで探すものがあるなら、上の欄にブログ内検索があるのでそれを利用されるのがよいと思います。 (カテゴリーはあてになりません。)
“菩提樹”というのは、ハート型の葉っぱで、良い香りがして、加工しやすいのでヨーロッパの人々にとってはたいへん親しみのある樹のようだ。
少しづつクラシック音楽の世界に興味をもってきている。きっかけはTBSラジオで1年前から、深夜3時より1時間『OTTAVA con brio』(オッターバ・コンブリオ)が放送されるようになり、時々聞くようになったことである。この番組のミュージック・ディレクター斉藤茂さんの話題のすすめかたに親しみを感じたということもある。この番組は元々はインターネットラジオ放送で毎日3時間半(18時~)ほどの番組で、放送後1週間の間はいつでも聞く事が出来る(無料である)。 それで僕はこの頃はPCをいじっている時はこの番組を聴きながら、ということが多い。
22日(木曜日、ただしTBSラジオでは金曜日深夜)の放送では(はじめから10分くらいの時間に)「ドイツ音楽と菩提樹」について斉藤茂さんが話していた。これは元々はある聴取者からの質問(2週間前)で、斉藤さんも「そういえばほんと菩提樹は音楽の中に登場しますね、なぜでしょうね?」と興味を持って、別の聴取者からの意見などもあったりして、どうやらこういうことらしいというような斉藤氏なりのまとめを話していた。その後で紹介された曲はマスネ(19世紀フランスの作曲家)の『組曲第7番:「アルザスの風景」 ~菩提樹の下で』。
僕にとっては、クラシック音楽は‘未知の新しい世界’で、とても新鮮だ。(そういえば『のだめカンタービレ』は完結したらしいね。)
興味がある方はこちらでどうぞ→『OTTAVA con brio』
(「OTTAVA con brio」とは「元気になる!」というような意味らしいです。)
そんな“菩提樹”の話を聞いて、たまたま上のような写真を何ヶ月か前に撮っていたことを思い出したので、それで今日の記事にしてみた。
「目覚めなければ…」と僕は感じている。
自分にとって‘目覚める’ということがどういうことなのか、半分くらいしかわからないのだが。
僕はずっと夢の中を旅しているように思っている。「目覚める」とは、夢の中の旅を終了して、リアルな世界に生きるということである。そのための準備をしなければ、と思っている。でも、「準備」とは、具体的に何をすることだろう…、そんなことを今はずっと考えている。「準備」のなかに、ブログを書くことをストップするということもあるかもしれない。
ブログを書くことで、僕の中ではいろいろなことが前にすすめた。有意義なことだった。自分のなかに、もやもやしたものがある。その正体を少しづつ明らかにしていく。そんな作業だった。それでも、もやもやしたものは、同じ割合で今もある。ブログに明らかにしたことは、「書きたいこと」その全体のうちの6分の1、つまり全体の1割7分くらいのような気がする。そして、書いても書いても、あとの8割3分ほどの「もやもや」の割合はいっこうにかわらないのだ。
そうなると、「量」で言えば、「明らかになる」分量よりも、「もやもや」の分量のほうがふえていくわけで、これでは…。
最近、コナン・ドイルの『ロストワールド(失われた世界)』を読んだ。これは怪獣映画のルーツとなる物語で、1912年に発表された。主人公はケンカ大好きの老教授チャレンジャー。彼はある詩人のスケッチブックを手にいれる。そこには“翼竜(プテラノドン)”が描かれていた…! チャレンジャー教授は、その怪物は、南アメリカのある地に生存していると確信し、若い新聞記者らとともに、冒険の旅に…。
現実世界での「恐竜の研究」の始まりは、1820年代のイギリス南部である。オックスフォード大学のバックランド教授(メガロサウルスの研究を発表)、医師ギデオン・マンテル(イグアノドンの歯を発見)、女性メアリーー・アニング(プレシオサウルス発見)の三人がその草分けである。
恐竜自体は、もちろんもっともっと昔に存在した。絶滅したのは6500年前…ではなく、6500万年前だ!!
(人類最古の芸術作品は3万5千年前だったが…、6500万前って…どんだけ~!?)
絶滅の原因でもっとも有力なのは、隕石(小惑星)衝突説だが、これはアルヴァレス父子が1980年(つい30年前のことだ)に発表したもの。彼らはたった一発(!)の小惑星の衝突の影響によって恐竜すべてがいっぺんに絶滅したと言ったのだ!
はじめはだれもそれを疑ったが、その後1992年メキシコ・ユカタン半島沖の海中にある直径190キロメートルの巨大クレーターが発見された! これを調べるとぴったり恐竜絶滅の時期と一致した(6498万年前)のだ! それは直径10キロメートルの小惑星が地球に時速4万キロメートルでの衝突によるものと推定された。今では、この小惑星のそのただ一回の衝突が恐竜を絶滅させたという説が最有力とされているそうだ。
アルヴァレス父子は、衝突後に生じる地上の温度変化を算出し、その温度変化によって恐竜は絶滅したとしたのだった。衝突後、膨大な量のチリが舞い上がり、何年にもわたって太陽を覆い隠す…すると地球の温度は低下する…。その寒さが恐竜たちを絶滅させた―――という。
「学ぶ」ということは、過去へ過去へとさかのぼって行くことらしい。学べば学ぶほど、こころは「過去へ」と飛んで行く…。
「過去へ飛ぶ」というのは、時間のながれに逆行するということである。現実のながれに自然に対応していくことが「リアルに生きる」ということであるなら、「学ぶ」という行為は、そこからどんどん離れていく行為となる。「学ぶ」のはおもしろいが、「現実」というものの手触りや温もりをわすれてしまいそうになって時々怖くなる。
自分はこれでいいのだろうか。幽霊になってしまってはいないだろうか。
どうやら、僕は、「学んで」いたようである。
ほんとうは、10代のときにしっかり「学んで」おくべきなのだ。「学んだ 」ことをリアルな世界で生かすつもりならば。旅は若い時のほうがいい。僕は、自分に、お前の学びたかったことはこういうことだろ、と納得させるために、そのために夢を見ていたのだと思っている。学びそこねた10代の自分に話しかけていたのだ。このブログを使って。
さあさあ、目覚めの準備をはじめよう。 (過去の空を飛ぶのはホドホドにして。)
まったく自信はないが、こうしていてもしかたがないから。 まず言葉にしてみる。
☆ ☆ ☆ ☆
《カテゴリー分類について、お詫び》
1年くらい前から、「しょうぎ」「つめしょうぎ」以外の内容は、すべて「はなし」のカテゴリーに入れています。(なにも考えずそうしています。)
ブログという形式は、過去にさかのぼって記事を読むのが大変ですよね。だから新しい読者のためにカテゴリーはしっかりまとめたほうが良いのですが、それがむつかしいのです。 僕の記事はもういろんな分野の内容を(煮込み料理のように)雑ぜて書くことに面白さを感じてしまったので、もう、分類しようがないのです。たとえば今回の記事も、植物なのか、音楽なのか、動物(恐竜)なのか、自分についてなのか、本なのか…。もはや、手におえません。御免なさい。
このブログ内でなにか興味のあるテーマで探すものがあるなら、上の欄にブログ内検索があるのでそれを利用されるのがよいと思います。 (カテゴリーはあてになりません。)
天の海に 雲の波立ち 月の船 星の林に 漕ぎ隠る見ゆ
柿本人麻呂
この写真は、何日か前の、早朝の月の船。
月の光はどこからくるのか?
そのこたえはもう大概の人が知っている。もちろん太陽から来た。
では、その太陽の光はどうやってうまれたのか?
そのこたえは、「核融合によって生まれた」、である。
「核融合反応」に最初に気づいた人物はアーネスト・ラザフォードである。
1917年イギリス・マンチェスター大学の実験室で、その核融合反応は偶然に起こっていた。ラザフォードはアルファ粒子(アルファ放射線、その正体はヘリウムの原子核)の実験を行っていた。ところがその中に、予測値を越える飛距離を出すアルファ粒子があることが認められた。どういうことだろうか? 「とてつもない重大なことが起こってるのではないか?」 ラザフォードは実験を繰り返し、考え、やがて1919年結論を得た。
空気中の「窒素原子(原子番号7)」が、アルファ粒子によって、「酸素原子(原子番号8)」に変換していたのだ!
これは、錬金術ではないか!
「窒素原子」にアルファ粒子の「陽子1個」が飛び込んで融合したのである。窒素原子は「酸素原子」に換わり、同時に、そこにはエネルギー(つまり光)が発生する。(アルファ粒子の飛距離が大きくなったのはそのためである。)
A・ラザフォードはニュージーランド人である。やがて彼はイギリス人となり、多くの貢献によって“ラザフォード卿”となった。その紋章には、放射能曲線、キウィ(ニュージーランドの鳥)、マオリ族、ヘルメス神(錬金術の神様)がデザインされている。
J・J・トムソンの後を継いで4代目のキャベンディッシュ研究所所長に就任したのがこの男である。
しかし核融合といってもいろいろある。太陽の光(エネルギー)はどのようにした生まれるのか? 具体的にどのような核融合反応が太陽の中で起こっているのか?
そのからくりが解明されたは、1930年代後半のことになる。
われわれの太陽で行われている核融合は、陽子(水素)が融合してヘリウムになるという型のもので、陽子-陽子連鎖反応という。これはドイツのフォン・ヴァイツゼッカーらによって考案された。
ところが、実のところ、太陽の温度はこのタイプの「核融合」を行うには温度が低すぎる(!)と考えられていた。 この核反応は、要するに、「陽子」と「陽子」が近づいて「融合」するのだが、それぞれの陽子にはバリアー(障壁)があってそう簡単には近づけない、そんなふうになっている。近づくためには、バリアーを壊すために大きなエネルギーが必要なのだが、それが「熱」というわけだ。ところが太陽の温度は15000000Kだが、計算上それでは足らないというわけだ。
だがやがてその問題は解決された。「トンネル効果」がそれを解決した。「トンネル効果」を使えば、少し低い温度でも「核融合」は起こり得るではないか…! それに気づいたのは、ドイツに生まれ、オーストリア人として育ったフリッツ・フスターマンスである。
なお、「トンネル効果」とは、ウクライナ生まれソビエト連邦の物理学者(後にアメリカに亡命)のジョージ・ガモフが、ドイツ・ゲッチンゲンに留学して量子力学を学んだ時に発見した理論である。量子の世界では、‘粒子’は同時に‘波’でもあるという。重ね合わせた存在なのだ。だから、‘粒子’では越えられない「壁」も、‘波’に変身することで越えることがあるのだという。それが「トンネル効果」である。
フスターマンスはドイツ・ゲッチンゲン大学でガモフと知り合い、「トンネル効果」のアイデアを吸収したのであった。 (ゲッチンゲン大学は量子力学の中心地だった。)
太陽の中では、「トンネル効果」を使って、水素と水素がぶつかり合い、「融合」してヘリウムとなり、同時に、「光」が生まれているのである。
(この反応ははつまり‘水爆’の基本原理である。)
フスターマンスは恋人と共によく晴れた夜空を眺めていた。彼女はこう言った「ねえ、星って本当にきれいね!」 彼はこう応えた「実はね、僕は昨日、星が輝いている理由を突き止めたんだ。」 2年後、彼は彼女と結婚した。

と、このように、水素の「核融合」には、巨大な「熱」(つまりエネルギー)を必要とする。太陽並みの「熱」を。 融合してしまえば、それ以上の見返り(エネルギー)が得られるのだが…。そういうわけで核融合の実用化はなかなか大変なのだ。
ふと、以前、‘常温核融合’がどうのという騒ぎがあったことを思い出した。あれはなんだったのだろう。
それは20年ほど前のことだが、ある科学者が「常温核融合に成功した」と発表したのだ。それが本当ならばすごい、というわけで、研究に乗り遅れてはいかん、と各国政府も色めきたった。
ところがどうも、その後それに成功したという話は全くない。
(追記; 全くない、というわけでもなさそうです。昨年日本で成功したとかそういう話があるようです。それが今後どう役に立つのか等は、僕にはさっぱりわかりません。)
そういえば同じ時期、‘常温超伝導’に成功したとか、そういう話もあった。
柿本人麻呂
この写真は、何日か前の、早朝の月の船。
月の光はどこからくるのか?
そのこたえはもう大概の人が知っている。もちろん太陽から来た。
では、その太陽の光はどうやってうまれたのか?
そのこたえは、「核融合によって生まれた」、である。
「核融合反応」に最初に気づいた人物はアーネスト・ラザフォードである。
1917年イギリス・マンチェスター大学の実験室で、その核融合反応は偶然に起こっていた。ラザフォードはアルファ粒子(アルファ放射線、その正体はヘリウムの原子核)の実験を行っていた。ところがその中に、予測値を越える飛距離を出すアルファ粒子があることが認められた。どういうことだろうか? 「とてつもない重大なことが起こってるのではないか?」 ラザフォードは実験を繰り返し、考え、やがて1919年結論を得た。
空気中の「窒素原子(原子番号7)」が、アルファ粒子によって、「酸素原子(原子番号8)」に変換していたのだ!
これは、錬金術ではないか!
「窒素原子」にアルファ粒子の「陽子1個」が飛び込んで融合したのである。窒素原子は「酸素原子」に換わり、同時に、そこにはエネルギー(つまり光)が発生する。(アルファ粒子の飛距離が大きくなったのはそのためである。)
A・ラザフォードはニュージーランド人である。やがて彼はイギリス人となり、多くの貢献によって“ラザフォード卿”となった。その紋章には、放射能曲線、キウィ(ニュージーランドの鳥)、マオリ族、ヘルメス神(錬金術の神様)がデザインされている。
J・J・トムソンの後を継いで4代目のキャベンディッシュ研究所所長に就任したのがこの男である。
しかし核融合といってもいろいろある。太陽の光(エネルギー)はどのようにした生まれるのか? 具体的にどのような核融合反応が太陽の中で起こっているのか?
そのからくりが解明されたは、1930年代後半のことになる。
われわれの太陽で行われている核融合は、陽子(水素)が融合してヘリウムになるという型のもので、陽子-陽子連鎖反応という。これはドイツのフォン・ヴァイツゼッカーらによって考案された。
ところが、実のところ、太陽の温度はこのタイプの「核融合」を行うには温度が低すぎる(!)と考えられていた。 この核反応は、要するに、「陽子」と「陽子」が近づいて「融合」するのだが、それぞれの陽子にはバリアー(障壁)があってそう簡単には近づけない、そんなふうになっている。近づくためには、バリアーを壊すために大きなエネルギーが必要なのだが、それが「熱」というわけだ。ところが太陽の温度は15000000Kだが、計算上それでは足らないというわけだ。
だがやがてその問題は解決された。「トンネル効果」がそれを解決した。「トンネル効果」を使えば、少し低い温度でも「核融合」は起こり得るではないか…! それに気づいたのは、ドイツに生まれ、オーストリア人として育ったフリッツ・フスターマンスである。
なお、「トンネル効果」とは、ウクライナ生まれソビエト連邦の物理学者(後にアメリカに亡命)のジョージ・ガモフが、ドイツ・ゲッチンゲンに留学して量子力学を学んだ時に発見した理論である。量子の世界では、‘粒子’は同時に‘波’でもあるという。重ね合わせた存在なのだ。だから、‘粒子’では越えられない「壁」も、‘波’に変身することで越えることがあるのだという。それが「トンネル効果」である。
フスターマンスはドイツ・ゲッチンゲン大学でガモフと知り合い、「トンネル効果」のアイデアを吸収したのであった。 (ゲッチンゲン大学は量子力学の中心地だった。)
太陽の中では、「トンネル効果」を使って、水素と水素がぶつかり合い、「融合」してヘリウムとなり、同時に、「光」が生まれているのである。
(この反応ははつまり‘水爆’の基本原理である。)
フスターマンスは恋人と共によく晴れた夜空を眺めていた。彼女はこう言った「ねえ、星って本当にきれいね!」 彼はこう応えた「実はね、僕は昨日、星が輝いている理由を突き止めたんだ。」 2年後、彼は彼女と結婚した。

と、このように、水素の「核融合」には、巨大な「熱」(つまりエネルギー)を必要とする。太陽並みの「熱」を。 融合してしまえば、それ以上の見返り(エネルギー)が得られるのだが…。そういうわけで核融合の実用化はなかなか大変なのだ。
ふと、以前、‘常温核融合’がどうのという騒ぎがあったことを思い出した。あれはなんだったのだろう。
それは20年ほど前のことだが、ある科学者が「常温核融合に成功した」と発表したのだ。それが本当ならばすごい、というわけで、研究に乗り遅れてはいかん、と各国政府も色めきたった。
ところがどうも、その後それに成功したという話は全くない。
(追記; 全くない、というわけでもなさそうです。昨年日本で成功したとかそういう話があるようです。それが今後どう役に立つのか等は、僕にはさっぱりわかりません。)
そういえば同じ時期、‘常温超伝導’に成功したとか、そういう話もあった。
熱力学には第1法則と第2法則とがある。
熱力学の第1法則とは「エネルギー保存の法則」のことで、これを19世紀にきっちり表現し整理したのがドイツ・ベルリン大学のヘルムホルツという人。日本の長岡半太郎はこの人のところに留学した。当時のドイツ物理学界を仕切っていた大親分がヘルムホルツだ。
「エネルギー保存の法則」とはつまり、エネルギーというものは姿かたちを変えるけれども(たとえば熱エネルギーが運動エネルギーに変化する)、全体としてはその「総量」は不変だよ、と言い切ったのである。
それなら、「エネルギーの総量が不変」であるなら、うまく考え工夫すれば、「永久機関」が発明できるのではないか、ということになる。
たとえば、石炭を燃やしてその熱エネルギーを蒸気の圧力エネルギーに変えるのが「蒸気機関」だが、それを機関車では車輪の回転運動に変える。それによって機関車は「仕事」をするのだが、その際に車輪自体が「熱」をもつ。その「熱」をもういちど回収して使うことができれば、効率がよい。仮に100パーセントその無駄に逃げていく「熱」のエネルギーを回収できれば、もう石炭は不要になって、その機関車は永久に動き続ける。「夢の永久機関」だ。
19世紀のヨーロッパの物理学者たちは、そんなことが可能なのかどうか、考えていた。 また、できないとしたら、それはなぜなのだろう、などと。
結局、「夢の永久機関」は無理だ、と(理論的にはっきりと)わかった。それが熱力学の第2法則だ。
その熱力学第2法則を「エントロピーは増大する、そしてこれは不可逆反応である」と表現したのが、ドイツの物理学者クラウジウスである。 彼こそが「エントロピー」という言葉を物理学の世界に持ちこんだ人物だ。
要するにこの法則は、「エネルギー(熱)は分散して、自然に元に戻ることは絶対にない」ということである。 だから「永久機関」はつくれないのだと理論的に証明された。

以上は、熱力学のやさしい本に紹介されていることである。一応説明しとくと、「エントロピーが増大する」とは、粒子やエネルギーが広がって平均化していくことである。
たとえば透明な水に青色インクをたらすと、インクは広がっていって薄まる。「エントロピーの増大」である。しかし元にはもどらない。つまり「不可逆」である。
しかしこの「エントロピー」という考えは、はじめはうんなるほどとわかっても、考えているとそのうちにだんだんわからなくなる。それなのに科学のいたるところに「エントロピーは増大する」という表現が出てきて困るのである。
上のブルーバックスの本の裏表紙にもこうある。
『定義は簡単だけれども、もうひとつよく解からないエントロピー』 そうなんだよな。
たとえば時間が流れる。それを逆の方向に、つまり過去の方向には戻せない。それは「世界はエントロピーが増大する方向にしか流れず、不可逆だから」なのである。
宇宙は膨張している。それも「エントロピーは増大する」という法則に当てはまる。もちろん、不可逆反応である。
そんなに「エントロピー」が大事ですか、なんでエントロピーがどうのといちいちうるさいんですかっ! なんて気分にもなる。
まあいい。 受け入れりゃいいのだ。
「エントロピー」は増大するんだ。 それでいい。
さてここからは別のはなしで、なにかの本に書いてあることではなく、‘僕の空想’です。
なんのことを書くかといえば、神経症、依存症(中毒)のことを書こうと思うのですが、僕はこれらのことについて、以前から理解しようと時々本を読んでみたりしましたが、あまりよくつかめなかった。医学用語というのは医者のためのものですからね。それでも気になるテーマなので(自分や社会の理解のために)、自分なりに考えて、それが次のようなイメージとなったわけです。
こころの中には一つの巨大な「ホール(穴)」があるのではないでしょうか。
まずそういうイメージからはじめます。
そしてその「ホール」のむこうからこちらに向けてて‘流れ’がある。その‘流れ’とは、生命力の‘流れ’です。「むこうからこっち」のながれが、エントロピーの“正”の方向のながれであり、これが自然なながれです。私達は産まれた時からずっとこの生命の‘流れ’に乗って生活しています。
ところが、何かの理由で(その理由には人それぞれのものがあると思いますが)、こころの一部が、その生命の‘流れ’を逆行しようとします…その状態を、「ノイローゼ」というのではないでしょうか。(ノイローゼとは神経症のことです)
生命の‘流れ’は、「ホール」のむこうからこっちにながれている。ところが、なぜか、ある種の人は、エントロピーの法則に逆らって、逆にすすむ。そうなりやすい体質の人が世の中にはいるのではないだろうかと思います。(自分もいくらかその体質をもってる一人だと思うのです。だから時間を逆行して19世紀のことなどに興味をもつ…。) 本人の意思ではなく、体質として、そうなるのです。まるで「ホール」が彼(または彼女)を吸い込むように。
そして「ホール」に近づくにしたがって、“異常”なことが起こるのです。(そういう場所なのだ。) 確率の低い偶然が連続して起こったり、予知夢を見たり…。ユング心理学はこれらを「共時性(シンクロニシティ)」と名付けて表しました。 (ユングの見た夢はほんとすごいですよね。)
しかし、そんな体質で生きることは苦しい。なにしろ、人間は“正”の方向に進むようにできています。人間社会もそうなっています。人間の幸福は、その“正”の‘流れ’に沿って生きることだろうと思います。
それでも「ホール」は、“負”のちからで、彼(彼女)を引き寄せる。なんとしても“正”の方向に前向きに生きたい彼(彼女)は、その“負”のちからに負けまいと、「何か」にしがみつく。
その「何か」が、アルコールであったり、薬物であったりすると、アルコール依存、薬物依存となる。仕事依存、恋愛依存、甘味依存、ゲーム依存もある。依存するものはなんでも可能性があります。(これらには「刺激物」という共通項がある。) そして責任ある立場の人ほど、社会人らしくあろうとするために、“負”の流れに負けないために、何かに依存する可能性が高くなるわけです。
しかしそれらは、一時的な避難の効果しかないようです。 一方で「ホール」の引っぱるちからは連続的…休みなしなので困ります。ですから、「依存」の頑張りもやがて限界がくるのですね。
だから頑張る人は何かに「依存」して“負”のエントロピーからくる苦しみを回避し、回避する手段を持たなかった(選ばなかった)人は、「神経症」の苦しみを受け入れる。「依存」していた人が「依存」をやめたら、やっぱりそこから苦しみと向きあわなきゃならなくなる。回り道している分だけ、また「苦しみ」に慣れていない分だけ、「依存タイプ」の人の方が、あとが大変ではなかろうか。
しかし、では、どうすればよいのか? なにものにもしがみつかず、その“負”のエントロピーのちからにどうやって対抗すればよいのか?
僕が思うに、対抗する方法はない、と思う。 対抗することをあきらめる以外にない…。(ほんとうにそうなのか?) ちからを抜いて、なるようになれ、とすれば、案外、どこかで落ち着くのではないか。(←これが僕の考える中で唯一の希望なのだ! 嗚呼!)
いやいや、そんな単純なものではないかもしれない。「ホール」のむこうは、狂気の世界かもしれない。 じゃあどうすれば…??
ようするに…それ以上はわからないということです(笑)。
ということで、この話はここでお仕舞いにしましょう。
わざわざ「エントロピー」という言葉を使って書かねばならぬ内容ではなかったですが… まあ、使ってみたかったのです。 (使ってみたかった「エントロピー」~♪)
物理の世界では、エントロピーは“正”の方向にしか流れないこととなっていますが、しかし…
オーストリア・ウィーン生まれの物理学者ボルツマンは、エントロピーの概念を、「原子」というまだ発見されていなかった粒子の運動として空想して、それを統計的に処理して表す計算方法を見つけた。
このボルツマンの考え方は、元々は、イギリスのJ・C・マックスウェルのはじめたものである。そもそも「熱」とは何だろう? それは「原子」の運動エネルギーだ…。
そのマックスウェルは、しかし、自分のつくったその考え方が根本的にもつ「問題点」を自ら指摘している。
それが「マックスウェルの悪魔」である。
熱力学を統計的に考えていくと、確率的にこうなる――というながれの論理になる。そうすると、99.999…%はOKだが、わずかに、熱力学第2法則つまりエントロピー増大の法則に違反する可能性が、(ほんのわずかではあっても)残ってしまう…、「絶対に不可逆である」とその法則ではうたっているのに。 未来の「可能性」が100億通りもあったとしたら、そのうち1通りは、「分散した熱が(偶然に)集まって元に戻る」なんてことも起こりうるということになるのではないのか? 統計的手法のそういう「あやふやさ」に天才マックスウェルは気づいていたのである。
「こんなヤツ(悪魔)がいたら、熱力学の法則は成り立たなくなる、それは困るんだよなあ…」と。
コイツが、“負”のエントロピーをこっそりと運びこむやんちゃボーイである。
そんな悪魔がいるんですかねえ…、僕のなかにも?
エジソンが白熱電球を発明したとき、管の中は真空だった。 フィラメントには苦心の末日本の竹を使ったことが知られている。しかしその電球は、現代の基準からすればすぐに切れやすく(一日もたなかったとか)、まだ実用的でなかったようだ。今は改良されて、タングステンのフィラメントに、真空ではなく、「アルゴン」が入っているようである。
アルゴン、Ar、原子番号18、不活性気体…
「アルゴン」という気体は、「怠け者」という意味で、1894年に発見された。発見者はイギリスのレイリー卿とラムゼー卿である。
これを彼らが発表した時、他の研究者達はそれを信じようとしなかった。空気(大気)の研究はすでにその100年も前にされつくされたと思っていたし、メンデレーエフの周期表の「空席」に、その新発見の空気「アルゴン」のすわる座席はなかったからだ。 (原子量の並びから、ClとKの間になるが、そこに「座席」はなかった。)
「未知の気体」なんて、まだあったのか!?
アルゴンは、不活性元素である。働かない元素…つまり、化学反応をしない‘無口なおとなしい’元素であり、だから誰も気づかなかったのである。アルゴンは大気中に1パーセント存在する。アルゴンだけでなく、「不活性元素」はまだあった。ヘリウム、ネオン、キセノン、ラドン…、それらをすべて科学者たちは、まとめて見逃してきたのだった。
だから、アルゴンの発見は、大発見!なのだった。この功績により、レイリー卿はノーベル物理学賞を、ラムゼー卿はノーベル化学賞を1904年に受賞している。
「空気を調べてごらんよ」
キャベンディッシュ研究所の妖精が、レイリー卿に、そうささやいたのだろうか。
僕はそんなことを思ってしまうのだ。
1879年J・C・マックスウェルの死によって、第2代キャベンディッシュ研究所所長に就任したのがレイリー卿である。 レイリー卿は物理学においてそれまでも十分な実績を残している。たとえば、「レイリー散乱」とよばれる式があって、それによって、空の色がなぜ青いかという証明もできるのだという。夕焼けが赤いということも。 また、熱力学にも、地震学にも、「レイリー」と名の付く式があるようだ。
キャベンディッシュ所長を5年間務めた後、その地位を若く優秀なJ・J・トムソンにゆずったレイリー卿は、その後ロンドンの教授などを勤めた後、自分の研究のための時間を持てるようになった。 そこでレイリー卿は、前から気になっていた問題に着手しはじめた。
それが「空気」の問題である。
「空気」について、その正体が盛んに分析・研究されるようになったのは、18世紀後半である。ジェームズ・ワットによる蒸気機関の発明、水素・酸素・二酸化炭素・窒素の発見…。調子に乗って「水素」入りの気球を造って大爆発が起きたり…ということもあった。
その結果、自然界の「空気」には、酸素が(体積で)21パーセント、残り79パーセントは窒素だということになった。それを長い間だれも疑うことはなかった。(100年の間、だれも!) およそ100年ほど経って、ただ一人、レイリー卿が、「もう一度よく調べてみよう」と思ったのだ。
そうしてレイリー卿は、慎重にその気体の質量を調べる実験を行った。
「空気」から、酸素、炭酸ガス、水分を完全に取り除く…すると残りは「窒素」(空気窒素という)になる。この質量と体積を計る。
一方、アンモニアから「窒素」をつくる方法があって、それでつくった「窒素」(化学窒素という)の質量・体積を計る。
するとなぜだろう、「空気窒素」と「化学窒素」はわずかに質量がちがうのだ? 両者は、同じ窒素ではないということか…?
レイリー卿はその結果を学会で発表した。 「まことに不可解である。みなさんの御意見をうかがいたい。」と。
するとそれに興味を示したのがラムゼー卿だった。 ラムゼーは、私もそれについて研究したいと申し出た。 (イギリスは紳士の国だ。つまりラムゼーは、私も同じ研究をしてもよいかと許可を求めたのである。) それで二人は、お互いに独自にこの研究をして、意見交換をしようということになった。
二人が考えたのは、「空気窒素」には、「なにか別のもの」が含まれているのではないかということだ。 それなら、「空気窒素」から、「窒素」をすべて取り去れば、その「なにか」が残ることになる。
問題は、取り除く、その方法だ。
ラムゼー卿は、マグネシウムに窒素を吸収させるというやりかたで、そのための装置を何度も改良し、そしてついに「なにか」を掴んだのだった。ラムゼーは残った気体を調べてみた。質量を計り、放電管に入れてスペクトルを調べる…。
これはまったく「未知の気体」であった。
ラムゼーはレイリーに連絡を取った。すると驚いたことに、レイリー卿も、ほぼ同時に(なんというすてきな偶然だろう!)、その「未知の気体」の分離と分析を終えたところであった。
その新しく発見した気体、「空気」の中にこっそりと1パーセント含まれていて、だれにも見つからずに隠れていたその気体に、「アルゴン」と名前をつけ、二人の科学者は連名でそれを発表した。 その発表は驚きを持って受け止められ、はじめは誰も信じようとしなかった。 実験ミスではないのか、と。 しかし物理学者クルックスがその「アルゴン」を調べたスペクトルを発表すると、もう反対者も黙る以外になくなった。 だれも気づかなかった「不活性気体」、それは確かに存在するのだと。 「メンデレ-エフの周期表」は修正され、新たな「座席」が1列まるごと追加されることとなった。
(クルックスは、「クルックス管」の発明で知られている。その「クルックス管」が、その後のドイツでのX線の発見や、トムソンの電子の発見に繋がることになる。)
レイリー卿が、「空気窒素」から「窒素」を取り除いた方法は、ラムゼー卿とは違う方法であった。
彼の方法は、「空気窒素」に適量の酸素をまぜ、そこに電気の火花を放電することで、「窒素」を二酸化窒素としてアルカリ水に吸収させるというやりかたであった。
二人が、この「アルゴンの発見」によって、それぞれノーベル賞に輝いたことはすでに述べたとおりである。
ラムゼー卿は、その後も助手とともにこうした研究を重ねた。 まだあるぞ、と思ったのである。アルゴンの中に、まだ未知の「不活性元素」があるのではないかと。 そして、科学史にさらに重要な貢献をすることになる。 化学の歴史にとり残されていた「未知の不活性元素」を次々と発見し「周期表」の空席を埋めたのである。 ヘリウム、クリプトン、キセノン、ネオン…
大阪の初代通天閣(現代のは2代目)は1912年に建築されたようだが、あの通天閣を象徴するネオンサインも、ラムゼー(とトラバース)によるネオンの発見(1898年)に由来するというわけ。 ネオン(Ne)は「新しい」という意味である。
さて、化学のお勉強でおなかいっぱい…な感じだが、「アルゴンの発見」についてもう一つ話が残っているので、おつきあいを願いたい。
以前に、マックスウェルの書いた『ヘンリー・キャベンディッシュ電気論文集』(1879年)のことにふれた。 そして、アルゴンの発見からさらに年月が過ぎた1920年頃、ヘンリー・キャベンディッシュの残された「ノート」についての未整理だった内容がまとめられ明らかになった。 そこには、「空気」についての、驚くべき内容が。
まさか…
そう、まさか…まさか… なのである!
ヘンリー・キャベンディッシュは、すでに18世紀に、「空気」の中に、酸素、窒素以外の「何か別の気体」が1パーセント存在することを、実験により、ただ一人、知っていたのである!!
その実験の方法は、レイリー卿がやったものと同じ方法であった。 電気火花を放電させてアルカリ水に二酸化窒素として吸収させるというやりかたで…。 その時代は、まだ発電機も電池も発明されていないから、静電気をびん(ライデンびん)に貯めたものを使って。
究極の「理系男子」とは、きっとヘンリー・キャベンディッシュのことであろう。
アルゴン、Ar、原子番号18、不活性気体…
「アルゴン」という気体は、「怠け者」という意味で、1894年に発見された。発見者はイギリスのレイリー卿とラムゼー卿である。
これを彼らが発表した時、他の研究者達はそれを信じようとしなかった。空気(大気)の研究はすでにその100年も前にされつくされたと思っていたし、メンデレーエフの周期表の「空席」に、その新発見の空気「アルゴン」のすわる座席はなかったからだ。 (原子量の並びから、ClとKの間になるが、そこに「座席」はなかった。)
「未知の気体」なんて、まだあったのか!?
アルゴンは、不活性元素である。働かない元素…つまり、化学反応をしない‘無口なおとなしい’元素であり、だから誰も気づかなかったのである。アルゴンは大気中に1パーセント存在する。アルゴンだけでなく、「不活性元素」はまだあった。ヘリウム、ネオン、キセノン、ラドン…、それらをすべて科学者たちは、まとめて見逃してきたのだった。
だから、アルゴンの発見は、大発見!なのだった。この功績により、レイリー卿はノーベル物理学賞を、ラムゼー卿はノーベル化学賞を1904年に受賞している。
「空気を調べてごらんよ」
キャベンディッシュ研究所の妖精が、レイリー卿に、そうささやいたのだろうか。
僕はそんなことを思ってしまうのだ。
1879年J・C・マックスウェルの死によって、第2代キャベンディッシュ研究所所長に就任したのがレイリー卿である。 レイリー卿は物理学においてそれまでも十分な実績を残している。たとえば、「レイリー散乱」とよばれる式があって、それによって、空の色がなぜ青いかという証明もできるのだという。夕焼けが赤いということも。 また、熱力学にも、地震学にも、「レイリー」と名の付く式があるようだ。
キャベンディッシュ所長を5年間務めた後、その地位を若く優秀なJ・J・トムソンにゆずったレイリー卿は、その後ロンドンの教授などを勤めた後、自分の研究のための時間を持てるようになった。 そこでレイリー卿は、前から気になっていた問題に着手しはじめた。
それが「空気」の問題である。
「空気」について、その正体が盛んに分析・研究されるようになったのは、18世紀後半である。ジェームズ・ワットによる蒸気機関の発明、水素・酸素・二酸化炭素・窒素の発見…。調子に乗って「水素」入りの気球を造って大爆発が起きたり…ということもあった。
その結果、自然界の「空気」には、酸素が(体積で)21パーセント、残り79パーセントは窒素だということになった。それを長い間だれも疑うことはなかった。(100年の間、だれも!) およそ100年ほど経って、ただ一人、レイリー卿が、「もう一度よく調べてみよう」と思ったのだ。
そうしてレイリー卿は、慎重にその気体の質量を調べる実験を行った。
「空気」から、酸素、炭酸ガス、水分を完全に取り除く…すると残りは「窒素」(空気窒素という)になる。この質量と体積を計る。
一方、アンモニアから「窒素」をつくる方法があって、それでつくった「窒素」(化学窒素という)の質量・体積を計る。
するとなぜだろう、「空気窒素」と「化学窒素」はわずかに質量がちがうのだ? 両者は、同じ窒素ではないということか…?
レイリー卿はその結果を学会で発表した。 「まことに不可解である。みなさんの御意見をうかがいたい。」と。
するとそれに興味を示したのがラムゼー卿だった。 ラムゼーは、私もそれについて研究したいと申し出た。 (イギリスは紳士の国だ。つまりラムゼーは、私も同じ研究をしてもよいかと許可を求めたのである。) それで二人は、お互いに独自にこの研究をして、意見交換をしようということになった。
二人が考えたのは、「空気窒素」には、「なにか別のもの」が含まれているのではないかということだ。 それなら、「空気窒素」から、「窒素」をすべて取り去れば、その「なにか」が残ることになる。
問題は、取り除く、その方法だ。
ラムゼー卿は、マグネシウムに窒素を吸収させるというやりかたで、そのための装置を何度も改良し、そしてついに「なにか」を掴んだのだった。ラムゼーは残った気体を調べてみた。質量を計り、放電管に入れてスペクトルを調べる…。
これはまったく「未知の気体」であった。
ラムゼーはレイリーに連絡を取った。すると驚いたことに、レイリー卿も、ほぼ同時に(なんというすてきな偶然だろう!)、その「未知の気体」の分離と分析を終えたところであった。
その新しく発見した気体、「空気」の中にこっそりと1パーセント含まれていて、だれにも見つからずに隠れていたその気体に、「アルゴン」と名前をつけ、二人の科学者は連名でそれを発表した。 その発表は驚きを持って受け止められ、はじめは誰も信じようとしなかった。 実験ミスではないのか、と。 しかし物理学者クルックスがその「アルゴン」を調べたスペクトルを発表すると、もう反対者も黙る以外になくなった。 だれも気づかなかった「不活性気体」、それは確かに存在するのだと。 「メンデレ-エフの周期表」は修正され、新たな「座席」が1列まるごと追加されることとなった。
(クルックスは、「クルックス管」の発明で知られている。その「クルックス管」が、その後のドイツでのX線の発見や、トムソンの電子の発見に繋がることになる。)
レイリー卿が、「空気窒素」から「窒素」を取り除いた方法は、ラムゼー卿とは違う方法であった。
彼の方法は、「空気窒素」に適量の酸素をまぜ、そこに電気の火花を放電することで、「窒素」を二酸化窒素としてアルカリ水に吸収させるというやりかたであった。
二人が、この「アルゴンの発見」によって、それぞれノーベル賞に輝いたことはすでに述べたとおりである。
ラムゼー卿は、その後も助手とともにこうした研究を重ねた。 まだあるぞ、と思ったのである。アルゴンの中に、まだ未知の「不活性元素」があるのではないかと。 そして、科学史にさらに重要な貢献をすることになる。 化学の歴史にとり残されていた「未知の不活性元素」を次々と発見し「周期表」の空席を埋めたのである。 ヘリウム、クリプトン、キセノン、ネオン…
大阪の初代通天閣(現代のは2代目)は1912年に建築されたようだが、あの通天閣を象徴するネオンサインも、ラムゼー(とトラバース)によるネオンの発見(1898年)に由来するというわけ。 ネオン(Ne)は「新しい」という意味である。
さて、化学のお勉強でおなかいっぱい…な感じだが、「アルゴンの発見」についてもう一つ話が残っているので、おつきあいを願いたい。
以前に、マックスウェルの書いた『ヘンリー・キャベンディッシュ電気論文集』(1879年)のことにふれた。 そして、アルゴンの発見からさらに年月が過ぎた1920年頃、ヘンリー・キャベンディッシュの残された「ノート」についての未整理だった内容がまとめられ明らかになった。 そこには、「空気」についての、驚くべき内容が。
まさか…
そう、まさか…まさか… なのである!
ヘンリー・キャベンディッシュは、すでに18世紀に、「空気」の中に、酸素、窒素以外の「何か別の気体」が1パーセント存在することを、実験により、ただ一人、知っていたのである!!
その実験の方法は、レイリー卿がやったものと同じ方法であった。 電気火花を放電させてアルカリ水に二酸化窒素として吸収させるというやりかたで…。 その時代は、まだ発電機も電池も発明されていないから、静電気をびん(ライデンびん)に貯めたものを使って。
究極の「理系男子」とは、きっとヘンリー・キャベンディッシュのことであろう。
先々週、渋谷駅に立ち寄った時の写真。中央後ろ姿の女性の頭のあたりに「ハチ公」の銅像があります。小さく、目立たない。
この日、三軒茶屋(東京世田谷区の地名です)に行く用事があって、それではとちょっと渋谷に立ち寄ることにした。岡本太郎『明日の神話』を観ようと思って。
簡単に見つかるだろうとの予定が、そういうことにならず、この日はあきらめることに。 これで2回目だ。半年前にも見つからなかった。 根性がないのですぐあきらめる。(10分で見つかると思っていた。) ま、いつでも見ることができますからね。 また今度。
あの「忠犬ハチ公」の話(リチャード・ギアも知っている♪)は、1925年の話であるという。
それなら「玉電」(玉川電車鉄道)があったはずだ。「玉電」は昔の東京都電の一つで、「渋谷―二子玉川」間を走っていて1907年に開通した。
この「玉電」に乗って、1910年8月8日豪雨の中、岡本一平(岡本太郎の父)は二子玉川まで行き、鉄橋を突っ走って川向こうに渡り、大貫カノ(岡本かの子=太郎の母)に結婚を申し込んだのである。 なぜに豪雨の日に? 要するに、嵐で気持ちを盛り上げて勢いをつけたのだろう。 それまで、いつ行こうかとウジウジしていたに違いない。
余談になるが、夏目漱石『坊ちゃん』の主人公は、四国松山から東京に戻ったあと、「都電の技師」としてずっと働いたという設定になっている。彼の働いたのは「玉電」だろう、という説を読んだことがある。(漱石の長女筆子の娘の婿半藤一利の随筆ではなかったかと思う。)
岡本太郎『明日の神話』は、巨大な絵である。(僕はまだ見ていないわけだが。)
この絵は、メキシコのある新設予定のホテルのための注文によって描かれた壁画である。そのホテルのロビーを飾る予定だった。あの万博の『太陽の塔』と同じ時期に、岡本太郎は日本とメキシコを行ったり来たりしてこの絵を描いていたのだ。
ところが、そのホテルは結局、立ち上がることがなかった。それでせっかく描いた太郎氏の壁画はそのまま行方不明になっていた。
岡本太郎は1996年に没した。最後は、パーキンソン病だったという。
岡本敏子さんは、岡本太郎の妻同然(あるいはそれ以上)の人だったが、太郎氏の『明日の神話』の発見・再生に執念をもって取り組んだのが、敏子さんだった。「どうしても見つけたい。」 敏子さんの望みが叶い、やがてそれは見つかった。彼女は、知らせを受けるとすぐにメキシコへ飛んだ。その壁画がシートの下で野ざらしになっていたのを確認した後、岡本敏子はすぐにその修復の決意をした。2003年のことである。
それが昨年秋、渋谷に設置されることになった『明日の神話』である。 (渋谷駅のどこか地下にあるらしい…。)
この絵は、核エネルギーがテーマなのだろうか。 手塚治虫の『鉄腕アトム』と重ねて鑑賞するのはどうだろうか。
あるいは、太郎と敏子の恋愛物語として鑑賞することもできる。
岡本敏子さんは、法律上は、岡本太郎の「養女」である。生涯独身を通した岡本太郎は、「俺はだれのものにもならない」とどうやら思っていたようである。「それなら養女にしてください」と敏子さんは言ったわけだ。
岡本かの子の書いた小説の大ファンだった瀬戸内晴美(寂聴)は、『かの子繚乱』を書くにあたり、岡本太郎に会いに行った。初めて会う時、やってきた岡本太郎は、松葉杖を突いていた。スキーで骨折したのだという。太郎のスキーは激しい、炎のような滑り方だったという。出会った頃の太郎と敏子さんのスキーを楽しむ写真が残されている。
瀬戸内晴美と岡本太郎はやがて親しくなり、瀬戸内は川端康成(岡本かの子の文学の師匠)と相談して、川崎の玉川新地にかの子の記念碑を、いやがる太郎を説得して建立した。そういう縁もあって、岡本太郎の住処に瀬戸内晴美は気軽におじゃまするようになったが、やがて太郎は瀬戸内を愛人として囲おうとしたようである。そのことは岡本敏子さんの本にも書いてある。瀬戸内は「私も一国一城の主ですので。」と断わったのだが。
岡本敏子さんが、TVで岡本太郎のことを語るところを僕は見たことがある。あのうれしそうな顔はなんなのだろう、と思ったものだ。
僕はこの日、そのまま田園都市線に乗り、三軒茶屋へ。
この田園都市線というのが、「玉電」のなきあと、「渋谷―二子玉川」を走っている鉄道である。 この線上には、「サザエさんの街」(桜新町)もある。
この日、三軒茶屋(東京世田谷区の地名です)に行く用事があって、それではとちょっと渋谷に立ち寄ることにした。岡本太郎『明日の神話』を観ようと思って。
簡単に見つかるだろうとの予定が、そういうことにならず、この日はあきらめることに。 これで2回目だ。半年前にも見つからなかった。 根性がないのですぐあきらめる。(10分で見つかると思っていた。) ま、いつでも見ることができますからね。 また今度。
あの「忠犬ハチ公」の話(リチャード・ギアも知っている♪)は、1925年の話であるという。
それなら「玉電」(玉川電車鉄道)があったはずだ。「玉電」は昔の東京都電の一つで、「渋谷―二子玉川」間を走っていて1907年に開通した。
この「玉電」に乗って、1910年8月8日豪雨の中、岡本一平(岡本太郎の父)は二子玉川まで行き、鉄橋を突っ走って川向こうに渡り、大貫カノ(岡本かの子=太郎の母)に結婚を申し込んだのである。 なぜに豪雨の日に? 要するに、嵐で気持ちを盛り上げて勢いをつけたのだろう。 それまで、いつ行こうかとウジウジしていたに違いない。
余談になるが、夏目漱石『坊ちゃん』の主人公は、四国松山から東京に戻ったあと、「都電の技師」としてずっと働いたという設定になっている。彼の働いたのは「玉電」だろう、という説を読んだことがある。(漱石の長女筆子の娘の婿半藤一利の随筆ではなかったかと思う。)
岡本太郎『明日の神話』は、巨大な絵である。(僕はまだ見ていないわけだが。)
この絵は、メキシコのある新設予定のホテルのための注文によって描かれた壁画である。そのホテルのロビーを飾る予定だった。あの万博の『太陽の塔』と同じ時期に、岡本太郎は日本とメキシコを行ったり来たりしてこの絵を描いていたのだ。
ところが、そのホテルは結局、立ち上がることがなかった。それでせっかく描いた太郎氏の壁画はそのまま行方不明になっていた。
岡本太郎は1996年に没した。最後は、パーキンソン病だったという。
岡本敏子さんは、岡本太郎の妻同然(あるいはそれ以上)の人だったが、太郎氏の『明日の神話』の発見・再生に執念をもって取り組んだのが、敏子さんだった。「どうしても見つけたい。」 敏子さんの望みが叶い、やがてそれは見つかった。彼女は、知らせを受けるとすぐにメキシコへ飛んだ。その壁画がシートの下で野ざらしになっていたのを確認した後、岡本敏子はすぐにその修復の決意をした。2003年のことである。
それが昨年秋、渋谷に設置されることになった『明日の神話』である。 (渋谷駅のどこか地下にあるらしい…。)
この絵は、核エネルギーがテーマなのだろうか。 手塚治虫の『鉄腕アトム』と重ねて鑑賞するのはどうだろうか。
あるいは、太郎と敏子の恋愛物語として鑑賞することもできる。
岡本敏子さんは、法律上は、岡本太郎の「養女」である。生涯独身を通した岡本太郎は、「俺はだれのものにもならない」とどうやら思っていたようである。「それなら養女にしてください」と敏子さんは言ったわけだ。
岡本かの子の書いた小説の大ファンだった瀬戸内晴美(寂聴)は、『かの子繚乱』を書くにあたり、岡本太郎に会いに行った。初めて会う時、やってきた岡本太郎は、松葉杖を突いていた。スキーで骨折したのだという。太郎のスキーは激しい、炎のような滑り方だったという。出会った頃の太郎と敏子さんのスキーを楽しむ写真が残されている。
瀬戸内晴美と岡本太郎はやがて親しくなり、瀬戸内は川端康成(岡本かの子の文学の師匠)と相談して、川崎の玉川新地にかの子の記念碑を、いやがる太郎を説得して建立した。そういう縁もあって、岡本太郎の住処に瀬戸内晴美は気軽におじゃまするようになったが、やがて太郎は瀬戸内を愛人として囲おうとしたようである。そのことは岡本敏子さんの本にも書いてある。瀬戸内は「私も一国一城の主ですので。」と断わったのだが。
岡本敏子さんが、TVで岡本太郎のことを語るところを僕は見たことがある。あのうれしそうな顔はなんなのだろう、と思ったものだ。
僕はこの日、そのまま田園都市線に乗り、三軒茶屋へ。
この田園都市線というのが、「玉電」のなきあと、「渋谷―二子玉川」を走っている鉄道である。 この線上には、「サザエさんの街」(桜新町)もある。