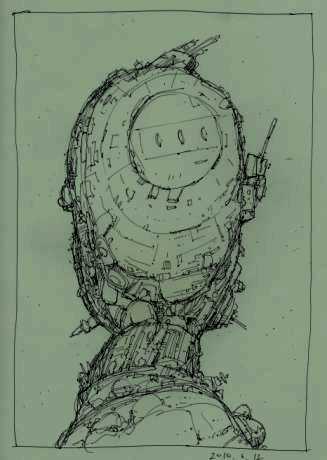放射性物質は崩壊する。これは自然現象であるが、それが発見されたのは今から100年ほど前のことで、この崩壊の謎のおおまかなところを解明したその中心人物は、ニュージーランド生まれの
アーネスト・ラザフォードであった。
驚いたことに、崩壊した放射性物質は、姿を変えて、他の元素になるのである!
崩壊の法則には2種類があった。
アルファ崩壊と
ベータ崩壊である。
1930年代、ベータ崩壊の「法則」に、物理学者達は首をひねっていた。
1932年に、ラザフォードの弟子
ジェームズ・チャドウィックが「中性子」を発見した。それによって、ベータ崩壊のしくみがだいたい判明してきたように見えた。ベータ崩壊というのは、核内の「中性子」が、「陽子」と「電子」(これがベータ線の正体)に変わることによって起こる現象であると。つまり、
「中性子」 → 「陽子」 + 「電子」(ベータ粒子)
となる。
ところが、実験からこれを調べてみると、どうも質量保存の法則が成立しないのである。
ニールス・ボーアも、
ヴォルフガング・パウリも、この謎に大いに悩んだのである。質量保存の法則が成立しない…そんなことがあっていいのだろうか!?
苦し紛れに、パウリは、「まだ発見されていない中性の粒子」があるのではないだろうか、と考えた。しかしパウリ自身もそれほど自信があったわけではなく、誰も賛成しなかったので、それを理論に仕上げることはなかった。
朝永振一郎『スピンはめぐる』には、パウリがドイツ・ベルリンの
リーゼ・マイトナーに宛てた英文で書かれた手紙が紹介されている。その手紙の書き出しは次のように始まっている。
〔 Dear radioactive ladies and gentlemen … 〕
「Dear radioactive ladies」=親愛なる放射性淑女、とパウリはリーゼ・マイトナーに呼びかけているのであるが(
リーゼ・マイトナーは、後に核分裂の発見ドラマの主役になる女性である。)、 この手紙の中で、パウリは、「electrically neutoral particles」と書いている。 直訳すると、「電気的に中性な粒子」である。 これはとりあえず、“
パウリの中性子”などと呼ばれることになった。
そして1933年。
エンリコ・フェルミとその愉快な仲間たち、
ラセッティ、アマルディ、セグレの4人は、アルプスの小さな村でクリスマス休暇を過ごしていた。スキーを楽しんだその日、フェルミは彼らを集めて、自分の書いた論文を披露した。
それはベータ崩壊を説明する論文だった。
ニュートリノ!!
ついに「パウリの中性子」は、新しい名前とフェルミの理論を纏って華々しく世に生まれ出たのであった!
「ニュートラル」(電気的に中性)な、「イノ」(小さなやつ)という意味で、イタリア人エンリコ・フェルミがその名付け親なのである。
(しかしこの論文を科学論文雑誌『ネイチャー』は採用しなかった。それで翌1934年イタリアの雑誌に発表された。)
そうして、ベータ崩壊はこうなった。
「中性子」 → 「陽子」 + 「電子」(ベータ粒子) + 「ニュートリノ」
とはいえ、これはまだ「架空の粒子」にすぎなかった。
しかし大戦後、アメリカ人
フレデリック・ライネスが原子炉の中から「ニュートリノ」を発見した。それは1950年代のことだったが、ライネスがノーベル賞を授与されたのは1995年のことである。ずいぶん時間が経っているが、それだけ「ニュートリノ」という存在に“そんなもの本当に存在しているのか?”という疑問符が、なおもずっとあったということだろうか。 いや実際のところ、「ニュートリノ」はつかまえにくく、実験室で扱えるものではなかったのだ。
「ニュートリノ」の存在感を確かにしたのは、なんといっても1987年のあの事件だろう。
小柴昌俊が、「カミオカンデ」によって、
超新星ニュートリノを捕らえたあの歴史的出来事である。 小柴さんが検出したその‘中性の小さなやつ’は、僕の記憶ではたしか、たったの14個だったと思う。 けれども、それは、絶大なインパクトだった。
(後日注: 正しくは「11個」です。)
余談ですが、僕は「ニュートリノ」のネーミングは、きっとニュートン――あのりんごと重力で有名な――からきているのだろうと、数年前までは思っていたのでした。
[追記] 上の文章は「ニュートリノの物語」をわかりやすくするためにいくらか歴史的な事実を“誤魔化して”書いています。その点について、正しいところを以下に説明しておきます。
パウリがベータ崩壊の謎に悩んで「パウリの中性子」を考えたのは1930年頃のことで、それはチャドウィックによる「中性子」の発見以前のことです。「パウリの中性子」よりも後、1932年にチャドウィックが「中性子」を発見します。
それで、ベータ崩壊を説明する一つのアイデアとして、もともと「中性子」というのは、「陽子」と「電子」が合体した姿なのではないか、というものが生まれてきました。しかしこれは今の知識では間違っていますが、それが当時の発想の限界でした。
そこにいきなりエンリコ・フェルミの論文が登場します。
1934年にイタリアで発表されたフェルミのベータ崩壊の論文です。この論文の画期的なところは(ニュートリノのアイデアも新しかったがそれ以上に凄いことは)、
「中性子」が「陽子」に変身する(=崩壊する)、と見抜いた点です。 そんな発想をする人はフェルミの前にはいませんでした。そしてフェルミによって示されたそのアイデアは、正しかったのです。彼は、その論文の中でベータ崩壊を‘弱い力(核力)’というものを設定して説明しました。
ニュートリノ、「中性子」の「陽子」への変身、‘弱い力(核力)’という独創的ななアイデアをいっぺんに持ち込み、それが今でも通用するという、まさに天才の仕事です。